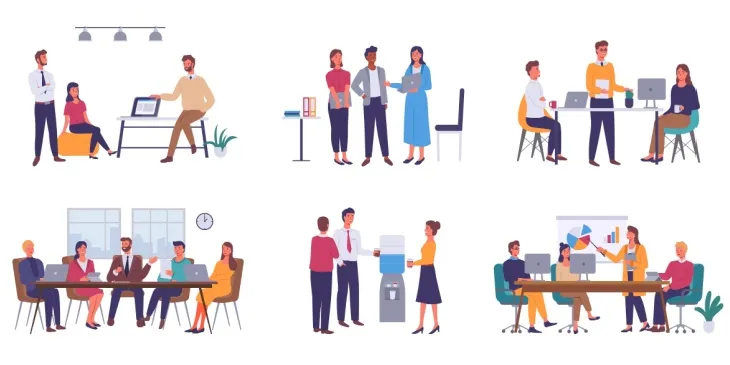


人材派遣の職場見学の流れとは?企業が注意すべきことを解説
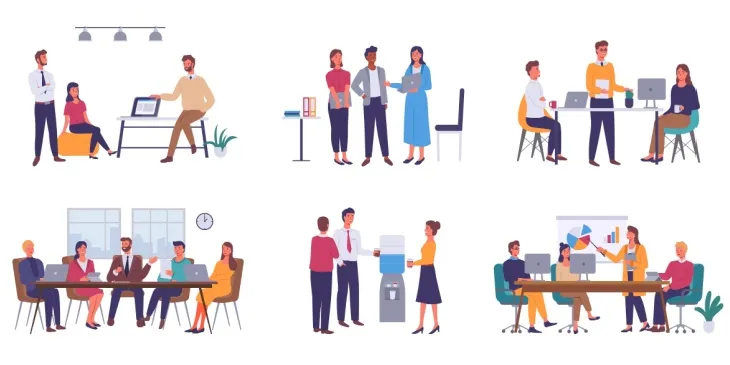
目次
人材派遣サービスを利用する場合、就業前に「職場見学」が実施されることがあります。本記事では、「職場見学」について、基礎知識および、当日の流れや実施の際の注意事項などを解説します。
職場見学の進め方と注意点
職場見学を担当する方向けにわかりやすく流れと注意点をまとめました。
<この資料でわかること>
- 職場見学の流れと注意点
- 派遣社員へ伝えるべき内容
- 派遣社員に質問してはいけないこと
人材派遣の職場見学とは?
人材派遣で実施される職場見学とは、派遣社員が実際に働く職場環境や業務内容を事前に確認する機会を指し、派遣社員の希望があった場合に行われます。
派遣先で詳しい業務内容の説明を直接受けたり、部門の責任者・メンバーとの対面で、就業先や業務の理解を深め、ミスマッチを防止するために行います。
職場見学は基本的に、派遣会社の担当者と派遣社員、派遣先の担当者の三者で行います。
職場見学は「面接」ではない
職場見学は、候補となっている派遣社員の希望で実施するものであり、派遣先が「応募者を面接する機会」ではありません。あくまでも、派遣社員が「業務と就業先を深く知るために実施」するものです。
派遣法では「事前面接の原則禁止」が定められています。(労働者派遣法第26条6項)そのため、派遣社員が希望していないのに職場見学を強制したり、選別のための質問をすることはできません。
派遣社員の特定行為については、「派遣社員の特定行為は禁止!指導例や例外をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。
※ただし、将来の直接雇用を前提とする紹介予定派遣の場合、面接などの選考を行うことが可能です。
関連資料:派遣法の基礎知識 知っておくべき12項目
職場見学の流れ
職場見学の一般的な流れについて、挨拶や簡単な自己紹介後の流れから説明します。
業務内容の説明
職場見学では、まず派遣先の現場担当者から業務内容の詳しい説明を行います。
派遣社員は、派遣会社から事前に業務内容に関する説明を受けていますが、指示を受ける、または一緒に働く派遣先からの説明により、業務についての理解を深め具体的にイメージできるようになります。
<説明しておきたいこと>
- 具体的な業務内容(1日・1か月の業務の流れ)
- 必要なスキル
- 職場環境(食堂・休憩室・更衣室・喫煙に関するルール等)
- 部署環境(人数・構成、雰囲気など)
- 残業の有無、時期、程度
- 服装規定
※以下も該当があれば説明する
- 現金や有価証券等の取扱い
- 朝礼や掃除など当番になる業務
- 会社行事への参加有無
派遣社員には契約内容以外の業務を依頼できないため、職場見学時に業務内容を明確に伝えることでトラブルを未然に防げるメリットがあります。
派遣後に、人事担当者または職場見学で聞いていた業務内容と実際に従事する業務内容が異なり、トラブルとなるケースもあるため、この段階でそのような相違がないか確認することが重要です。
派遣社員から派遣先へ質問
次に、派遣社員からの質問を受けます。派遣社員は、「自分の認識と実際の業務内容に相違がないか」「自身のスキルで本当に対応できるのか」といった不安を持っており、その解消のために質疑応答の場が設けられます。
<よくある質問例>
- 使用ソフトにExcelとありますが、具体的にはどのような機能を使いますか?
- 繁忙期はありますか?
- 同じ仕事を担当する方は何人くらいいらっしゃいますか?
- 一緒に働く方の年代や性別、人数等を教えてください
- 業務に慣れるまでは、どれくらいの期間を想定していますか?
- 質問できる人はいますか?
- OJTはありますか?
- 業務に必要なもので、持参してもよい私物(使い慣れた電卓など)は持ち込みは可能ですか?
- オフィスカジュアルという服装規定ですが、特に禁止されているものはありますか?
- 髪色、ネイルなどに制限はありますか?
- 更衣室はありますか?
派遣先から派遣社員へ質問
職場見学は面接の機会ではありませんが、業務に必要なスキルや知識を派遣社員自身にきちんと判断してもらうために、派遣社員への質問をすることは可能です。
例えば、以下のような質問ができます。
- 前職ではどのようなお仕事を経験されていらっしゃいますか?
- 似たような業務の経験はありますか?
- 基本の業務に慣れていただいたら、社内研修を受けて〇〇の業務も担当いただきたいと考えていますが、問題はありませんか?
- 絶対に残業できない曜日や期間はありますか?
- 自転車やバイクでの通勤も可能です。ご希望はありますか?
- 月に数回、税理士事務所や金融機関への外出があります。問題ありませんか?
- 日中、事務所でひとりになることがあります。その時間帯、電話対応をお願いすることになりますが問題ありませんか?
- 数ヶ月に一度、社員全員が参加する研修があります。依頼する業務に直接は関係がありませんが、受けていただけますか?
- 〇〇資格の取得時期を教えてください
- 〇〇資格を取得したきっかけを教えてください
※資格に関する質問は、業務に関係する場合のみ。興味本位での質問は避けること
職場の見学
派遣後に働く予定の実際の職場環境を見せるかは必須事項ではありませんが、見学をしておくと派遣社員は働くイメージがつきやすくなります。
更衣室や休憩室、給湯室、お手洗い、社員用通用口、社員食堂など、一日の流れの中で使う可能性のある場所も含めて案内することで、就業場所としての魅力が伝わり、就業意欲が高まる可能性があります。
オフィスを見せる場合の注意点
オフィスを案内する際の注意点をいくつかお伝えします。
- 社員に事前に通知しておく
- 顧客の個人情報、経営上重要な数字など、機密情報が見えないようにする
- 印象が下がるような言動を避ける
職場見学で企業が気を付けたい5つの注意点
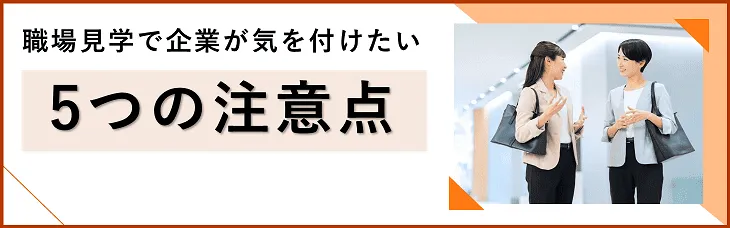
職場見学を実施するうえで、対応する担当者が注意する点について解説します。注意点については、職場見学に対応するすべての従業員に共有するようにしましょう。
- 個人情報に関することは質問しない
- 派遣先が決定していると誤解される言動に気を付ける
- 職歴・スキル以外の質問は控える
- 履歴書やエントリーシートなどへの記入を求めない
- 職場環境や社内ルールについても説明する
個人情報に関することは質問しない
派遣社員は、派遣会社の社員であり自社の社員になるわけではありません。職場見学では、個人情報についての質問は避けましょう。
例えば、以下のような質問はNGです。
- ご自宅の最寄り駅はどこですか?
- ご自宅からここまで通勤時間はどれくらいかかりますか?
- お住まいはどちらですか?
- 今、おいくつですか?
- 前職はどちらに勤めていたのですか?
ただし、お互いに一般的な挨拶をする中で、派遣社員が自発的に行う自己紹介に含まれる、名前をはじめとする個人情報を伝えることに問題はありません。企業側から質問をしないように気をつけましょう。
派遣先が決定していると誤解される言動に気を付ける
繰り返しになりますが、派遣の職場見学は「企業が自社への派遣社員候補を選考する場」ではありません。
「何らかの選別を行っているのではないか?」と誤解してしまう可能性がある質問や言動には注意してください。
一例を挙げます。
- 志望動機を教えてください
- あなたの長所と短所を教えてください
- 前職でどのような成果をあげられましたか?
- どのように仕事に取り組みたいとお考えですか?
- 当社でどのように成長していきたいですか?
- どのようなことにやりがいを感じますか?
- 前職の退職理由を教えてください
- なぜ派遣を選んだのですか?
採用面接では一般的な質問ですが、職場見学は「選考する場」ではありませんので注意しましょう。
職歴・スキル以外の質問は控える
派遣社員の緊張を和らげようとアイスブレイクを挟むこともあると思いますが、不用意にプライベートに関する質問をしないようにしましょう。
例えば、以下のような質問はNGです。
- ご結婚はされていますか?
- ご主人は何のお仕事をされているのですか?
- お子さんはいらっしゃいますか?
- お子さんは今おいくつですか?
- これからご出産の予定はありますか?
- 子どもができてもお仕事を続ける予定はありますか?
- ご両親とはご一緒にお住まいですか?
- 前職は何が理由で退職されたのですか?
- 前職での雇用形態を教えてください
- 長期の休みには何をして過ごすことが多いですか?
- 趣味は何ですか?
履歴書やエントリーシートなどへの記入を求めない
職場見学への履歴書の持参、職場見学当日のエントリーシートなどへの記入や筆記試験の受験を要求することはできません。
代わりに、派遣会社が用意する「スキルシート」を通じて保有資格やこれまでの実務経験を確認できます。スキルシートとは、一般的な履歴書のフォーマットから住所や連絡先などの個人情報をなくし、保有資格や経験してきた業務内容など「仕事に必要なスキル」だけを記載したものです。
基本的には、こちらのスキルシートを確認しながら質疑応答を行います。スキルシートでは確認できなかった細かい実務経験や業務環境などを質問していきましょう。
なお、紹介予定派遣の場合は、派遣会社を通じて一般的な履歴書やエントリーシートの提出を求めることができます。
職場環境や社内ルールについても説明する
派遣社員が、職場見学後に就業を辞退することは珍しいことではありません。複数の派遣会社から仕事の紹介を受けているなど、さまざまな企業の条件を比較しながら就業先を検討している人が多いためです。
働く場所として安心して選んでもらうためにも、利用可能な福利厚生などについても紹介することをおすすめします。
一例
- ウォーターサーバーやコーヒーの利用ができる
- ロッカーや更衣室、トイレに私物保管スペースがある
- 私物の持ち込みルールなど
細かいことかもしれませんが、派遣社員に伝わっていない場合、「契約と違う」「聞いていた話と違う」ということにもなりかねません。就業後のトラブルとならないように、社内ルールについては、共有しておくと安心です。
職場見学で起こりがちなトラブルと対策

最後に、職場見学で起こりがちなトラブルの事例と、トラブルを防止するために気をつけるべきポイントを解説します。
人事から聞いていた業務内容と相違がある
最もよくあるケースが、人材派遣の依頼をかけた人事担当者が伝えた業務や必要なスキルに関する内容と、現場の話とが異なるケースです。
<トラブルになりやすい相違の例>
- 業務内容の範囲が違う
- 簡単なエクセルスキルと聞いていたのに、関数を多用する
- 電話対応がないと聞いていたが、問い合わせ対応も依頼された
- Excelのスキルを活かせると聞いていたのに、使用場面が少なそう
- 英語を使うと聞いていたのに、「必要ない」と言われた
認識していた業務内容に相違があると、求めるスキルをそもそも持っていない人が派遣され、業務に支障がでたり、派遣社員の早期離職を起こしてしまいます。また、自身のスキルを活かしたい派遣社員の場合、業務内容の不一致が原因で職場見学後に辞退されることも珍しくありません。
まずは、人材派遣を依頼する前に現場部門と依頼内容に相違がないかを確認することが大切です。職場見学では、採用担当者だけでなく、該当部署で一緒に働く上長や一緒に働くメンバーが同席し、認識にずれがないか確認することで対策しましょう。
勤務条件や契約内容が違う
勤務条件や契約内容の相違も職場見学で発覚することがあります。特に勤務時間や残業時間は、派遣社員の給与に直結することなので、相違がないように確認しておきたいところです。
<トラブルになりやすい相違の例>
- 残業がないと聞いていたのに、月末にかなり発生する
- 残業が20時間ほどあると聞いていたが、ほぼ発生しない
- 長期の仕事と聞いていたが、3カ月で終わると言われた
- 出張があるとは聞いていない
- 年末年始も出勤してほしいと言われた
職場環境についても相違がでることも
派遣社員のなかには、業務内容や契約内容だけでなく、職場環境を重視する人もいます。派遣会社から聞いていた話と実態が異なる場合、辞退につながることもあります。
<一例>
- カジュアルな服装で勤務と聞いていたが、ジャケット着用と言われた
- 在宅勤務ができると聞いていたが、派遣社員は対象外だった
- 同じ仕事をする人がいると聞いていたが、実際には一人でやるみたいだ
職場見学では、業務内容だけでなく、確認の意味を含めて勤務条件なども派遣先・派遣社員・派遣会社の三社で確認しておくと安心です。
契約に影響する社内ルールがあった
契約に影響する社内ルールが実はあった、というのもトラブルになります。
<トラブルになりやすい相違の例>
- 9時始業だが、8時55分に朝礼が始まる
- 社員も含め、当番制でゴミ捨て作業がある
- 会社カレンダー以外に部門で有給奨励日があり、派遣社員にも休んでほしい
例えば、朝礼が8:55からある場合、「契約時間は8:55から」となります。朝礼は派遣社員に限らず、労働時間とされることが多いです。あらかじめ伝えており、契約も8:55開始となっていれば問題ありません。
ゴミ捨ても業務となるため、事前に伝えていなかった場合、「聞いていない」とトラブルになります。派遣は業務内容を明確に契約に示す必要があるため注意が必要です。
現場担当者が「職場見学」を理解していない
現場が職場見学の意図を理解していない場合、不適切な質問をしてしまい、「面接の場だったのでは」「個人的なことを聞かれて不快だ」とトラブルになる可能性がでてきます。
派遣先が派遣社員を選ぶことは派遣法で禁止されていることをしっかり担当者に伝え、職場見学の本来の目的である「派遣社員の業務理解を深める場」であることを理解してもらうようにしましょう。職場見学の注意点をまとめたリーフレットなどを配布するのもおすすめです。
職場見学のトラブル防止に「職場見学の進め方と注意点」ガイドブック
派遣社員の受け入れ前に行う職場見学の流れや注意点をまとめたガイドです。職場見学に不慣れな現場担当者の方でもスムーズに対応できるよう、わかりやすく整理しています。
<この資料でわかること>
・ 職場見学の基本的な進め方
・ 確認しておくべき注意点
・ 当日の対応ポイントやよくある質問

まとめ
職場見学は企業の選考のための機会ではなく、派遣社員の希望による業務理解を深めるための場です。
具体的な仕事内容や職場の雰囲気、就業して身に付けられる経験など、就業先選びの参考になる情報を提供できるよう準備しましょう。このような機会を通して、結果的にミスマッチを防ぐことができます。
また、初めての派遣依頼で職場見学を実施する場合は、派遣会社の担当者に事前に流れなどを確認しておくとよいでしょう。本記事で紹介した注意点なども参考に、ミスマッチを事前に防ぎ、トラブルのない職場見学を実施してみてください。
こちらの資料もおすすめです



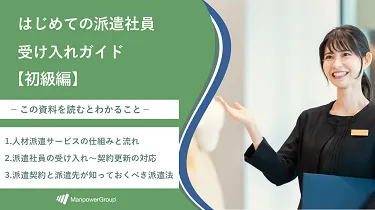
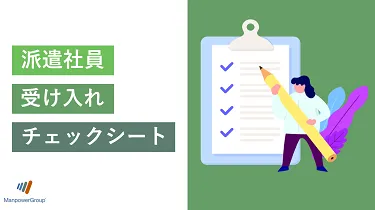
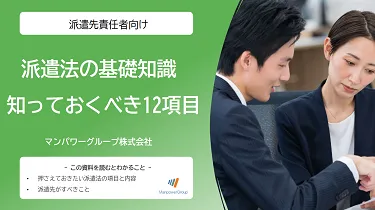

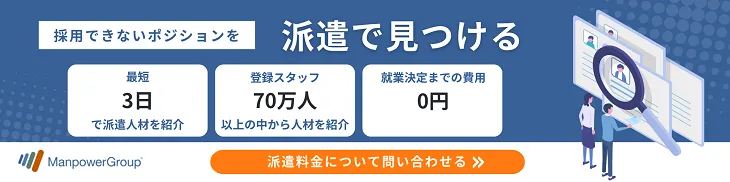

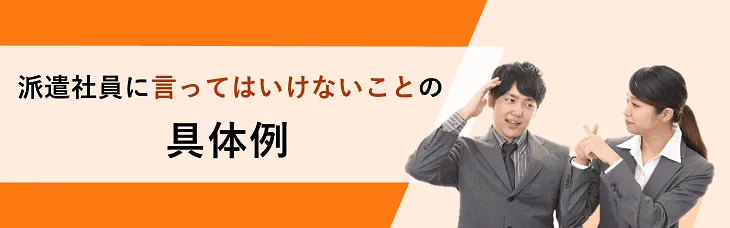
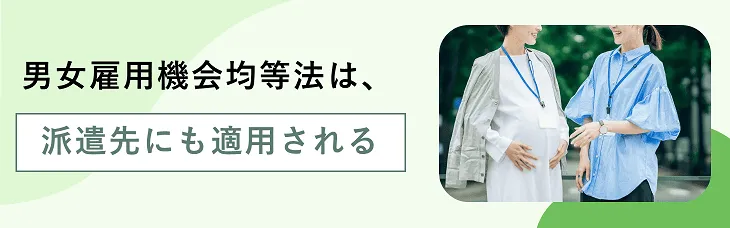
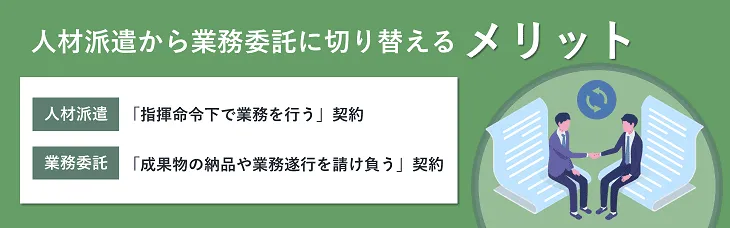
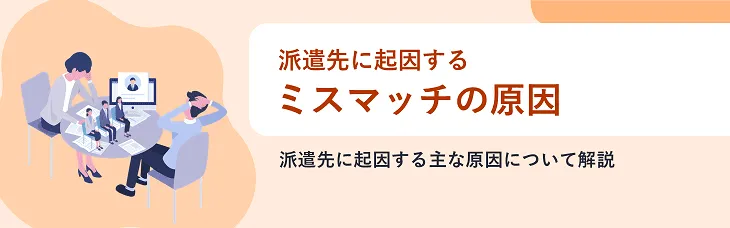
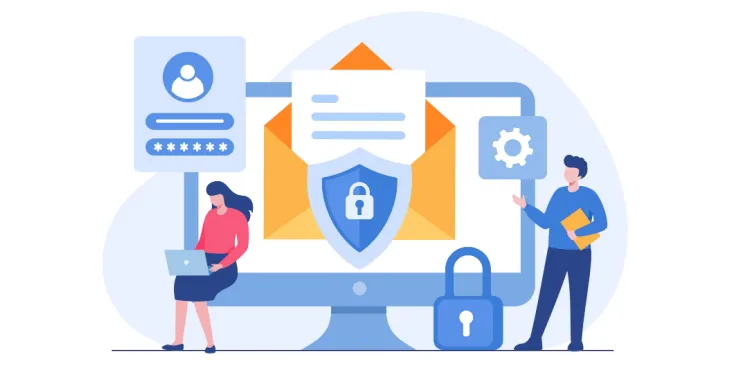
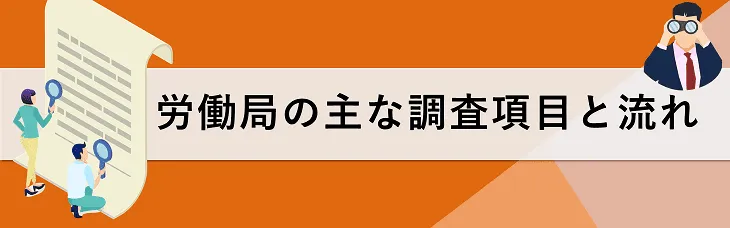






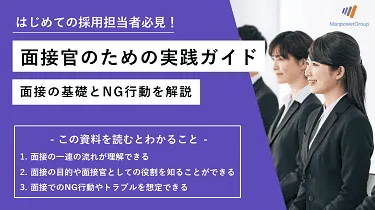

 目次
目次