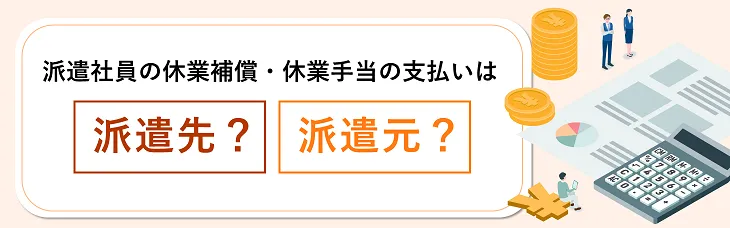


派遣社員の休業補償・休業手当|負担は誰?ケーススタディでわかりやすく解説
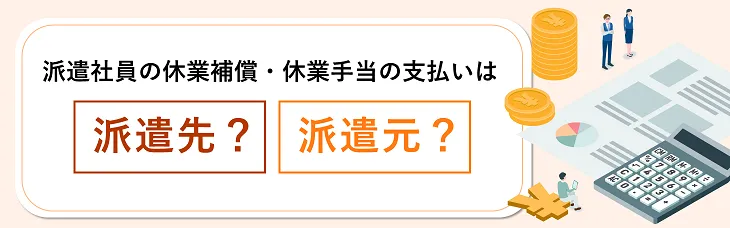
目次
【派遣先責任者向け】派遣法の基礎知識 知っておきたい12項目
派遣法は、派遣会社だけでなく派遣先企業にも責任や努力義務などを課しています。
さまざまなことが派遣法で規定されていますが、派遣先責任者が知っておくべき項目を12つピックアップし、わかりやすく解説した資料をご用意しています。
人材派遣サービスを利用した企業が、諸事情で派遣社員を休業させた場合、休んだ日の賃金補償をどのようにすればいいか、実務上の扱いに迷ったことはないでしょうか。
労働者への休業補償制度には、休業補償、休業手当、傷病手当金などがあり、どの制度を適用させるかも状況によって変わります。本記事では、主に休業補償・休業手当の概要、計算方法、派遣社員への支給、よくある質問について解説します。
休業手当・休業補償とは

休業補償と休業手当は、労働者が就業できず賃金の支払いがない場合、その一部を補てんする制度です。いずれの制度も、正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関係なく、従業員は適用条件に合えば給付を受けられます。
休業補償と休業手当は、制度の趣旨は似ていますが、給付条件や給付額が異なります。それぞれの制度の内容を解説します。
| 休業手当 | 休業補償 | |
| 支払いの理由 | 企業の都合で休業となった | 業務に起因するケガや病気で働けなくなった |
| 支払元 | 企業 | 国(労働基準監督署) |
| 支給額 | 平均賃金の60%以上 | 平均賃金の80% |
| 扱い | 給与所得 | 損害賠償 |
| 税金 | 課税 | 非課税 |
休業手当とは
休業手当は、使用者(企業)の都合により労働者を休ませた場合に企業が労働者に対して支払う義務がある手当のことで、労働基準法第26条に定められています。
休業手当の支給条件
休業手当の支給条件である「使用者(企業)の都合」とは、例えば次のようなケースです。
- 企業の経営不振により労働者を休ませた
- 資材、材料などの不足や電力などのエネルギー供給不足により、工場や事業場の操業ができない
- 稼働場所の機械や設備の故障、点検などにより業務ができない
- 公共交通機関の運行が危ういので、早退させた
休業補償とは
休業補償は、労働災害補償保険法(労災)の制度です。
「仕事中や通勤中にケガをした」「仕事をしたことが原因で病気になった」ことを企業もしくは労働者本人が所轄の労働基準監督署に申請し、認定を受けることで休業補償の対象になります。
つまり、労災で働けなくなったことにより賃金の支給がない場合、休業補償として国から保険の給付があります。
休業補償の支給条件
休業補償を受けるためには、次の条件を全部満たす必要があります。
- 労災による病気やケガでの療養中であること
- 療養中のため働くことができない状態であること
- 企業から賃金の支給がないこと
傷病手当とはどう違う?
傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が病気やケガのために休業し賃金の支払いがない場合に、健康保険から手当が支給される制度です。
休業補償と似ていますが、休業補償は業務中や通勤途中に起因した病気やケガで休業したときに適用される一方、傷病手当金は業務外で病気やケガをして休業したときに適用されるという違いがあります。
また休業手当は、社員が企業の責任で仕事ができないときに賃金が一部補てんされる制度で、病気やケガは対象ではありません。
派遣社員の休業補償・休業手当の支払いは派遣先?派遣元?
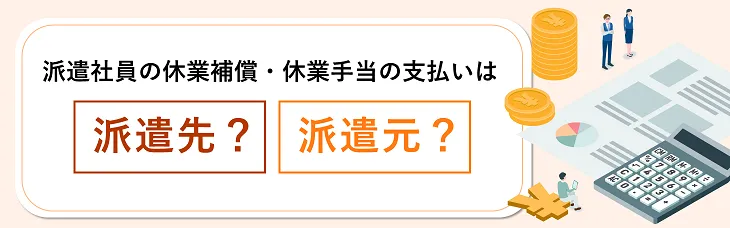
派遣社員が雇用契約を結んでいるのは、派遣先ではなく派遣元です。そのため、派遣先が派遣社員の休業補償の手続きをしたり、休業手当の支払いをしたりすることは原則としてありません。
派遣社員の休業補償
派遣社員の休業補償は、派遣元の労災が適用されます。派遣先で労災事故が起こった場合、派遣先はすみやかに派遣元に連絡します。労災申請の手続きは、派遣元もしくは派遣社員本人が所轄の労働基準監督署に行います。
派遣社員の休業手当
派遣社員の休業手当の支払い義務は派遣元にあります。派遣先の都合で派遣社員に休業手当が発生するケースとして次の2つがあります。
- 派遣契約の期間が満了する前に契約を解除した場合
- 派遣契約の解除はしないが、諸事情で一時的に休業させる場合
(休業の理由がなくなれば職場に復帰させる)
1 の場合、労働者派遣法の定めにより、派遣元が派遣社員に支払う休業手当、解雇予告手当等に相当する額以上の損害賠償額について、派遣先が派遣元に支払う義務があります。
2 の場合は1 と違い、一時休業に関する労働者派遣法の定めはなく、派遣契約の締結内容によります。
派遣契約の事項に派遣社員の休業分に対する補償の定めがあれば、派遣先は派遣元に対して休業手当相当の費用を支払う必要があります。
派遣社員の傷病手当金
派遣社員の傷病手当金は、派遣元で加入している健康保険が適用されます。
派遣社員の休業補償・休業手当のケーススタディ
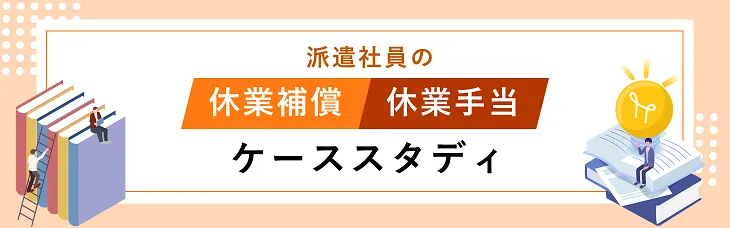
休業手当や休業補償が適用されるか否かをよくあるケーススタディをご紹介します。
- 派遣社員のパフォーマンスが悪いので、契約期間は残っているが、お休みして欲しい場合
- 地震や台風などの自然災害で一時的に休業する必要がある場合
- 業務中の事故やケガで派遣社員がお休みをする場合
- 派遣社員が新型コロナウイルスに感染した場合
- 派遣先の従業員が新型コロナウイルスに感染した場合
- 派遣社員がインフルエンザに感染した場合
- 緊急事態宣言や自治体からの要請によって休業する場合
- 夏季休暇や年末年始休暇の期間中に有給奨励日を設けている場合
派遣社員のパフォーマンスが悪いので、契約期間は残っているが、お休みして欲しい場合
適切な指導を繰り返してもパフォーマンスの向上が見られない場合は、派遣元に連絡の上、別の方との交代を要請できます。派遣社員本人とは雇用関係にないため、派遣先の判断で勝手に解雇したり休業させたりすることはできません。必ず派遣元に連絡しましょう。
その後は、派遣元の担当者が派遣先と派遣社員両方から事情を聞いた上で対処を決めることになります。派遣契約の変更については、社労士が解説!派遣契約の変更・更新・終了に関するルールをご覧ください。
地震や台風などの自然災害で一時的に休業する必要がある場合
自然災害が原因で派遣先が一時的に休業した場合、派遣社員も休業します。その間の派遣費用の取扱いは、あらかじめ派遣先と派遣元で締結していた基本契約の内容によって決まります。もし契約に定めがない場合は、双方で話し合いの上決定します。
業務中の事故やケガで派遣社員がお休みをする場合
派遣社員が派遣先で業務中にケガをしたことが原因で休業する場合、まずはそのアクシデントが起きた時点で派遣先から派遣元に連絡する必要があります。派遣先が派遣元に対して休業補償相当分の費用を支払うことはありません。
しかし、派遣先は派遣元同様に派遣社員の安全配慮義務を負うため、労災が認定された場合、企業の安全配慮義務違反として派遣社員から損害賠償を請求されるケースもあります。
また、派遣社員が派遣先の業務が原因で新型コロナウイルスに感染した場合、業務中に発生したケガなどと同様に労災が認定される可能性があり、その場合は派遣元企業で加入している労災の休業補償の対象となります。
派遣社員が新型コロナウイルスに感染した場合
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが2類感染症から5類感染症に変更されたため、感染症法の定めによる出勤停止扱いがなくなりました。
従って、新型コロナウイルスに感染したり、発熱などの症状があるなど派遣社員を派遣先の自主的な判断で出勤停止にした場合、企業側都合の休業にあてはまるので派遣元が休業手当を支払うことになります。
また派遣社員が感染を懸念して自主的に仕事を休んだ場合は、派遣先の命令による休業ではないので、欠勤扱いになります。
派遣先の従業員が新型コロナウイルスに感染した場合
濃厚接触者となった、もしくは新型コロナウイルスに感染した疑いがある派遣社員は、法律の定めによる出勤停止の対象には該当しません。
派遣先の社員が新型コロナウイルスに感染し、派遣先が濃厚接触者として派遣社員を出勤停止にした場合は、企業側都合の休業にあてはまるので派遣元が休業手当を支払うことになります。
派遣先が派遣元に支払う補償額については、派遣契約を解除する場合は労働者派遣法に定めた額以上を支払う必要があり、一時的休業の場合は派遣契約の締結内容もしくは派遣先と派遣元との協議により決めます。
また派遣社員が感染を懸念して自主的に仕事を休んだ場合は、派遣先の命令による休業ではないので、欠勤扱いになります。
派遣社員がインフルエンザに感染した場合
派遣社員がインフルエンザに罹患した場合、その種類が新型インフルエンザか季節性インフルエンザかによって休業手当の有無が変わります。
新型インフルエンザに罹患した場合、感染症法の定めにより出勤停止扱いになるため、休業手当の対象にはなりません。
一方、おもに冬の時期などに流行する季節性インフルエンザは感染章法の定めによる出勤停止対象になっていません。派遣社員を休ませる場合、派遣先の自主的な判断に基づくものとして扱われるため、派遣元が休業手当を支払う必要があります。
この場合、派遣先の都合となるため、派遣先は派遣元に対して休業手当相当の費用を支払う可能性があります。
緊急事態宣言や自治体からの要請によって休業する場合
緊急事態宣言や自治体からの休業要請は、あくまでも「お願い」であって「休業しなければならない」というような義務ではなく、休業は企業の自主判断によってなされたものとして扱います。したがって、派遣社員が休業した場合は、派遣元が休業手当を支払うことになります。
一時的休業の場合の補償については、派遣契約の締結内容もしくは派遣先と派遣元との協議により決めます。
夏季休暇や年末年始休暇の期間中に有給奨励日を設けている場合
派遣先が夏季休暇や年末年始休暇の前後などに、有給奨励日を設け、実質的に全従業員が休む運用をしているケースは、注意が必要です。
この場合、有給取得はあくまでも奨励であり、会社の休日ではないため、派遣社員を強制的に休ませることはできません。派遣社員が自主的に有給を取得した場合は有給扱いとなりますが、取得を希望せず、かつ出勤できる業務がない場合は、派遣先都合による休業とみなされ、休業手当の支給対象となる可能性があります。
こうしたトラブルを防ぐためにも、派遣契約開始前に、有給奨励日の取扱いや就業可否、会社カレンダー等について、派遣会社と十分に情報共有しておくことが重要です。
派遣先が知っておきたい派遣法とは
派遣先担当者が知っておきたい派遣法の12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。
<この資料でわかること>
・ 派遣先が押さえておきたい項目
・ 派遣法の概要と注意事項
・ 派遣先がすべきこと

休業補償・休業手当の支給額の計算方法

ここでは派遣社員に限らず、休業補償や休業手当の支給額の原則的な計算方法を、具体的な例をあげて説明します。
休業補償の計算方法
休業補償を計算する手順は次のとおりです。
1. 給付基礎日額を算出する
給付基礎日額は原則、労働基準法に定められた平均賃金の計算式に基づきます。
平均賃金の計算式は、ケースによって次のアからウのいずれが採用されます。
ア)【労災事故が発生した日(※)の直前3か月間に支払われた賃金総額(通勤手当などの諸手当も含む・ただし賞与は除く)】 ÷ 【その期間の暦日数】
イ)【労災事故が発生した日(※)の直前3か月間に支払われた賃金総額】 ÷ 【その期間の労働日数】 × 60%
ウ)給付基礎日額の最低保障額(令和3年8月1日時点3,940円)
※賃金締切日が決まっているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間に支払われた賃金総額(通勤手当などの諸手当も含む・ただし賞与は除く
社員の賃金が月給制の場合はア、日給・時給・出来高制の場合はアからウの中で最も給付額が高い計算式を採用します。
2. 1日あたりの休業補償額を計算する
休業補償額は、給付基礎日額の80%(休業補償給付が60%・休業補償特別支給金が20%)です。
3. 2で算出した額×休業日数で休業補償の総額を計算する
休業補償は、休業4日目から病気やケガにより休業している期間で支給されます。ただし、ケースによっては1年6か月が経過した日に休業補償から労災の傷病(補償)年金に切り替わることもあります。
休業補償の計算例
1. 毎月末日を賃金締切日とする企業で月給30万円(諸手当含む)の社員が、8月20日から休業した場合
給付基礎日額
30万円 × 3か月 ÷ 92日(5月・6月・7月の暦日数) = 9783円(1円未満切り上げ)
1日当たりの休業補償給付額
5869円 + 1956円 = 7825円
(内訳)
保険給付:9783円 × 0.6= 5869円(1円未満切り捨て)
特別支給金:9783円 × 0.2 = 1956円(1円未満切り捨て)
休業補償の総額
7825円×休業した日数で計算する
2. 毎月末日を賃金締切日とする企業で、日給1万円(通勤手当を含む)、5月・6月・7月の3か月の労働日数が合計30日の社員が、8月20日から休業した場合
給付基礎日数
アの場合:30万円 ÷ 92日 = 3261円
イの場合:30万円 ÷ 30日 × 0.6 = 6000円
ウの場合:最低保障額3940円
よって今回のケースではイの6000円を採用する
1日当たりの休業補償給付額
3600円 + 1200円 = 4800円
(内訳)
休業補償給付:6000円 × 0.6 = 3600円
休業補償特別給付金:6000円 × 0.2 = 1200円
休業補償の総額
4800円 × 休業した日数で計算する
休業補償の計算での注意点
休業日数は待機期間の経過後から起算され、待機期間中は労災での休業補償の対象にはなりません。しかし、業務災害の場合は労働基準法により、事業主が1日につき平均賃金の60%以上の休業補償をする義務があります。なお、通勤災害の場合は事業主の休業補償義務はありません。
休業中にも拘わらず、労働者に1日当たり平均賃金の60%以上の賃金を支払った場合、その日の休業補償は支給されません。
休業手当の計算方法
休業手当の計算方法は下記のとおりです。
1. 1日あたりの平均賃金を算出する
平均賃金は休業補償の「給付基礎日額」の計算方法と同じです。
2. 1日あたりの休業手当額を計算する
休業手当額は平均賃金の60%です。
ただし、この額は労働基準法で決められた最低基準額です。最低基準額未満の休業手当を支給した場合は労働基準法違反となるので、最低基準額まで引き上げる必要があります。就業規則で最低基準額以上の手当額(例:平均賃金額の80% など)を定めている場合は、その額で計算し支給します。
3. 2で算出した額×休業日数で休業手当の総額を計算する
休業手当の支給日数の上限はありません。
休業手当の計算例
1. 毎月末日を賃金締切日とする企業で、月給30万円(諸手当含む)の社員が8月20日から休業した場合
平均賃金額
30万円 × 3か月 ÷ 92日(5月・6月・7月の暦日数)=9782円(1円未満端数切り捨て)
1日あたりの最低休業手当額
9782円 × 0.6 = 5869円(1円未満の端数 50銭未満切捨て、50銭以上切上げ)
休業手当の総額
5869円 × 休業した日数で計算する
2. 毎月末日を賃金締切日とする企業で、日給1万円(通勤手当を含む)、5月・6月・7月の3か月の労働日数が合計30日の社員が、8月20日から休業した場合
給付基礎日数
アの場合:30万円 ÷ 92日 = 3261円
イの場合:30万円 ÷ 30日 × 0.6 = 6000円
ウの場合:最低保障額3940円
よって今回のケースでの給付基礎日額は6000円です。
1日あたりの休業手当額
6000円 × 0.6 = 3600円
休業手当の総額
3600円 × 休業した日数で計算する
出典:休業手当の計算方法|山形労働局(PDF) ![]()
休業補償・休業手当は課税される?
休業補償は労働基準法8条による「災害補償」の扱いなので、所得税はかかりません。一方、休業手当は所得扱いとなり、賃金や賞与と同じく所得税の対象です。そのため、休業手当を支給した社員には源泉徴収が必要です。
まとめ
派遣社員が休業した場合、その理由によっては休業補償や休業手当の対象者に該当することがあります。派遣先が派遣社員に直接休業補償や休業手当を支払うことはありませんが、特に昨今は、大規模な自然災害や感染症などが増加しています。
適切な対処をするためにも、派遣契約を締結する際には派遣社員が休業した場合の補償額などの取り扱い事項をよく確認し、労働者派遣法などの定めに抵触しないようにしましょう。
こちらの資料もおすすめです

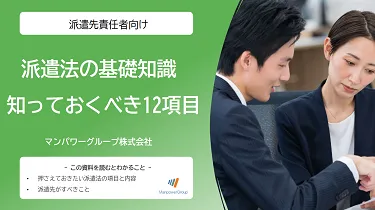
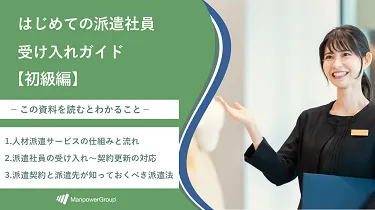


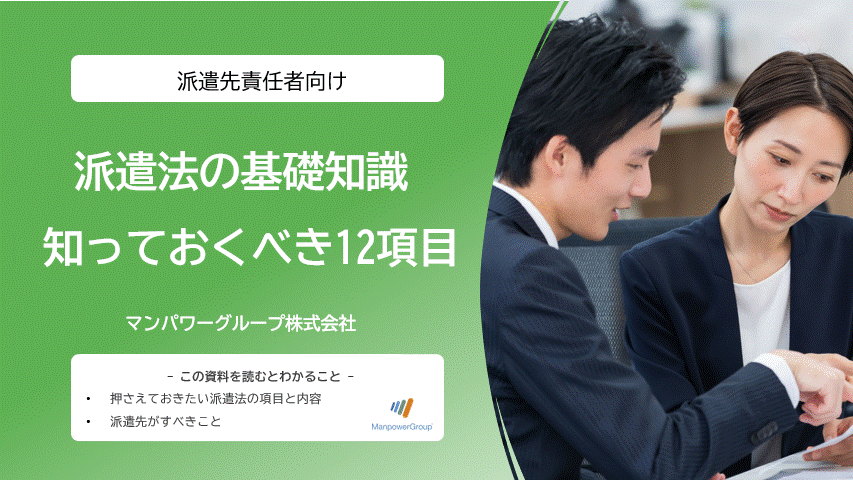

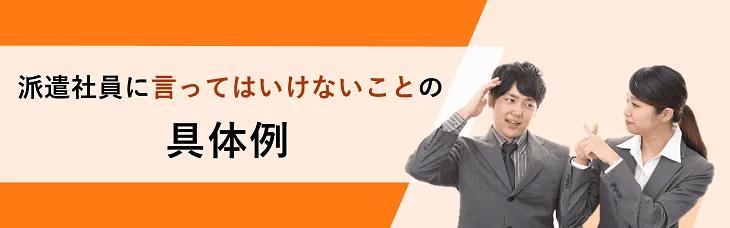
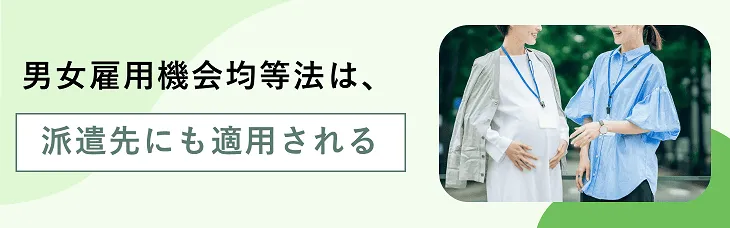
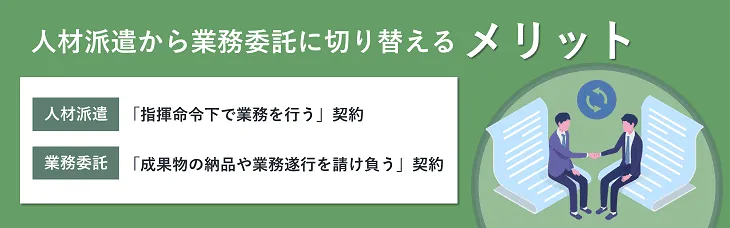
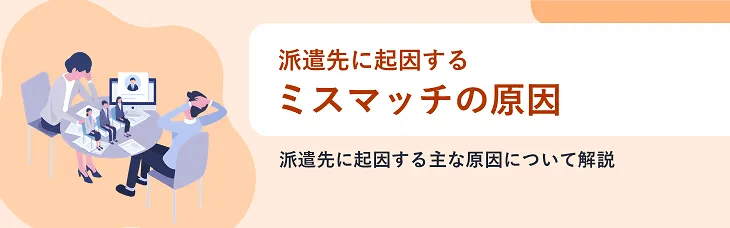

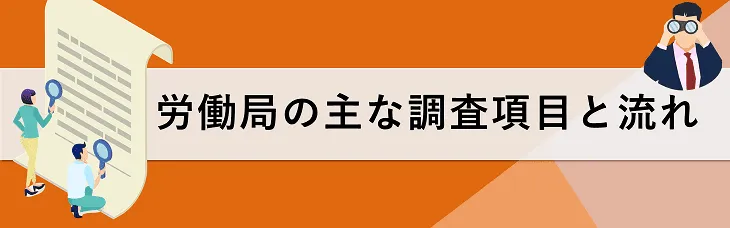






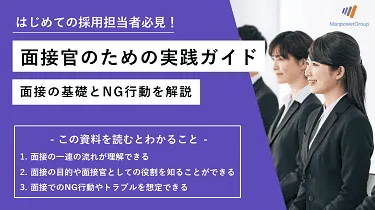

 目次
目次