


社労士が解説!派遣契約の変更・更新・終了に関するルール

目次
【派遣先責任者向け】派遣法の基礎知識 知っておきたい12項目
派遣法は、派遣会社だけでなく派遣先企業にも責任や努力義務などを課しています。
さまざまなことが派遣法で規定されていますが、派遣先責任者が知っておくべき項目を12つピックアップし、わかりやすく解説した資料をご用意しています。
新型コロナウイルス感染拡大の影響が長引く中、雇用情勢はまだまだ厳しいものがあります。この状況下、既存の派遣契約を見直す動きが非常に大きくなっています。雇用の調整をしやすいと考えられがちな派遣社員ですが、派遣契約については正社員とは違ったルールがあり、このルールに反すると様々なトラブルを招きかねません。今回は、このルールについて解説します。
派遣契約が締結できる期間
派遣契約については、原則として3年が限度となっています。派遣開始日から3年を超えて派遣を行うと労働者派遣法に抵触することになります。派遣開始日から3年を超えた最初の日を「抵触日」といいます。
「抵触日」は、事業所単位と個人単位の2種類があります。事業所単位は、初めて派遣社員を受け入れた日から3年が限度となります。但し、これは、抵触日の一ヶ月前までに当該事業所の労働者過半数労働組合または過半数代表者の意見聴取を行えば延長可能です。この手続きは回数の制限がないため、この手続きを繰り返すことにより、いつまでも派遣労働者を受け入れることが可能となります。
対して、個人単位の抵触日は、事業所内の組織単位に派遣された日から3年となります。「組織単位」とは、業務の類似性・関連性があり、組織の長が業務配分・労務管理上の指揮監督権を有するものをいい、「部」「課」といった単位がこれにあたります。個人単位では延長手続きはなく、個人単位の抵触日を迎えると、同じ派遣社員を同一組織で受け入れることはできません。但し、同一事業所内でも組織単位が変われば、同じ派遣社員を受け入れることが可能です。
但し、下記については期間制限の例外とされ、抵触日は適用されません。
- 派遣元に無期雇用される派遣労働者
- 60歳以上の派遣労働者
- 産休・育児休業・介護休業中の社員の代替要員として派遣される派遣労働者
- 就業日数が限定された業務に派遣される派遣労働者(1か月あたりの就業日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下)
- 終期があらかじめ決まっているプロジェクト業務に派遣される派遣労働者
また、日雇派遣は原則として認められませんが、例外的に下記の場合のみ認められています。
- 適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認められる業務
(ソフトウェア開発、機械設計、事務用機器操作、通訳・翻訳・速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、受付・案内、研究開発、事業の実施体制の企画・立案、書籍等の制作・編集、広告デザイン、OAインストラクション、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 - 60歳以上の派遣労働者
- 雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)
- 年収500万円以上で副業として日雇派遣に従事する者
- 世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者でない者
派遣契約を更新または終了する場合の注意点
労働者派遣法第26条により、派遣期間を明確に設定することが必要です。そのため、労働者派遣契約については、自動更新は認められません。更新の都度、新たに契約を締結し直す必要があります。
派遣契約を更新する際は、抵触日の確認も大切です。これを怠り、抵触日を超えて派遣を受け入れると、違法派遣となり「労働契約申し込みみなし制度」の対象となる可能性があります。これは、派遣先が当該派遣労働者について、派遣元の労働条件と同じ労働条件での直接雇用の労働契約の申し込みをしたものとみなされる制度です。
雇止めについては、派遣契約が複数回更新され、次の契約満了時にも派遣契約が当然更新されるものとの期待がある中での契約満了は、違法な雇止めとされる可能性があります(労働契約法第19条)。具体的には、当該派遣契約を3回以上更新するか、派遣期間が1年を超えて継続した場合となります(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準第1条)。
なお、派遣契約につきましては、文書であるか否かを問いません。そのため、口頭での契約でも成立することになります(労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和3年1月1日以降)第5章1(1))。ですが、派遣則第21条第3項により、派遣契約の内容については書面に残すことになっています。この書面は、必ずしも契約書でなくても構いませんが、トラブル防止のためにも記載すべき内容を盛り込んだ契約書を取り交わすことが一般的です。
派遣契約を途中で解除または変更することは可能か
派遣契約は、基本的に契約期間の途中で解除することはできません。有期雇用契約を途中で解除できるのは、やむを得ない事由がある場合に限られますが(民法第628条、労働契約法第17条第1項)、この事由とは、客観的に見て合理的であり、社会通念上相当と認められるものとされており、解雇権の濫用にあたるようなものは当然認められません。
とはいえ、経営難による事業縮小等の予期せぬ理由により、派遣契約を途中解除せざるを得ない場合もあり得ます。その場合、派遣先は、派遣元と協議しつつ様々な措置を講じる義務が生じます(派遣法第29条の2)。派遣先に義務付けられた措置は、次のように定められています(派遣先が講ずべき措置に関する指針第2の6)。
- 派遣先の関連会社等、代わりの就業先を斡旋すること。
- 派遣契約の途中解除により派遣社員への休業手当が発生した場合、支払義務者である派遣元に対して、休業手当相当額以上の損害賠償を行うこと。
- 派遣先への途中解除の申し入れは、相当の猶予期間(少なくとも解除日の30日以上前)をもって行うこと。
- 派遣契約の途中解除により派遣元が派遣社員を解雇せざるを得ず、派遣社員への解雇予告手当が発生した場合、支払義務者である派遣元に対して、解雇予告手当相当額以上の額の損害賠償を行うこと。
- 派遣元から求めがあった場合、当該派遣契約の途中解除理由の明示を行うこと。
- その他善後処理方策を講じること。
この指針に反した場合、派遣先は労働局の指導対象となることがあり得ます。
また、令和3年1月1日からは、日雇派遣においても、派遣契約の解除を受けて、代わりの就業先の確保ができない場合は、その日を休業として扱い休業手当を支払う等、日雇派遣労働者に対しても労働基準法に基づく責務を果たすべきことが明確化されました(日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針第2の5(2))。
一方、派遣契約の途中で契約内容を変更することは、派遣先と派遣元との間で協議の上、派遣元と派遣社員との間で合意があれば可能です。派遣社員の担当業務や勤務時間、就業場所等に変更が必要となった場合は、派遣先は派遣社員と直接協議せず、派遣社員の雇用主である派遣元を通じて行うことが必要です。
派遣先が知っておきたい派遣法とは
派遣先担当者が知っておきたい派遣法の12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。
<この資料でわかること>
・ 派遣先が押さえておきたい項目
・ 派遣法の概要と注意事項
・ 派遣先がすべきこと

まとめ
ここまでお話したように、派遣契約の途中解除については、相当の理由がない限りは行うことができません。例えば、契約解除の理由が事業縮小である場合でも、単に事業縮小であるだけでは足りず、雇用の継続が困難となる経営難等の深刻な理由が求められます。どうしてもやむを得ない場合、派遣元との連携による措置が必要となってきます。
そのため、派遣契約の存続が危ぶまれる事由が発生した場合は、派遣契約の解除を決定する前に、早めに派遣会社に相談して下さい。
こちらの資料もおすすめです




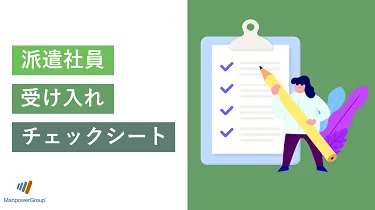
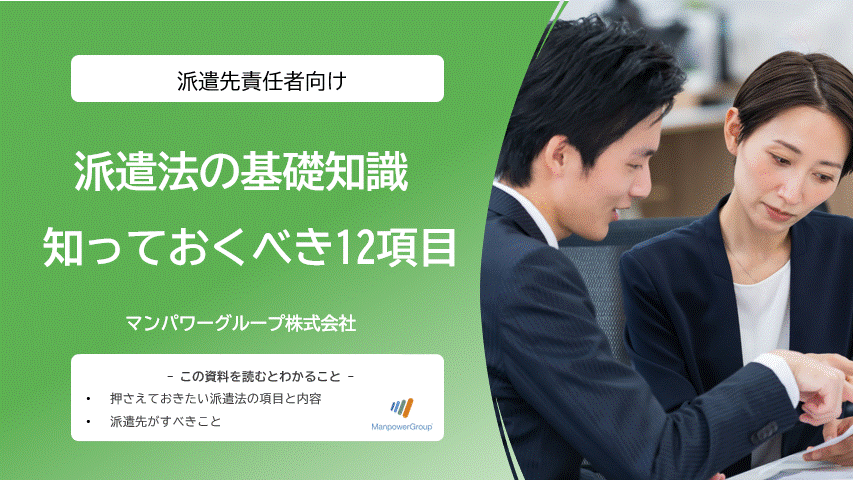






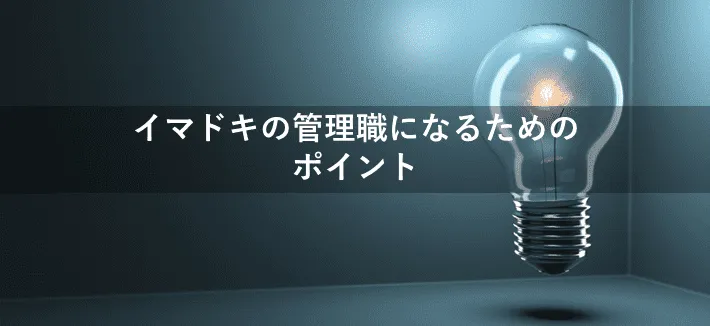








 目次
目次