


「派遣社員の管理」派遣先に求められる対応とポイントを解説

目次
派遣サービスを利用する企業が増えていますが、派遣社員を受け入れるにあたり、派遣先企業にどのような責任があり、どのような対応が必要なのかというご相談を数多くいただきます。
本コラムでは派遣先企業に求められる派遣社員の管理について解説します。
関連記事
派遣法のこれまでの改正内容および、企業担当者が気を付けたいポイントについては、「【2022年最新】労働者派遣法 改正の歴史早見表│違反しないためには」でも解説しています。
派遣社員の受け入れ準備に使えるチェックシート
派遣社員受け入れ時に必要な準備について、人事担当者向け・受け入れ先部門向けチェックシートをそれぞれご用意しました。
受入体制が不十分だと、早期離職に繋がりかねません。もれなく対応できているかどうかのチェックにご活用ください。
派遣法で定められている派遣管理に関する役割とは
雇用している企業と就業している企業が異なる派遣社員が適正に就業できるよう、労働者派遣法ではいくつかのポジションを派遣先企業内で選任するように定めています 。それぞれのポジションの役割や責任について解説します。
派遣先責任者
派遣先責任者とは、派遣社員の適正な就業を確保する責任者です。指揮命令者や苦情処理担当者を指導しながら、派遣社員の就業管理の責任を負う重要な役割 です。事業所単位で、派遣社員100名につき1人以上ずつ選任します。
選任の要件
- 労働関係法令に関する知識を有する者
- 人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者
- 派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者
- 派遣社員と同一の就業場所にいる者
役割
- 指揮命令者や関係者全てに派遣法や労働基準法などの規定、派遣契約の内容、派遣会社からの通知などを周知
- 派遣受け入れ期間の管理、変更通知
- 均等均衡待遇の確保
- 派遣先管理台帳の作成・通知
- 派遣社員からの申し出があった苦情への対応
- 安全衛生教育・健康管理
- 派遣会社との連絡業務全般
関連記事
派遣先責任者の選任要件や条件などは「派遣先責任者とは?役割や留意点を解説」で詳しく説明をしています。
指揮命令者
指揮命令者とは、就業している派遣社員に業務指示をする役割です。派遣社員の上司的役割を担うので、必要に応じて派遣先責任者と連携し、情報共有や問題解決に努めます。
選任の要件
- 同一部署に所属する人。業務内容を理解しており、指示できる者
- 派遣先責任者との兼任は認められている
- 居場所が明確でいつでも連絡が取れるのであれば、派遣社員と同一の就業場所である必要はない
役割
- 派遣会社と締結した契約内容に基づき、業務指示を出す
- 派遣社員の業務内容、就業日・時間が派遣契約に則しているかを適宜確認
- 勤怠管理
- 就業環境が適正であるかのチェック
関連記事
指揮命令者の選任要件や条件などは「【人材派遣】指揮命令者とは?役割と注意点を解説」で詳しく説明をしています。
苦情処理担当者
苦情処理担当者は、派遣社員からの就業に関する苦情を受け、対応する役割を担います。
派遣先の講ずべき指針では「派遣社員から苦情を受けたら、速やかに派遣会社へ通知し、連携して解決を図らなければならない」とあります。そのため、派遣社員からの苦情の申し出を受けた際に遅延なく適切に対応するために、担当者を派遣契約に明示し、苦情処理体制が派遣社員にもわかるようにする必要があります。
選任の要件
- 指揮命令者が苦情処理担当者を兼務することは望ましくない
- 派遣先責任者が兼任することは可能
- 人事・労務管理等について専門的な知識を有する者
役割
- 苦情を受けた際は、速やかに関係者と派遣会社に連携
- 受けた苦情は、主体的に誠意をもって対応(2021年派遣法改正により、派遣先も主体的に対応することが義務付けられました)
- 派遣先管理台帳に苦情の内容、対応などを記載
関連記事
指揮命令者の選任要件や条件などは「【人材派遣】派遣先苦情申出先担当者とは?役割と注意点を解説」で詳しく説明をしています。
派遣先が講ずべき措置とは?派遣法で定められている10の指針
派遣サービスを利用する場合、受け入れる側の企業にも対処すべきことが派遣法では定められています。上記の派遣先責任者の選任を含め、派遣先が講ずべき措置として、以下の10の指針が出されています。
- 労働者派遣契約に関する措置
- 適正な派遣就業の確保等のための措置
- 派遣先による均衡待遇の確保
- 派遣先の事業所単位の派遣期間の制限の適切な運用
- 派遣労働者個人単位の期間制限の適切な運用
- 派遣労働者の雇用の努力義務
- 派遣先での常用労働者(いわゆる「正社員」)化の推進
- 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止
- 派遣先責任者の選任
- 派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び記載事項の通知
理解が難しいこの10の指針をわかりやすく解説した資料をご用意しています。
ぜひご覧ください。
派遣先に求められる5つの管理項目と対応方法
派遣社員の雇用主は派遣会社ですが、受け入れるにあたり派遣先企業にも管理責任は発生します。派遣先企業として管理しなければいけない管理項目について解説します。
勤怠管理
出勤・欠勤状況の把握は派遣先企業の責任です。派遣社員の健康管理はもちろんのこと、派遣社員の就業時間に応じて派遣料金が変動するので、派遣社員の労働時間を適切に管理する必要があります。
対応方法
派遣社員の勤怠管理は、出欠簿の用紙、打刻・勤怠管理システムなどの様式は問われませんが、派遣社員が稼働した日の開始時間・休憩時間・終了時間・残業時間などが記録できるよう整備します。
時間外労働時間の上限は派遣会社が締結している36協定の範囲内となります。依頼できる時間外労働時間は締結している派遣契約の内容で確認しておくようにしましょう。
就業開始前には想定していなかった休日出勤の可能性がでてきた場合には、事前に派遣会社に可能かどうか相談しておく必要があります。また有給休暇の取得義務は派遣社員も対象になります。派遣社員が休暇を取得しやすいよう派遣先企業は業務量の調整などを行い、派遣会社が適切に有給休暇を派遣社員に与えられるような配慮が必要です。
派遣先企業には勤怠情報などを、月に1回以上、派遣会社へ報告する義務があります。また、派遣会社から問い合わせがあった場合にも、すぐに応じられるようにしなければなりません。
業務指導・指示
派遣先企業は、「業務に関する指揮命令者」を定め、派遣社員に業務指示を行います。派遣契約で定めている業務以外の業務を行うことは法律で禁じられています。派遣社員が契約外の業務を行わないように管理する必要があります。
対応方法
派遣社員の就業開始が決まったら、所属する部門や関連部門の関係者に「指揮命令者は誰か」、「どのような業務を担当するか」などを事前に周知し、契約外の業務を指示することがないようにします。
また指揮命令者は派遣社員が円滑に業務をはじめられるように、手順を示したマニュアルの整備や就業開始後の研修、各業務の指導係の任命などについても必要に応じて準備します。業務内容の不明点や社内ルールなどで派遣社員が戸惑わないように整備しておきます。
自社内ではあたり前の事でも、雇用主が異なる派遣社員にはあたり前ではないことが沢山あります。適切に業務指示をすることで派遣社員の良いパフォーマンスが期待できます。
関連記事
派遣社員が就業開始する際の受け入れポイントは「派遣社員を受け入れるときに知っておきたい注意点」で詳しく解説しています。
安全管理と健康・衛生管理
派遣社員の就業に伴う安全管理や衛生管理の責任は派遣先企業にもあるため、派遣社員が安心して業務に取り組める環境を整える必要があります。
対応方法
作業スペースの確保、業務に適した空調、室内の明るさなど、自社の従業員と同様の配慮が必要です。更衣室(ロッカー)やリフレッシュルームなどの福利厚生施設も、自社の従業員と同様に利用ができるようにします。また、災害時の避難方法や安否確認などのルール・情報も伝えるようにしましょう。
健康診断は派遣会社に実施義務がありますが、業務における健康・衛生管理は、派遣先にも配慮が求められます。適切な休憩時間が確保できているか、健康に害を及ぼすような原材料などを取り扱いさせていないか、などを注意しておきます。
2020年改正労働者派遣法において、派遣社員の不合理な待遇差をなくすことが求められるようになりました。
職場環境だけでなく、派遣社員が正当な待遇を受けられるよう、派遣会社の求めに応じて自社従業員の待遇情報や、派遣社員の業務遂行状況などを提供する必要があります。
関連記事
派遣社員の待遇は「同一労働同一賃金とは?派遣社員にはどう適用される?」で詳しく解説しています。
ハラスメント・苦情対応
派遣先企業には、自社従業員と同様に派遣社員にも職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント、障がい者に対するハラスメントなどの防止を図ることが義務づけられています。
対応方法
苦情処理の体制(受付者、対処者)を構築し、派遣社員に説明しておきます。実際に派遣社員から苦情の申し出あった場合は、速やかに解決すると同時に、派遣会社にも連絡します。
また、苦情を申し入れた派遣社員に対して、「業務量を増やす」や「契約終了する」など派遣社員の不利益になる取り扱いは禁止されています。
ハラスメントにあたるかどうか微妙な問題であっても、派遣社員が気兼ねなく相談できる体制づくりが必要です。
契約・抵触日に関する管理
派遣契約には一部例外を除き、派遣期間の制限があります。更新対応や後任を探すタイミングなどもあるため、契約・抵触日の管理はしっかりと行いましょう。
対応方法
契約書や台帳はしっかりと管理します。派遣就業開始時に抵触日通知を派遣会社に提出し、両社で管理しましょう。
<事業所単位の期間制限>
派遣先企業の同一事業所が派遣社員を受け入れられる期間は、原則3年が限度となります。3年を超えて派遣社員を受け入れたい場合は、労働組合などからの意見を聞く必要があります。3年までの間に派遣社員が交替したり、他の労働者派遣契約に基づく労働者派遣を始めた場合でも、派遣可能期間の起算日は変わりません。
<個人単位の期間制限>
派遣社員を受け入れる際、派遣会社と契約を交わしますが、ひとりの派遣社員が同一の組織で働くことができるのは、原則3年です。3年を超える場合、後任の派遣社員を依頼する、もしくは派遣会社で無期雇用の予定があるかを確認します。すでに派遣会社の無期雇用である派遣社員については、この制限を受けません。詳しくは、無期雇用派遣とは?|企業・求職者別にメリット・デメリットを解説で解説しています。
3年満了が決定している場合、「後任が見つからないから」といった理由などで延長はできません。いつまで就業できるのかを確認し、必要な対策を取りましょう。
<個別契約書の管理>
派遣会社と取り交わす派遣契約(個別契約書)の期間は、だいたい3か月くらいです。派遣社員の意思を確認しながら、契約更新を行いますが、個別契約書の30日前までには、更新有無を決定しておく必要があります。
派遣サービスを利用する上で押さえておきたいこと
派遣先担当者が知っておきたい派遣法の12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。
<この資料でわかること>
・ 派遣先が押さえておきたい項目
・ 派遣法の概要と注意事項
・ 派遣先がすべきこと

派遣先管理台帳について
派遣法では派遣先企業に派遣先管理台帳の作成を義務付けています。その台帳作成の目的や記載内容などを解説します。
派遣先管理台帳とは?
派遣先企業が「派遣社員の稼働した日」や「労働時間」といった就業の実態を確実に把握すると同時に、「派遣社員が従事した業務内容」や「申し出のあった苦情内容」など日々、前述にある派遣先企業が管理しなければならないことを記録する台帳です。
台帳は必要事項が記載されていれば、紙でもWebシステムでも問題ありません。派遣社員毎に派遣先管理台帳を作成し、該当派遣社員の契約終了から3年間保存が必要です。
派遣会社に対しては、月に1回以上、管理台帳の内容の一部を通知します。通知方法は、派遣社員毎にFAX、メール、書面のいずれかの方法で行います。また、派遣会社から開示請求があった場合は、速やかに開示する必要があります。
派遣先管理台帳の記載事項
派遣先管理台帳に記載すべき事項は、以下のとおりです。
★の項目が月1回以上、派遣会社に通知が義務づけられている項目です。
- 派遣労働者の氏名(★)
- 派遣元事業主の名称・事業所名・所在地
- 労使協定派遣社員であるか否か
- 「無期雇用派遣社員」か「有期雇用派遣社員」か
- 就業状況(就業日、就業日毎の就業時間・休憩時間)(★)
- 派遣社員が従事した業務の種類・責任の程度(★)
- 派遣就業した事業所の名称・就業場所・組織単位(★)
- 派遣社員から申し出があった苦情の状況
- 紹介予定派遣に関する事項
- 教育訓練を行った日時・内容
- 派遣元責任者名・派遣先責任者名
- 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項(該当する場合に記載)
- 労働、社会保険の被保険者資格取得届の有無
- その他厚生労働省令で定める事項
関連記事
派遣先管理台帳については、「派遣先管理台帳とは?通知必須の6項目・記載必須の17項目を解説」で詳しく解説しています。
派遣社員の管理工数をどう効率化するか
人材派遣サービスには、必要とする期間だけ必要な人材を迎え入れることで、労務管理工数が大幅に削減できるなどのメリットが数多くあります。その一方で、派遣社員や派遣会社の管理は必ず発生します。また、派遣法だけではなく、労働に関する法律を遵守した運営には、管理工数がかかることを理解しておく必要があります。
派遣社員の人数が増えてくると管理工数も膨らむ傾向にあります。最後に、派遣管理工数を軽減する派遣管理デスクについて紹介します。
派遣管理デスクとは
派遣管理デスクとは、派遣サービス利用に関する事務的業務や適切なサービス利用のサポートを請け負うサービスです。
自社で派遣管理の専任を設置する余裕がない、現場担当者の負荷を軽減したい、などの目的で利用されています。
対応業務
主な対応業務例は以下のとおりです。多くの場合、業務内容には企業のニーズに合わせたカスタマイズがされています。
- 派遣会社へのオーダー発注とその管理
- 個別契約の管理(更新確認や内容に関する質問対応など)
- 派遣会社への各種連絡事項の対応
- 派遣管理台帳の管理と確認
- 請求書の内容確認とチェック
- 派遣法に関する相談窓口
- 派遣法改正の対応
- 派遣会社のパフォーマンス分析・評価など
- トラブル対応
派遣管理デスクの導入に向いている企業
多くの派遣社員が働いている場合、契約管理や勤怠管理など人数に比例して工数が増えます。また、多くの派遣会社とやり取りをしていると、派遣会社ごとに個別契約書のフォーマットが異なる、請求書の数が増える、契約管理やコミュニケーションコストがかかるなどの課題があります。
派遣管理デスクは、派遣管理に詳しい人材が対応するため、日常の管理業務の負担軽減だけでなく法改正などへの対応なども安心して任せられるなど、さまざまなメリットがありますが、費用などの発生もあるため、全ての企業に適しているものではありません。
以下のような課題がある場合、派遣管理デスクの導入を検討してみてもよいでしょう。
- 派遣社員が多く、契約管理に不安を感じている
- 常に多くの派遣オーダーがあり、多数の派遣会社と付き合いがある
派遣管理デスクサービスを提供している企業
派遣管理デスクサービスは、人材派遣や派遣法に詳しい企業が対応することが望ましいことから、主に派遣会社がサービスを提供しています。
派遣先企業への常駐型もあれば、非常駐型(メールや電話などで対応)など、サービスの提供形式は様々です。また、派遣社員の管理だけではなく、業務委託先を含めた外部人材の管理を包括的に対応するサービスもあります。
人材派遣のご相談はこちらから
マンパワーグループは、日本で最初の人材派遣会社です。全国68万人以上の登録者から、貴社に最適な人材をご提案いたします。
人材派遣の利用をご検討の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

関連記事
「派遣管理デスクとは メリット・デメリットと対応業務を解説」では、派遣管理デスクの導入事例なども紹介しています。
まとめ
派遣社員は自社従業員とは異なるため、自社従業員には発生しない管理台帳の作成のような管理業務も発生しますが、派遣社員管理の基本となるのは自社従業員と同様の職場環境を提供し、派遣契約を遵守することです。
指揮命令する派遣先企業が派遣契約の内容を理解し、雇用主である派遣会社と密に連携することで、派遣社員は安心して業務に従事することができ、長期的かつ安定した就業が可能になります。
参考:
派遣労働者を受け入れる派遣先として留意すべき点について|大阪労働局 ![]()
派遣労働者を受け入れるに当たって|東京都労働相談情報センター ![]()
派遣労働者の安全衛生対策について|厚生労働省 ![]()
派遣先にも、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます(PDF)|厚生労働省 ![]()
こちらの資料もおすすめです
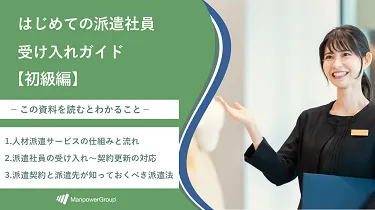

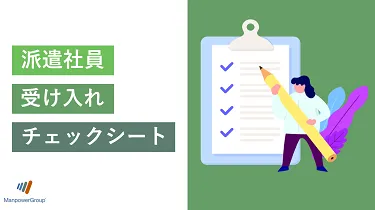

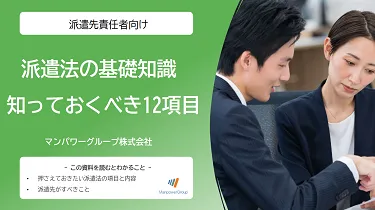


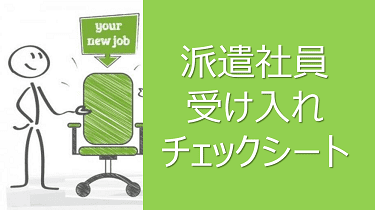
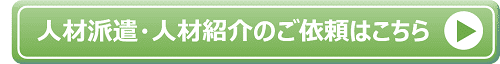

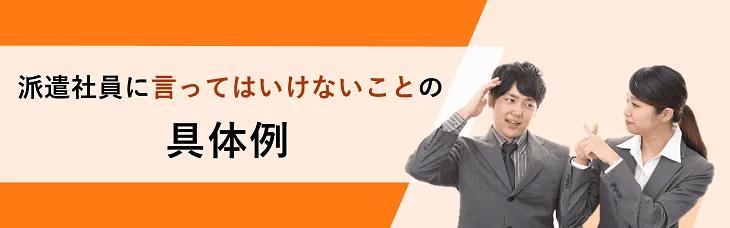
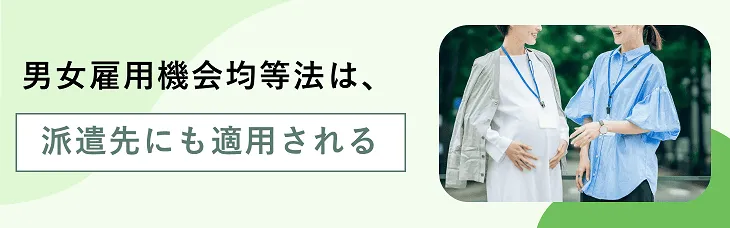
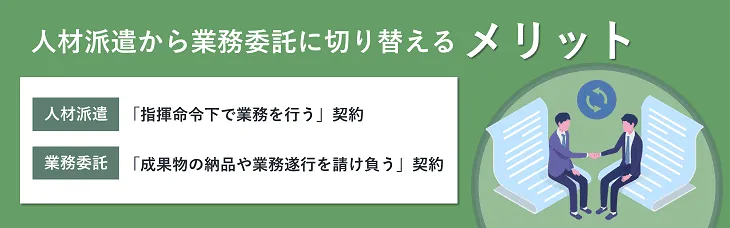
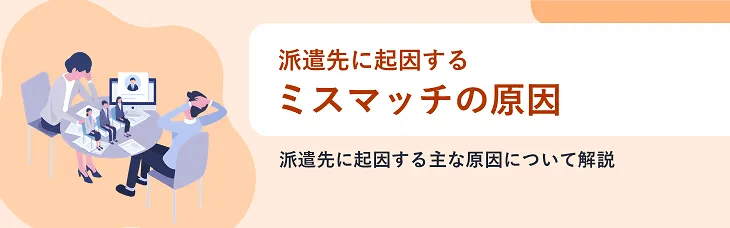

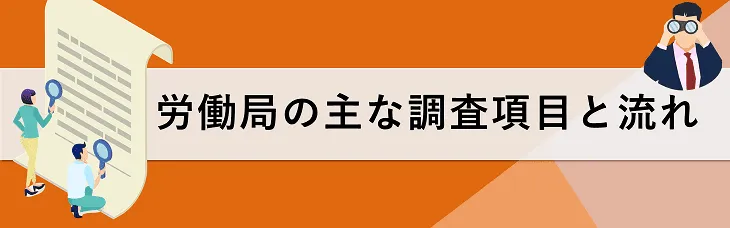





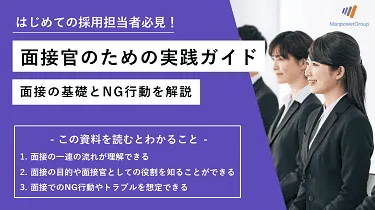
 目次
目次