


派遣における指揮命令者とは?役割と選任条件、よくある質問を解説

目次
指揮命令者ガイドブック
派遣社員の指揮命令者向けのガイドブックをご用意しています。
指揮命令者の役割や派遣社員の管理、よくあるトラブルなどを簡潔に解説しています。
人材派遣サービスを利用する場合、派遣法の定めにより派遣先となる企業は、「指揮命令者」「派遣先責任者」「派遣先苦情申出先の担当者」を設置する必要があります。
その中でも一番、派遣社員と接する機会が多いのが「指揮命令者」です。この記事では、指揮命令者について解説します。
指揮命令者とは
指揮命令者とは、労働者派遣法により派遣社員を受け入れる企業(派遣先企業)が設置しなければならない役割のひとつで、主に派遣社員への業務指示を行います。
労働者派遣契約を締結する際にも、指揮命令者の氏名・所属部署・役職・連絡先などを記載する必要があり、派遣会社が派遣社員と交わす就業条件明示書にも指揮命令者の氏名・所属部署・役職などが明記されます。
指揮命令者の選任条件
指揮命令者には特別な選任条件はなく、資格なども不要です。ただし、「派遣社員への業務指示・指導・監督」を担うため、派遣社員が配属される部署から選出します。派遣社員が担う業務は契約書どおりである必要があり、同じ部署から選出することは正しい運用の証明にもつながります。
また、指揮命令者は派遣先が直接雇用している人に限ります。他の派遣社員や業務アウトソーシング先の従業員など、外部の雇用者を選任することはできません。
ほかの役割と兼任できるか
同じく派遣法で定められている「派遣先責任者」「派遣先苦情申出先の担当者」と指揮命令者の兼任についてですが、派遣先責任者と兼任することに問題はありません。
ただし、苦情申出先の担当者との兼任については、指揮命令者以外の人が担うことが望ましいとされています。理由としては、派遣社員の苦情の対象が指揮命令者であるケースが想定されるためです。
指揮命令者の役割
指揮命令者には、主に3つの役割があります。
派遣社員への業務指示・指導
派遣契約に基づいた業務の指示・指導を行います。ポイントは、「派遣契約の範囲内であること」です。
業務外の仕事を指示してしまうと、派遣法に反してしまうだけではなく、トラブルにもつながりかねません。そのため、指揮命令者は契約内容についてしっかり把握しておく必要があります。
勤怠管理
日々の派遣社員の勤怠管理も指揮命令者のタスクになります。勤怠の承認だけではなく、勤務状況が契約内容から大きく逸脱していないかも管理します。
派遣契約を結ぶ際には、始業・終業・休憩時間のほかに、残業時間の目安や休暇(夏季休暇や年末年始など)についても合意した上で就業開始となります。派遣会社や派遣社員に無断で就業時間の変更や祝日出勤等をさせることはできません。
就業環境のチェック
派遣先には、男女雇用機会均等法や労働安全衛生法に基づく就業環境への配慮が求められます。併せて、ハラスメントが起きないよう適切に管理・対処しなければなりません。
また、均等待遇のひとつとして業務遂行に必要な教育の実施も派遣先が講ずべきこととされています。派遣先責任者や派遣会社と協力しながら、派遣社員が安心して働ける環境を維持していきましょう。
指揮命令者が気を付けたい6つのポイント
派遣社員が安心してパフォーマンスを発揮できるよう、指揮命令者が意識しておきたいポイントを6つ解説します。
- 「指揮命令者が誰か」を周知しておく
- 派遣契約以外の業務を指示しない
- 派遣社員の受け入れ体制を整える
- 派遣社員の個人情報を尊重する
- 派遣社員にも各種労働に関する法律が適用されると知っておく
- 契約については派遣社員と直接話さない
順番に解説します。
「指揮命令者が誰か」を周知しておく
派遣社員が就業する前に部門や業務で関わる部署などに指揮命令者は誰かを伝えておきましょう。
どんな業務を誰の指示のもと行うかを周囲も理解しておくことで、派遣社員が働きやすい環境をつくることができます。
また、契約内容を理解していない第三者が、契約外の仕事を指示したり、派遣法で定められた派遣社員にさせてはいけない業務をうっかり依頼してしまうなどのトラブルを防ぐ効果もあります。
派遣契約以外の業務を指示しない
繰り返しになりますが、派遣社員の業務は派遣契約でしっかりと決められています。契約業務以外を依頼することはできませんので、改めて注意しましょう。
もし、業務を追加したい、一時的に別の仕事もしてほしい、などの要望がある場合は、派遣先責任者・派遣会社に相談し、派遣社員の同意を得た上で依頼します。
また、外出や出張などが発生する場合は、経費処理のフローや勤務時間をどのように定義するか(移動時間の扱いなど)を事前に決めておく方がスムーズに進むため、契約内容に含まれていた場合であっても、一度派遣会社に確認しておくとよいでしょう。
派遣社員の受け入れ体制を整える
指揮命令者が気を付けたい点のひとつは、派遣社員の「早期離職」です。早期離職の原因はさまざまですが、理由のひとつとして受け入れ体制の不備があげられます。
就業開始したものの、仕事が無くて手持ち無沙汰である
就業開始したものの業務に必要なパソコンやデスク、各種IDが揃っていない、派遣社員に依頼する業務は想定していたが、思いのほか業務量がなくて依頼するものがない、などは時々起こる問題です。
派遣社員側に「必要とされていない」受け取られ、何もしない時間を苦痛に感じる人も少なくありません。
就業先が忙しすぎて、業務を教えてもらえず困惑した
指揮命令者を含めたメンバーが忙しすぎるために派遣社員へ十分に業務を教えることができず、不安やストレスとなり離職するケースがあります。
また、経験豊富な派遣社員といえども、社内のルールを知って動く必要はあります。同じ業務だとしても、企業によって業務の進め方は異なりますし、どの企業でも一般的に発生する電話対応のような業務であっても、その企業独自の「お作法」的なローカルルールが存在することもあります。
「来てもらえばなんとかなる」ではなく、受け入れ体制を整えることで、派遣社員の早期離職を防ぎ、パフォーマンスを発揮しやすい状況ができます。
派遣社員の個人情報を尊重する
派遣社員の就業にあたり、派遣会社から派遣社員の個人情報が提供されますが、それは関係者以外にむやみに知らせてはいけません。また、業務に必要のない個人情報(前職や家族、出身校など)を聞かないように注意しましょう。
派遣社員にも各種労働に関する法律が適用されると知っておく
派遣社員も労働に関する各法律が適用されることについても知っておきましょう。
例えば、有給取得の権利は派遣社員にもあります。有給を付与するのは派遣会社ですが、派遣先は有給取得に協力する必要があります。
また、時間外・休日労働に関しては、雇用主である派遣会社の36協定で定められた範囲内となります。
契約については派遣社員と直接話さない
派遣契約に関することを、派遣社員と直接話すのは避けましょう。派遣社員の雇用主は、派遣会社です。雇用条件や契約期間なども派遣社員と派遣会社で取り交わされる契約であり、派遣先が行うものではありません。
話題にしないほうがいいトピックの一例
- 賃金(時給、手当など)
- 契約期間の延長
- 契約期間の短縮
- 業務内容の変更や追加
- 直接雇用のオファー
など
例えば、時給を上げたい場合、満額が派遣社員に還元できるわけではありません。派遣社員の収入が上がれば、社会保険料にも影響があるなど、派遣会社でも経費の調整が必要になるためです。
また、契約期間についても派遣法や労働契約法などの考慮すべき法律があります。そのため、派遣契約について派遣社員と直接話してしまうと、トラブルの元になりかねません。
契約については、派遣先責任者・派遣会社に相談した上で、派遣会社を介し進めていきます。
指揮命令者とほかの役割との違い
派遣法で定められている他の役割との違いについて簡単に説明します。
派遣先責任者
派遣先責任者は、派遣会社との調整や抵触日の管理、派遣先管理台帳の作成・管理といった派遣サービスの正しい運用、派遣社員が安心して働ける就業環境の維持などが主な役割です。
誰でもなれるわけではなく、労働関係法令の知識を有している、人事・労務管理の経験者など、派遣先責任者の職務を適切に遂行できる人を選任するよう努めること、とされています。
また、派遣社員100名につき1名以上など、人数にも定めがあります。
前述しましたが、指揮命令者と派遣先責任者は兼任できます。派遣先責任者については、「派遣先責任者とは|役割と選任基準をわかりやすく解説 」で詳しく解説しています。
派遣先苦情申出先の担当者
派遣先苦情申出先の担当者は、派遣社員からの苦情を受ける役割を担います。そのため、業務だけではなく、職場環境などの就業状況についても理解できる人が望ましいです。
指揮命令者と派遣先苦情申出先の担当者の兼任は、その役割の特徴から望ましくないとされています。
また、指揮命令者は自社の社員である必要がありますが、派遣先苦情申出先の担当者については、顧問弁護士などの第三者の選任も認められています。
関連記事:【人材派遣】派遣先苦情申出先担当者とは?役割と注意点を解説
指揮命令者に関するよくある質問
派遣社員を別の派遣社員の指揮命令者にするのは違法ですか?
派遣社員を別の派遣社員の指揮命令者とすることは派遣法で禁止されています。指揮命令者は必ず派遣先企業に直接雇用されている社員でなければならないと定められています。
また、業務委託先のメンバーや個人事業主などの外注先の従業員も指揮命令者にはできません。
社外の担当者が派遣社員に指示してしまうと、「二重派遣」に相当し法律に抵触します。二重派遣については、二重派遣とは|基本知識と派遣先の罰則をわかりやすく解説をご覧ください。
指揮命令者を変更したいです
指揮命令者に変更が出る場合は、速やかに派遣先責任者に連絡し、派遣会社や派遣社員にも共有しましょう。
指揮命令者は、派遣先管理台帳や就業条件明示書などにも記載されているため、関係書類の変更も必要になります。
常駐していない社員を指揮命令者に選定してもいいですか?
派遣社員と指揮命令者は、管理上のリスク回避の面からも同じ就業場所で働くことが望ましくありますが、必ずしも常駐している必要はありません。
居場所が明確で連絡が取れ、「指揮命令」が滞りなくできるのであれば、常駐していない社員も担うことができます。
指揮命令者が不在中はどうすればいいですか?
休暇や出張など指揮命令者が不在になる場合は、事前に業務指示をだしておく、代理の人を立てるなどで対応してください。
代理人を立てる場合、社外の人にしてしまうと二重派遣に抵触するため、必ず社内の人に依頼してください。
歓迎会や飲み会に誘いたいが問題ないでしょうか?
歓迎会や飲み会は、業務ではないため強制はできません。本人の意思を尊重した上で、確認を取ってみてください。
クライアントが同席する会合を兼ねているなど、業務に関わる会食の場合、派遣会社に相談して対応を決定します。こちらも本人の意思を尊重した上で、強制しないよう気を付けましょう。
指揮命令者のためのガイドブック
派遣社員へ業務指示を出し、勤怠管理を行う指揮命令者は、その役割を理解しておく必要があります。 派遣法に詳しくない場合、トラブルも起きやすくなってしまいます。 指揮命令者が知っておきたいことを簡潔にまとめた資料をご用意しています。ぜひご覧ください。
<この資料でわかること>
・ 指揮命令者の役割
・ 派遣社員への対応
・ よくあるトラブル

まとめ
派遣社員を受け入れ時の、指揮命令者の設置は必須事項です。派遣法で定められているだけではなく、派遣社員が実力を発揮する上でも指揮命令者の任務は重要です。役割を理解した上で、人材派遣サービスを活用していきましょう。
こちらの資料もおすすめです




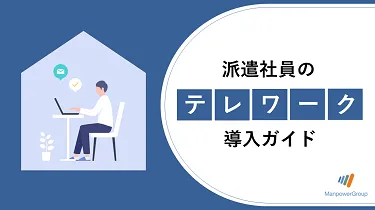
















 目次
目次