


派遣社員を受け入れるときの注意点とチェックリスト

目次
昨今の人材獲得の難しさや、社会ニーズの急激な動き・多様化などを背景に人材派遣サービスの活用を検討する企業は増えています。
では実際に派遣社員の受け入れが決まった際、どのような点に留意しておく必要があるのでしょうか。
本コラムでは、派遣社員受け入れの準備から長期的就業に向けての注意点など、押さえておきたいポイントについて解説します。
派遣社員の受け入れ準備
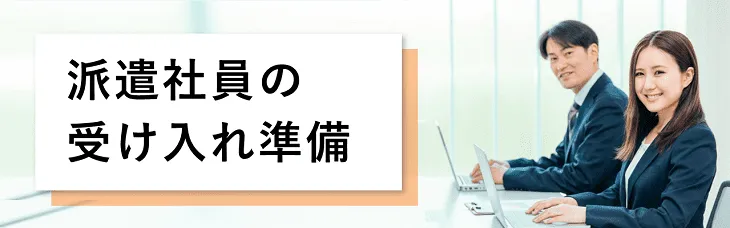
派遣社員は自社の社員ではありませんが、共に働く仲間です。しっかりと受け入れ体制を確認し、早く活躍してもらえるよう環境を整備することが大切です。
社内で確認しておくべきこと
人材派遣サービスは、派遣会社にすべてを任せるわけにはいきません。派遣先として整えるべき事項もあるため、受け入れ前にしっかりと確認しておきましょう。
指揮命令者・派遣先責任者・苦情処理担当者の確認
派遣社員への業務指示は誰が行うか、問題が起きたときは誰に相談するのかなど担当となる責任者を確認しておきます。
下記の3つの役割は、派遣法に基づき派遣先で担当者を設置することが義務付けられています。各役割を理解し、それぞれの担当者は派遣契約に関する資料に事前に目を通し、自身の役割を再確認しておきましょう。
| 指揮命令者 | 派遣社員に業務指示を出す |
| 派遣先責任者 | 派遣社員が派遣先企業で業務を円滑に遂行できるように管理を行う |
| 苦情処理担当者 | 派遣社員から就業に関する苦情を受付けて対応する |
なお、指揮命令者や派遣先責任者、苦情処理担当者については、派遣法に基づき、契約書に記載しなければならない事項として定められています。
社内への周知
派遣社員が就業を開始することを、社内に周知します。派遣社員が出社した際に、周知が不十分だと、会社の対応に不安を感じさせてしまう可能性があります。派遣社員が行う業務内容とその範囲、契約期間、勤務日時やシフトなどの詳細を、派遣社員が所属する部署だけでなく、関連部門のメンバーにも事前に伝えておきましょう。
事前に揃えておくべきもの
業務で使う物品などの準備も必要です。
業務に必要な物品
社内関連の物品を準備します。すぐに用意できない可能性もあるため、余裕をもって確認しておきましょう。また、派遣社員側で用意すべきものなどがあれば、派遣会社を通し事前に伝えます。
準備物の一例
- IDカード(入館証)
- 身分証
- パソコン、マウス
- デスク
- 電話・携帯電話
- 業務用機器・備品、事務用品
- 制服
- マニュアル
- 組織図や座席表、フロアマップ、社内連絡先の一覧など
アカウント発行、ネットワーク権限の付与
社内の専用端末やメール、クラウドツールなど、業務に必要なアカウントの発行も事前に行います。
また、社内ネットワークの権限についても確認しておきましょう。必要な情報が閲覧できるか、不必要な情報が閲覧できないか、セキュリティ面も考慮して確認します。
派遣会社と連携し、整えておくべきこと
派遣社員を受け入れる前に、派遣の契約締結をしっかり行っておきましょう。派遣先から提供する情報や通知書などがあります。
また、保険適用が適切になされているか、雇用保険法・健康保険法を遵守しているか、などを派遣会社に確認します。
派遣先管理台帳の作成
派遣先管理台帳の作成は、派遣法によって定められており、各種保険の加入状況や就業日・労働時間などを派遣社員ごとに記載する必要があります。さらに、法定記載事項を漏れなく記載し、派遣契約が終了した後も3年間保管する義務があります。
派遣先管理台帳の作成については、派遣先管理台帳とは?作成ルールと記載必須事項について詳しく解説で詳しく解説しています。
関連記事:「派遣社員の管理」派遣先に求められる対応とポイントを解説
【派遣社員の受け入れチェックシート】
用意すべき物品、申請すべきこと、必要な契約書など、受け入れる際に必要な事項をチェックシートにまとめました。
- Excelだからカスタマイズが簡単
- 人事向け、部門担当者向けで作成
派遣社員の初日の対応

社会人経験の長さに関わらず、誰もが勤務初日は緊張感と期待を抱きながら業務を開始します。職場環境の第一印象が良いか悪いかは、その後のパフォーマンスや定着に影響を与えるため、非常に重要なポイントです。
受け入れ担当者は、案内に過不足がないよう、以下の項目に関する手順書を事前に準備しておくとよいでしょう。
関係者への紹介
派遣先責任者、指揮命令者、所属部署の社員、就業する部門や関連部門の業務関係者に派遣社員を紹介します。可能であれば、組織図や座席表なども渡しておくと良いでしょう。
社内設備、社内フロアの案内
会議室や更衣室、休憩所、自動販売機、トイレ、社内食堂など利用する可能性がある施設を紹介しておきます。併せて、入室方法や利用ルールも伝えておきましょう。
また、派遣社員の安全配慮義務は原則派遣元にありますが、派遣社員と指揮命令関係がある派遣先企業も事業者としての責任を負うことがあります。避難や安否確認など、災害発生時の対応ルールを事前に派遣会社にも共有しておくと安心です。
設備の使い方、備品の保管場所と使用ルール
電話・FAX、コピー機、シュレッダーなどの業務設備の使用ルールを説明します。また、事務用品や用紙など、各種備品の保管場所や利用ルールなども併せて伝えます。
社内ルールの共有
出退社時や休憩時間、欠勤時の連絡方法、電話の取次ぎ方など、社内の基本ルールを説明します。電話の取次ぎ方などは、企業によって異なることが多いため、特に注意が必要です。
セキュリティに関するルール
取引先や機密情報に関するルールは特に重要なため、口頭での説明に加えて、誓約書などが必要な場合は事前に派遣会社に伝え、署名が必要であることを派遣社員に通知しておきましょう。
また、セキュリティに関する研修を導入することもおすすめです。
その他
社内組織の概要を説明し、自部署の位置づけを説明しておくと、業務の理解が進みやすくなります。同じチームのメンバーの役割なども説明しておくとよいでしょう。
派遣社員の受け入れ環境の注意点
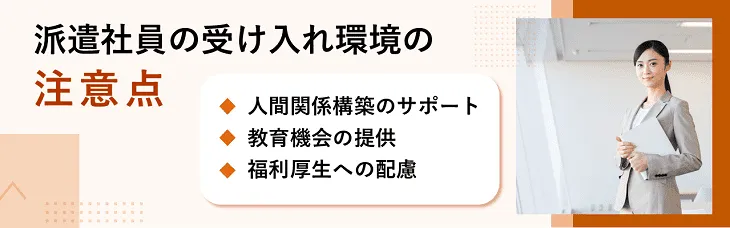
派遣社員は、自社と雇用関係がないとはいえ、同じ目標に向かって仕事をする立場です。期待したパフォーマンスの発揮や、安定的な稼働のためには、配慮しておきたい点があります。
人間関係構築のサポート
職場でのコミュニケーション構築が重要です。一緒に働く部門や関連部門、同じ派遣社員と円滑なコミュニケーションを構築できるようにサポートします。
人事担当者は、指揮命令者と連携し「派遣社員が安心して働ける環境」について常に配慮しておきましょう。業務習得や社内への適応状況などを適宜確認し、必要なサポートを提供できるようにします。
また、派遣社員本人に対しても、戸惑うことなく指示を受けられているか、業務内容と相違はないかなど、相談しやすい機会を設けるのもよいでしょう。
契約書からの逸脱がないか、定期的に派遣社員から聞き取りを実施するのも大切です。問題があれば、派遣会社の担当者にも相談し早期解決を心がけます。
教育機会の提供
派遣先企業には、業務遂行に必要となるスキル習得・向上について、派遣先企業の社員と同等の教育訓練を受けさせる義務があります。また、派遣社員が自主的に行うスキルアップについても、派遣先企業として可能な限り協力することも求められています。
自社の求める業務を正しく遂行してもらうためにも、スキル向上や知識獲得のサポートの実施は有効な施策です。
関連記事:派遣社員の教育はどこまで必要?労働者派遣法に即した対応を解説
福利厚生への配慮
派遣社員にも自社社員と同様の福利厚生の提供が求められます。社員食堂や更衣室、休憩室など、自社社員と同等の福利厚生を提供しましょう。
関連記事:同一労働同一賃金とは?派遣社員にはどう適用される?
派遣社員受け入れのチェックチェックシート
派遣社員のスタートが決定した場合の受け入れ準備、スムーズに業務に就いてもらうだけではなく、派遣法に則した対応も必要です。準備状況をチェックするためのシートを派遣先責任者向け(人事担当者)と現場担当者向けにご用意しています。
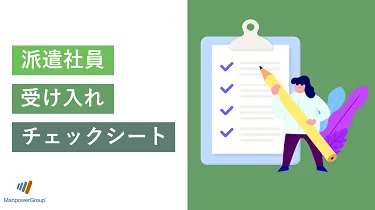
現場担当者が知っておきたいトラブルを避けるための注意点
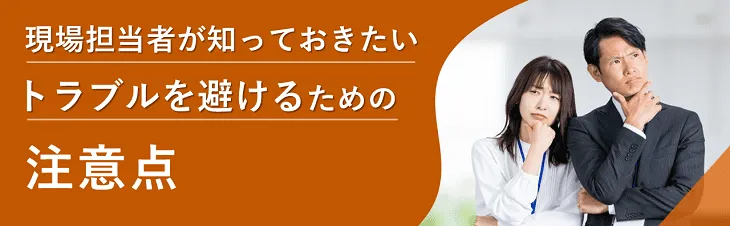
派遣サービスには、派遣法によってさまざまなルールが定められています。派遣先責任者は人事関連法に詳しい担当者が担いますが、現場担当者(指揮命令者など)は詳細に理解していないことが多いかもしれません。ここでは、トラブルになりやすいケースをいくつか紹介します。
大前提として、「派遣社員は自社の社員ではなく、派遣会社から派遣されている」という点を常に意識しておきましょう。
むやみに個人情報を聞かない
派遣社員が働きやすいように声をかけたり、コミュニケーションを意識することは重要ですが、個人情報を必要以上に聞き出さないよう注意しましょう。
一例
- 年齢や出身地、居住地
- 学歴
- 連絡先(電話やメールアドレス)
など
業務上の理由で確認が必要な場合は、まず派遣会社に相談してください。
契約外の仕事を気軽に依頼しない
派遣サービスでは、派遣社員に依頼する業務内容を契約書で厳密に定めなければなりません。「隣の部署が忙しいから」「会社のイベントがあるから」といった理由で、突発的な業務を気軽に依頼しないようにしましょう。
もし、継続的に行ってほしい業務が発生した場合は、依頼する前に派遣会社に連絡し、派遣社員本人の同意を得ることが必要です。
更新確認や時給の話を直接話さない
更新確認や時給など、派遣契約に関する話題を派遣社員と直接話すことは避けましょう。
派遣社員と雇用契約を結んでいるのは派遣会社であり、派遣先企業は派遣会社と契約を結んでいるため、派遣社員と派遣先企業の間には雇用契約は存在しません。
契約に関する話題は、センシティブな内容として慎重に扱うようにしましょう。
TIPS
よくあるケースとして、時給を上げる場合が挙げられます。例えば、100円の時給アップをする際、派遣会社がその100円をすべて派遣社員に還元するとは限りません。派遣社員の給与が上がると、派遣会社側の経費負担(社会保険など)も増えるため、その分を差し引くことがよくあります。
「時給を〇〇円上げるよ」と直接派遣社員に伝えてしまうと、実際の金額が異なる場合、トラブルが発生し、派遣社員のモチベーション低下につながる可能性があるので注意しましょう。
業務の都合で早退・休ませる際は慎重に
何らかの理由で派遣社員に早退や休暇を指示する場合は、慎重に行いましょう。会社都合での早退や休暇は、休業手当の対象となることがあります。会社カレンダーなど、事前に休みが決まっている場合は、必ず派遣会社を通じて派遣社員の了承を得るようにしましょう。
派遣社員は勤務時間が給与に直結するため、会社都合で契約時間を短縮することはトラブルの原因になりやすいです。詳しくは、派遣社員の休業補償・休業手当|負担は誰?ケーススタディでわかりやすく解説をご覧ください。
歓迎会やイベントの参加について
歓迎会や会社イベントへの参加は業務ではないため、強制することはできません。本人の意思を尊重し、参加の可否を確認するようにしましょう。
クライアントとの会食など、業務に関わる場合はまず派遣会社に相談し、対応の可否を確認してください。
派遣社員を受け入れる際に理解しておくべきルール
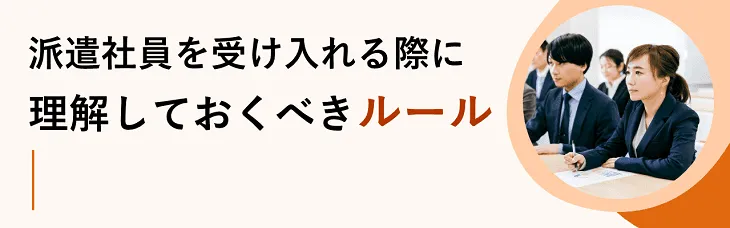
派遣社員を受け入れる際は、「労働者派遣法」が定めるルールへの十分な理解が求められます。
派遣期間には、期間制限がある
派遣社員については、事業所単位・個人単位の期間制限があります。派遣社員は、同一の組織単位で3年以上働くことができません。(原則延長不可)
例えば、人事課で3年働いた派遣社員が、会計課で別業務に従事することは問題ありません。(派遣社員の特定行為には気を付ける必要があります)同部署に3年ごとに異なる派遣社員を派遣することも問題ありません。
また、以下の場合は期間制限の対象にはなりません。
- 派遣会社で無期雇用されている派遣社員である場合
- 60歳以上の派遣社員である場合
- 有期プロジェクト業務への従事
- 日数限定業務(1カ月間に行われる日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ、月10日以下であるもの)
- 産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する社員の業務
関連記事:【企業向け】派遣法の3年ルール完全ガイド|無期雇用・延長方法・罰則を徹底解説
派遣社員の特定行為は禁止
派遣先企業は派遣社員を指名することができません。また、事前の書類審査や面接も禁止されています。派遣社員の選考は派遣会社が行います。ただし、紹介予定派遣については、直接雇用が前提となっているため、この限りではありません。
関連記事:紹介予定派遣とは?仕組みとルール、料金について解説
派遣社員を従事させてはいけない禁止業務がある
人材派遣では、建設業務や港湾運送業務、警備業務など派遣社員を従事させてはいけない禁止業務があります。
例えば、受付業務に従事する派遣社員が、受付前で不審な動きをする人物に声をかけるなどの行為は、警備に該当する可能性があります。
詳しくは、派遣禁止業務とは?禁止の理由と例外や罰則を解説で解説しています。
取引先など自社以外に派遣社員を派遣するのは違法
派遣社員を取引先など自社以外の企業へ派遣することは、二重派遣となり労働基準法や職業安定法に違反します。
詳しくは、二重派遣とは?該当する行為と罰則を解説で解説しています。
労働契約申込みみなし制度
「労働契約申込みみなし制度」とは、派遣先企業が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合に、派遣先が派遣社員に対して直接雇用を申し込んだものとみなす制度です。
たとえ申込みの実体がなくても、派遣先企業は自動的に派遣社員に対して労働契約の申し込みを行ったことになり、派遣会社との雇用条件と同一の条件で雇用する義務が生じます。
「労働契約申込みみなし制度」に該当するケースは以下の通りです。
- 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
- 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
- 事業所単位または個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
- いわゆる偽装請負の場合
派遣先などが違法派遣に該当することを知らず、かつ知らなかったことに過失がない場合、この制度は適用されませんが、トラブルに巻き込まれないためにも、実績と社会的な信頼のある派遣会社と契約することが重要です。
関連記事:労働契約申込みみなし制度とは 対策方法や事例を紹介
はじめての派遣社員受け入れガイド【初級編】
派遣社員の受け入れがはじめての企業向けに、基本的な知識や対応ポイントをまとめた入門ガイドをご用意しました。派遣の仕組みや注意点をわかりやすく解説しています。
<この資料でわかること>
・ 派遣の基本的な仕組み
・ 派遣契約と受け入れの流れ
・ 受け入れ時の注意点と管理ポイント

まとめ:十分な理解と準備で最大の効果を引き出す
人材派遣サービスを活用することで、人材不足の解消やコストの適正化といったメリットを得ることができます。
しかし、これらのメリットを十分に活かすためには、派遣社員を受け入れるための体制の整備や、派遣法などのルールを正しく理解し、適切にサービスを活用することが不可欠です。
派遣社員が持つスキルを最大限に発揮し、安定した就業を実現するためにも、これらの準備と理解は非常に重要な要素となります。
こちらの資料もおすすめです

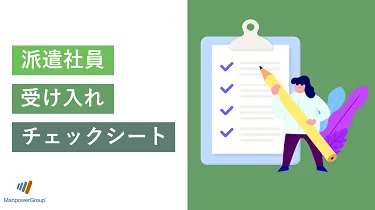

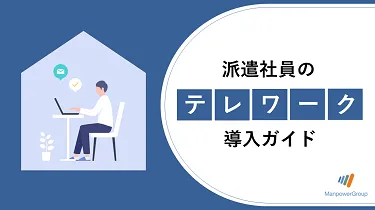



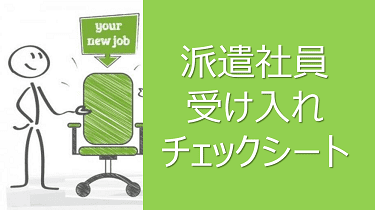















 目次
目次