


【2024年障害者雇用促進法の改正】法定雇用率の上昇と7つの変更点

目次
はじめての障がい者社員受け入れガイド【採用前準備編】
初めて障がい者雇用をする方向けに障がい者雇用の準備についてのガイドブックをご用意しています。
2024年に障害者雇用促進法が改正され、法定雇用率が2024年4月から段階的に引き上げられることになりました。これにより雇用すべき人数が上昇し、また義務対象となる企業の範囲が拡大されることになります。
本記事では、2024年の法改正内容を中心に2025年以降の改正点について詳しく解説します。これまでの障がい者雇用の歴史を振り返りながら、既に障がい者雇用を実施している企業の方だけでなく、新たに義務対象となる企業の方にも、障がい者雇用の意義と必要な対応についてわかりやすく解説します。
おさらい|2023年に変更になった点
近年、企業で働く障がい者数の増加という点において、障がい者雇用の推進は着実に進展しているものの、一方では法定雇用率の達成が目的となってしまい、持てる能力を十分に発揮できる雇用の場が提供されているとはいえない状況もありました。
そのため2025年の法改正では、雇用後のキャリア形成の支援を含めた、安定した雇用に繋がるような施策の充実強化が行われています。
なお、2023年に決定された障害者雇用促進法の法改正(省令改正を含む)は、段階的に施行されます。2023年の施行は責務の明記や特例の延長などにとどまり、直接影響のある法定雇用率や調整金・納付金などについては、2024年以降に施行されます。
また、法定雇用率については、これまでの改正では概ね5年毎に0.1~0.2%の上昇であったものが、今回は大きく0.4%上昇します。現行の2.3%から2024年からは2.5%、2025年からは2.7%と段階的に上がっていきます。
いずれにしろ、雇用率の算定の対象となる対象者の拡大もあるものの、対象事業主の範囲の拡大もあり、企業にとって非常に大きな影響があるため、準備をすすめていきましょう。
精神障がい者の算定特例の延長
2018年4月以降、それまでの身体・知的障がい者に加え精神障がい者の雇用が義務化され、同時に障害者雇用率も引き上げられました。
精神障がい者は身体・知的障がい者に比べて職場定着率が低い状況にあったものの、就職当初は週20~30時間勤務であってもその後に週30時間以上に移行する割合が高かったことから、「一定の条件」に当てはまる「週20~30時間勤務」の精神障がい者については、障害者雇用率の算定において身体・知的障がい者の「0.5人」ではなく「1人」としてカウントする5年間の特例が行われていました。
2023年4月以降は、「一定の条件」をなくした上で、当分の間は「1人」としてカウントする特例が継続されることになりました。
障がい者従業員に対する職業能力の開発および向上に関する措置
2023年4月からは、障がい者のある従業員に対する職業能力の開発および向上に関する措置が事業主の責務として法律に明記されました。
それにより今後は、これまでの雇用機会の確保および必要な合理的配慮を行うことに加え、下記のような職場環境の整備や適切な雇用管理の取り組みを行うことが望まれます。
一例
- 特性や希望に応じて能力を発揮できる業務の提供
- 雇入れ後も、職域開発や業務の選定を通じて多様な業務に取り組む機会、特性を生かしその能力を発揮する機会の提供
- 本人の希望、能力等を踏まえた業務目標の設定、業務実績等を踏まえた人事評価、その結果に基づく待遇の実施
- キャリア形成の視点を踏まえた継続的な能力開発・向上の機会の提供
これらの施策を義務として捉えるのではなく、企業の強みとして活かしていけば、単なる法対応としての採用・雇用に終わらず、組織全体の強化に発展します。
一例
- すべての従業員の能力開発を考えることでコミュニケーションが活性化する
- 従業員のダイバーシティに関する意識が向上する
- 業務分担を見直すことで生産性が高くなる
- 企業ブランディングが強化される
2024年の障害者雇用促進法の改正内容
2024年の施行は直接実務に影響のある改正が多くなります。
法定雇用率のアップに伴い対象となる企業の範囲が広がるため、自社が対象となる場合は、早急に対応を進めましょう。
法定雇用率は2.3%→2.5%へ
| 民間企業 | 2023年(令和5年度) | 2024年(令和6年)4月 | 2026年(令和8年)7月 |
| 法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
| 対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
法定雇用率は、2024年4月から0.2%上昇し2.5%となります。また、対象事業主の範囲も広がり、「従業員43.5人以上」から「従業員40.0人以上」へ拡大します。
ここで気を付けておきたいのは、2026年にも法定雇用率の改正と対象事業主の拡大があることです。2年後の変更であるため、企業はここまで見据えて対策を立てる必要がでてきます。
出典:厚生労働省 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について![]()
雇用率算定の対象となる労働者の拡大
これまで障害者雇用率制度においては週20時間未満での雇用は対象とされていませんでした。これは、通常の労働者が週40時間労働するとした場合に、その半分に満たない時間での労働は職業生活において自立しているとは言えない、という考え方に基づいていました。
しかし、週20時間未満での雇用を希望する障がい者が一定数いることや、症状悪化等により週20時間以上働けなくなった場合でも雇用を継続していくことが望ましいことから、2024年度以降について、10時間以上20時間未満で働く労働者(特定短時間労働者)である重度の身体・知的障がい者、精神障がい者についても雇用率の対象とし、対象者1人につき「0.5人」としてカウントすることになります。
| 週所定労働時間 | 30H以上 | 20H以上 30H未満 |
10H以上 20H未満 |
|
| 身体障がい者 | 一般 | 1 | 0.5 | - |
| 重度 | 2 | 1 | 0.5 | |
| 知的障がい者 | 一般 | 1 | 0.5 | - |
| 重度 | 2 | 1 | 0.5 | |
| 精神障がい者 | 一般 | 1 | 0.5※ | 0.5 |
出典:厚生労働省 算定対象となる労働者の範囲や算定方法(第129回障害者雇用分科会資料より抜粋![]() )
)
障害者雇用調整金・報奨金の支給の減額
障がい者雇用には、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別な雇用管理などの経済的負担が伴うことから、障がい者を数多く雇用している企業に対して支給される調整金や報奨金があります。
常時雇用労働者数が100人を超える企業においては、障害者雇用率を超えて雇用している障がい者数1人につき月額29,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
また、常時雇用労働者数が100人以下の企業においては、各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数(各月、常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合、その数を超えて雇用している障がい者1人につき21,000円の報奨金が支給されます。
この障害者雇用調整金・報奨金については、2024年度の実績に基づく2025年度の支給から、一定数を超えた場合に調整(減額)されることが決まっています。
| 常時雇用労働者数 | 支給名称 | 支給対象人数および支給額 | |
| 100人超 | 障害者雇用調整金 | 障害者雇用率を超えて雇用している障がい者数 | |
| 月10人以下 1人月額29,000円 |
月10人超 1人月額23,000円 |
||
| 100人以下 | 報奨金 | 「各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数」又は「年間72人(月平均6人)」の いずれか多い人数を超えて雇用している障がい者数 |
|
| 年間420人(月平均35人)以下 1人月額21,000円 |
年間420人(月平均35人)超 1人月額16,000円 |
||
納付金・助成金の新設・拡充
障がい者雇用の促進のため、障害者雇用相談援助助成金および中高齢者等障害者職場適応助成金(仮称)が新設されることになりました。それぞれの概要は以下のとおりです。
障害者雇用相談援助助成金
【支給対象】
- 2の①と②を満たすもの
- ①都道府県労働局長の認定を受け、②対象障がい者の雇入れ及び雇用の継続を図るために必要な対象障がい者の一連の雇用管理に関する援助の事業(以下、「障害者雇用相談援助事業」という。)を行うもの
- (1)、(2)のいずれかに該当するもの
(1)その事業所で、対象障がい者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を行った事業主に対して、相談援助事業を行ったもの
(2)その事業所で、対象労働者の雇入れ、6ケ月以上その雇用の継続を行った事業主に対して、相談援助事業を行ったもの
【支給額】
- 60万円(中小事業主又は除外率設定業種の事業主にあっては80万円)
- 1の助成額に、一人当たり7.5万円(中小企業事業主又は除外設定業種の事業主にあっては10万円)を上乗せ(ただし、4人までを上限とする。)
【支給回数】
1事業主につき、1回
そのほか、詳細は下記にてご確認ください。
中高齢者等障害者職場適応助成金
【支給対象及び支給額】
その雇用する中高年齢等障がい者に対して、次のいずれかの措置を行った事業主に対して支給する。
①業務の遂行に必要な施設の設置等
| 助成対象措置 | 助成率 | 上限額 |
| 設置又は整備(賃借によるものを除く。) | 2/3 | 年・450万円/人(作業設備のみ:150万円。中途障がい者は450万円) 会計年度・4,500万円/事業所 |
| 賃借 | 2/3 | 月13万円/人(作業設備のみ:5万円。中途障がい者は13万円) |
②職務の遂行のための能力開発
| 対象事業主 | 助成率 | 上限額(年額・一人当たり) |
| 中小企業事業主等以外の事業主 | 3/4 | 20万円 |
| 中小企業事業主等(※1) | 3/4 | 30万円 |
※1 中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主
③業務の遂行に必要な者の配置又は委嘱
| 助成金 | 配置 | 委嘱 |
| 職場介助者(助成率:2/3) 手話通訳・要約筆記等担当者(助成率:2/3) |
月13万円/人 (※1:15万円/人) |
1人0.9万円/回(※1:1万円) (上限:年135万円/人(※1:150万円)) |
| 職場支援員 | 月3万円/人 (※1:4万円) |
1人 1万円/回 (上限:※2) |
| 助成金 | 訪問型 | 企業在籍型 | |
| 精神障がい者 以外 |
精神障がい者 | ||
| 職場適応援助者 | 4時間以上1.8万円。4時間未満9千円 上限額:3.6万円/日(支援ケースごと) | 月6万円 (※1:8万円) |
月9万円 (※1:12万円) |
※1 中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主
※2 既存メニューの上限が4万円/月であることを踏まえ、288回(4回×12か月×6年)最大6年間の中で柔軟に使えるよう設定
【支給回数・期間】
- 賃借の場合:最大3年間
- 最大1年間
- 最大10年間(職場介助者、手話通訳担当者)
最大6年間(職場支援員)
そのほか、以下の助成金については拡充が予定されています。
障害者介助等助成金
職場介助者の整理・拡充事項(助成上限額)
※助成率:3/4(継続については2/3)
| 対象障がい者等 | 現行 | 改正案 | 期間(最大) | |||
| 配置 | 参考)四肢機能障がい | 月15万円/人 | 月15万円/人 | 10年 | ||
| 視覚障がい | 事務的業務 | |||||
| 事務的業務以外 | なし | |||||
| 委嘱 | 参考)四肢機能障がい | 1万円/回 (1年につき150万円/人) |
1万円/回 (1年につき150万円/人) |
10年 | ||
| 視覚障がい | 事務的業務 | |||||
| 事務的業務以外 | 1万円/回 (1年につき24万円/人) |
|||||
| 継続 | 配置 | 参考)四肢機能障がい | 月13万円/人 | 月13万円/人 | 5年 | |
| 視覚障がい | 事務的業務 | |||||
| 事務的業務以外 | なし | |||||
| 委嘱 | 参考)四肢機能障がい | 9千円/回 (1年につき135万円/人) |
9千円/回 (1年につき135万円/人) |
5年 | ||
| 視覚障がい | 事務的業務 | |||||
| 事務的業務以外 | 9千円/回 (1年につき22万円/人) |
|||||
※中高年齢等障がい者以外への能力開発の措置に対する助成については、職場適応措置の実施を要件としないこととするほか、助成額について、費用額に応じた支給ではなく一定額とする。(助成率:3/4、上限額:①中小事業主 年30万円/人、②それ以外の事業主 年20万円/人、期間:最大1年)
手話通訳・要約筆記等担当者の整理・拡充事項(助成上限額)
※助成率:3/4(継続については2/3)
| 現行 | 改正案 | 期間(最大) | ||
| 配置 | なし | 月15万円/人 | 10年 | |
| 委嘱 | 6千円/回 (1年につき28万8千円/企業) |
1万円/回 (1年につき150万円/人) |
10年 | |
| 継続 | 配置 | なし | 月13万円/人(※) | 5年 |
| 委嘱 | なし | 9千円/回 (1年につき135万円/人)(※) |
5年 | |
※職場介助者の継続措置の助成金の上限額と同額
【支給対象】
①障がい者の雇用管理のために必要な専門職(医師又は職業生活相談支援専門員)の配置又は委嘱
(1)雇用する5人以上の障がい者の健康相談のために必要な医師の委嘱
(2)雇用する5人以上の障がい者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び支援の業務を専門に担当する者(※1)の配置又は委嘱
※1 精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、公認心理師、産業カウンセラー、看護師、保健師の資格を保有し、一定期間以上の障がい者雇用に関する実務経験を有する者等を想定
②障がい者の職業能力の開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者(職業能力開発向上支援専門員)の配置又は委嘱
雇用する5人以上の障がい者の職業能力開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者(※2)の配置又は委嘱
※2 キャリアコンサルタントの資格を有し、一定期間以上の障がい者雇用に関する実務経験を有する者等を想定
③障がい者の介助の業務等を行なう者の資質の向上のための措置
障がい者である労働者の介助等の業務を行なう者の資質の向上のための措置
【支給額】
①、② 費用の3/4を助成。ただし、上限等は以下のとおり。
① (1) 委嘱:1回 2.5万円/人(上限:年額30万円)
① (2) ② 配置:1人 15万円/月、委嘱:1回 1万円/人(上限:150万円/年)
③ 費用の3/4を助成。ただし、1事業主 100万円/年を上限。
【支給回数・期間】
①、② 10年間
職場適応援助者助成金
| 現行 | 改正案 | |
| 訪問型職場適応援助者助成金 | 単価 支援4時間*以上 16,000円 支援4時間*未満 8,000円 1日当たり上限額:16,000円 (複数の企業等において支援を実施しても、 1日の支援時間の合計で算定) |
単価 支援4時間*以上 18,000円 支援4時間※未満 9,000円 1日当たり上限額:36,000円 (支援ケースごとに算定) |
| 企業在籍型職場適応援助者 助成金 |
同一事業主の同一事業所において 2回目以降の支援は支給対象外 |
支援回数の上限なし (ただし、事業主1年度当たり助成金額の上限は300万円) |
*支援対象障がい者が精神障がい者の場合は「3時間」
重度障害者等通勤対策助成金
| 現行 | 改正案 | |
| 重度障害者等通勤対策助成金 | 第一号通勤援助者の委嘱の期間 1ヶ月 | 第一号通勤援助者の委嘱の期間 3ヶ月 |
【ガイドブック】障がい者雇用の担当者向けにわかりやすくまとめました
2025年の障害者雇用促進法の改正内容
2024年と2026年には法定雇用率の引き上げがあることから、2025年の改正は「除外率」のみとなっています。
除外率の引き下げ
法定雇用率を設定する際、雇用率を一律で適用することになじまない性質の職務もあることから、障がい者の就業が一般的に困難であると認められる業種については、雇用する労働者数を計算する際に「除外率」に相当する労働者数を控除する制度が設けられていました。
この除外率制度そのものは、ノーマライゼーションの観点から2002年に廃止が決定されていますが、経過措置として当分の間は除外率設定業種ごとに除外率が設定されています。
この除外率も段階的に引き下げ・縮小することとされており、2025年7月から以下のように変更されます。
| 除外率設定業種 | 除外率 |
| 非鉄金属第一次製錬・精製業・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) | 5% |
| 建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業(信書便事業を含む) | 10% |
| 港湾運送業・警備業 | 15% |
| 鉄道業・医療業・高等教育機関・介護老人保健施設・介護医療院 | 20% |
| 林業(狩猟業を除く) | 25% |
| 金属工業・児童福祉業 | 30% |
| 特別支援学校(専ら視覚障がい者に対する教育を行う学校を除く) | 35% |
| 石炭・亜炭鉱業 | 40% |
| 道路旅客運送業・小学校 | 45% |
| 幼稚園・幼保連携型認定こども園 | 50% |
| 船員等による船舶運航等の事業 | 70% |
出典:厚生労働省 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について![]()
障害者雇用促進法の改正・早見表
2009年に施行された「障害者雇用促進法」は、1960年に制定された「身体障害者雇用促進法」から始まりました。当初は戦争による負傷者の職業更生を図る施策として施行され、度々の改正を経て現在に至ります。
障がい者にとって雇用・就業は自立・社会参加のための重要な柱であり、障がい者がその適性に応じて自身の能力を発揮して働くことができるようにしていく必要があります。
国際的な規範の変化や雇用状況の変動などの社会の変化にも対応の必要があり、障害者雇用促進法は改正し続けられてきました。
| 障害者雇用促進法の改正 早見表 | |
| 1960年施行 | 身体障害者雇用促進法を制定し努力目標に |
| 1976年改正 | 努力目標から義務雇用へ |
| 1987年改正 | 法の名称を「身体障がい者」から 「障がい者」へ改称 |
| 1992年改正 | 「重度知的障がい者」をダブルカウントへ |
| 1997年改正 | 知的障がい者雇用が義務化 |
| 2006年改正 | 精神障がい者雇用が努力目標に |
| 2013年改正 | 「雇用差別の禁止」と「合理的配慮の提供」が義務化 |
| 2016年改正 | 改正された障害者雇用促進法が施行 |
| 2018年改正 | 精神障がい者雇用が義務化 |
1960年「身体障害者雇用促進法」制定
高度経済成長期を迎え人手不足が叫ばれる中、第二次世界大戦により身体障がい者となった人々の職業生活における自立を促すため、当初は「身体障がい者」のみを対象として法律が制定。
当時は民間企業に対して従業員の「1.3%」の雇用を「努力目標」としたものであり、「義務」づけられたものではありませんでした。
1976年改正「努力目標」から「義務雇用」へ
オイルショックの影響もあり経済低成長時代に突入したことで、身体障がい者の雇用が難しくなったことを打開するため、これまでの「努力目標」から「義務雇用」へ変更。雇用率が法定義務化され、民間企業の法定雇用率は「1.5%」にアップされました。
同時に、法定雇用率の未達成企業から「納付金」を徴収し、それを財源として障がい者雇用に積極的に取り組む企業に対して「調整金」や「助成金」を支給する雇用納付金制度ができあがりました。
1987年改正「身体障がい者」から「障がい者」へ拡大
法の対象となる障がい者の範囲を拡大し、その名称も「身体障害者雇用促進法」から「障障害者雇用促進法」に改称されました。「知的障がい者」は義務雇用の対象ではないものの、雇用率への算入や給付金制度の適用等は身体障がい者と同等の扱いになりました。
また、民間企業の法定雇用率が「1.6%」にアップされ、「“重度”身体障がい者」は1人を2人分としてカウント(ダブルカウント)できるようになりました。
1992年改正「重度知的障がい者」をダブルカウントへ
1987年にダブルカウントの対象となった「“重度”身体障がい者」に加え、「“重度”知的障がい者」を雇用した場合も、雇用率においてダブルカウントできるようになりました。
また「“重度”知的障がい者」の「短時間労働者(週20時間以上30時間未満)」を雇用した場合は「1人分」としてカウントできるようになりました。
1997年改正「知的障がい者」が義務化
知的障がい者が義務雇用の対象とされました。民間企業の法定雇用率は「1.8%」にアップされ、1998年7月に施行。
2006年改正「精神障がい者雇用」努力目標に
精神障がい者に対する雇用対策が強化され、精神障がい者が雇用率への算入に含まれることになりました。
2013年改正「合理的配慮の提供」義務化
障がい者の権利に関する条約の批准に向けた対応として、障がい者に対する差別の禁止および障がい者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずること(合理的配慮の提供)の義務が制定されました。
民間企業の法定雇用率は「2.0%」にアップ。
2016年改正「(改正)障害者雇用促進法」施行
2013年に改正された障害者雇用促進法が施行されました。
2018年改正「精神障がい者雇用」義務化
障がい者雇用義務の対象に精神障がい者が加わり、あわせて民間企業の法定雇用率は「2.2%」にアップされました。
障がい者雇用、面接を実施する場合のポイント
まとめ
障害者雇用促進法は、世の中の変化に対応しながら徐々にその範囲を広げ、障がい者の自立や社会との共生に寄与してきました。
2023年の法改正により対象となる企業の範囲が拡大されたことで、既に障がい者雇用を実施している企業だけでなく新たに義務対象となる企業も対応が必要です。障がい者雇用のための設備を用意するなど、ある程度の時間が必要になる場合もあります。事前に必要な手続きを確認した上で助成金なども活用し、今からでも準備を進めておきましょう。
こちらの資料もおすすめです
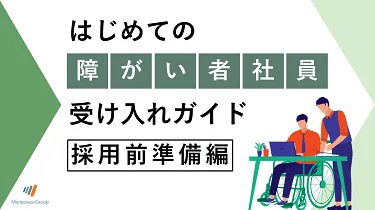
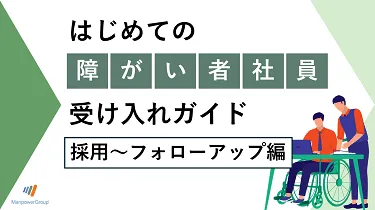
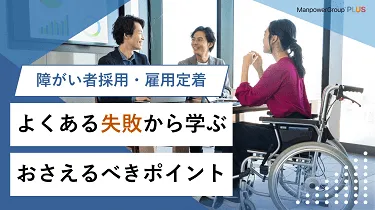

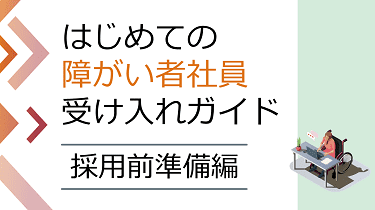
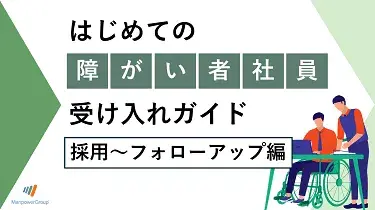


















 目次
目次