


【2025年改正】育児・介護休業法をわかりやすく解説

目次
2025年4月1日および10月1日の2回にわけて改正育児・介護休業法が施行されます。この記事では、育児・介護休業法の改正の背景や制度内容、企業に求められる対応などについて、順に解説します。
育児・介護休業法とは?含まれる制度
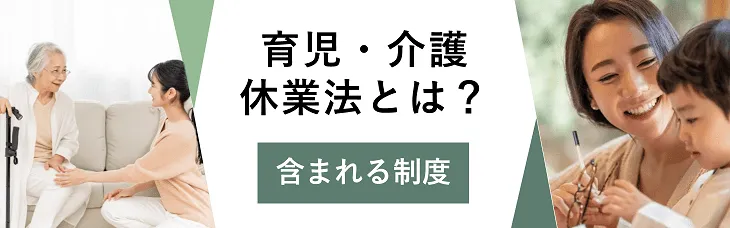
育児・介護休業法とは、働きながら育児や介護を行う従業員が、仕事と家庭生活をスムーズに両立できるようなサポートをするための法律です。
正式には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といい、その名のとおり育児・介護休業を取得する従業員だけではなく、育児や介護を行いながら仕事をする従業員も対象とした法律です。
育児休業制度
育児休業とは、子どもを育てる従業員が申し出ることで取得できる休業のことをいいます。企業側は、従業員が育児休業取得を申し出た場合は、以下のような場合を除き取得の申し出を拒否できません。
- 継続雇用期間が1年に満たない場合
- 1年以内に退職予定の場合
- 週あたり2日以下の出勤をする場合
など
育児休業の期間は、原則として子どもが1歳になるまでの間と決められています。ただし、子どもが1歳に達しても保育園へ入所できないなどの事情がある場合は、1歳6カ月まで延長が可能です。
さらに、子どもが1歳6カ月になっても事態が改善しない場合は、再度申請することで2歳まで延長して育児休業を取得できます。
育児休業は男女問わず取得可能で、男性従業員は子どもの出産日から、女性従業員は産後休業終了後から取得できます。
そのほか、両親ともに育児休業を取得した場合は、子どもが1歳2カ月になるまで休業期間が延長される「パパ・ママ育休プラス」や、妻が産後休業期間の間に育児休業を取得した男性従業員が特段の事情がなくても再度育児休業を取得できる「パパ休暇」制度など、男性従業員向けの育児休業制度も展開されています。
関連記事:産休代替とは?通常派遣との違いや利用する際の注意点を解説
介護休業制度
介護休業とは、要介護状態の家族を介護するための休業をいいます。なお、要介護状態とは、「負傷や疾病、身体上・精神上の障害を抱えており、2週間以上の期間にわたって常時介護が必要となる状態」のことを指します。
対象
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母
- 子
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
育児休業の場合と同じく、企業側は従業員が介護休業取得を申し出た場合、原則として取得の申し出を拒否できません。さらに、育児休業や介護休業の取得を理由として、その従業員の待遇を不当に扱うことも禁止されています。
介護休業は、入社1年以上で、取得予定日から数えて93日目を経過する日から6カ月以内に退職予定(契約満了)ではない従業員が取得できます。また、取得日数は対象家族1人あたり3回で、通算93日までです。
子の看護休暇
子の看護休暇とは、従業員が子どもの看護をするために取得できる休暇で、年次有給休暇とは別に設定する必要があります。看護とは、単に看病することをいうのではなく、予防接種(必須・任意ともに)や健康診断の受診にあてる時間も含まれることに注意が必要です。
対象となる子どもは小学校就学前の子で、休暇の取得限度は従業員1人あたり5日です。ただし、子が2人以上いる場合は10日となります。取得単位は、1日単位・半日単位に加え、2021年以降は時間単位も認められており、子を育てる従業員が仕事と家庭を両立させながら柔軟な働き方をできるよう設定されています。
介護休暇制度
介護休暇とは、要介護状態の家族を介護または世話をするためにあてる休業をいいます。要介護状態の定義や対象家族は、介護休業のケースと同様です。
介護休暇は、対象家族を介護する従業員(日雇い勤務者を除く)が取得できます。
ただし、入社6カ月未満の従業員や、所定労働日数が一週間あたり2日以下の従業員は、労使協定で対象外とすることも可能です。
なお、2025年4月1日からは、入社6カ月未満の従業員に対する除外規定が廃止され、介護休暇を取得することができます。
介護休業との違いのひとつは、介護休暇の取得可能日数が短期間ということです。子の看護休暇の場合と同じく、取得限度は従業員1人あたり5日で、対象家族が2人以上いる場合は10日です。
取得単位も、看護休暇と同様に1日単位、半日単位、2021年以降は時間単位も含めて認められており、家族の病院への付き添いやケアマネージャーとの面談時間を介護休暇としてあてることも可能です。
さらに、2週間前までの申請が必要となる介護休業と比べ、介護休暇は取得当日に口頭で申し出ることも認められています。
介護休暇は、介護休業と比較すると、気軽に家族の介護をサポートできる制度として定められている点に特徴があります。
| 介護休暇 | 介護休業 | |
| 対象家族 | 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹 | 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹 |
| 取得条件 | 入社6カ月未満の従業員や週あたり2日以下の出勤の従業員は対象外 (2025年4月1日からは入社6カ月未満の従業員も対象) |
入社1年以上で、取得予定日から数えて93日目を経過する日から6カ月以内に退職予定ではない従業員 |
| 取得日数 | 5日 (対象家族が2人以上の場合は10日) |
対象家族1人あたり3回で、通算93日まで |
| 取得単位 | 1日単位、半日単位、時間単位 | 1日単位 |
| 申請方法 | 当日に口頭で申し出ることも可能 | 2週間前までに申請が必要 |
育児・介護休業法の改正の背景とは
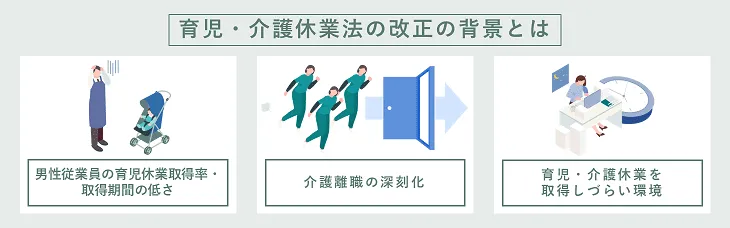
育児・介護休業法が改正されるに至った経緯を、現状も踏まえ説明します。
男性従業員の育児休業取得率・取得期間の低さ
「雇用均等基本調査」によれば、育児休業取得率は、女性は8割台で推移している一方、男性は上昇傾向にあるものの女性に比べて低い水準(2023年度30.1%)です。また、育児休業の取得期間は、女性の9割以上が6カ月以上の取得をしていますが、男性の取得期間は徐々に伸びているとはいえ、2週間未満の取得者が4割と、依然として女性と比べて短期間の取得が多いのが現状です。
介護離職の深刻化
介護離職とは、介護と仕事を両立させながら生活することが難しくなり、勤め先を退職してしまうことです。昨今では、この介護離職が深刻化しています。
介護の担い手が多くみられる世代は主に40代前後が多く、いわゆる働き盛りの世代でもあります。
企業としては、業務の中核を担う従業員の退職は大きな損失になり得ます。また、若い世代と比較すると、介護離職者の再就職は年齢的にも難しい傾向にあり、これまでに培った経験や能力が生かせず未就労のままにある人が多いことも問題です。
超高齢社会の日本では、今後も介護をしながら働く従業員は増加するだろうと考えられ、早急に対処しなければならない問題の一つとして挙げられています。
育児・介護休業を取得しづらい環境
有給休暇取得率の伸び悩みが懸念されている日本では、「会社を休む」という行為にも抵抗を感じる従業員が少なくありません。
特に、育児休業や介護休業を取得する状況になった場合、まとまった期間の休業になることから、さまざまな理由で取得に踏み切れないケースがみられます。
例えば、出世など今後のキャリアに影響するのではないかという懸念に加え、上司や同僚に気兼ねしてしまうこともあり得ます。
企業が育児・介護休業の取得に対して消極的だと従業員側から「育児休業を取得したい」とはなかなか言いづらいため、企業側が積極的に推奨していく必要性があるといえるでしょう。
関連記事:産休代替とは?通常派遣との違いや利用する際の注意点を解説
【2025年施行】育児・介護休業法の11の改正
育児・介護休業法では、2025年に施行される11の改正があります。
| 施行日 | 改正内容 |
| 2025年4月1日 | 子の看護休暇の見直し義務 |
| 2025年4月1日 | 所定外労働の制限の対象拡大義務 |
| 2025年4月1日 | 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加 |
| 2025年4月1日 | 育児のテレワーク導入努力義務 |
| 2025年4月1日 | 育児休業取得状況の公表義務適用拡大努力義務 |
| 2025年4月1日 | 介護休暇を取得できる従業員の要件緩和義務 |
| 2025年4月1日 | 介護離職防止のための雇用環境整備義務 |
| 2025年4月1日 | 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等義務 |
| 2025年4月1日 | 介護のためのテレワーク導入努力義務 |
| 2025年10月1日 | 柔軟な働き方を実現するための措置等義務 |
| 2025年10月1日 | 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴収・配慮義務 |
子の看護休暇の見直し(2025年4月1日施行)義務
今までは、対象となる子が「小学校就学前の始期に達するまで」とされていましたが、「小学3年生修了まで」に拡大されます。それと共に取得事由に、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式が新たに追加となり、休暇が取りやすくなります。また、取得事由の増加により、名称が「子の看護休暇等」に変更されます。
さらに、労使協定により除外されていた「継続期間6カ月未満の従業員」に対する除外規定が廃止され、採用期間が短くても子の看護休暇を使えるようになります。
ただし、週の所定労働日数が2日以下の従業員は、従来どおり除外されます。なお、取得日数の変更はなく、1年に5日、子が2人以上の場合は10日取得できます。
変更内容
小学校就学前の始期に達するまで → 小学3年生修了まで
取得事由の追加 → 「感染症に伴う学級閉鎖等」や「入園(入学)式、卒園式」
対象者の変更 → 継続期間6カ月未満の従業員が撤廃
所定外労働の制限の対象拡大(2025年4月1日施行)義務
これまでは3歳未満の子を養育する従業員が、子を養育するための所定外労働の免除を企業に請求をした場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはできませんでした。今回の改正により、所定外労働の制限の対象が「小学校就学前の子を養育する従業員」に拡大されます。
なお、所定外労働の制限とは、法定労働時間(8時間)を超えて働かせることを禁止しているのではなく、各企業が定めた所定労働時間を超えて働かせることを禁止するものです。
例えば、所定労働時間が7時間の企業であれば、法定労働時間の8時間を超える時間外労働ではなく、7時間を超える時間外労働が禁止されていることになります。そのため、所定労働時間が8時間に満たない企業は、特に注意が必要です。
▽所定労働時間の免除をできる従業員
3歳未満の子を養育する従業員 → 小学校就学前の子を養育する従業員
短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加(2024年4月1日施行)
短時間勤務制度を利用することができない業務に従事する従業員に対しては、労使協定を締結して代替措置を講じることが求められていました。
これまでの代替措置として、フレックスタイム制、時差出勤制度、事業所内託児施設等の3つがありましたが、今回の改正により、テレワークが追加されます。なお、テレワークを選択する場合は、就業規則等の見直しが必要です。
- フレックスタイム制
- 時差出勤制度
- 事業所内託児施設等
- テレワーク
育児のテレワーク導入(2025年4月1日施行)努力義務
3歳未満の子を養育する従業員がテレワークを選択できるよう、企業が措置を講じることが努力義務化されます。
コロナ禍をきっかけにテレワークを導入した企業も多く、テレワークに積極的な企業も多く見かけます。
今回の改正では、テレワーク導入は義務ではないので、すぐに導入しなくても構いませんが、努力義務事項は数年後に義務化されるのが定石ですので、今から準備を始めることをおすすめします。
育児休業取得状況の公表義務適用拡大(2025年4月1日施行)義務
公表義務の対象企業が、従業員数1,000人超の企業から300人超の企業に拡大されます。
公表する内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。公表は年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3カ月以内に、インターネットなど一般の人も閲覧できる方法で行います。
公表内容
- 男性の育児休業等の取得率
- 育児休業等と育児目的休暇の取得率
※育児目的休暇とは、育児を目的とする休暇であることがあきらかな企業独自の休暇制度
▽公表義務の対象企業
従業員数 1,000人超 → 300人超
介護休暇を取得できる従業員の要件緩和(2025年4月1日施行)義務
労使協定による継続雇用期間6カ月未満の従業員を休暇の対象から除外していた場合、この除外規定が廃止されます。なお、週の所定労働日数が2日以下の従業員については、今までと同様に対象外とすることができます。
▽対象者の拡大
継続雇用期間6カ月未満 → 対象者に
介護離職防止のための雇用環境整備(2025年4月1日施行)義務
介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、企業は以下の①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。
なお、介護両立支援制度とは、介護休暇に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に関する制度、深夜業の制限に関する制度、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を指します。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
- 自社の従業員の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
- 自社の従業員へ介護休業・両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
これらの4つの措置のうち1つを講じれば義務を果たすことになりますが、複数の措置を講じることが望ましいとされています。
介護休業等に関しては制度をよく知らない従業員も多いため、研修実施の際は年代を絞らず全従業員を対象とすることをおすすめします。
相談体制の整備については、特別に介護専用の相談窓口を設ける必要はなく、ハラスメント相談窓口など既存の相談窓口を活用しても問題ありません。ただし、どのような相談に対応をするのかを明確にし、全従業員に周知する必要があります。
介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(2025年4月1日施行)義務
介護離職防止のための個別の周知・意向確認等に関しては、以下2つの義務があります。
(1)介護休業制度等についての周知
介護に直面した旨の申出をした従業員には、介護休業制度等に関する以下の事項の周知と、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用意向の確認を個別に行わなければなりません。
- 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
- 介護休業・介護両立支援制度の申出先
- 介護休業給付金に関すること
これらは個別に周知し、意向を確認することになり、面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかで行いますが、FAXと電子メールは、対象者が希望した時にのみ利用することができます。
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
従業員が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援等の理解を深めるため、以下の情報提供が義務化されます。
①情報提供機関
- 従業員が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
- 従業員が40歳に達した日の翌日から1年間 のいずれか
②情報提供事項
- 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
- 介護休業・介護両立支援制度等の申出先
- 介護休業給付金に関すること
③情報の提供方法
(1)と同様に面談、書面交付、FAX,電子メール等 のいずれか
(1)の介護に直面した従業員だけでなく、その前段階の従業員に対しても早期に情報提供を行うことが求められます。
前述した介護離職のための雇用環境整備の義務化とともに、全従業員を対象にした介護に関する研修や個別説明の実施が、介護と仕事の両立を支援する職場環境の形成に役立ちます。
介護のためのテレワーク導入(2025年4月1日施行)努力義務
要介護状態にある対象家族を介護するために従業員がテレワークを選択できるよう措置を講じることが努力義務化されます。
テレワークに関しては、すでに就業規則等に規定している企業も増えていますが、今後はその対象者に介護をしている従業員を含まれることになります。
どの程度の介護状態でテレワークを認めるかという問題もありますが、介護休業が認めている「要介護状態にある対象家族を介護する従業員」と同様に考慮するのがよいでしょう。
ただし、介護休業で規定されている「要介護状態」は比較的重度のケースが多いため、自社の従業員の意見を参考にし、どの程度の介護状態からテレワークを導入すべきか、義務化前の検討が重要です。
柔軟な働き方を実現するための措置等(2025年10月1日)義務
柔軟な働き方を実現するための措置等に関する義務は、以下の2つがあります。
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等
企業は、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に関して、以下5つの講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して実施する必要があります。
また、従業員は、企業が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。会社が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を向ける必要があります。
【選択して講ずべき措置】
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/月)
⑤短時間勤務制度
※②と④は時間単位での取得を認める必要があります。
これらの措置のなかで2つ以上を選択することは、一部の企業においては難しいかもしれませんが、⑤の短時間勤務制度は、小学校就学前までの子どもを対象に延長するだけなので導入しやすく、従業員の利便性も高いでしょう。
また、②のテレワーク導入に関しては、これを機に導入を進めるきっかけとしてもいいでしょう。ただし、業務の内容によりテレワークの利用が難しい場合もあるので、④の養育両立支援休暇の導入も無給であることを考慮すれば比較的導入しやすい措置だといえるでしょう。
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳に満たない子を養育する従業員に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、企業は柔軟な働き方を実現するための措置として上記(1)で選択した制度に関する以下の事項の周知と制度利用の意向確認を、個別に行わなければなりません。
周知時期
従業員の子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間
周知事項
- 企業が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容
- 対象措置の申出先
- 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
個別周知・意向確認の方法
面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれか
子が3歳になる前の1年間に対象者と面談を実施し、復帰後の働き方や選択できる働き方について説明します。その上で、仕事と育児の両立ができるよう、企業と従業員双方が協力して柔軟な働き方を実現していくことが重要です。利用しやすい措置を講じることが求められます。
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴収・配慮(2025年10月1日施行)義務
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴収・配慮についての義務は、2つあります。
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
企業は、従業員が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た際、従業員の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、従業員の意向を個別に聴取しなければなりません。
意向聴取の時期
- 従業員が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
- 従業員の子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間
聴取内容
- 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
- 勤務地(就業の場所)
- 両立支援制度等の利用期間
- 仕事と育児の両立に関する就業の条件(業務量、労働条件等の見直し等)
意向聴取の方法
面談、書面交付、FAX、電子メールのいずれか
この面談では、妊娠・出産時期と育児時期における仕事の具体的な調整について、説明・相談を行います。
(2)聴取した従業員の意向についての配慮
企業は、(1)により聴取した従業員の仕事と育児の両立に関する意向を尊重し、自社の状況に応じて配慮してなければなりません。
配慮は必要ですが、希望が就業規則に反する場合や、同僚に大きな負担がかかるような業務を要求される場合には、その点を説明して納得させることも必要です。企業に過度の負担がかかるケースもありますので、その働き方が適切かどうか慎重に検討しましょう。
【参照】2022年~2023年の育児・介護休業法の改正
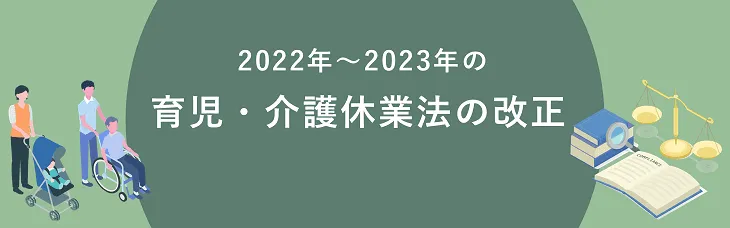
参考までに直近の改正内容もご確認ください。
育児・介護休業法の主な改正ポイントは以下の5つです。
| 施行日 | 改正内容 |
| 2022年10月1日 | 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設 |
| 2022年10月1日 | 育児休業の分割取得が可能に |
| 2022年4月1日 | 企業の育休における雇用環境整備などが義務化 |
| 2022年4月1日 | 有期雇用労働者の取得要件緩和 |
| 2023年4月1日 | 育児休業の取得状況の公表義務化 |
具体的な改正ポイントを内容別に確認しましょう。
出生時育児休業(産後パパ育休)の創設(2022年10月1日施行)
改正の目玉である施策は「出生時育児休業(産後パパ育休)」の創設です。
出生時育児休業とは、子どもが生まれた後の8週間(女性労働者が産後休業を取得している期間)について、育児休業とは別に最大4週間まで休業できる制度です。休業の2週間前までに申し出れば、2回に分割して取得することも可能です。
出産直後は、母親が体調を回復させながら子どもとの生活リズムを整える重要な時期です。その時期に男性労働者が取得できる休暇制度を設けることで、男性が積極的に家事や育児にかかわる機会が生まれ、性別に関わらず育児と仕事を両立させた生活がしやすくなるねらいがあります。
育児休業の分割取得が可能に(2022年10月1日施行)
これまでは、特段の事情がある場合を除き育児休業の回数は子ども一人(双子以上の場合も同様)あたり1回となり、育児休業の延長も子どもが1歳、1歳半、2歳の誕生日を迎えるタイミングに限られていることから、介護休業のような分割取得が認められていませんでした。
改正により、育児休業を2回まで分割して取得できるようになりました。子どもが1歳以上になって育児休業を延長する場合などにも、育児休業を分割し2度目の休業の開始日を調整することで、夫婦がバトンタッチしながら育児休業を取得できるようになりました。
企業の育休における雇用環境整備などが義務化(2022年4月1日施行)
育児休業を取得しやすい環境づくりのためには、企業側が育児休業に対する理解を深め、積極的な姿勢を取ることが必要です。
改正により、育児休業を取りやすい雇用環境の整備や、妊娠・出産を申し出た労働者に対する個別対応が義務づけられることになりました。
雇用環境の整備には具体的に以下の措置が挙げられ、事業主はこのいずれかの内容を講じる必要があります。
- 育児休業や産後パパ育休についての研修を実施
- 育児休業や産後パパ育休についての相談窓口体制の整備
- 自社の労働者が育児休業や産後パパ育休を取得した際の事例を提供
- 自社の労働者への、育児休業や産後パパ育休制度・取得促進に関する方針の周知
また、妊娠・出産を申し出た労働者に対する個別対応とは、育児休業制度の詳細を知らせた上で、面談・書面交付・FAX・メールなどにより休業申し出の労働者の意向を確認することです。
これは、あくまでも労働者からの申し出がスムーズに行われることを目的とするものであり、取得を控えさせるような行為は認められない点に注意が必要です。
有期雇用労働者の取得要件緩和(2022年4月1日施行)
これまでは、育児休業を取得できる有期雇用労働者の要件には「継続雇用期間が1年以上であること」と設定されていました。
改正により、これが撤廃となりました。なお、「子どもが1歳6ヶ月を迎えるまでの期間に契約満了をしないことが明らかであること」という要件は継続されますが、これは実際に育児休業の申し出があった際に労使間で労働契約が更新されるかどうかで判断されます。
なお介護休業の場合も同様で、これまでの要件のひとつであった「継続雇用期間が1年以上であること」が撤廃となり、「介護休業開始予定日から93日経過後より6ヶ月間の間に契約満了をしないことが明らかであること」のみが判断基準となりました。
育児休業の取得状況の公表義務化(2023年4月1日施行)
今回の改正により、常時雇用の従業員数が1000人を超える大企業(2025年からは300人以上)には、「育児休業など」の取得状況、特に男性従業員の育児休業などの取得状況に関して、毎年1回公表することが義務づけられました。
「育児休業など」には、育児休業や産後パパ育休に加え、3歳未満の子を養育する従業員向けの制度や、小学校就学前の子を養育する従業員向けの制度なども含みます。
具体的には、次のいずれかの割合を、インターネットなど一般者が閲覧できるような形式で公表する必要があります。
- 育児休業などの取得割合:配偶者の出産数から、男性労働者が育児休業などを取得した割合を算出する
- 育児休業など・育児目的休暇の取得割合:配偶者の出産数から、男性労働者の育児休業など取得と育児を目的とした休暇制度を利用した者の合計割合を算出する
育児・介護休業法で企業が求められる5つの対応

本章では、法改正を受けて企業がどのような対応を進めればよいか、具体的な説明をします。
就業規則を改定する
就業規則の改定にあたり、まず現状の就業規則内容の洗い出しを行います。昨今、労働者の雇用にまつわる法律の改正が相次いでおり、それぞれの改正内容が自社の就業規則に適用されているか確認しておきましょう。
厚生労働省のホームページなどで確認できる、最新の法律に沿った就業規則モデルを参考にしながら内容の見直しを行う方法が効果的です。
その上で、育児休業・介護休業などの内容を改定します。育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇など、制度内容ごとに就業規則が最新の改正内容に沿っているか、一つずつ確認しましょう。育児や介護休業の対象者向けの労使協定締結が必要な場合は、早急に準備を進める必要があります。
また、テレワークは仕事と育児・介護の両立に欠かせない働き方なので、これを機にテレワーク規程を新しく作ることをおすすめします。
育児・介護休業を取得しやすい環境を整備する
今回の法改正で注目されているのが、男性の育児休業取得を促進するための制度です。したがって、企業側がまず念頭に置かなければならないのは、「男女問わず、育児・介護休業を取得しやすい環境づくりを心がける」ことです。
これまで女性労働者を中心に実施されることが多かった出産・育児を想定した人材配置や欠員時の補充体制、業務量の調整などを、今後はすべての世代の男女労働者向けに拡大し、実施する必要があります。
また、社員が育児・介護休業に対する知識を深められるよう、育児・介護休業に関する最新情報を適宜周知することを怠らないようにしましょう。
さらに、休業取得者に対するハラスメント防止研修の実施や、相談窓口の設置などを通じて、企業全体が育児・介護休業の意義を深く理解していく必要があります。
育児・介護休業取得状況を把握する
社員の育児・介護休業取得状況を把握するためには、常日頃から社員へリサーチを行うことが必須です。
社員本人が妊娠した場合ならば企業側も把握が容易ですが、男性労働者の配偶者が妊娠をした場合や、家族・親族の介護が必要となりそうな場合など、一見して分かりにくいところで育児休業や介護休業の要因となる事態が発生している可能性があります。
実際に育児・介護休業を取得する可能性が生じた場合は、早めに対応することが効果的です。対象労働者の所属部署に対して、ヘルプ体制や連携体制を整えるなどを開始し、慌てず準備を行いましょう。
休業から復帰した社員のためのサポート環境を整備する
育児休業や介護休業から復帰する社員は、職場の雰囲気や仕事のペース、家庭との両立生活に慣れるまではさまざまな不安を抱えているものです。
企業側では、その不安を少しでも取り除けるよう、サポート環境を整備する必要があります。
まず、社員が復帰する前段階で、復帰後に社員が利用できる制度を確認しておきます。例えば、時短勤務や残業・深夜業の制限、子の看護休暇や介護休暇など、仕事と介護・育児を両立する際の負担を減らすためのさまざまな制度があります。
そして、社員の復帰前の面談でこれらの制度を確認しながら、希望の働き方のすり合わせを行いましょう。
ですが、たとえ企業と社員の双方が入念に準備をしても、実際に復帰してみると予想とは違う状態になることもあるでしょう。
「復帰したらサポートは終了」というのではなく、育児や介護にかかわる社員を取り巻く状況は常に変化していくことを念頭に置き、長期的なサポートを実施していきましょう。
業務をカバーする社員のサポートに派遣を活用しませんか
休業や時短勤務を取得する社員をサポートするために、派遣サービスが利用されています。
<人材派遣を活用するメリット>
・必要な時間、期間で契約できる
・負担を減らすことで、従業員間の不満を解消
・人手不足による部門のパフォーマンス低下を防止
人材派遣の利用を検討されている方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

派遣社員も対象になることに留意
派遣社員は派遣会社が雇用主ではありますが、派遣先にも使用者として、法律に基づく一定の責務があります。自社社員と同様に派遣社員に対しても、育児・介護休業法等の法律が適用されることを認識しておきましょう。
例えば、派遣社員の妊娠・出産を理由に契約を更新しない、または途中解除することは、不利益扱いと判定され違法となる可能性があります。
まとめ
今回の改正は、単に制度を整備することから進んだ、制度を使いやすく効果的なものにするためのさまざまな措置の拡充や個別の説明・意向確認等を義務化しています。
企業にとっては、制度の導入だけでなく、いかに従業員に使ってもらいやすい環境を作るかの工夫が必要です。仕事と育児・介護の両立が実現できるようになることは、安心して働ける職場環境の形成につながりますので、従業員が使いやすく、自社に合う制度を考えていきましょう。
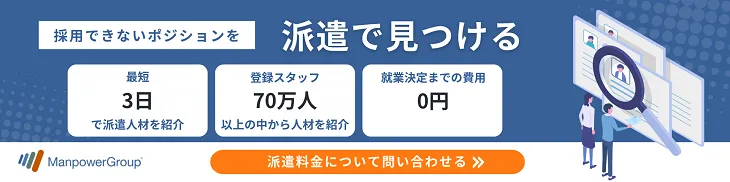




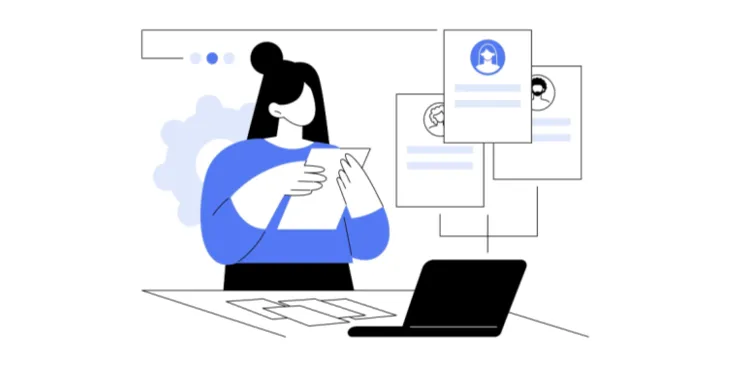











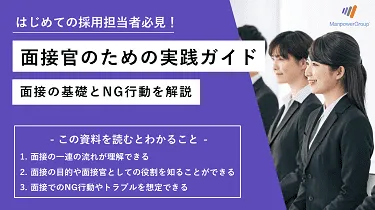




 目次
目次