


2025年(令和7年)の人事関連法改正について解説

目次
毎年多くの法律が改正されますが、特に4月1日は多くの改正法が施行されます。2025年の人事に関連した法改正のポイントと、対応すべき事項を解説します。
2024年の人事関連法改正の振り返り
以下は、2024年に施行された人事関連の法改正一覧です。
| 法律(施行月) | 内容 |
| 健康保険法・厚生年金保険法(10月) | 社会保険の適用拡大 |
| 障害者雇用促進法(4月) | 法定雇用率のアップ、対象事業所の範囲拡大 |
| 労働基準法(4月) | 労働条件明示ルールの変更 |
| 職業安定法(4月) | 求人募集の明示事項の追加 |
2024年施行の人事関連法改正は少なく、大きな改正がある2025年の施行に向けての準備
時期と言えるかもしれません。この中では社会保険の適用が拡大されたことと、有期雇用における5年ルールの対象者に対する書面での明示義務が、企業にとっては負担がある大きな改正でした。
2025年に予定されている人事関連法改正
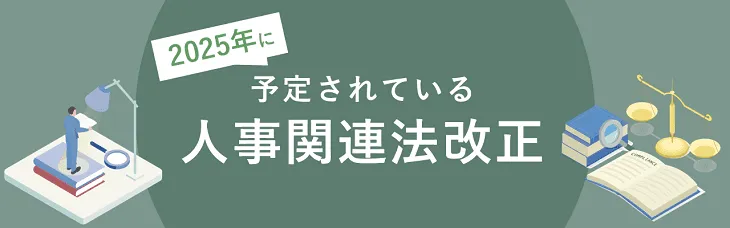
以下は、2025年に施行される人事関連の法改正の一覧です。
| 法律(施行月) | 内容 |
|
男女とも仕事育児を両立できるような柔軟な働き方を実現するための措置や拡充 介護離職防止のための雇用環境の整備、個別周知・意向確認の義務化 |
|
| 65歳までの雇用確保の義務化 | |
| 高齢者雇用継続給付金の縮小 | |
| 除外率の引き下げ | |
|
柔軟な働き方を実現するための措置等 両立に関する個別の意向聴収・配慮 |
2025年の人事関連法改正は2024年に比べて多く、特に育児・介護休業法は、施行日が2回に分けてあるにも関わらず、対応すべき事項が多いと考えられます。また、高年齢者雇用安定法や雇用保険法の改正も企業にとっては、負担が大きい改正です。
2025年の改正の具体的な内容、そして企業として準備すべきポイントについて詳しく解説します。
育児・介護休業法
2025年4月1日施行の育児介護休業法の改正点は、具体的には以下のようになります。
1.子の看護休暇の見直し
義務:就業規則の見直し等必要
- 対象が小学校入学前の子から小学校3年生終了時までとなり、対象が拡大。
- 病気やケガ、予防接種等以外に感染症に伴う学級閉鎖等や入園(入学)式、卒園式でも取得が可能に。
- 継続雇用期間が6カ月未満の労働者も新たに対象に。
- 「子の看護休暇」という名称が「子の看護等休暇」に変更。
2.残業免除の対象拡大
義務:就業規則の見直し等必要
- 対象労働者が、3歳未満の子を養育する労働者から小学校就学前の子を養育する労働者に拡大。
3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
追加:選択する場合は就業規則の見直し等必要
- 短時間勤務制度を利用できない業務の労働者への代替措置にテレワークが追加。
4.育児のためのテレワークの導入(努力義務:就業規則の見直し等必要)
- 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが企業の努力義務となる。
- 努力義務だが、努力義務は数年後には義務となるので、今から準備が必要。
5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大(義務)
- 今までは従業員数1,000人超の企業が対象だったが、4月からは300人超の企業も対象。
6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
義務:労使協定で除外できる設定している場合は就業規則の見直し等必要
- 労使協定により継続雇用期間6カ月未満の労働者を除外していた企業は、その規定を廃止。
7.介護離職防止のための雇用環境整備
義務:介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の ①~④いずれかの措置を講じなければならない。
①研修の実施
②相談窓口の設置
③事例の収集・提供
④利用促進に関する方針の周知
8.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
義務:下記の措置を講じる
- 介護をしなければならなくなったと申し出た労働者に対して個別に面談等を行い、介護休業制度等についての説明と制度利用の確認を行う。
- 介護に直面する前の早い時期(40歳等)に、個別に面談をして介護休業制度等について情報提供をしなければならない。
9.介護のためのテレワークの導入
努力義務:就業規則の見直し等必要
- 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるようにする。
10.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置(2025年10月1日施行)
義務:就業規則の見直し等必要
- 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して5つの選択肢から2つ以上の措置を選択して制度化する
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(月に10日以上)
③保育施設の設置運営等
④養育両立支援休暇の付与(年10日以上)
⑤短時間勤務制度
- 3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、個別に面談等をして、選択した制度に関する周知と制度利用の意向の確認を行わなければならない
11.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴収・配慮(2025年10月1日施行)
義務:下記の措置を講じる
- 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前に個別の意向を聴収する
- 聴収した労働者の意向に配慮する
高年齢者雇用安定法
高年齢者雇用安定法の改正に伴って「65歳までの雇用確保」が完全義務化されました。
定年年齢を65歳未満に定めている企業は、以下の3つの措置のうちいずれかを講じることが義務となっています。
- 65歳までの定年の引上げ
- 希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度の導入
- 定年の廃止
この中で65歳までの継続雇用制度を導入した企業が多かったのですが、この導入制度については、対象者を限定する経過措置が認められていました。この経過措置が2025年3月31日に終了して、4月1日からは希望する従業員全員に対して、65歳までの雇用機会の確保が義務化されます。
この継続雇用に関しては、制度対象者はあくまでも希望者が対象となりますので全員を雇用する義務はありません。
また、以前から継続雇用の対象者を限定していなかった企業は、今まで通りで変更する必要はありません。
雇用保険法
高年齢雇用継続給付金について、賃金の最大15%から最大10%に縮小されます。
60歳を超えた従業員の賃金が多くの企業で引き下げられるため、賃金減少を補うために高年齢雇用継続給付金を活用するケースも多かったのではないでしょうか。従業員の生活の安定と経験豊富な人材の継続雇用が叶う企業と従業員の双方にとってプラスの影響をあたえるものでした。
この給付金が2025年4月1日から最大10%に縮小されます。また、この改正は2025年4月1日時点から60歳になる労働者が対象となります。
障害者雇用促進法
障害者雇用除外率が10%引き下げられます。除外率設定業種の企業は、障がい者の雇用人数を計算する場合に一定の割合で人数を控除することができます。この除外率が引き下げられることにより、対象企業は今までより多くの障がい者を雇用する必要がでてきます。
| 除外率設定業種 | 除外率 |
|
5% |
|
10% |
|
15% |
|
20% |
|
25% |
|
30% |
|
35% |
|
40% |
|
45% |
|
50% |
|
70% |
引用:除外率設定業種及び除外率(令和7年4月以降)|厚生労働省 ![]()
2025年の法改正に向けて企業が備えるべきこと
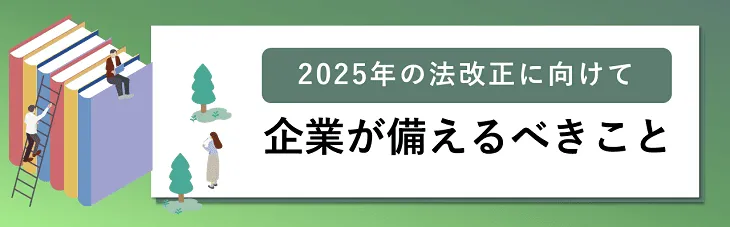
2025年は、育児・介護休業法について大きな改正があり、就業規則の大幅な見直しや新たな制度の構築などやるべきことがたくさんあります。また雇用保険法など賃金規程の改正なども必要です。そこで、改正された法律の施行に向けて何をすればよいのか等その一例をご紹介します。
育児・介護休業法
今回の法改正は多岐にわたっており、特に柔軟な働き方を実現するためにさまざまな対策を検討する必要があります。
子の看護休暇
子の看護休暇等については、対象者の拡大とともにその取得理由も幅広くなりましたので今後休暇を取る従業員が増えてくる可能性があります。
現在は1日単位で取得を認めている企業が多いものの、これを機に半日単位や時間単位での取得を認めることで、人手不足に対応しつつ、従業員の定着促進への効果が期待できます。
残業免除への対策
残業免除については、対象者が拡大します。残業を免除された従業員がいる職場では、他の同僚が残業の負担増に不満を抱く可能性があります。チーム内の軋轢が起きてしまうと、チームの業績や離職などにも影響がでてしまいます。
派遣サービスなどを利用する、ITツールを導入し業務を効率化するなど、従業員同士で不公平感が増さないような対策が必要です。
育児のためのテレワークの導入
育児のためのテレワーク導入は今回努力義務となりましたが、同時に介護のためのテレワーク導入も努力義務として改正されています。数年後に義務となることを見越して今からテレワークの規程を新たに作成することをおすすめします。
努力義務の段階で導入することは、他社との差別化を図り、人材募集時のアピールポイントとなります。また、テレワークの対象を育児や介護に限定せず、病気療養中の従業員などにも拡大することで、従業員間の不満を抑え、企業の魅力を強化することができるでしょう。
関連記事:
介護離職の防止
介護離職防止のための措置としては、まず育児と介護の両立支援に関する専任担当者を選任することが重要です。制度や関連法律に精通した専任者を配置することで、相談対応や、法改正で義務となった個別説明や意向確認を適切に行うことができます。
担当者は希望者を募ることで意欲を持って取り組むことが期待され、他社に負けない両立支援制度の構築につながるでしょう。
高年齢者雇用安定法・雇用保険法
継続雇用制度の対象者を限定していた企業は、2025年4月1日から希望者全員を対象とする必要があるため、雇用契約書や就業規則の改定を行いましょう。
高年齢雇用継続給付を収入の一部として60歳以降の賃金設定をしていた企業では、給付金の減少により従業員の収入が減少することが懸念されます。その結果、モチベーション低下や退職者の増加につながる懸念があります。
このような事態を防ぐためには、給付金の5%減少に伴い、基本賃金を引き上げる、または新たな手当を設けて基本賃金に上乗せするなど、総支給額を従来と変えない60歳以降の新たな賃金制度の構築を検討しましょう。
ポイントは、60歳以降働く従業員の総支給額を今までと変えないことです。「同じ仕事をしているのに自分の方が少ないのはおかしい」といった不公平感を与えない工夫が必要です。
関連資料:定年後を見据えた人事制度設計とは 5つのポイントを解説
障害者雇用促進法
障害者雇用除外率が10%引き下げられることにより、除外率設定業種の企業においては、障がい者の雇用が増えることになります。障がい者の雇用に関しては、障害者雇用支援サービスを利用するのも一つの手です。障害者雇用支援サービスは、障がい者と企業の間に入ってマッチングをしたり、雇用につなげるための支援をしたりする事業者です。
障害者雇用除外率の引き下げを機に、障がい者だけでなく全ての従業員が働きやすい職場環境形成につながっていくように、規程を見直すことをおすすめします。
まとめ
法改正に対する早めの準備は、人事担当者にとって重要な役割です。2025年の改正では、柔軟な働き方を実現するための改正が多くみられました。一つひとつ自社に合うように制度を構築し、少しでも従業員が働きやすい職場を形成することで、自社でずっと働きたいと考える従業員が増えることにつながっていきます。従業員が安心して働ける職場環境を目指して取り組んでいきましょう。
こちらの資料もおすすめです


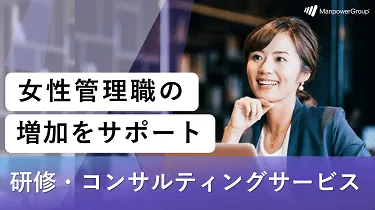
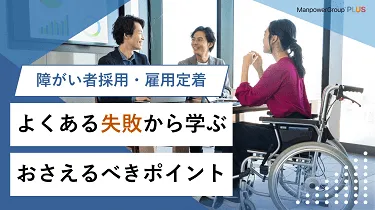
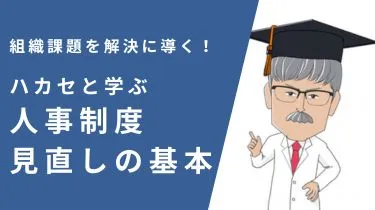

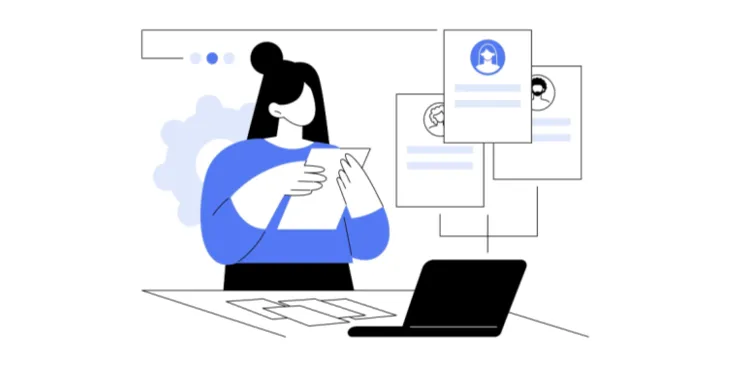















 目次
目次