


人事のキャリアプランとは?キャリアパスの描き方と実践ポイント

目次
人事の仕事には、労務管理、採用、研修、人事制度設計など様々な分野があります。それぞれの業務ごとに役割やスタンス、求められるスキルが異なるため、キャリアの積み方もひとつではありません。
また、特定の分野を深めて専門性を高める道もあれば、幅広い業務を経験して活躍の場を広げることもできます。
本記事では、人事担当者の主な業務について整理し、どのようなキャリアの築き方があるかを解説します。
人事業務の種類とルート

人事の仕事は大きく分けて4つに分類できます。それぞれの業務の役割ややりがい、課題、そしてキャリアパスとしての関係性を紹介します。
採用業務
業務内容
採用戦略の立案に始まり、求人票・募集要項の作成、応募者の書類選考、面接運営、選考過程の管理、内定通知の作成まで幅広い業務を担います。
採用手法は、求人媒体、人材紹介、採用代行、ダイレクトリクルーティングなど多岐にわたり、アルバイト・新卒・中途採用のそれぞれに適した手法の選定が必要です。
また、応募者とのコミュニケーションや社内関係部門との調整、会社説明会の企画・実施、採用マーケティングなども重要な業務に含まれます。
やりがい
- 採用手法やマーケティングの工夫によって応募者数や応募者層が変化し、取り組みの成果をダイレクトに実感できる
- 自身の言動が入社の決め手になった、配属先から感謝されたなど、社内からのポジティブな反応が励みになる
- 採用した人材の活躍を目にすることで、取り組みの意義を実感できる
- 経営戦略を人材面から支える役割を担っている実感が得られる
苦心する点
- 応募が集まらない、選考辞退が続くなど、採用活動が思うように進まないプレッシャー
- 採用活動の精度を高めるには、市場動向や競合の採用状況を常に把握する必要がある
- 経営層や現場とのすり合わせで情報発信や調整役を担う場面も多い
- 面接官全体での判断基準の統一や、選考の質を保つ調整の難しさがある
労務管理業務
業務内容
労務管理業務は、従業員が適切な環境で働けるように支援する役割です。
主な業務内容
- 勤怠管理
- 給与計算
- 社会保険手続き
- 入退社管理
- メンタルヘルス対応
- 定期健康診断
- 社内制度(各種手当や福利厚生の管理・運用)
- 労働組合との交渉や調整
- 産休・育休・介護休業の手続き
- マイナンバー管理
- 各種証明書の発行
など
また、法令遵守の確認、働き方改革の推進、HRテクノロジー(DX)導入などを人事労務担当が主導することもあります。
やりがい
- 出産や育児、病気など従業員の人生の節目に寄り添い、制度案内や手続きを通じて安心を支えられる
- ハラスメントや働き方の相談対応を通じて、信頼される存在として頼られる
- 法令知識や実務スキルを活かし、企業のコンプライアンス体制を支える重要な役割を担える
- 社会保険労務士など、専門性を高めるキャリアステップにもつながる
苦心する点
- 同じ質問でも、従業員にとっては初めての場合が多く、毎回丁寧な対応が求められる
- 労使トラブルやメンタル不調への対応など、一人ひとりの事情に向き合う必要があり、柔軟さや感情労働への対応力が必要になる
- 個人情報や機微なテーマを扱う場面が多く、高い倫理観と注意力が求められる
- 制度や法改正への対応など、継続的なインプットが欠かせない
研修業務(人材開発)
業務内容
研修業務は、研修計画の立案から実施、参加者の管理、研修資料・教材作成、研修の進行・運営、アンケートや成果の分析、フォローアップ、研修制度の改善提案などを担当します。
教育は企業の方向性や将来性に影響するので、現場の課題に即したボトムアップの視点と、経営の意向を踏まえたトップダウンの視点の両方から支援する業務と言えます。
階層別研修(新入社員研修や管理職研修など)、業務スキル向上を目的とした研修、法令周知のための研修など、さまざまな種類の研修を実施します。
また、自社の成長戦略に即した研修体系の構築も重要な役割です。
eラーニングや外部プログラムなども活用し、研修の目的に応じた最適な手法で、企業と従業員双方の成長を支えます。
やりがい
- 自身が担当した研修を通じて、従業員の成長を実感できる
例:プレゼン研修後に自信を持って全社プロジェクトの発表ができるようになる、管理職研修後にチームの雰囲気が改善される など
- 「わかりやすかった」「役に立った」などの受講者からの反応が、やりがいや自信につながる
- 教育を通じて企業全体のレベルアップを後押しできる実感がある
- 多様な研修テーマや講師・受講者層に関わることで、企画・運営力やファシリテーション力など自分自身のスキル向上にもつながる
苦心する点
- 研修の成果が目に見えにくく、効果の評価が難しい
- 法改正などテーマによっては成果が見えやすいが、行動変容に関わる研修はビフォーアフターの判断がしづらい
- 現場要望に対して納得感のあるメニューを設定するまでに、時間や労力を要することがある
- 「受講して終わり」にしないために、現場への定着や行動変容までを見据えた工夫やフォローが求められる
人事制度業務
業務内容
人事制度業務は、企業の経営戦略に基づき、採用、評価、報酬、育成など人事制度全般の設計・運用を担います。
等級制度、給与体系、評価制度、福利厚生、キャリアパスの構築に加え、就業規則の作成・改訂、昇進・昇格基準の策定や従業員満足度の向上施策などを行います。
また、障がい者雇用、定年延長、女性管理職の登用など多様な人材の活躍を支えるダイバーシティ推進や、企業文化や業界特性を踏まえた制度設計も重要な役割です。
やりがい
- 人事制度の改革を通じて、従業員のモチベーション向上や業績改善に貢献していると実感できる
- 制度導入後、従業員の意識や行動に変化が現れ、意識調査などで感謝の声などポジティブな反応を得られることもある
- 企業の働きやすさや組織の雰囲気を良くするために、課題を見つけ、それを改善する施策を打ち出すことで、企業成長を支えている実感が持てる
苦心する点
- 経営層と現場の要望を調整する必要があり、利害の異なる関係者間での調整力が求められる
- 公平性を意識するあまり制度が複雑になり、理解・運用が難しくなると“制度倒れ”になるおそれがある
- 制度が従業員の意欲や社風に影響を与えるため、慎重でセンシティブな対応が求められる
- 制度の効果が出るまでに時間がかかり、粘り強く検証・改善を続ける必要がある
人事部内でのキャリアパスのルート
人事部内でのキャリアパスは企業によって異なりますが、典型的なステップとしては、まず労務管理、採用、研修のいずれかの実務からキャリアをスタートするケースが一般的です。
一方で、人事制度設計の業務には、ある程度の経験を積んだ後キャリアの中盤以降に携わることが一般的です。
この背景には、人事業務間の密接なつながりがあります。制度設計を担うには、現場の実態や従業員の声を把握しておく必要があり、幅広い業務経験が制度の現実的な運用に活かせるためです。
<人事業務間の結びつきの例>
- 採用業務で得た市況理解は、柔軟な勤務制度や福利厚生などの制度設計に活かされます
- 労務管理の実務経験(残業の実態や部署間の業務負荷の把握)は、給与制度改革において公平で実効性のある仕組みづくりに役立ちます
- 研修業務でのスキルマップ作成は、人材育成と評価を結びつける基盤になります
- 給与制度改革を通じた「公正な評価」が実現し、それを採用ページなどで具体的に伝えると、求職者にとって魅力的な企業イメージを構築できます
- 給与計算担当時に把握した人件費構造は、新卒採用戦略の予測に活かされます
このように、各領域での経験は他の業務にも深く影響し合います。各業務のスペシャリストとして成長する場合にも、業務間のつながりを意識しながら経験を重ねることが、どの領域でも強みとなります。
人事担当者の主なキャリアプラン

人事の仕事は専門性が求められる一方、業務領域の広さから多様なキャリアパスが存在します。ここでは、代表的なキャリアの方向性として以下の5つを紹介します。
人事部門のスペシャリスト
人事スペシャリストとして、特定分野における専門性を高めていくキャリアパスです。
リクルーター、タレントマネジメントの推進担当、社内トレーニング担当、豊富な実務経験から業務効率化やシステム導入などをリードする役割、従業員満足度向上施策を実施する担当者などが挙げられます。
領域ごとの知見や実務経験を蓄積して業務品質を高め、社内外から信頼される専門人材を目指します。企業によってはプロジェクトリーダーなど複数部門を横断する施策に携わる機会もあります。
例)
- 社会保険労務士
- 海外人事スペシャリスト
- HRテック/人事データアナリスト
- 採用スペシャリスト(リクルーター)
- ダイバーシティ推進・ウェルビーイング担当
- タレントマネジメントスペシャリスト
必要なスキル
特定分野における専門知識と実務経験が不可欠です。法令の理解、データ分析力、論理的思考力に加え、提案力やプロジェクト推進力も求められます。さらに、社内の様々な部門と協働するためのコミュニケーション能力も重要です。
やりがい
- 専門性が組織や従業員に良い影響を与えている実感が得られる
- 継続的な学びと成長が求められる環境で、自身のキャリアを発展させられる
- 「この分野ならこの人」と社内で信頼を得ることで、スペシャリストとしての自覚と充実感が得られる
- 将来的に独立の道が拓ける可能性もある
苦心する点
- 常に最新知識の習得と実務への応用が求められるプレッシャーがある
- 専門以外の業務に携わる機会が減ることで、視野の広がりが限定される可能性がある
- 担当領域に深く入り込む分、社内の他業務や全体方針との接点を意識し続ける必要がある
バックオフィス部門のジェネラリスト
人事だけでなく、総務、経理、法務など管理部門業務全般にかかわる幅広い業務経験を積み、組織の運営基盤を支える役割を担います。各部門の実務を理解したうえで、部署間の調整役として、社内全体の業務が円滑に進むよう支援します。
将来的には、バックオフィス部門全体を束ねるマネージャーや、経営陣に近い立場での管理業務に携わるキャリアパスも見込まれます。
必要なスキル
幅広い業務知識と基本的な実務スキルに加え、臨機応変な対応力が求められます。正確性と効率性を両立させた事務処理能力や、様々な部署と円滑に連携するコミュニケーション力も重要です。業務の幅が広いため、優先順位を判断する決断力も必要です。
やりがい
- 幅広い業務を通じて、組織全体の運営を支えている実感が持てる
- 多様な業務経験を通じて、汎用的な知識やスキルを幅広く習得できる
- 将来的なキャリアの選択肢が広がる
- 社内の様々な部署や役職との関わりを通じて人脈を築ける
苦心する点
- 多岐にわたる業務を並行して処理する必要があり、優先順位の判断が難しい
- 突発的な対応が多く、計画通りに業務を進めにくい
- 目立ちにくい業務が多く、成果が見えづらい場合がある
- 担当領域が広いため、特定分野の専門性を高めにくい傾向がある
人事部長(マネジメント)
人事部長は、組織全体の人材戦略を統括するポジションです。
採用計画の立案・実行、評価制度や報酬体系の設計、人材育成の枠組みづくり、労務管理、組織開発など、管理職として部門横断的に人事業務全般を指揮します。経営層と連携し、事業戦略と人材戦略を結びつける役割も担います。
必要なスキル
経営視点と専門知識のバランス、リーダーシップ、コミュニケーション能力が不可欠です。データ分析力、問題解決能力、変化を推進する実行力も重要です。また、法令の理解、予算管理能力、危機管理能力も求められます。
やりがい
- 組織の成長に直接貢献できる
- 適切な人材戦略を通じて業績向上や企業文化に影響を与える
- 従業員の成長や満足度向上を実感できる
- 経営の意思決定に参画できる
苦心する点
- 経営課題と現場のニーズのバランス感覚が求められる
- 組織変革や労使関係の調整など、複雑な課題に最終責任者として対応する重圧
- 長期的視点での人材戦略を描きつつ、短期的な人事課題にも即応する必要がある
人事専門のコンサルティング職
クライアント企業の人事課題を分析し、専門的な知見をもとに課題の特定から解決策を提案・導入支援までを行います。組織診断や人事制度の設計・改定、採用・育成戦略の立案など人事全般にわたる課題を外部の立場から戦略的な視点や高い分析力で解決に導きます。
あわせて、人材派遣・人材紹介、採用支援、研修提供などのサービスを通じて企業を支援する人材サービス業界へ転職するという選択肢もあります。人事経験を活かした実務支援やソリューション提案で、クライアントの人事課題の解決に寄与できます。
必要なスキル
人事領域の専門知識と経験に加え、経営視点での問題発見・解決能力が求められます。データ分析、論理的思考、プレゼンテーションなどの力量も必須です。また、クライアントとの信頼関係構築、プロジェクトマネジメントの能力、業界・市場動向への洞察力も重要です。
やりがい
- クライアント企業の経営課題の解決に直接関われる達成感がある
- 経営層とのやりとりを通じて、提案が経営判断に活かされる手応えを得られる
- 多様な業界・企業の課題に触れることで、幅広い知見と経験を得られる
苦心する点
- 顧客の多様なニーズに応えつつ、法令や最新情報への対応も求められる
- 成果を見える形で提示し、信頼を獲得し続けるプレッシャーがある
- クライアント社内の利害調整や現場とのギャップを埋める調整力が問われる
フリーランスの人事として独立
フリーランスとして企業の人事業務を請け負います。採用支援や人事制度設計、評価制度構築、研修実施、組織開発など特定領域に特化した支援のほか、企業の人事機能全般を支援する人もいます。
また、労務管理や社会保険手続きの実務経験を活かし、社労士資格を取得して独立する選択肢もあります。社労士として、労働法規に基づくアドバイスや、給与計算、労務管理、労使紛争の解決を行うなど、多くの企業の労務課題解決を支援できます。
必要なスキル
特定分野における専門性と実績に加え、契約や会計に関する知識、営業力、提案力、自己ブランディング能力が求められます。自己管理の徹底も不可欠です。 信柔軟な対応力と信頼関係を築く力も重要です。
やりがい
- 自身の専門性を活かしてクライアントの課題解決に直接貢献できる
- プロとして指名される喜びがある
- 裁量が大きく、ワークライフバランスも含め、自分に合った環境を築きやすい
- 努力や成果がダイレクトに評価され、自身のスキルや実績が報酬や収入に直結する
苦心する点
- 収入の安定や継続的な案件確保に対する不安が生じることも
- 営業と業務の両立、案件のない時期のやりくりなど経営面の負担が大きい
- 判断を一人で担う責任の重さがある
- クライアントとの交渉や、自己研鑽のための時間確保が求められる
人事のキャリアアップに役立つ資格

人事のキャリアアップに役立つ資格の一部を紹介します。
社会保険労務士
労働・社会保険法令に関する国家資格です。法令を遵守した企業の労務管理や制度設計に寄与できるだけでなく、独立開業のチャンスもあります。
キャリアコンサルタント
労働者の職業選択やキャリア形成支援に関する国家資格です。人事部内では、採用業務をはじめ人事制度やキャリアパスの設計に活かせますし、独立開業も可能です。
ビジネス・キャリア検定
事務系職種に必要なスキルを習得していることを証明する公的資格です。厚生労働省が定める職業能力評価基準に基づいています。また、人事、経理、総務など職種ごとにコースが分かれているため、体系的な知識習得に向いています。
労務管理士
労務管理のスキルを習得していることを証明する民間資格です。基本的な労務管理の知識を習得できるので、人事部門での実務に役立ちます。
まとめ
人事業務の根本的な魅力は、人と組織の成長と発展を支える点にあります。企業の最大の資産である「人材」に関わる業務は、経営の成否を左右する重要な役割です。
採用や労務など、特定の分野からスタートする人事のキャリアパスも、ローテーションにより幅広く業務を経験することで、見えてくるものが増え、次第に多様な分野へと視野が広がっていきます。
専門性を深める道も、領域を横断して幅広い経験を積む道も、それぞれに魅力と可能性があります。将来どういった立場で人と組織に関わっていきたいかを思い描き、自身の強みや興味関心を見つけていくことがキャリア形成の第一歩です。ゴールに向けた長期的な目標を設定し、次のステップを考えていきましょう。
こちらの資料もおすすめです
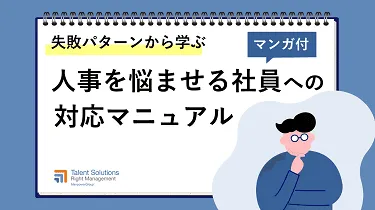


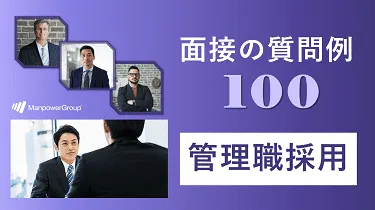


















 目次
目次