


効果的な人材育成を阻む4つの課題と解決までの5ステップを解説

目次
国内の労働力が減少するなか、人材育成は企業の存続に関わる企業戦略の大きな柱です。
しかし、グローバル化によって激しい市場競争にさらされ、社会構造が激変する環境のなか、人材育成に課題を抱えている企業は少なくありません。
時代の変化に対応し、企業の未来を担う社員を育てるために、今、何をしていくべきなのでしょうか。
ここでは、効果的な人材育成を阻む4つの課題と、課題解決へのステップや効果的な人材育成方法を解説します。
関連記事
人材育成に関して、より全体的に理解したいという方にはこちらのコラムもおすすめです。
企業が抱える人材育成の具体的な4つの課題
人材育成の改善を図るには、抱えている課題を明らかにする必要があります。まずは、企業が抱える人材育成の具体的な4つの課題を見ていきましょう。
課題1:旧来型の人材育成制度と社会環境の不整合
多くの企業が自社の人材育成制度が社会変化に対応できていないと考えています。
大きな課題となっているのが、旧来型制度への固執や硬直化です。育成モデルが現状に合わないと知りつつも、「自分たちの時代」から抜け出せずにいる企業も珍しくありません。
過去において企業の原動力となっていた人材マネジメントでは、入れ替わりの少ない社員層を基盤に、意識共有の下、密で強固なつながりが形成されていました。年次による昇進機会が得られ、長期安定雇用という枠組みのなかで、社員はそれなりのモチベーションを保ちつつ、企業運営が良好に機能していました。
そうした時代であれば、「上を見て育つ」方式に任せておいてもさしたる支障は生じなかったでしょう。しかし、終身雇用制度が弱体化し、人生100年時代と呼ばれる労働期間長期化の時代に、個人のキャリア意識は向上しています。社員の意識と能力の均一化を図るのが、企業にとって容易ではなくなっています。
既存の人材育成モデルでは個々の資質やスキルへの注目度が不足し、社員のもつ力をうまく成長させられない可能性があります。企業としてまとまっていくためには、自社における単一文化がベースでなければなりません。今はそれに加えて、多様性を受け入れ、個々の社員の個性やスキルを伸ばせるモデルが必要となります。
課題2:人材育成にかけられる時間の不足
現代の日本企業が抱える大きな悩みのひとつは、「時間が足りない」ことです。人口構造の変化によって、日本の労働力は減少を続けています。
人手不足を訴える企業は実に9割にも上るという調査結果もあり、限られた人員のなかで行う業務が在籍する社員を圧迫します。教える側・教えられる側とも時間がないなかでは、じっくりと人材を育てられるわけもありません。
特に、指導役として期待されるミドル層には業務が集中する傾向があり、後輩を指導する余裕がないというのが実情です。
課題3:育成能力・指導意識の欠如
企業の教育体制が整備されていなかった、あるいは前時代的な指導しか受けてこなかったという場合、指導する立場の社員にその能力が備わっていないということも考えられます。自分自身が系統立てた指導を受けてきていないと、人材育成のノウハウの蓄積がありません。
「育てられた」という気持ちがなければ、育てる意識がもてないのも当然です。若手に対してどのような声かけをして良いかわからないと、相互理解の不足からさらに指導が困難となります。
ミドル層の育成がなされていない企業は、後進を育てる人材がいないということになります。
最近では「働かないおじさん」問題が企業の悩みとなっていますが、これも指導意識の欠如の表れといえます。自分の企業人としての役割が不確かなために、業務に対する熱がなく、また後に続く者を育てようという気持ちもありません。とりあえず最小限の仕事をこなしておけば給料がもらえる、といった先輩や上司の下では、優秀な人材は育ちようがないといえるのではないでしょうか。
(注)「働かないおじさん」とは__
働いていないように見える、もしくは給与に見合った生産性が出せていない従業員の通称
(本編での「働かないおじさん」は、年齢・性別を限定するものではありません)
成果が思ったようにあがらないメンバーへの指導法
課題4:人材育成体制の整備不足
人材育成システムの体制がきちんと整備されていないと、結局は現場に任せきりとなりかねません。
人材育成においてOJT(On-The-Job Training)をメインに据える企業が数多く見られますが、計画の策定が適切になされていなければ、人材の成長へとつなげられません。ただでさえ忙しい現場で社員が自分の業務を行いながら、企業が求めるような人材を育てるのは至難の業です。
現場に預けるのであれば会社側がしっかりとしたスケジュールを組み、負担なく育成が進められるよう、フォローアップしていく必要があります。
企業内での成長を個人の自己責任とする丸投げ型は、いくら多様性を尊重するといっても無理があります。人材育成は、一部署、一個人に全責任を負わせるのではなく、全社的に考えていかなければなりません。
人材育成の課題解決に向けた5つのステップ
人材育成の課題を、企業はどのように解決していけばよいのでしょうか。
取り組むべき具体的な対策を5つのステップに分けて解説します。
ステップ1:ニーズと課題を整理する
ここまで一般的な企業の課題について見てきましたが、自社の人材育成環境を改善していくためには、各企業のニーズとそれに対する課題を整理することが求められます。
その場合、ある一部分の層にスポットを当てるのではなく、「全社的な人材育成」という捉え方をしていかなければなりません。人材育成をテーマとし、トップおよび管理・ミドル・若手と各層を分けて現状を整理していきます。そこからそれぞれの層における課題を把握し、取り組みへの優先順位をつけていくようにします。
特にトップや管理層の意識改革は、人材育成の成功において重要なポイントとなります。下からの自然的なボトムアップによる改善は望めないことをよく理解し、機能的な人材育成システムの構築をけん引していきます。
ステップ2:人材育成のロードマップを作成する
どのような企業体制となっていくことが望ましいのか、そのためにどのような人材が必要となるのかを明らかにして、そこから逆算したロードマップを作成していきましょう。
ロードマップを作成する手順は、次のとおりです。
手順1:経営理念と経営目標の明確化
自社は社会に対してどのような存在でありたいのか、それを踏まえた上でどのような形で成長を遂げていきたいのかを明らかにしましょう。
手順2:求める人材像の明確化
階層ごとにどのような人材に育ってほしいのか、人材育成のゴールを定義しましょう。
手順3:人材育成の基本計画を立案
階層ごとの育成目的を明らかにした上で、おのおのの育成時期や期間、方法などの基本計画を立てましょう。
手順4:育成後に活用する仕組みの明確化
育成後に、現場で活躍や定着を促すための仕組みを明らかにしましょう。
ロードマップでは、3年後、5年後といったスパンで、年齢別、スキル別、役職別などの望ましい社員構成を具体化しましょう。
その結果、どの時期までにどのような能力や経験を有した人材がどの程度必要なのかを明らかにできます。年度ごとや階層ごとの基本計画を定めることで、人材育成への取り組みが容易になるでしょう。
関連記事
社員ひとりひとりの目標設定については、こちらのコラムで詳しく説明しています。
ステップ3:人材育成のためのリソースを確保する
人材育成は金銭的・時間的コストを伴うため、リソースを確保する必要があります。
金銭的コストに対するリソースを確保するには、経営層が人材育成のためのコストを織り込んだ上で、経営目標に則した利潤を獲得できる中長期的な経営計画や、予算を設定しましょう。
一方、時間的コストに対するリソースは、人的資源の投入の他、生産性の向上や業務の効率化を推進することで確保します。
以下のような対策で、人材育成のための時間を創出しましょう。
- ITツールの活用やペーパーレス化の推進などにより業務効率の向上を図る
- 不要な会議の時間を削減する など
ステップ4:本人がキャリアアップを実現するための育成手法・環境を整える
各層や各時点でのスキルを達成できるようにするためにそれぞれに適した育成手法を選択し、習得した能力やスキルを活かして、本人がキャリアアップを実現できる環境を確保することが重要です。
育成手法を選択する際には、他社事例を研究するのも効果的な方法です。具体的な育成手法については後ほど解説します。
そのほか、人材育成には、「育ちやすい環境」の存在が重要になるので、次のような組織風土の形成を心がけると良いでしょう。
- 経営層や管理職層が成長した人材を積極的に活用するように意識改革を行う
- チャレンジすることを歓迎する など
ステップ5:育成効果を測定する
リソースや育成環境が整ったら、人材育成の効果を測定しましょう。
継続的な課題解決のためには、教えられる側の社員が着実に育ち、現場で活躍できることが人材育成の理想の姿だからです。
具体的には、次のような項目を測定しましょう。
- あらかじめ立てた計画に基づいた人材育成が行われたのか
- 人材育成に対して管理職や上司がどのような関わり方をしたのか
- 目標とする能力やスキルの向上が実現されたか
- 習得、成長した能力やスキルを今後の業務に活かせているか
- 人材育成を行ったことで企業や組織の業績にどの程度貢献できたのか など
効果が期待できる人材育成方法とは?
人材育成の手法は多種多様です。その中から自社の目的に合い、成果が期待できて実施可能な方法を模索しながら、継続していくためのコストとのバランスを図ることが重要です。
人材育成は、一度きりや短期間で済ませられるようなものではありません。社員の習熟度や成長を的確に把握できる仕組みを構築し、より効果的な方法を探りながら、柔軟性をもって進めていきましょう。
具体的な人材育成の種類と方法を解説します。
OJT(On-the-Job Training)
OJTは、職場の中で仕事をしながら学んでいく方法です。人材育成の手法としてもっともポピュラーなもので、多くの企業が活用しています。
その反面、トレーナー役の上司や先輩社員のスキル不足、時間的な制約、新人社員とのコミュニケーションの問題など、クリアすべき課題は少なくありません。
OJTは「計画的」「重点的」「継続的」が原則とされていますが、それぞれの段階で「見極め」も重要な要素となります。この原則を企業が十分に理解し、OJTの成果を正しく把握するために、「1on1ミーティング」などの手法を採用するなどの工夫も大切です。
トレーナー役に対してはコーチング研修を実施するなど、OJTを通じて指導役と新人社員双方の成長を促す意識が求められます 。
Off-JT(Off-the Job Training)
職場内で業務とともに学んでいくOJTに対し、通常業務外で行われる研修やセミナーがOff-JTです。
2021年の厚生労働省による「能力開発基本調査 ![]() 」の 結果では、Off-JTを正社員に対して実施した事業所が70.4%と、「計画的なOJT」の61.8%を上回っています。
」の 結果では、Off-JTを正社員に対して実施した事業所が70.4%と、「計画的なOJT」の61.8%を上回っています。
Off-JTは外部講師や、外部の教育訓練機関などによって実施されるのが一般的です。具体的には新入社員に対しての基本的なスキルやマナー研修といったものから、社員全体のスキルのバラつきを平均化するといった内容もあります。
自己啓発・SD(Self Development)
自己啓発は、社員自身が自発的に社外や就業時間外で学びを実施します。
勉強会やセミナーへの参加だけではなく、書籍を購入したり図書館で勉強したりする行為も含まれます。業務に直接関連するもの以外に、将来に向けた資格取得などもこれに該当します。
自己啓発では空き時間の利用や朝活といった方法で柔軟に学びの機会が得られる一方、強制力がなく自律性にまかせるため、継続が難しいといったマイナス面もあります。
最近では自己啓発のサポート策として、eラーニングの提供やテキスト・資料代、セミナー参加費の補助を行う企業もあります。
【社員層別】人材育成の方法
社員の階層に応じて、会社が求める職務遂行上の役割は異なります。それに伴い、発揮してもらいたい能力や必要なスキルの内容も異なるため、それぞれの階層ごとに効果的な内容・実施方法を考えましょう。
内定者・新入社員の人材育成方法
人材育成の目的として、内定者には不安からくる内定辞退の防止や、入社後いち早く業務に順応し戦力化してもらうことを、新入社員には社会人としての適応力の向上や担当職務に対する遂行能力の向上を目的として行われます。
内定者、新入社員におすすめの人材育成方法を紹介します。
新入研修
社会人としての基礎を固め、自分らしいキャリアビジョンを描くための研修です。業務知識やビジネスマナーはもちろんですが、それ以外にも社会人としての意識を身に着け、必要となるスキルや知識を学びます。
タイムマネジメント&コミュニケーション研修
限られた時間で効率的に仕事をこなすために、優先順位の考え方や、仕事上での人間関係をよりよくするためのコミュニケーションについて学ぶ研修です。
内定者フォロープログラム
入社までの期間に抱えている不安を入社意欲や期待に変えるためのプログラムです。社会人としての心構えを学ぶだけでなく、内定者同士でもコミュニケーションが取れることもメリットです。
若手~中堅社員の人材育成方法
若手~中堅社員の人材育成は、職務遂行能力に磨きをかけ、その上で課題への対応力や後輩への指導力を向上させることでリーダー候補人材へと育ってもらうことを目的として行われます。
若手~中堅社員におすすめの人材育成方法を紹介します。
問題解決力強化研修
問題や課題を論理的に考えて、解決策を導くリーダーを養成するための研修です。現場でおこるさまざまな問題を解決するための思考方法を身に着けます。
ストレスマネジメント研修
自らストレスをコントロールできるように、ストレスについて知り、ストレスうまく付き合う考え方を身に付けるための研修です。
管理職社員の人材育成方法
管理職社員の人材育成は、組織マネジメント能力に磨きをかけ、組織としての目標を実現させる能力を向上させることで幹部人材へと育ってもらうことを目的として行われます。
管理職社員におすすめの研修内容を紹介します。
管理職基礎研修
プレイヤーとしてではなく、メンバーをマネジメントする管理職としての、育成指導スキルや心構えなどの基礎を身に着けるための研修です。
評価面談研修/フィードバックスキル向上研修
部下の評価を行っていく中で、部下のモチベーションをコントロールするために効果的な面談の方法などを学ぶ研修です。
そのほか、年代別や課題別など、企業の課題やニーズにあったセミナーを取り入れる方法もおすすめです。
まとめ
社会環境の変化も相まってこれからは、旧来型の「上の背中を見て育つ」方式から脱却し、全社的に人材育成に取り組むことがどの企業にも必要になりました。しかし人材育成は、企業の環境や抱えている課題などによって最適な解決方法が異なります。
今回取り上げた5つのステップをもとに、自社に適した人材育成をぜひ検討してみてください。
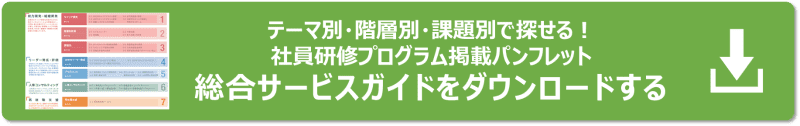
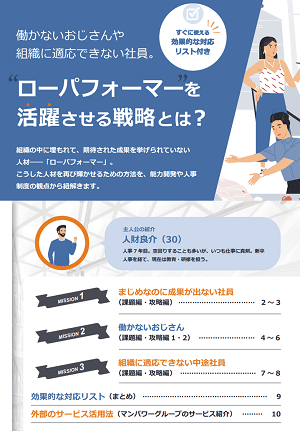


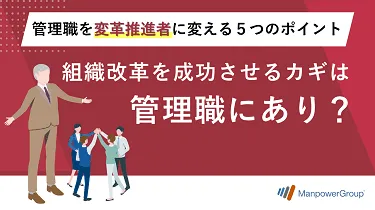






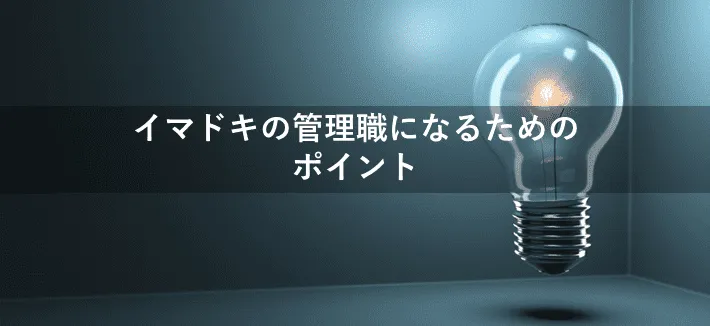











 目次
目次