


採用してはいけない人材の共通点とは?合否判定で迷わない、面接での違和感の見極め方

目次
企業の成長を左右する重要な要素の一つが「人材採用」です。優秀な人材を獲得できれば組織力は向上しますが、問題のある人材を採用してしまった場合、その影響は想像以上に深刻なものとなります。
特に限られた人員で運営している組織では、たった一人の問題人材が全体のパフォーマンスを大きく左右することも珍しくありません。
本記事では、採用してはいけない人材に共通する5つの特徴を整理し、面接で効果的に見極めるための具体的な質問例と着眼点をご紹介します。
なぜ「採用ミス」は企業にとって大きな損失なのか

人材を採用する場合には少なからず費用がかかります。求人サイトへの登録や人材紹介会社への手数料などだけでなく、採用担当者の人件費も必要です。
ただそういった直接的な採用費用だけでなく、現場で指導する社員の負担が増えるなど間接的な負担が増えることは、採用担当者であれば実感されていると思います。
新規採用における教育や指導は企業として必要な投資ですが、採用した人材が期待に応えられなかった場合のリスクは深刻です。パフォーマンス不足や顧客トラブルを起こす人材は、現場の負担増加だけでなく、他の社員のモチベーション低下を招き、結果的に組織全体の業績悪化につながるケースが少なくありません。
また、早期退職が発生した場合は、再度採用活動を実施する必要があり、追加的な採用コストや人事担当者の工数負担が発生することになります。
そのため「採用ミス」の発生は企業にとって大きな損失なのです。
採用してはいけない人材の5つの共通点

ではそういった損失を未然に防止するためには、どうしたら良いのでしょうか?
もちろん、それぞれの会社や組織ごとに必要とされる人材の特徴は異なります。
地道にコツコツと取り組むタイプの人材が必要とされる会社や職種もあれば、アクティブでガツガツいくタイプが必要な会社もあると思います。
しかし、採用してはいけない人材にはある程度の共通点があります。
ここでは5つのタイプに分けて解説していきます。
失敗や課題の原因を自分で引き受けようとしない
失敗時の原因を自分自身に求めるか他者に転嫁するかは、人材の本質を見極める重要な指標です。
責任を他者に押し付ける人材は、プライドや保身を優先し、建設的な改善策を立てることができません。このような姿勢は本人の成長機会を奪うだけでなく、同僚のモチベーション低下やチーム内の不満を拡大させる要因となります。
責任回避を繰り返す人材は個人の成長が期待できず、場合によってはモチベーションの高い同僚の足をひっぱるなど、組織全体に悪影響を与えるリスクがあるため、採用時には慎重な見極めが必要です。
ルールやモラルを軽視する姿勢が見える
組織には守るべきルールとモラルがあり、現代社会ではコンプライアンス遵守は必須条件です。しかし、これらを軽視する姿勢を見せる人材には十分な注意が必要です。
機密保持の意識が低い人材は情報漏洩リスクを高め、万が一発生した場合は対応に追われるだけでなく、企業の信用失墜という深刻な事態を招きます。
また、目先の利益のみを追求する人材は長期的視点を欠き、結果的に大きな損失を生む可能性があります。
同僚や顧客を軽視する傾向のある人材は、社内組織の破綻や外部との関係悪化を引き起こし、企業全体に甚大な影響を与えるリスクがあります。
時間や体調などの自己管理がルーズ
何事にも管理がルーズな人材は注意が必要です。特に時間を守れない人材は避けた方が良いでしょう。
社内会議や取引先との打ち合わせの時間に遅れる、日程を忘れているなどの時間の管理がルーズな人は、社内外において信頼関係を築くのが難しくなるだけでなく、同僚からのフォローが必要になるなど結果的にマイナスになることも考えられます。
また、体調の管理がルーズな人材も避けた方が無難です。たとえ仕事が忙しくても、計画的な行動や私生活の管理によってある程度の体調管理は可能です。コンディションの安定について、意識的であることが大切です。
関連記事:社員の無断欠勤をどうするか?やるべき対処と解雇条件をわかりやすく解説
変化に消極的で、柔軟に対応できない
世の中は常に変化しており、DXの推進や法改正、国際情勢などの要因により、働き方やシステム、コミュニケーション方法は今後も変化し続けます。このような変化に柔軟に対応できない人材は大きな懸念材料となります。
過去の成功体験が将来の成功を保証するとは限らず、新しい方法への挑戦が不可欠です。
例えば、市場環境の変化に伴って営業戦略が見直された際に、「今までこの方法でうまくいっていた」と過去のやり方に固執し、改善の提案や新しい試みに背を向ける人は組織の成長や変革を妨げる要因になり得ます。
また、業務効率化のための新しいツールや手法の導入に対して、「覚えるのが面倒」と学ぶ姿勢を見せず、周囲のサポートに頼りきりになる人も問題です。
法改正による業務プロセスの改善に適応できない場合、業務効率の低下だけでなく、コンプライアンス違反のリスクが生じる可能性もあります。
学習意欲や自己成長への無関心に起因する成長意欲の低さは、本人の停滞だけでなく、周囲の成長意欲を阻害し、組織全体に停滞感をもたらすリスクがあります。
相手の立場を思いやる視点に欠ける
仕事をする上で大切なことの一つとして人との繋がりがあります。同僚であり、上司・部下であり、取引先の担当者にもそれぞれの立場があります。その人それぞれの立場に立って考えることができない人材の採用は避けた方が良いでしょう。
同僚であれば多くの時間を共に過ごすことから、その人の気持ちを理解することも組織としては大切です。常に自己中心的で配慮に欠けた態度をとる人が組織に含まれている場合、そのチームの雰囲気を悪くしたり、その人に限らず他の人を孤立させるような状態を生じさせたりする傾向があります。
例えば、個人の成功を優先し、周囲のサポートには関心を示さない、または、部下や同僚に対して、自分の業務を一方的に振り、相手のスケジュールや負荷をまったく考慮しないケースが挙げられます。
また取引先と直に接する仕事をする場合は、顧客視点でものごとを考える必要があります。
にもかかわらず、取引先の予算や納期、社内事情などを配慮せず、自社の都合ばかりを強硬に主張するなど、自分の立場だけを考えて行動してしまう人材の採用は、クレームの頻発や取引の中止に繋がってしまうことも考えられます。
面接で見極めるポイント(質問例あり)
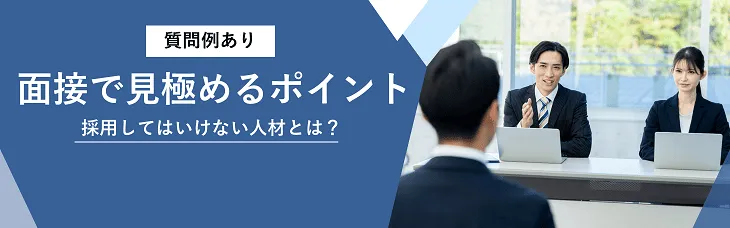
では、どのような人が「採用してはいけない人材」といえるのでしょう。
採用面接において見極めるポイントのそれぞれについて、①傾向、②質問例、③着目点を挙げてご案内します。
失敗や課題の原因を自分で引き受けようとしない
失敗を周囲のせいにし、自ら改善しようとしない傾向があります。
過去の失敗経験の語り方
最近の業務で想定どおりに行かなかったプロジェクトを教えてください。原因は何で、あなたはどう関わりましたか?
着目点
- “自分は悪くない”と外部要因ばかり挙げるか
- 主語が常に“会社”“上司”など―責任の所在をぼかす表現が多いか
- 自分の改善行動・学びを具体的に語れるか
フィードバックの受け止め方
上司や同僚から厳しい指摘を受けたとき、どう対処しましたか?
着目点
- 指摘内容を正当化する/相手への不満を強調するか
- 受け入れて次に活かした具体策を話せるか
- 感情面だけでなく行動面を説明できるか
チーム内トラブル時の立ち位置
チームでうまくいかなかった経験はありますか?またその時あなたに求められた役割は何でしたか?
着目点
- “自分の役割外”を強調し逃げ腰か
- 連携や巻き込みの具体例が乏しいか
- ミスを機にプロセス改善を提案した経験があるか
深堀りのコツ
- “I” と “We” と“They”のバランス
― 貢献を語る場面で “We”、ミスの場面で “They” になっていないか
チーム(“We”)として成功した場面においては、自分(“I”)はその中で実際にどのような貢献をしたのかを問い、逆に失敗した場面では、他の人(“They”)ではなく、その時に自分(“I”)に不足していた部分を聴き、その後どのようにその経験を活かしているかを問います。 - 具体性の深掘り
― “頑張りました”を放置せず、「具体的に何を?」で掘ると責任感の有無が浮き彫りに - 反省⇒行動変化の線
失敗談→学び→改善策→成果まで一続きで語れるかがポイント
― 単なる失敗談として終わらせることなく、それを糧としてどのように次に繋げることが出来たのかを語らせます。
この視点で質問と掘り下げを行えば、「責任転嫁グセ」を察知しやすくなります。
ルールやモラルを軽視する姿勢が見える
ルールやモラルを軽視しがちな人は、過去に倫理的な問題行動をほのめかす発言があり、コンプライアンスに関する質問にも軽率な回答をする傾向があります。
不正・モラル違反への即時対応力と倫理観
チーム内で不正やモラル違反を見かけた場合、あなたはどうしますか?
着目点
- 具体的な行動プロセスを即答できるか(関係者への報告、証拠保全、是正提案など)
- “自分の立場では…”と傍観を正当化しないか
- 一次対応と再発防止の両面を語れるか
ルールへの批判的思考と建設的行動
過去に職場でルールや方針に納得がいかなかった経験があれば教えてください。また、その時あなたはどう対応しましたか?
着目点
- “従う/従わない”の二択ではなく、改善提案や対話を試みたか
- 感情的な不満の羅列で終わらず、論拠と解決策を示せるか
- 結果として組織にどんなプラスをもたらしたかを説明できるか
周囲のルール違反への影響力行使と協働姿勢
ルールを守らない人と一緒に働くことになった場合、あなたはどうしますか?
着目点
- “放置する/上司に丸投げ”ではなく、自らの働きかけ(対話・サポート)を説明できるか
- 相手を責めずにルール遵守の意義を共有する視点があるか
- 状況悪化時のエスカレーション手順やチーム全体への波及を考慮できるか
深堀りのコツ
- “なぜその行動を選ぶのか”を問う
― 行動原理を聞くことでモラルの根底にある価値観が透ける。 - 事実→判断→行動→結果 の順で語らせる
― 具体性と一貫性の有無をチェック。 - 非言語シグナル
― 規範の話題で笑いを交える、視線を逸らすなどは軽視の兆候。
時間や体調の管理がルーズ
時間や体調の管理がルーズな人は、自己管理や責任感が甘く、感情や私生活に振り回されやすい上に、計画性や優先順位付けにも欠ける傾向があります。
締め切り・遅刻へのスタンス
これまでに遅刻や締め切り遅延を起こしたことはありますか? そのときはどう対応しましたか?
着目点
- 遅延を“交通渋滞”“他部門の遅れ”など外部要因だけで正当化しないか
- 再発を防ぐ具体策(出発時刻の前倒し、タスク分解など)があるか
優先順位付けとスケジュール設計
タイトな期限が複数重なった際、どのように予定を組み立てましたか?
着目点
- タスク管理ツール・カレンダー活用の有無
- “とりあえず残業で乗り切る”だけの計画性不足が見えないか
体調管理と自己ケア習慣
繁忙期でもコンディションを維持するために日頃から意識していることを教えてください
着目点
- 睡眠・食事・運動など具体的習慣を語れるか
- “気合で何とかする”と精神論に寄り過ぎていないか
深掘りのコツ
- “事実→判断→行動→結果”で時系列を聞く
― 計画変更やリカバリーの意思決定プロセスが具体的か。 - “防ぐための仕組み”を問う
― アラート設定やバッファ日を入れるなど、再発防止をシステム化できているかを見る。 - “周囲への影響”への自覚
― スケジュール管理不足・欠勤がチーム全体に及ぼすコストを語れるかで責任感を測る。
これらの質問と掘り下げを通じて、時間や体調の自己管理の甘さを確認することができます。
変化に消極的で、柔軟に対応できない
変化に消極的な人は、現状維持を良しとし、新しい取り組みを否定的に捉えがちで、最新知識への関心も薄い傾向があります。
新しい環境・ツールへの適応力
もし、あなたが長年続けてきた業務のやり方が新しいシステム導入で全く変わってしまうとしたら、どのように感じますか?
着目点
- “前のやり方の方が楽だった”と消極的発言が多くないか
- 導入プロセスで自ら学習・周囲へ共有した具体例があるか
変化に対する感情と行動
仕事のやり方が大きく変わった経験について教えてください。また、その時はどのように対応しましたか?
着目点
- 不安や戸惑いを認めつつ前向きな行動に移れたか
- “指示待ち”でなく、自分から情報収集・相談を行ったか
フィードバックを活かす柔軟性
上司や周囲から“やり方を変えてみては?”と言われた経験は?その後どうしましたか?
着目点
- 防御的にならず、提案を試した経緯を語れるか
- 変化後の成果や学びを自分の言葉で説明できるか
将来の変化に向けた準備
業界が今後大きく変わるとしたら、ご自身はどう備えますか?
着目点
- “会社が指示してくれるはず”と他責にしないか
- 不確実性の中での学習計画やネットワークづくりを語れるか
深堀りのコツ
- “感じたこと・考えたこと・やったこと”の順にたずねる
― 気持ち→判断→行動をセットで聞くと、変化への心の動きと実際の対応が見えやすくなります。 - “小さなアップデート”も話題にする
― ツールのショートカットや会議の進め方など、身近な改善例を聞くと日頃の柔軟性が浮き彫りになります。 - “失敗→リカバリー”のエピソードを誘う
― 変化に挑戦してうまくいかなかったケースも共有してもらい、諦めずに修正できるかを確認します。 - 未来に向けた“ワクワク感”を探る
― “こうなったら面白い”というポジティブな視点が出るかどうかで、変化を楽しめるタイプかがわかります。
この視点と質問の組み合わせで、変化を避けがちな候補者か、変化をチャンスと捉えられる候補者かを見極めやすくなります。
相手の立場を思いやる視点に欠ける
相手への思いやりが欠ける人は、過去に人間関係のトラブルが多く、相手の気持ちを尋ねる問いにも表面的な返答で済ませがちです。
異なる視点への配慮
最近、立場や考え方が異なる相手と協働した場面を教えてください。そのとき、相手の意見を理解するためにどんな工夫をしましたか?
着目点
- “自分の方が正しい”と主張し続けていないか
- 相手の背景・感情を言語化できているか
- 両者が納得する落としどころを模索したか
衝突時の感情コントロール
自分が正しいと思っていたことを相手から否定された経験はありますか?またその時どう感じどう対応しましたか?
着目点
- 感情的に反論せず、相手の主張を言い換えて確認しているか
- 事実と感情を切り分けて対話できているか
共感と建設的フィードバック力
もし、あなたのチームメンバーがミスをした時、あなたはどのように声を掛けますか?
着目点
- まず相手の気持ちに寄り添う言葉が出るか
- 責めるのではなく事実確認→改善提案の順で話すか
- 「一緒に振り返ろう」「フォローするよ」など協働姿勢があるか
思いやりとチームケア
チーム内で体調が不良であるなど事情のある人がいた場合、どのように接しましたか?
着目点
- 相手の負荷を下げる提案(タスク調整・在宅推奨など)が出るか
- プライバシーへの配慮を語れるか
- チーム全体への共有とサポート体制まで視野に入れているか
優先順位付けと助け合いの姿勢
自分が忙しい時に誰かから頼みごとをされたらどう感じますか? またどのように対応しますか?
着目点
- 断る/受けるの二択ではなく、期限や重要度を確認する姿勢があるか
- 代替案(後で対応・他メンバー紹介)を提示できるか
- 忙しさを感情的に強調せず、相手の立場も尊重しているか
深掘りのコツ
- “相手がどう感じたか”を問い返す
― 事実だけでなく、相手の感情に理解を示すかを確認 - エピソード内の主語の使い方を聞く
― “I” ばかりで “They” や “We” が極端に少ない場合は要注意。 - 実績よりプロセスに注目
― 結果が良くても、相手視点を欠いた強引な進め方だったかを掘り下げる。
選考のポイント・工夫

面接という限られた時間で全てを判断することには限度があります。ここでは、実際の面接時以外でできる工夫やポイントを解説します。
評価基準と評価表の工夫
「自社が求める人材像」を明確にした上で、それに反する「採用してはいけない人材」の特徴を整理した「評価表」を作成することも効果があります。
例えば、前記のような質問項目を「評価表」としてまとめてみてください。
その上で、想定される回答や着目点もまとめておきましょう。
評価基準も併せて明確にしておきます。
「〇△×」の3段階評価でも良いですし、「5・4・3・2・1」や「A・B・C・D・E」の5段階評価でも良いでしょう。
前記のような着目点や想定される回答に基づき、どういう場合に「A」になり、どういう回答が「×」になるのかを明確にしておきます。
ただし、人が人を評価する以上、初めから絶対的な基準を設けるのは難しいかもしれません。そのため、初めは「これだけは譲れない」という基準だけは明確にしておきつつ、記録と経験を積み重ねながら、自社の評価基準を明確にしていくことでもよいでしょう。
それにより、 誰が面接官になっても出来るだけ平準的な質問や判断が出来る体制が構築されることとなります。
面接官トレーニングの実施
たとえ評価基準を明確にしても、それを運用する面接官にジャッジミスがあっては元も子もありません。しっかりとしたトレーニングを受けずに面接官を任せた場合、以下のような傾向があります。
主観的で偏った評価をしてしまう
- 自分の好みや価値観だけで判断してしまう
- 学歴、出身校、年齢、性別、外見などで先入観を持ち、応募者の本質を見ようとしない
- 特定の質問に固執し、応募者の多様な側面を理解しようとしない
- 過去の個人的な経験に基づいて応募者をステレオタイプに判断する
質問スキルが低い
- 表面的な質問しかせず、応募者の深層心理や能力を引き出せない
- 誘導的な質問やYES/NOで答えられる質問が多く、応募者の本音や考えを探れない
- 質問が曖昧で応募者が意図を理解できず、適切な回答ができない
- 圧迫的な質問や威圧的な態度を取り、応募者の本質的な部分を引き出す前に委縮させてしまう
倫理観や公平性に欠ける
- ハラスメントに該当するような質問をしてしまう(性別、家族構成、思想信条など)
- 選考情報を漏洩したり、個人的な感情で評価を左右したりする
- 約束を守らない、不誠実な対応をする
スキル偏重型
- 目先の技術や資格ばかりに注目し、社風や価値観の適合性を無視する
- 高スキルでも文化に合わない人材を採ってしまい、後でチームが崩れる原因になる
このような対応とならないために、面接官となる人にはトレーニングの実施により上記のような傾向があることを事前に伝えます。
その上で、「自社が求める人材像」および「採用してはいけない人材」の特徴を明確にし、「評価表」や「評価基準」をトレーニングによってしっかりと認識してもらった後に、適任となる面接官を選任しましょう。
なお、トレーニングはそこで終わりではありません。
記録と経験の積み重ねにより明確になってきた評価基準について常にブラッシュアップし、継続的にトレーニングを行うことが重要といえます。
適性検査の導入
適性検査の導入も検討しましょう。
検査結果を社内で累積することによって、より精度の高い判断が出来るようになります。
最終的な検査結果だけでなく、適性検査の特定の項目に対してどのような回答をしているのかを確認することでも、その人の考え方を知ることができる場合もあります。
例えば、「苦しくても途中でやめてしまうことはない」という検査項目に対して「いいえ」と回答している場合、たとえ標準的な総合評価が採用を示していたとしても、慎重な判断が必要となるでしょう。
また、アンケート形式の適性検査を会社で独自に作成することも考えられます。
一般的な適性検査は標準的な基準に基づいて検査結果が出されますが、「自社が求める人材像」や「採用してはいけない人材」が記録と経験の積み重ねによって明確になっているならば、「こんな時にはどう行動するか?」といった検査項目をオリジナルで作成し出題することで、より平準的な判断ができるようになるかもしれません。
面接の結果と適性検査の評価配分を明確にし、セットで評価することで、より精度の高い判断ができるようになるでしょう。
注意点
ここまで様々な方法やポイントを解説しましたが、人が人を選ぶということはとても難しいことです。そして、十人十色と言われるように人それぞれに特徴があり、その人に合っている仕事は必ず存在します。
ここで「採用してはいけない」とした特徴がある人にも、その他の点でとても優れた特徴があるかもしれません。避けたい要素を参考に自社や配属ポジションに合う人材像を描いてみてください。
関連記事:採用で適性検査はどう活用する?種類や目的・業務別の選び方を解説
まとめ
限られた人員で構成される組織では、価値観や行動パターンが合わない人材が及ぼす影響は大きく、結果として早期退職やチームの混乱につながりやすくなります。それを避けるためには、長期に活躍できる人材かどうかを見抜くための準備と判断力が重要です。
したがって、採用の段階ではスキルだけでなく、組織への影響という視点からも判断する必要があります。「欲しい要素」と「避けたい要素」の両軸で検討することで、「自社が求める人材像」がさらに明確になります。
ただし、面接時にネガティブに見える特徴が、一時的な緊張によるものや修正可能な特性、配属と相性によって活かせる可能性もあります。この様な多角的な視点も持ち合わせることにより、最適な人材の選定が可能となります。
参考資料:
よりプロフェッショナルなサービス、アドバイスをご希望の方はこちらをご覧ください。
こちらの資料もおすすめです



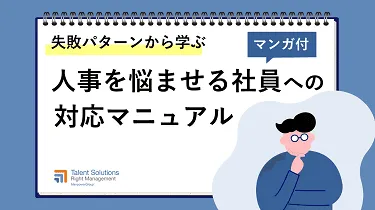
















 目次
目次