


AIで人事業務はどう変わる?活用方法やメリット・デメリットやリスクも

目次
AIがビジネスの在り方を塗り替えつつある今、人事業務の効率化と品質向上に企業が注目しています。実際に、採用活動から労務管理、人事評価、従業員エンゲージメント向上まで、AI技術は従来の業務フローに活用できるまでになっています。しかし、導入には適切な理解と慎重な準備が不可欠です。
そこで今回は、人事分野でのAI活用の具体的な方法と効果、そして注意すべきリスクについて詳しく解説します。
人事業務でAIの活用に注目が集まっている背景

人事業務は幅が広く、担当者の採用も厳しい側面があり、人手不足に陥りやすい傾向にあります。企業のDX化も進み、人手不足をシステムで補う考え方には大きな関心が寄せられています。
直近では、AI技術の発展に注目が集まっています。AIの進化は著しく、性能の向上、導入費用の低コスト化も進み、業務で実用可能なレベルに到達しました。有料のAIもあるものの、多くのAIはChatGPTに代表されるように、無償で手軽に利用できることも注目される要因の1つでしょう。
AIは業務が自動化できる上、大量のデータを扱うことができ、うまく活用できれば企業にとって不可欠なツールと言えます。
このような背景から、人事業務でのAIの活用が注目されているのです。
人事業務でAIを活用した業務例

ここからは、AIを活用できる人事業務例を紹介します。
AIは、大きく「汎用型」と「業務特化型」に分けられます。汎用型AIは、ChatGPTやGeminiのように幅広い用途に対応できる生成系AIを指します。一方、業務特化型AIは、議事録作成や適性分析など、特定の用途に最適化されたツールやアプリケーションを指します。多くは汎用型AIモデルを用い、業務に即した設計や機能追加がなされたものです。
文書作成やアイデア出しには汎用型の柔軟さが役立ちます。一方で、採用や人材評価のような重要な判断には、制度や目的に応じて調整された業務特化型の活用が効果的です。
AIの業務活用においては、AIの種類だけでなく、ツールの設計や仕組みにも目を向けながら、目的に合ったものを選ぶことが大切です。
- 採用業務における書類作成
- 選考書類の分析・評価
- チャットボットでの質問対応
- 社内規定やポリシーの草案作成
- 採用活動や研修のコンテンツ作成
- 従業員向けサーベイの設問作成や結果分析
- 配属先・異動の最適化
- AIによる面接
- 議事録や会議内容の要約
採用業務における書類作成
採用業務における各種文書の作成にAIは活用できます。
例えば、選考案内のメールや内定通知書などをはじめとした、文書の雛形や標準的な文書例をAIで自動生成することが可能です。文書にしたい内容を箇条書きで入力し、出力したい形式を指示すれば、短時間で完成度の高い文書が作成できます。
また、募集の際のキャッチコピーにもAIを活用できます。ターゲット層や自社の強みなど必要な情報を与えることで、応募者の興味を惹くようなメッセージの作成も可能です。文字数の指示もできるので、各項目に文字数制限のある採用チャネルを利用するときにも適しています。
選考書類の分析・評価
AIに履歴書やエントリーシートを読み込ませ、分析させることもできます。特に、志望動機や自己PRなど自由記述欄は、表現の個人差が大きく、評価基準を設けていても判断が属人的になりがちです。
AIを活用することで効率化だけでなく、評価の標準化を図ることができます。AIに事前に設定した評価軸に基づいて、内容を要約・分析、スコアリングを指示し、一定の基準を基にした評価を行わせることが可能です。これにより、担当者による評価のばらつきを最小限に抑え、公平性を担保した選考が可能になります。
また、大量の履歴書・エントリーシートを1枚ずつ読み込むのは膨大な時間がかかるため、大幅な効率化も図れます。採用活動の効率化は、採用のスピードを上げることにも繋がり、選考辞退を防ぐ効果もあります。
チャットボットでの質問対応
人事部門は、従業員や求職者からの問い合わせが多い部門です。そこで、チャットボットによる質問対応をAIで行い、問い合わせ対応の時間を削減する事例もあります。チャットボットは特化型のツールを利用することが一般的です。
これまでもチャットで質問ができるツールはありましたが、オペレーターとのリアルタイムでのチャットや、事前に用意されたFAQから用語にヒットするものを検索するものなどが主流でした。チャットボットはAIを用いることで、リアルタイムで対応する人員は不要で、曖昧な質問でも内容を予測し回答することが可能です。
社内の問い合わせをチャットボットで対応
住所変更や氏名変更などの社内での申請方法や、勤怠システムでのよくある質問など、人事部門に寄せられる質問と回答をチャットボットに登録することで、問い合わせ対応の自動化が実現できます。
担当者の負担削減につながるだけでなく、問い合わせをする従業員にとっても、待ち時間の削減になる上、担当者によって回答が変わることもなくなるため、品質向上を実感しやすいです。
採用活動時の問い合わせをチャットボットで対応
応募期日や選考会場へのアクセスなどの応募者からの問い合わせ対応をチャットボットで自動化することもできます。書類提出時や選考時のよくある質問を登録することはもちろん、年次有給休暇取得率や勤続年数、育休取得率などのデータをFAQとして登録すれば、応募者が企業理解を深めることにも繋がります。
社内規定やポリシーの草案作成
社内規定などの草案作成も生成AIの得意分野のひとつです。規定の新設はもちろん、既存の規定の見直しや修正案も、AIを活用することが可能です。社内規定は条文形式や定型表現が多く、一般の文書とは異なるスタイルで書かれることが多いため、生成AIで草案を作成することで業務効率化にも繋がります。
指示の際には「2025年の法改正内容を含んで」「退職トラブル回避の観点で」「一般的な内容で」など、出力書式のポイントを含むと、より企業に合った草案が作成できます。
採用活動や研修のコンテンツ作成
採用活動や研修でも次のような分野でAIを活用できます。
研修や採用施策の最適化
従業員の経験業務や人事評価などのデータを基にAIで分析することで、社内のスキルを可視化できます。これにより、企業や部門が求めるスキルとのギャップを把握でき、必要な研修や教育プログラムを客観的に判断できるようになります。
さらに、研修後や採用施策後のアンケート・フィードバックをAIで分析すれば、改善点を抽出しやすくなり、次回以降の精度向上が期待できます。
コンテンツ作成の効率化
AIは、研修用コンテンツだけでなく、会社説明会で使用する動画や資料、採用向けパンフレット、SNS投稿用の画像など、人事部門が利用するあらゆるコンテンツの作成にも活用できます。構成案や原稿、デザインの草案をAIで作成すれば、制作時間を大幅に短縮でき、より戦略的な採用・研修活動に注力することが可能です。
関連記事
採用広報とは?目的と進め方を徹底解説
従業員向けサーベイの設問作成や結果分析
従業員満足度の向上や離職率の低下を目的に、従業員向けのサーベイを行う企業が増えています。このサーベイにもAIを活用できます。
例えば、サーベイの設問をAIに作成させることで、サーベイの目的を達成しやすい設問を、より多角的に提案してくれます。また、結果の分析も短時間で行えますので、効率的に社内の課題を把握することが可能です。
AI搭載ツールの中には従業員向けのサーベイに特化したものもあり、AIがチャットのやりとりを分析し、コミュニケーションの質を測る、従業員の中でトピックになっている単語を抽出するなどの機能を提供するものもあります。こういった情報から、通常のアンケートでは見えにくい「現場の空気感」や「隠れた課題」を把握することができ、今後の対応を検討につなげることが可能です。
配属先・異動の最適化
適材適所の人材配置にもAIが活用できます。
AIが、本人の希望やキャリア志向、適性検査の結果、保有スキルや資格情報、過去の異動歴や評価などの多様な情報を総合的に分析し、配属や異動の最適な候補案を提示することが可能です。
これにより、新たな配置の可能性が見つかったり、本人の志向と業務の特性が合致するポジションを提案できるため、ミスマッチの防止になり、社員のモチベーション向上や定着率の向上が期待できます。
AIによる面接
近年、採用面接をAIが行うサービスも出てきています。志望動機や業務経験など面接での質問を登録しておき、応募者への質問もオンラインでAIが行います。面接時の回答をAIが分析し、評価まで出してくれるというものです。
24時間365日、世界中どこでも面接ができるため、日程や場所の調整を行う必要がなくなり機会損失を防げます。担当者による採用基準のバラつきを防ぎ、面接にかかる時間をその他業務に専念することができることも大きなメリットです。
また、採用面接に限らず、社内の昇進昇格試験でAI面接を用いる企業も増加してきています。
議事録や会議内容の要約
議事録作成や会議内容の要約にはAIの活用が適しており、特化型のツールも複数出てきています。議事録作成に特化したサービスもあれば、最近ではWeb会議ツールに要約作成機能が付随しているものもあります。
いずれも基本的には、会議の内容を録音・録画し、そのデータをAIが処理・要約するといった仕組みです。音声認識もできるため、話者の区別も自動で行えます。
ただし、専門用語や固有名詞、音声が聞き取りにくい箇所は正しく文字起こしされていないこともあるので、人の目による最終確認は必要ですが、議事録作成の時間を大幅に減らすことが可能です。
また、記録を簡単に残せるため、トラブル防止対策も容易に行うことができます。
採用業務の効率化を支援します
「AIの導入は難しい、でも採用業務は効率化したい」
そのようなお悩みに対し、マンパワーグループでは「採用代行・コンサルティングサービス」を提供しています。
支援内容やお見積もりはお気軽にお問い合わせください。
人事業務にAIを活用するメリット
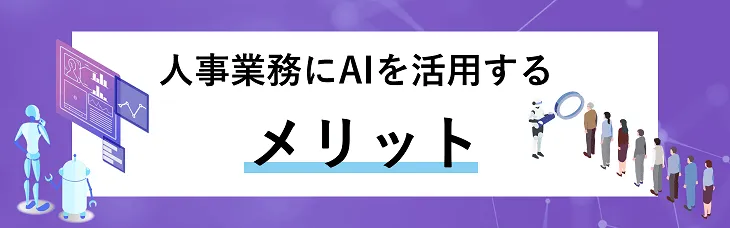
続いて、人事業務にAIを活用するメリットを紹介します。ただし、AIを利用すれば必ずこれらのメリットを享受できるわけではありません。投入するデータの質や、指示の出し方(プロンプト)などに大きく左右される点には留意が必要です。
採用担当者を「採用できない」を解消する
AIは候補者検索やスカウト文面作成、応募情報の整理・要約、必須条件の自動チェックや重複検出、面接日程の調整、FAQ対応といったルーティンを24時間365日で担い、対応遅れ・滞留・属人化といったボトルネックを取り除きます。
少人数体制でも候補者対応の速度と品質を一定に保ちやすく、担当者は要件の磨き込み、候補者の口説き(クロージング)、採用広報の強化といった付加価値の高い業務に割り当て、事務作業やルーティン業務を行う人員を減らすことが可能です。
客観的なデータをもとに評価できる
データ分析はAIの得意な分野です。採用や人事評価など、何らかの評価・判断をする際、評価者の主観や感情、経験則に左右されることが多く、評価のばらつきや不公平感が生じやすいのが実情です。
このように客観的なデータを基に評価をすることで、評価の一貫性が高まり、従業員の納得感やモチベーションの維持にもつながる可能性があります。
膨大なデータをもとに人事戦略を遂行できる
人間が把握しきれないような膨大かつ多様な情報も、AIは高速かつ網羅的に分析することが可能です。例えば、サーベイの分析や人員配置の分析、人事評価などの際は、より多くのデータを用いた方が多角的で納得感のある分析ができます。
また、人事データに限らず、自社の業績などのデータ、業界の動向、公的なデータなども取り込むことで、より多角的な分析が可能になります。このように、AIを用いることで、これまでは活用できていなかったデータを含んだ分析が実施でき、より最適化された人事戦略を遂行できるようになります。
人事の業務にAIを活用するリスク
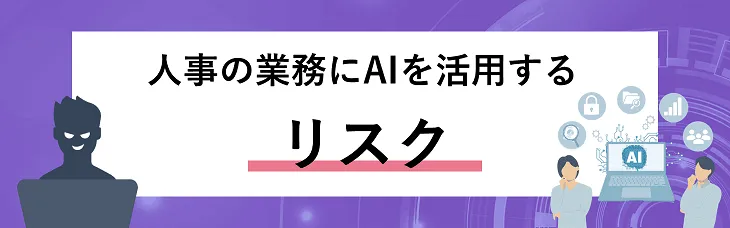
一方で、AI活用にはリスクも存在します。ここでは、実際に想定される主なリスクとその対策を紹介します。
偏った学習をして不適切な回答をする懸念
AIが生成する情報は必ずしも正しいとは限りません。蓄積・学習している情報が誤っている、情報が古いなどの要因により、不適切な回答が生成されることがあります。誤った情報を基に資料を作成したり、拡散したりすると、企業の信頼失墜になる恐れがあります。
また、人事業務は労働法などの法改正が影響する業務も多いです。古い情報がAIに蓄積・学習されたままだと、最新の法令を遵守していない回答が生成され、知らない間に違法な対応をしてしまうリスクもあります。
【対策例】
- AIにより生成された回答はあくまで参考程度とする
- 最終的には人の目による確認・判断を行う
個人情報・機微情報の取り扱いに注意が必要
AIは入力されたデータを蓄積・学習します。そのため、AIに個人情報や顧客情報のような機密性の高い情報を入力してしまうと、別のユーザーの回答に利用されてしまうなどのリスクがあります。ただし、商用サービスの中には、入力情報を学習に利用しないよう設定できるものもあります。一方で、情報が一時的に保存されたり、社内利用の範囲で分析に使われるケースもあるため、注意は必要です。
また、通常のシステムと同様、AIもサイバー攻撃の対象になりうるため、セキュリティ対策が不十分だと情報漏洩につながる可能性もあります。
人事業務は採用時の応募者情報や従業員情報など多くの個人情報を扱うため、AIの活用時にはより注意したい問題です。
【対策例】
- AI活用のガイドラインを作成する
- AIに入力して良い情報・業務範囲のラインを定める
- データの暗号化やアクセス制限のあるAIツールを選定する
従業員からの不安や抵抗感
AIの活用に対しては、さまざまな不安や抵抗感を持つ従業員がいる可能性があります。例えば、AIに依存しすぎることで社内コミュニケーションが減り、上司との会話や面談の機会が少なくなると、不安や孤立感が増すことがあります。また、採用や人事評価にAIを利用した場合、評価基準が見えにくくなり、「なぜその評価になったのか」がわからないことから、不信感や不満につながる恐れもあります。
さらに、AI導入によって自分の仕事が奪われると感じる人や、従来の業務スタイルを変えることへの抵抗を持つ人も少なくありません。こうした懸念を無視して強引に導入を進めると、モチベーションの低下や離職リスクを招く可能性があります。
【対応策】
- メリットや背景を丁寧に説明し、理解と協力を得る
- 一部業務や特定部門で試験導入し、その成果をもとに段階的に活用範囲を広げる
与える情報や質問スキルによる精度の変化
AIの回答精度は、利用する側が与える情報の質や質問の仕方によって大きく左右されます。前提条件や背景情報が不足していると、AIは適切な判断ができず、誤った結論や不正確な提案を返す可能性があります。また、質問が抽象的すぎたり曖昧だったりすると、回答も表面的になりがちです。
【対策例】
- 情報を整理して的確に伝えるスキルや、必要な情報を引き出すための質問力が求められるため、利用者のトレーニングやガイドラインの整備を実施する
人事業務にAIを導入した成功事例
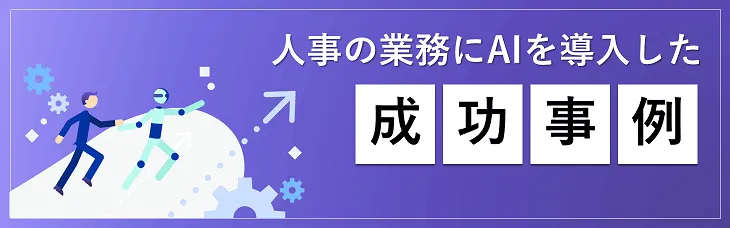
では、実際に人事業務にAIを活用している成功事例を紹介します。
事例① チャットボット導入による問い合わせ対応時間削減(A社/製薬業界)
全国約1万超の従業員からの問い合わせ対応の効率化のため、チャットボットを導入した事例です。社内問い合わせ対応により、担当者が他の業務に時間を割けない上に、回答までに時間がかかってしまうケースもあり問題視されていました。
AIチャットボットを導入したことで、問い合わせの約75%を自動化でき、約3,500時間の削減を実現しました。回答の待ち時間もなくなり、人事部門だけでなく問い合わせをする従業員からも好評です。
事例② エントリーシートのAI判定導入による作業時間削減(B社/情報通信業界)
これまでは、新卒採用時のエントリーシートを採用担当者が1枚ずつ読んで合否を評価していましたが、数も多く評価に時間がかかっていました。また、評価基準は決めているものの、複数人で担当していると人によって判断に多少の差が出てしまう可能性も課題に感じていました。そこで、テキスト分析をするAIを導入し、エントリーシートを解析させることにしました。
AIの評価は必ず正しいものではないことを考慮し、AIが「不合格」としたエントリーシートは担当者が読み、合否の最終判断を行う運用を行っています。最終的に人の目で確認はしますが、不合格となったエントリーシートのみを確認すれば良いので、大幅な時間削減を実現できました。年間680時間かかっていたエントリーシートの評価時間を170時間まで短縮し、実に75%の削減を実現しています。
人材派遣のご相談はこちらから
マンパワーグループは、日本で最初の人材派遣会社です。全国68万人以上の登録者から、貴社に最適な人材をご提案いたします。
人材派遣の利用をご検討の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

まとめ
AI技術は、人事業務の効率化と品質向上に大きな可能性をもたらします。ただし、その導入には戦略的なアプローチが欠かせません。採用の精度向上、労務管理の自動化、データ分析による意思決定の支援など、多方面でのメリットが期待できる一方で、プライバシー保護や人間らしい判断の重要性といった課題も存在します。まずは自社の課題を明確にしたうえで、段階的な導入を進め、AIの活用を実現していきましょう。
こちらの資料もおすすめです
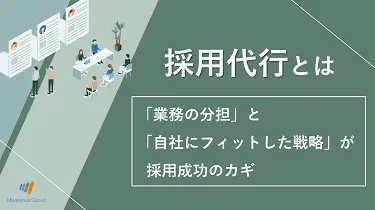









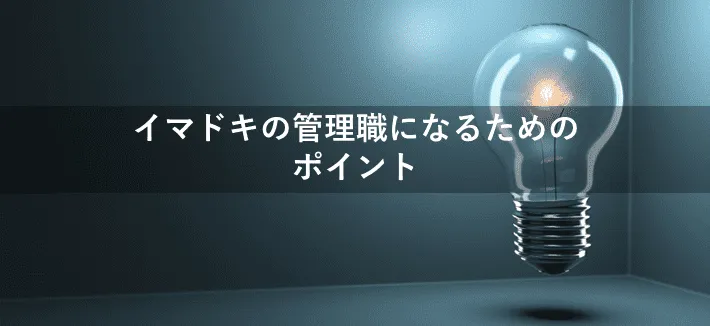











 目次
目次