


内定と採用の違いは?各通知書の種類とよくあるトラブル・対策

目次
採用から入社までの期間はおおよそ1カ月~数カ月を要します。新卒者は学校を卒業後、転職者は現職を退職してからの入社となるためです。このような事情から、「採用」決定から入社までを「内定」期間として、企業と応募者は互いに入社の約束を取り交わします。
しかし、「内定」と「採用」は定義があいまいで、誤った使い方をされることがよくあります。その結果、辞退や取り消しなどのトラブルが発生することも珍しくありません。今回は「内定」と「採用」の違いを明らかにしながら、トラブル対策についても解説します。
あらゆる採用の悩みに、採用のプロならではの知見を
マンパワーグループでは、採用プロセスの業務代行サービス、採用戦略立案や採用プロセス設計などのコンサルティングサービスを提供しています。本資料では、採用活動から採用後の定着に至るまでの各種課題に応じたソリューションを紹介しています。
<この資料でわかること>
・ サービスの特徴
・ 採用支援実績
・ サービスの種類
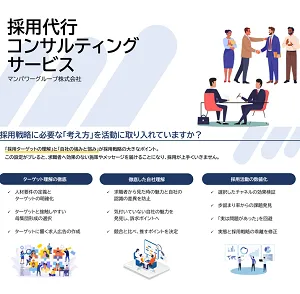
「内定」と「採用」の違い
一般的に「採用」や「内定」というと広い意味で使われています。しかし、法的観点では、それぞれの語句の意味に違いがあります。「採用」と「内定」にはどんな違いがあるのか見ていきましょう。
採用は採用試験に合格した状態
現在「採用」という言葉は、広い意味を含んで使われています。例えば、入社や内定、募集活動などが挙げられます。定義においては諸説あり、見解が分かれるところでしょう。法的観点において「採用」とは、企業が応募者に雇用する意思を伝えること、すなわち『採用の意思を応募者に伝えた状態』のことです。
内定では法的拘束力が発生する
一般的に「内定」は、企業から採用通知がなされた状態として認識されています。なお、採用通知に同意することを「内定受諾」、断ることを「内定辞退」と呼びます。
一方、法的観点における「内定」は『労働契約を締結した状態』のことです。これは、企業が応募者に雇用する意思を伝え、応募者も入社する意思を示し、双方が合意していることを意味します。
また、契約を結ぶことで法的拘束力が生じます。ただし、内定から入社までは数カ月単位で期間が空くこともあるため、「始期付解約権留保付労働契約」とされており、合理的な理由があれば取り消しが可能です。
内々定とは内定を約束すること
新卒採用において、内定に似た「内々定」という言葉がよく使われます。内々定とは、内定を約束しながらも、労働契約は締結していない状態のことです。法的拘束力は生じません。
なぜ、正式な内定に先立って、企業は内々定を出すのでしょうか。
これは、政府が定める新卒採用ルールで、正式な内定日は「卒業・修了年度の10月1日以降」と決められていることが関係しています。早期段階で内定を出したくても、新卒採用ルール上できないケースがあります。そこで、労働契約が締結できる期間までは、内々定という形で正式な内定の予定を約束しているのです。
内定時に提示すべき「通知書」の種類と書き方
採用選考で合格した後、内定に向けてなにを準備すればよいのでしょうか。内定時に「通知書」という書面を提示するのが一般的です。代表的な通知書には、「採用通知書」「内定通知書」「労働条件通知書」の3つがあります。これらの詳細と、書面に記載すべき内容について紹介します。
内定時は内定通知書など書面での提示が基本
採用内定者に対して、「内定通知書」という書面で内定を通知します。「あなたは採用内定です」という口約束だけでも、法的拘束力が生じると考えられています。しかし、口頭では採用内定にかかわるトラブルが多いことから、「内定通知書」で書面に残す形が有効です。
また、労働条件(従業場所や賃金・労働時間など)に関しては、労働基準法によって労働契約締結時に明示することが義務付けられています。内定は、始期付き解約権留保付きの労働契約と考えられています。入社時に労働条件通知書を提示する企業もありますが、内定時に労働条件の提示を行う方が望ましいでしょう。
特に、中途採用においては、就業場所や賃金などが内定時に決まっているケースが多いため、入社後のトラブル回避に役立ちます。
「採用通知書」・「内定通知書」・「労働条件通知書」の違い
内定時に活用される通知書には「採用通知書」「内定通知書」「労働条件通知書」があります。
採用通知書は「採用を通知する書面」で、内定通知書は「内定を通知する書面」です。内定通知書は、法的拘束力を持つ内定の「証し」となり得ます。しかし、法的定義が明確ではないため、区分けなく使われているのが実状です。
他方、労働条件通知書は、労働基準法第15条第1項において提示義務が定められています。詳しくは後述します。
なお、中途採用では以下のとおりに、提示することが一般的です。
- 内定通知書とともに労働条件通知書をセットで提示
- 内定通知と労働条件通知を同じ書面にて提示
内定通知書の内容
「内定通知書」や「採用通知書」は、様式や内容が明確に定まっているわけではありません。だだし、内定は「始期付き解約権留保付きの労働契約」とされています。そのため、「始期=入社日」と「解約権=内定取り消しの権利」がどのようなときに行使されるかという内定取り消し事由を、内定通知書には入れておくのがよいでしょう。
【内定通知書の記載内容例】
- 採用が決定した旨の連絡
- 入社日(入社予定日)
- 内定取り消し事由:(例)予定どおり学校を卒業できなかった場合、病気・事故などにより正常な勤務ができない場合、犯罪行為、経歴の詐称、書類の虚偽などが発覚した場合など
企業は、必要事項を記載した内定通知書と内定承諾書をセットで提示します。一方、内定者は内定承諾をした旨の「承諾書」を本人サイン入りにて提出する形式が主流です。
労働条件通知書の内容と例
労働条件の通知においては、法律で明示事項が規定されています。また、書面での交付が義務付けられている項目もあります。
労働条件の明示事項は、以下のとおりです。
- (1)労働契約の期間に関する事項
- (2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
- (3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
- (4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- (5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
- (6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
- (7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
- (8)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
- (9)安全及び衛生に関する事項
- (10)職業訓練に関する事項
- (11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- (12)表彰及び制裁に関する事項
- (13)休職に関する事項
※これらの内(1)から(5)((4)の内、昇給に関する事項を除く。)については書面の交付により明示しなければなりません。
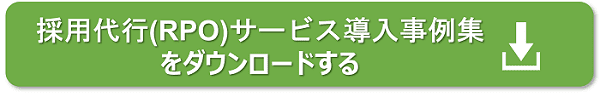


















 目次
目次