


【完全ガイド】採用活動における数値指標 公的指標・社内指標をそれぞれ解説

目次
採用活動において優秀な人材を効率的に獲得し、競合他社との差別化を図るためには、客観的な数値指標に基づいた戦略的アプローチが不可欠です。本記事では、賃金相場や業界統計などの外部環境を把握する公的指標と、選考通過率や採用コストなどの自社の採用パフォーマンスを測る社内指標の両面から、実践的な活用方法を詳しく解説します。
関連資料:採用代行・コンサルティング サービス案内
採用活動における指標とは?
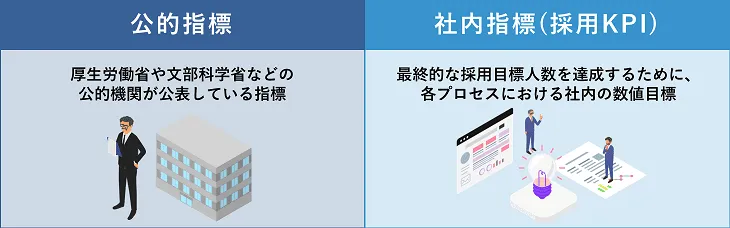
採用活動における指標には、公的指標と社内指標があります。
公的指標とは、厚生労働省や文部科学省などの公的機関が公表している指標です。景気などの社会情勢が強く反映され、労働市場全体を把握するのに適しています。
一方で社内指標は「採用KPI」とも呼ばれ、最終的な採用目標人数を達成するために、各プロセスにおける社内の数値目標を定めたものです。自社の状況や取り組みの成果が反映されるのが特徴です。
例えば、「今年度の新卒採用は3人を目標にする」と決めた場合、「3人を採用するには、応募者数・書類選考通過率・内定辞退率など、各プロセスでどのような数値を目指すべきか」を定めます。これらが採用KPIです。
採用指標活用のメリット
公的指標の活用により労働市場全体の状況の把握ができます。公的指標は採用活動の前提情報とも言えるでしょう。仕事を探している人がどれほどいるのか、同業の給与相場はいくらなのかなど、労働市場の現況や推移を知った上で採用計画を立てることができます。
社内指標は採用活動の最適化に活用できます。採用チャネルごとの費用対効果を数値化することにより、採用広告費の最適化が可能となり、また選考通過率の比較を行うことで採用基準の最適化にも繋がります。
また、採用活動終了後に各プロセスの実績を数値で算出し、目標と比較・分析することで、次回の採用活動の改善に繋がります。また、実績データを蓄積することで自社の採用傾向が把握でき、さらに施策の効果を客観的に評価することも可能です。
採用指標の利用により、こういった課題に対し「何となく」ではなく客観的な数値に基づいた対策が可能となります。
重要なのは、1度分析して終わりにしないことです。定期的に情報を更新し、毎月・毎年の各指標の推移を把握し、直近の傾向の分析・改善を繰り返していくことです。
採用環境を把握するための公的な指標
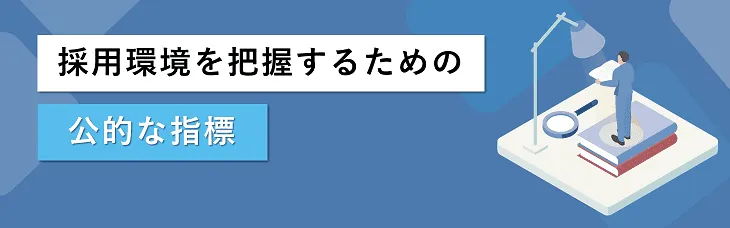
まずは、採用の外部環境を把握するために活用できる公的指標について解説します。
- 有効求人倍率
- 新規求人倍率
- 完全失業率
- 大学等就職内定率・就職率
- 新規学卒3年以内離職率
- 雇用動向調査(入職・離職の傾向)
- 職業安定業務統計(求人票データ分析/職種ごとのニーズ)
- 賃金構造基本統計調査(給与動向の基礎)
- 消費者物価指数
- 法人企業統計調査
採用環境を把握するための公的な指標URL一覧
| 有効求人倍率 | |
| 新規求人倍率 | |
| 完全失業率 | |
| 大学等就職内定率・就職率 | |
| 新規学卒3年以内離職率 | |
| 雇用動向調査 (入職・離職の傾向) |
|
| 職業安定業務統計 (求人票データ分析/職種ごとのニーズ) |
|
| 賃金構造基本統計調査 (給与動向の基礎) |
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/13.pdf |
| 消費者物価指数 |
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei08_01000317.html |
| 法人企業統計調査 |
https://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/results/release_info.htm |
有効求人倍率
有効求人倍率 ![]() は、厚生労働省が毎月発表している、労働市場が「売り手市場」か「買い手市場」かを見極める尺度です。倍率1.0を境に、企業側が人材を確保しにくい状況(売り手市場)か、求職者が仕事を見つけにくい状況(買い手市場)かを判断できます。
は、厚生労働省が毎月発表している、労働市場が「売り手市場」か「買い手市場」かを見極める尺度です。倍率1.0を境に、企業側が人材を確保しにくい状況(売り手市場)か、求職者が仕事を見つけにくい状況(買い手市場)かを判断できます。
算出方法
有効求人倍率 = 有効求人数 ÷ 有効求職者数
(いずれもハローワークでの申し込みから効力が存続している“有効”データを使用)
- 求人50件 ÷ 求職者100人 = 0.5 仕事不足(買い手市場)
- 求人100件 ÷ 求職者100人 = 1.0
- 求人100件 ÷ 求職者50人 = 2.0 人手不足(売り手市場)
活用法
●指標としての活用
- 月次の推移や職種別の倍率を追い、採用計画の時期・目標人数・予算配分を調整
- 景気変動や法改正の影響を把握するための材料として、経営層向けのレポートに活用
●倍率の水準に応じた対応策
倍率が高い(売り手市場)のとき
- 競合を調査し、労働条件を強化するなど他社との差別化を図る
- リファラルやダイレクトリクルーティングなどチャネルを多様化し、母集団を広げる
倍率が低い(買い手市場)のとき
- 採用媒体などを絞るなど、採用費を削減できないか検討
- 応募が伸びない場合は市場状況と照らし合わせて原因を特定し、内容や訴求方法を見直す
留意点
有効求人倍率はハローワーク経由の中途採用データのみを反映しています。民間求人媒体・エージェント経由や新卒採用は含まれないため、全体像をつかむには自社データや民間調査と併用するとより精度が高まります。
新規求人倍率
新規求人倍率 ![]() は 「今月新たに出された求人」と「新たに仕事を探し始めた人」のバランスを示す指標です。有効求人倍率と同様、厚生労働省が毎月発表しています。
は 「今月新たに出された求人」と「新たに仕事を探し始めた人」のバランスを示す指標です。有効求人倍率と同様、厚生労働省が毎月発表しています。
- 倍率0を超えると、企業の新規求人が求職者より多く、採用難が強まる兆候。
- 有効求人倍率より変化が早く現れるため、景気や労働市場の“転換点”を敏感に捉えられる
算出方法
新規求人倍率 = 新規求人数 ÷ 新規求職者数
(ともに当月にハローワークに“新規”登録されたデータを使用)
- 新規求人30件 ÷ 新規求職者100人 =3
- 新規求人100件 ÷ 新規求職者100人 =0
- 新規求人150件 ÷ 新規求職者100人 =5
活用法
●短期の採用計画を微調整
- 倍率が上昇傾向なら、採用枠拡大や広告出稿を前倒しし、早期に母集団を確保。
- 下降傾向なら、有料求人媒体の利用を縮小する
留意点
- 対象はハローワーク経由の中途採用に限られ、民間求人媒体やエージェント経由、新卒採用は含まれません。
- 月次での変動が大きい指標なので、トレンドを把握するためには、3カ月移動平均で数値のブレをならすと、傾向が見えやすくなります。
完全失業率
完全失業率 ![]() は 「働く意思と能力があるのに就業できていない人」の割合を示し、労働市場にどれだけ“余剰人材”が存在しているかを測る代表的な景気指標です。総務省の「労働力調査」で毎月発表されています。
は 「働く意思と能力があるのに就業できていない人」の割合を示し、労働市場にどれだけ“余剰人材”が存在しているかを測る代表的な景気指標です。総務省の「労働力調査」で毎月発表されています。
- 率が上昇すると求職者が増え、企業にとっては応募者を集めやすい傾向(=採用しやすい環境)。
- 率が低下すると求職者数が減り、企業間の採用競争が激化。条件改善や採用戦略の見直しが必要になる兆し。
算出方法
完全失業率 = 完全失業者数 ÷ 労働力人口 × 100(%)
- 完全失業者 150万人 ÷ 労働力人口 6,600万人 × 100 ≒ 2.3 %
- 完全失業者 330万人 ÷ 労働力人口 6,600万人 × 100 ≒ 5.0 %
労働力人口:15歳以上のうち「働いている人」または「職を探している人」の合計
完全失業者 とは次の条件をすべて満たす人:
- 調査週にまったく仕事をしていない
- すぐに就業可能
- 直近4週間に求職活動や開業準備を行った
活用法
● 採用難易度の目安として
- 率が高い局面では、応募者プールが豊富になりやすく、即戦力採用の好機。
- 率が低い局面では、競合他社との差別化(報酬・福利厚生・選考スピード)が重要。
留意点
- 就業意思がない人(家事専念者・学生・引退者)や“就業をあきらめた人”の“潜在失業”は含まれないため、実態を過小評価する可能性がある。
- 労働力調査は無作為に抽出された約4万世帯を対象にしたサンプル調査であり、ハローワーク登録データに基づく有効求人倍率などとは統計の性質や対象が異なる。有効求人倍率などと直接比較する際は調査対象の違いに注意。
- 季節要因で変動するため、季節調整値と3カ月移動平均を併用してトレンドを見ると判断精度が高まる。
大学等就職内定率・就職率
大学等就職内定率・就職率 ![]() は、新卒採用市場の“内定競争の早さ”と“最終的な採用充足度”を読み取る指標です。
は、新卒採用市場の“内定競争の早さ”と“最終的な採用充足度”を読み取る指標です。
- 内定率(在籍学生のうち就職希望者に対して内定を得た学生の割合)は「いつ・どれだけ内定が出回っているか」を把握でき、他社より早いタイミングでオファーを出す目安になります。
- 就職率(就職希望者に対して就職が決定した学生の割合)は「卒業時点までにどれほど採用活動が完結しているか」を把握でき、前年との難易度比較に役立ちます。
厚生労働省・文部科学省が共同で 年4回(10月1日、12月1日、2月1日、4月1日時点) の速報値を公表します。
算出方法
- 内定率 = 内定取得者数 ÷ 就職希望者数 × 100(%)
- 就職率 = 就職決定者数 ÷ 就職希望者数 × 100(%)
〈例〉卒業予定者1万人のうち、就職希望者7千人/内定取得者5千人/就職決定者6千人の場合
- 内定率:5,000 ÷ 7,000 × 100 = 71.4 %
- 就職率:6,000 ÷ 7,000 × 100 = 85.7 %
活用法
●リカバリーの要否判断
10月時点で内定率が例年より高い場合:すでに母集団が小さくなっている可能性大。追加採用は難航が予想されるため、来年度計画の前倒しや、ダイレクトソーシングなど少数精鋭ルートの検討が現実的。
12月時点で内定率が低い場合:まだ就活継続層が多い。追加説明会・SNS施策・早期選考など“まだ探している学生”に向けた施策を打つと効果が見込める。
留意点
- 対象は大学、短期大学、高等専門学校等の卒業予定者で、専修学校(専門学校)や大学院修了予定者は含まれていない。
- 調査対象校は抽出方式(サンプル調査)のため、個別大学の状況と必ずしも一致しない。
- 4月1日時点の就職率が最も確定値に近いが、10〜2月の速報値は変動が大きいため、トレンド把握には前年同時期との比較が欠かせない。
- 内定取消しや入社辞退は反映されないため、最終的な入社数を見極めるには自社の辞退率データも合わせてチェックすることが望ましい。
新規学卒3年以内離職率
新規学卒3年以内離職率 ![]() は、「新卒で入社した社員が3年以内に離職した割合」を示し、
は、「新卒で入社した社員が3年以内に離職した割合」を示し、
- 若手の定着難易度(=オンボーディングや職場環境の適合度)
- 定着率をふまえた採用数の調整(早期離職による人材ロスの想定)
を客観的に把握できます。厚生労働省が毎年、最終学歴・企業規模・業種別に公表しているため、同業他社や規模の近い企業と比較しやすい点も大きな特長です。
直近データ(令和3年3月卒業者)では、大卒は34.9%、高卒は38.4%と新卒入社の3人に1人以上が3年以内に離職しています。
算出方法
3年以内離職率 = 3年間に離職した新卒者数 ÷ 新卒入社者数 × 100(%)
〈例〉入社100人のうち、3年間で35人が退職
→ 35 ÷ 100 × 100 = 35 %
※ 離職・在籍の把握には、事業所がハローワークへ提出する雇用保険の資格取得・喪失データが用いられます。そのため雇用保険の適用外(週20時間未満の短時間契約・海外勤務など)は集計に含まれません。
活用法
● 採用目標の設定に反映
- 自社と近い業種・規模の離職率を参考に、必要人員に対する採用数を調整
- 想定される離職率を踏まえて、中長期の採用・育成計画を最適化
● 競合比較でアピール
- 同業より低い離職率を維持できていれば、説明会や採用サイトで「早期定着率の高さ」を訴求し差別化。
留意点
- 雇用保険加入者のみ が対象。研修生・フリーランス契約などは含まれず、実態より低く出るケースがある。
- 調査は「卒業年次 × 3年後」のクロス集計で毎年秋頃に更新されるため、 最新年度の値が把握できるまで タイムラグ がある。
- 産業別・企業規模別で大きく水準が異なるため、自社と属性が近い区分を参照することが重要。
関連記事:新卒採用で用いられる9つの採用手法を解説
採用環境を把握するための公的な指標URL一覧
| 有効求人倍率 | |
| 新規求人倍率 | |
| 完全失業率 | |
| 大学等就職内定率・就職率 | |
| 新規学卒3年以内離職率 | |
| 雇用動向調査 (入職・離職の傾向) |
|
| 職業安定業務統計 (求人票データ分析/職種ごとのニーズ) |
|
| 賃金構造基本統計調査 (給与動向の基礎) |
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/13.pdf |
| 消費者物価指数 |
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei08_01000317.html |
| 法人企業統計調査 |
https://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/results/release_info.htm |
雇用動向調査(入職・離職の傾向)
厚生労働省の「雇用動向調査 ![]() 」は、サンプル抽出した企業に上半期と下半期の2回、入職者数と離職者数を尋ね、労働市場の“人の流れ(流入・流出)”を数値化しています。
」は、サンプル抽出した企業に上半期と下半期の2回、入職者数と離職者数を尋ね、労働市場の“人の流れ(流入・流出)”を数値化しています。
- 入職率が高い業種・雇用形態ほど「採用は活発」
- 離職率が高いほど「人材が流出しやすい環境」または「景気悪化による退職増」の可能性
- 両方が高い場合は転職市場の流動性が大きく、中途採用しやすい環境
業種別・企業規模別など多面的に公表されるため、競合と比較した自社の採用・定着状況を客観視できます。
算出方法
- 入職率= 入職者数 ÷ 1月1日現在の常用労働者数 × 100 (%)
〈例〉年初在籍1,000人/年間入職180人/離職150人 - 入職率 = 180 ÷ 1,000 × 100 = 18 %
- 離職率 = 150 ÷ 1,000 × 100 = 15 %
- 入職超過率 = 入職率–離職率 = +3 pt(人員純増)
活用法
● 中途採用の難易度把握
- 業種Aで入職・離職とも20%超なら転職活動が活発。採用の進捗を慎重に注視し、芳しくない場合は、早期に施策を講じる
● 景気・人手不足感の先読み
- 離職率だけ上昇していれば、業界に不況や人手不足が波及し始めたシグナル。追加採用や派遣活用を検討。
● 定着施策のヒント
- 調査には「転職理由」の集計も含まれる。退職理由の上位(人間関係・処遇・仕事内容など)を参考にリテンション施策を講じる。
留意点
- サンプル調査で回答企業のみが集計対象。母集団は全国の企業全体と完全には一致しない。
- 対象は雇用保険加入者(週20時間以上、31日以上雇用見込み)で、短時間パートや業務委託は含まれない。
- 季節要因や業種特性で数値が大きく異なるため、自社と属性が近い区分で比較することが重要。
職業安定業務統計(求人票データ分析/職種ごとのニーズ)
職業安定業務統計 ![]() は、ハローワークに集まる求人・求職・就職データを毎月集計し、職種別・都道府県別・雇用形態別など多軸で公表しています。
は、ハローワークに集まる求人・求職・就職データを毎月集計し、職種別・都道府県別・雇用形態別など多軸で公表しています。
主な指標
- 有効求人倍率
- 新規求人数
- 新規求職者数
- 有効求人数
- 有効求職者数
- 就職件数
活用法
- 業種別の有効求人倍率で「いま人手不足が深刻な業種」や「比較的応募が集めやすい業種」が分かる。
- 都道府県別の倍率から、隣県や近隣都市の需給バランスを比較でき、エリア拡大やリモート勤務可否の検討材料になる。
- 雇用形態別の状況で、正社員・パートそれぞれの人材確保難易度を把握できる。
留意点
- ハローワーク経由のみのデータであり、民間求人サイト・エージェント経由や新卒求人は含まれない。
- 2021年9月以降はオンライン登録求職者もカウントされるなど、集計方法が随時アップデートされているため、前年比較時は注記を確認する必要がある。
- 職種区分は日本標準職業分類を使用。自社職種と完全に一致しない場合は近い区分で代替する。
- 季節要因で倍率が振れやすいため、3カ月移動平均や前年同月比でトレンドを読むと精度が高まる。
賃金構造基本統計調査(給与動向の基礎)
厚生労働省が毎年公表する賃金構造基本統計調査 ![]() は、産業・職種・都道府県・企業規模・年齢・性別など多様な切り口で「どのような属性の人が、どの地域で、どの程度の賃金を得ているか」を把握できる最も詳細な公的データです。
は、産業・職種・都道府県・企業規模・年齢・性別など多様な切り口で「どのような属性の人が、どの地域で、どの程度の賃金を得ているか」を把握できる最も詳細な公的データです。
例えば令和6年調査では、一般労働者(フルタイム)の平均所定内給与額は月額33万400円、前年比+3.8%と33年ぶりの伸び率となりました。
主な指標と読み方
| 主な指標 | 意味・ポイント | 代表的な使いどころ |
| 所定内給与額(月額・時間額) | 基本給+各種手当の合計(残業除く) | 基準賃金の相場把握、職種・地域別比較 |
| きまって支給する現金給与額 | 所定内+残業+通勤等を含む毎月決まって支払う総額 | 募集要項の月給水準チェック |
| 年間特別給与額(賞与) | 夏・冬の賞与など年1回以上の一時金合計 | 年収シミュレーション、インセンティブ設計 |
| 初任給 | 新卒(学歴別)の月給 | 新卒採用の提示額検討 |
※調査は常用労働者5人以上の事業所を抽出し、6月分給与と前年賞与を回答してもらう仕組みです。
活用法
- 求人賃金の設定
- 募集職種が「県平均+10%」なら競合優位、「−10%」なら応募が細る恐れ。
- 隣県より相場が高い場合、リモート勤務可を打ち出せば採用コスト圧縮も可能。
- 報酬テーブルの改定
- 性別・年齢・勤続年数別データで、自社賃金カーブが市場とかい離していないか検証。
- 昇給・賞与原資の確保
- 残業時間や賞与の伸び率も確認し、年次予算や労使交渉の根拠資料に。
留意点
- サンプル調査:回答事業所(約5〜9万人規模)からの推計値で、母集団全体とは誤差が生じる。
- 時点のズレ:給与は6月支給額、賞与は前年1〜12月分を集計。昇給や臨時ボーナスの動きをリアルタイムに捉えるには、月例の「毎月勤労統計」と併用が望ましい。
- 非常勤・フリーランスは除外:週20時間未満や請負契約者は対象外のため、実態より賃金水準が高めに出る場合がある。
- 産業・職種分類の改定が入る年は、前年比較時に注釈を確認しないと誤読の原因になる。
消費者物価指数
消費者物価指数 ![]() は、物価の変動を測定するもので、総務省が毎月公表しています。
は、物価の変動を測定するもので、総務省が毎月公表しています。
活用法
消費者物価指数の上昇率を参考に給与・昇給額の設定を行うことで、物価動向に見合った賃金提示ができます。特に中途採用では、収入アップを求める人も多いため、物価を考慮した賃金の提示ができると優位になります。
また、地域別の情報も公表されているので、勤務地による物価の違いを賃金に反映しやすくなり、各地域で公平感のある賃金設定が可能になります。
実質賃金
消費者物価指数は「実質賃金」の算出にも利用されています。
実質賃金とは、名目賃金(税金や社会保険料などを引く前の金額)を物価の上昇率で調整したもので、労働者の生活水準や経済の健全性を表しています。
例えば、3%の賃上げをしても、物価が5%上がっていれば、実質的に生活水準は低下していることになります。
実質賃金の算出方法は次の通りです。
- 実質賃金:名目賃金 ÷ 消費者物価指数 × 100
このように、消費者物価指数が変動すれば、実質賃金も変動します。
留意点
実際の公表までに1カ月程度のラグが発生するため、物価変動が激しい時期には、公表されたデータと実態にズレが生じている可能性があります。また、消費者物価指数はあくまで平均的な家計支出を基準にしているため、生活スタイルや家族構成により、物価上昇の影響が異なる点も理解が必要です。
法人企業統計調査
法人企業統計調査 ![]() は、財務省が四半期ごとに公表している、営利法人の財務状況を調査したもので、企業規模・業種別の企業動向を知ることができます。
は、財務省が四半期ごとに公表している、営利法人の財務状況を調査したもので、企業規模・業種別の企業動向を知ることができます。
活用法
社会全体の景気の把握ができるのはもちろん、業績情報からは自社の業界の経営状況や成長性がわかり、業界の将来性や業界内での自社のポジションを把握できます。
同業他社との比較により、自社の強みの明確化もしやすくなるでしょう。
また、設備投資などの投資動向からは、将来的に需要が高まる分野や、必要となるスキルセットも予測できます。同業他社と自社の投資額を比較することで、成長性のある企業、経営が健全な企業というアピールポイントとしても活用できます。
留意点
金融・保険業は除くデータのため、全業種が掲載されているわけではありません。また、資本金1千万円以上の企業の調査は年4回(3月・6月・9月・12月)、資本金1千万円未満の企業の調査は年1回(9月)が公表される点に留意が必要です。
採用環境を把握するための公的な指標URL一覧
| 有効求人倍率 | |
| 新規求人倍率 | |
| 完全失業率 | |
| 大学等就職内定率・就職率 | |
| 新規学卒3年以内離職率 | |
| 雇用動向調査 (入職・離職の傾向) |
|
| 職業安定業務統計 (求人票データ分析/職種ごとのニーズ) |
|
| 賃金構造基本統計調査 (給与動向の基礎) |
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/13.pdf |
| 消費者物価指数 |
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei08_01000317.html |
| 法人企業統計調査 |
https://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/results/release_info.htm |
関連資料:採用代行・コンサルティング サービス案内
企業内で押さえるべき採用KPI

ここからは、企業内で押さえるべき採用KPIを紹介します。基本的には採用活動全体の数値を出しますが、採用チャネル別・入社後の部署別など、細かな単位での数値も算出し比較すると、より問題点が見えてきます。また、以降で紹介するKPIの特徴によって、1か月ごと、1年ごとなど、複数の期間の数値を算出し、それぞれを比較することも効果的です。
関連記事:採用KPIの立て方│設定と運用のポイントを具体例で解説
必要母集団数
必要母集団数とは、目標人数を採用するために何名の応募者が必要かを算出した数値です。「採用目標人数÷各選考通過率÷内定承諾率」で算出できます。
例えば、自社の採用の書類選考通過率・面接通過率・内定承諾率がいずれも50%と仮定したとします。採用目標人数が3人のとき、「3÷50%÷50%÷50%」で24人の応募があれば良いことになります。これが必要母集団数です。
理論上、母集団数が少なければ採用人数も当然少なくなります。母集団数を把握しておくと、採用目標人数に対して応募者が少ないときには採用チャネルを増やすなどの対策を検討できます。
関連記事:失敗しない採用のための15の母集団形成方法の選び方
応募者数・応募率
求人に対してどれだけの人が応募しているかを測る指標です。応募者数は求人に対して応募があった数、応募率は「応募者数÷求人広告の表示回数×100」で算出できます。
複数のチャネルや求人内容で出している場合は、チャネル別・求人別の応募率を比較すると、どの採用チャネルから応募が多いか、どの求人内容の反応が多いかなどの傾向が見えてきます。
自社の求人が魅力的か、広く知れ渡っているかを把握できるため、応募率が低ければ、求人の内容や応募条件の見直し、別チャネルの利用を検討しても良いかもしれません。
応募者数・応募率は、その後の選考や採用人数に大きく影響する出発点です。まずは応募者数・応募率を上げることが不可欠です。
書類通過率・面接通過率
応募者のうち書類選考や面接を通過した人の割合を測る指標です。選考辞退した人数も含みます。
- 書類通過率:書類選考通過人数÷応募者数×100
- 面接通過率:面接通過人数÷面接実施者数×100
面接を複数回実施する場合には、一次・二次・最終と、フェーズごとに通過率を設定しておくと、選考プロセスの課題が可視化されます。
通過率が想定よりも低い場合、まずはその基準が適切に設計されているかを確認することが重要です。特に初めて行う採用活動を行った場合、例年と違う採用手法を取った場合には、判断の妥当性を検証する視点が求められます。
また、基準やプロセスに変更がないのに通過率が大きく変動している場合は、母集団形成(求人の出し方・ターゲット設定・訴求内容など)に何らかの要因がある可能性も考えられます。
内定数・内定承諾率
内定数は実際に内定を出した数、内定承諾率は内定を出した人のうち、実際に内定を承諾した割合を示す指標です。
- 内定承諾率:内定承諾者数÷内定者数×100
内定承諾率の上下に一喜一憂せず、その要因を分析することが重要です。内定承諾率が著しく変化している場合には、内定を出す基準が妥当かを見直す、労働条件や職場環境の何が影響しているのかを分析することも効果的です。
内定辞退数・内定辞退率
内定辞退数は内定を出したあとに辞退された数、内定辞退率は内定者のうちどれぐらいが辞退したのかを測る指標です。
- 内定辞退率:内定辞退者数÷内定者数×100
内定を出すまでには採用コストがかかっていますから、この数値は低ければ低いほど良いとされています。数値の分析だけでなく、内定辞退の理由も併せて把握し、労働条件や競合他社との差別化、採用期間の見直しなど、内定辞退を防ぐための改善案の検討に繋げることが重要です。
採用単価
採用活動にかかった費用を測る指標です。
- 採用単価:採用活動全般にかかった総費用÷採用人数
採用に複数のチャネルを利用しているときには、チャネルごとのコストを出すとより効果的です。
チャネルごとに費用対効果がわかれば、次回の採用での予算配分の見直しができます。また、1人あたりの採用コストを把握することで、採用全体の予算計画を最適化できたり、内定辞退率や離職率を下げるための施策提案がより具体的なものにできるでしょう。
採用予算は無限ではありませんから、費用対効果を把握することは採用において重要なポイントの1つです。
関連記事:採用コストとは|計算方法と一人あたりの平均、5つの削減ポイントを解説
平均採用期間
1人採用するのに平均でどれくらいの期間がかかったかを測る指標です。
- 平均採用期間:募集開始から採用決定までの日数÷採用人数
採用期間が長くなると、応募者が不安になり選考辞退をしてしまう、選考中に他社からの内定が出るなどの影響があり、自社への入社機会損失に繋がるおそれがあります。採用スピードが遅くなっていないかを確認するためにも必要な指標です。
また、全体だけでなく選考フェーズごとの平均期間を算出することで、ボトルネックとなっている工程の特定にも繋がります。
入社後定着率・離職率
入社後定着率・離職率は、いずれも採用後の状況を測る指標です。
社員定着率は、採用後一定期間経過しても継続勤務している人の割合のことで、離職率は、採用後に離職した人の割合です。
- 社員定着率:採用後在籍している社員数÷採用人数×100
- 離職率:離職した社員数÷採用人数×100
両者とも、採用後1年間・3年間など、一定期間を区切って算出・分析するとよいでしょう。
前述の公的指標「新規学卒3年以内離職率」と自社の離職率を比較することで、自社の離職率が一般的かどうかを把握することもできます。また、離職率と共に離職理由を把握することで、自社に合うかどうかを選考基準で重視する、入社後のフォロー体制を手厚くするなど、採用活動時の対策にも繋げられます。配属先ごとに定着率・離職率を算出することで、特定の職場の問題点が浮かび上がってくることもあります。
さらに、配属後の満足度や入社後の評価(考課)も入社後の採用KPIとして活用されることがあります。入社後の満足度はミスマッチの把握や配属後のフォローが適切だったかの評価指標に、入社後の評価(考課)は、採用した従業員の能力が期待したものだったか、面接で能力や職場への適応力を見抜けていたかなどの評価指標になります。
関連記事:【離職防止】9の打ち手と事例を徹底解説
まとめ
このように、採用活動を成功させるには、公的指標と社内指標の両方を効果的に活用することが不可欠です。有効求人倍率や就職率などの公的指標により市場動向を把握し、内定承諾率や採用単価などの社内指標で具体的な改善点を明確にすることで、戦略的な採用活動が実現可能になります。指標を継続的に分析し、採用活動を改善することで、限られた予算と時間の中で自社に適した人材を着実に確保していきましょう。
こちらの資料もおすすめです


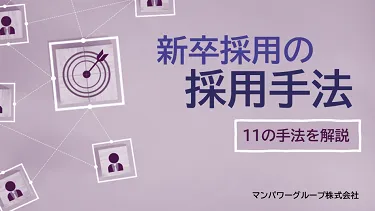
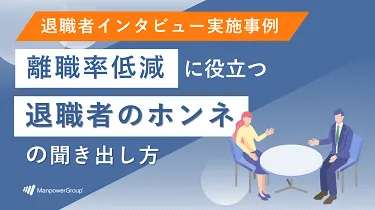


















 目次
目次