


【障がい者雇用】企業が対応すべき合理的配慮|導入ステップとポイント

目次
障がい者の採用過程でも合理的配慮を
障がい者雇用では、障がい者一人ひとりに寄り添った「合理的配慮」の対応が求められます。しかし、合理的配慮とはどのようなものか、具体的にどのような対応を取れば良いかがわからず、不安を抱える企業も少なくないでしょう。本記事では、合理的配慮とはどのような内容か、合理的配慮を行う際のポイントや具体的な事例を解説します。
障がい者への合理的配慮とは
合理的配慮とは、障がい者が生活する際に、何らかの援助が必要な場合に、その原因となる障壁を取り払うために必要な変更や調整対応を指します。このことは、障がい者がほかの者と同様に人権や基本的自由を確保するために必要な考え方として、「障害者差別解消法」などの法律で定められています。
合理的配慮の特徴は、「一方的な配慮ではなく、配慮する側・される側がともに意思表示が確認できた場合に成立する」ということです。
つまり、何らかの対応が必要であるという障がい者からの意思が確認できた際に、負担が大きすぎない範囲内で対応に努めることが「合理的配慮」といえます。
合理的配慮が義務化された背景
合理的配慮は、2016年に成立した「障害者差別解消法」や「障害者雇用促進法」の改正により生まれた考え方です。これらの法律が定められる前までは、障がい者が抱える身体障がいや知的障がい、精神障がいは障がい者個人の問題であるため、障がい者自身が社会で生活していくために訓練する必要があるという考え方が主流でした。
しかしその後、「障がい者がほかの者と同様に生活することに困難が生じてしまうような社会のほうに問題があるのではないだろうか」という考え方が生まれました。
そこから、障がい者を取りまく考え方や環境を整備していく流れが生まれ、2016年成立の「障害者差別解消法」などへつながっていったのです。
障害者雇用促進法における合理的配慮
障害者雇用促進法における合理的配慮とは、障害を持つ人が仕事や社会生活において平等に参加できるように、個々の障害の内容や程度に応じて必要な支援や環境の調整を行うことを指します。
改正障害者雇用促進法の施行により、障がい者が仕事をする際に生じる支障を改善するため、事業主に対して合理的配慮の実施が義務づけられています。
配慮が「合理的」であるかは"過度な負担でないこと"
合理的配慮とは、障がい者とほかの者の双方で意見を出し合い、すり合わせを行うことが必要 です。しかし、障害者雇用促進法の第36条において、事業主に対して過度な負担でないこと、とされています。
事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
過度な負担ではないことの基準については、後述します。
合理的配慮を実施しない企業への罰則は
合理的配慮を実施しない企業への罰則規定は、現時点では設けられていません。
しかし、同じ事業主が障がい者の権利を幾度となく阻害するような差別を行うケースや、改善の兆しが見られないケースなどには、その事業主に対して事業担当の大臣が報告を求める場合があります。これに対し、虚偽の報告内容を伝える場合や報告をしない場合は、20万円以下の過料が科せられる場合があります。
他の法律と合理的配慮の関係
障害者雇用促進法以外の法律と合理的配慮とどのようにつながっているかを解説します。
障害者差別解消法と合理的配慮
障害者差別解消法とは、障がい者とほかの者がともに住みやすい社会になるように定められた法律で、障がい者に対する障がいを理由とした不当な差別を禁止しています。
この法律では、障がい者が普段の生活の中で何らかの障壁により生活しづらいと感じ、対応が必要だと意思表示した場合に、行政や事業者が可能な範囲内で対応する合理的配慮を実施するよう求めています。
障害者雇用促進法と合理的配慮
障害者差別解消法とは、障がい者とほかの者がともに住みやすい社会になるように定められた法律で、障がい者に対する障がいを理由とした不当な差別を禁止しています。
この法律では、障がい者が普段の生活の中で何らかの障壁により生活しづらいと感じ、対応が必要だと意思表示した場合に、行政や事業者が可能な範囲内で対応する合理的配慮を実施するよう求めています。
障害者権利条約と合理的配慮
「障害者権利条約」という名称に馴染みのない事業主もいるかもしれませんが、これは21世紀初めの国際人権法に基づいた条約で、障がい者の人権や基本的自由の享有を確保し、尊厳が尊重されるための措置が定められています。この条約をもとにして、前述の「障害者差別解消法」や「障害者雇用促進法」が成立し、障がい者を取りまく法律が整備されてきました。
合理的配慮という考え方も本条約で具体的に定義づけられ、「障がい者がほかの者と同じく平等な立場であることを基礎として、人権および基本的自由が確保されるために必要な対応のうち、特定の場合において必要であり、過度の負担がかからないもの」とされています。
合理的配慮での「過重な負担」を判断する際の要因
厚生労働省が発表している合理的配慮指針では、「過重な負担」になるかどうかを判断する際、以下のポイントを考慮して決定するとされています。
| ポイント | |
|---|---|
| 事業への影響 | 配慮をすることで、生産やサービス提供などの事業活動にどれほどの影響があるか |
| 実施の難しさ | 事業所の位置や所有形態により、必要な機器や人材、設備などの確保の難しさ |
| コストや負担 | その配慮を行うための経費やその他の負担。複数の障害者から要望がある場合は、それら全体のコストも考慮 |
| 企業の大きさ | 企業の規模に応じて、何が「重い負担」であるかは変わることがある |
| 企業の財務状態 | その企業の経済的な健全さによって、何が「重い負担」であるかが異なる |
| 公的な助成や支援の存在 | 公的な支援や補助金を利用できるかどうか。利用可能な場合、それを考慮して判断 |
障がい者への合理的配慮を考える際の3つのポイント
障がい者に対する合理的配慮を実施していく際に重要な3つのポイントを解説します。
申し出てもらうための下地作りが重要
合理的配慮を成立させるためには、障がい者が仕事において何らかの支障をきたす状況に置かれた際に、遠慮せずに申し出てもらえる環境を作ることが必要です。
有効な対応策の一つは、企業と障がい者が初めて対面する採用面接の中で、どのような配慮が必要なのかなどを申し出やすい状況を作りましょう。障がい者の中には、自分自身がどのような対応が必要なのかを把握しておらず申し出る必要性に気づいていない者や、配慮を申し出ると採用されないのではないかという不安を抱える者などがいる可能性があります。
まずは企業側から、配慮の申し出を行うことは双方にとって重要であること、そして申し出を遠慮する必要はないことを伝え、障がい者に安心してもらうことがポイントです。
採用後の配慮事項について認識を合わせる
事業主は、障がい者の希望や意向をしっかり尊重しながら、具体的な措置を決定します。
求職者と話し合いの結果、提案する措置が障がい者の希望と違う場合、または障がい者の要望が過重な負担と判断される場合、求職者に明確に伝える必要があります。
また複数の措置の選択肢があるとき、事業主は障がい者の意向を尊重した上で、実現しやすい措置を選ぶことができます。
求職者の要求に応じられない場合の対処
合理的配慮とは、障がい者とほかの者の双方で意見を出し合い、すり合わせを行うことが必要 です。しかし、事業主側に過度な負担がかからないことが要件となるため、たとえば、サポート人員が大幅に必要となる場合や、多額の資金を要する場合、作業スペースの増築などの大掛かりな工事が求められる場合などは検討が必要です。
過度な負担がかかり実施が難しい場合でも、「無理です」と拒絶してしまうのではなく、実現が難しい理由を丁寧に伝えた上で、ともに代替案を検討するなどの措置が求められる点に注意しましょう。
障がい者への合理的配慮を導入する4つのステップ
障がい者が合理的配慮を申し出るまでの流れについて、順に解説します。
当該障がい者から申し出を受ける
合理的配慮は、障がい者からの意思表明がスタート地点です。
障がい者自身が、仕事をするにあたってどのような支障や懸念点を抱えているか、本人の申し出から確認します。また申し出と同時に、障がい者手帳や医師の診断書、専門家の所見が記載された資料などを参考にすることも必要です。
前述のとおり、意思表明がない場合でも、障がい者自身が状況を理解していない場合や申し出を遠慮している可能性もあるため、話しやすい環境づくりを心がけましょう。
配慮内容を話し合う
具体的な配慮の内容について、双方で意見交換をしながらすり合わせします。障がいの程度により話し合いを進めることが難しい場合は、保護者などの支援を受けながら、障がい者本人の意思ができる限り尊重されるように進める必要があります。
また、配慮内容により事業主側へ過度な負担が強いられ対応が難しい場合は、事業主が真摯に説明を行い、ほかの対応候補を提案する態度が求められます。
配慮内容を確定し、周知、実施する
具体的な配慮を実施するための段階として、社内へ周知する必要があります。
障がい者に対する配慮は、事業主のみならず、社員の理解が必要不可欠です。会社全体で配慮内容を理解し、実施できる環境を整備しましょう。
定期的な評価や見直しを行う
合理的配慮は、前述のとおり障がい者とほかの者との相互理解が必須です。ただし、常に変化する社会情勢の影響を受け、合理的措置と判断されていた内容が、しばらく後になって妥当ではないと判断されるケースも考えられます。
これに対応するため、事業主は合理的配慮内容の評価を定期的に行い、必要であれば内容の見直しを実施しなければなりません。
募集・採用時と採用後における「合理的配慮」の一例
障がい者雇用・採用、採用後における、合理的配慮を実施すべき一例をご紹介します。
募集・採用時に関する配慮
障がい者が求人や採用時に特別な配慮を必要とする場合、企業はできる限り配慮を行います。
- 募集内容の告知方法(音声や点字)
- 面接方法(オンラインや筆談、手話など)
- 面接時間(体調に配慮)
など
採用後の合理的配慮
採用後は障がい特性を考慮した配慮を講じます。
- 出退勤時間や勤務時間の調整
- オフィス環境の整備
- 業務量の調整
- 音声ソフトなどツールの提供
など
障がい者への合理的配慮の5つの具体例
障がい者に対する合理的配慮を行う具体例を紹介します。
職場配置に関する配慮
職場の席や備品の場所、給湯室やトイレの場所が分からない場合に備え、事前に一日の流れを説明しながら移動訓練を実施する。
視覚障がいを持つ者などが転倒しないよう、危険と判断される荷物をあらかじめ撤去する。
ホワイトボードや掲示内容に関する配慮
記載内容が見づらい場合に備え、見やすい色・見えにくい色の事前リサーチを実施し、太字・波線による協調など、記載内容を工夫する。
読み上げソフトを活用し、ソフトの使用方法を事前に教示する。
ほかの社員とのコミュニケーションに関する配慮
関係者に障がい特性などへの理解を深めてもらい、コミュニケーションを工夫する。
一例としては、発言者の名前が分かるよう、ほかの社員は発言前や挨拶時に名前を名乗るようにするなど。
座席に関する配慮
仕事中に業務内容の確認がしやすいよう、言葉が聞き取りやすいように座席配置を工夫する。
出入り口やトイレ、非常口などの動線が分かりやすいような場所へ配置する。
通訳者や保護者、介助者の同行が必要な場合は、その者の座席を準備する。
教育に関する配慮
障がい特性や個人により、対応できる業務量や習熟度が異なるため、業務を徐々に増やしていく。
まとめ
合理的配慮は、障がい者への差別を禁止するためではなく、国民すべてが障がいの有無で隔てられないようにするための配慮といえます。職場で能力を発揮できない障がい者が一人でも少なくなるよう、まずは社内環境の整備や事業主、社員の意識を変えていく取り組みから始めてみてはいかがでしょうか。
障がい者雇用で陥りやすい失敗とは?
こちらの資料もおすすめです

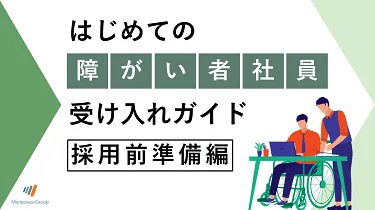
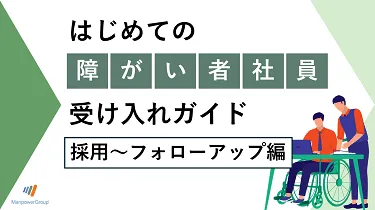


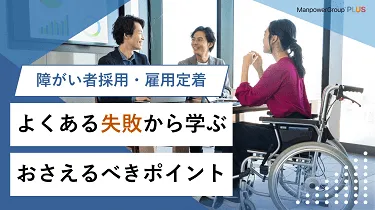
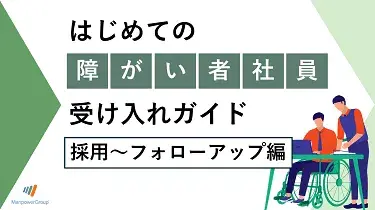
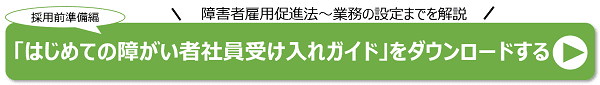


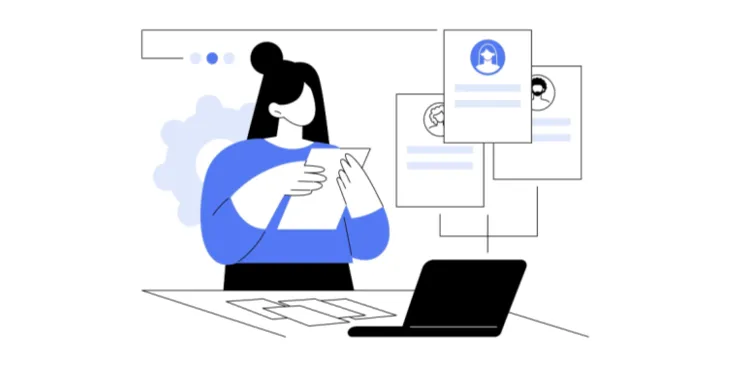
















 目次
目次