


みなし残業制度とは?メリットや違法リスク、適切に導入するポイントを解説

目次
あらかじめ一定の残業時間を見込み、その時間に応じた残業代を固定で支給するみなし残業制度は、企業や従業員に一定のメリットがあるものの、運用を誤ると違法なケースにつながるリスクがあります。
本記事では、みなし残業制度の仕組みやメリット・デメリットのほか、違法リスクや判例、適法に導入するポイントを解説します。
みなし残業(固定残業)制度とは?
はじめに、みなし残業(固定残業)制度の概要や仕組みを解説します。
そもそも残業とは?
残業とは、法律上の労働時間上限を超えた場合に支払う割増賃金を指します。労働基準法第36条では、原則、労働時間は「1⽇8時間・1週40時間以内」と定めており、この上限を超える残業をさせる場合は、いわゆる「36協定」という労使協定を締結する必要があります。
なお、法律上、残業の上限時間は、臨時的な特別の事情がない限り「⽉45時間・年360時間」と法定されているため、36協定は残業上限をこの範囲で締結します。そのため、これから説明する「みなし残業」の設定時間は、月45時間以内に収める必要があります。
残業(時間外労働)の制度を詳しく知りたい方は、次の厚生労働省資料をご参考ください。
参考:厚生労働省|時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(PDF) ![]()
みなし残業(固定残業)制度とは
みなし残業制度とは、あらかじめ一定の残業時間数を見込み、その時間数に応じた残業代を固定で毎月給与として支払う制度で、固定残業制度といわれることもあります。具体的には、従業員個々人の残業単価を基礎に、その時間数を乗じて残業代を計算します。
みなし残業(固定残業)の計算方法
みなし残業(固定残業)代 = 時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × みなし残業時間数
このみなし残業制度は、法律で定める制度ではありませんが、労働基準法37条の規制対象となります。この37条では、「通常の残業は25%以上」など所定の割増率「以上」の支払いが義務付けられています。そのため、実際の残業時間について、所定の割増率で計算した残業代がみなし残業代を下回る場合は違法となります。
割増率
- 時間外、深夜(22時~5時)の労働は25%以上
- 法定休日の労働は35%以上
みなし残業制度(固定残業)の仕組み
みなし残業制度は、みなし残業時間数に応じた残業代を月々の給与で固定的に支払う仕組みです。
みなしで残業代を支払うため、実際に残業していなくても必ず発生する一方、みなし残業時間数以下における残業代の計算はおこないません。そのため、給与明細では、実残業がみなし残業時間数以下の場合、「みなし残業手当」や「固定残業手当」といったみなし残業代の支給項目で、定額が表記されます。
次に、みなし残業制度における給与明細例を記しますので参考にしてください。
みなし残業制度の給与明細表示例
- みなし残業(固定残業)時間数:30時間
- 実残業時間数 :35時間
- 時間あたりの基礎賃金 :1,000円
- 割増率 :25%
|
残業時間数 |
5時間 |
|
みなし残業手当(固定残業手当) |
37,500円 |
|
残業手当 |
6,250円 |
この場合、みなし残業(固定残業)手当は、30時間分の残業代37,500円(1,000円×125%×30時間)を定額で支給する一方、みなし残業時間数を超える割増賃金については、追加分として、実残業時間数とみなし残業時間数の差となる5時間分の残業手当6,250円(1,000円×125%×5時間)を支給する必要があります。
みなし残業制度(固定残業)の留意点
みなし残業や固定残業という名称から、実際の残業時間数がみなし残業時間をどんなに超えても、みなし残業(固定残業)代を支払えばよいと誤解している人も少なくないかもしれません。
しかし、労働基準法は、所定の割増率「以上」の支払いを義務付けています。そのため、みなし残業時間数を超えた残業時間においては、前節で示した給与明細表示例のように、別途残業代を支給しなければならない点に留意してください。
関連記事:時間外労働の定義とは?労働形態ごとの残業代について解説
みなし労働時間制度とは?みなし残業(固定残業)制度との違い
みなし残業制度とは別に、みなし労働時間制度があります。どちらも同様に「みなし」という言葉が使われているため、混同してしまうこともあるかもしれません。ここでは、みなし労働時間制度の概要や違いを説明します。
みなし労働時間制度とは
みなし労働時間制度とは、労働基準法の下、1日における労働時間の算定について、実労働時間に拘わらず、所定労働時間を働いたとみなす制度です。この制度は、出張によって従業員の労働時間の算定が困難な場合や、労働時間を従業員の裁量に任せたほうが合理的な場合に一定条件の下で適用します。
みなし労働時間制度3つの種類(労働基準法第38条2〜4)
みなし労働時間制度は、労働基準法第38条の2〜4にて、次の3つのみなし労働時間制度を定めています。
- 事業場外労働
- 専門業務型裁量労働制
- 企画業務型裁量労働制
事業場外労働(労働基準法第38条2)
出張や営業活動における外出など、会社が労働時間を把握できない職種を対象とした制度です。なお、社外業務であっても、会社における指揮監督の下、時間管理ができる場合は対象外です。
制度内容を詳しく知りたい方は、次の厚生労働省の資料をご参考ください。
参考:厚生労働省(東京労働局・労働基準監督署)|「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために」(PDF) ![]()
専門業務型裁量労働時間制(労働基準法第38条3)
職務の性質上、労働時間を従業員の裁量に委ねる必要があるケースで適用します。この制度の対象は、研究開発職やシステムエンジニア、公認会計士、弁護士など、労働基準法施行規則に定める19の職種です。なお、制度の導入には、労使協定の締結と労働基準監督署長へ届け出が必要です。
具体的な対象職種は、次の厚生労働省のサイトをご確認ください。
企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条4)
専門業務型裁量労働時間制と同様、職務の性質上、従業員に労働時間の裁量を委ねる場合に適用する制度です。対象職種は、事業運営における企画や立案、調査、分析の職種が対象となります。
ただし、この制度を有効に機能させるため、導入時にあたっては、労使の十分な協議を必要とする枠組みとなっています。具体的には、十分な労使協議の下、必要事項を労使委員会で決議し、従業員の同意を得る必要があります。
制度を詳しく知りたい方は、次の厚生労働省の資料をご参考ください。
みなし残業(固定残業)導入3つのメリット
ここでは、みなし残業制度導入における3つのメリットを紹介します。
原則、残業計算が不要
第1のメリットは、原則として残業計算が不要なことです。
ただし、実残業時間数がみなし残業時間数を超えた場合は、割増賃金の計算が必要です。そのため、みなし残業時間を超えるか否かを判定し、超過した場合は、その超過分の残業計算をおこないます。
人件費の管理がしやすい
第2のメリットは、人件費の管理がしやすいことです。
実際の残業時間がみなし残業時間を超えない限り、人件費が一定となります。そのため、予算管理上、人件費の想定を大幅に超えることがないなど、人件費を管理しやすいメリットがあります。
従業員の収入が安定する
第3のメリットは、従業員の収入が安定することです。
みなし残業制度を適用していない場合、業務の多寡によって、月々の賃金が大幅に増減することもあります。みなし残業制度の導入によって、毎月の賃金が一定となるため、従業員の生活が安定することもメリットのひとつです。
みなし残業(固定残業)導入3つのデメリット
次に、みなし残業制度導入における3つのデメリットを紹介します。
必ず固定残業代が発生する
第1のデメリットは、必ず固定残業代が発生することです。
「実際に残業した時間が少ない」や「まったくない」月でも、あらかじめ定めたみなし残業手当を支給する必要があります。そのため、みなし残業時間を下回る従業員が多いほど、人件費の無駄が発生するといえます。業務の効率化を促進する側面はありますが、企業によっては大きな損失が生じるケースもあるでしょう。
サービス残業リスクが発生しやすい
第2のデメリットは、サービス残業リスクが発生しやすいことです。
みなし残業や固定残業という言葉が与える印象から、残業代の支払いに上限があると誤認し、管理者が実質的にサービス残業を強いるリスクもあるでしょう。
制度をよく理解していないと、管理者はもちろん、人事担当者も誤認する恐れがあります。人事担当者や管理者は法の趣旨を理解し、みなし残業時間を超える残業については、追加の残業代を支払う必要があることに留意してください。
長時間労働に陥りやすい
第3のデメリットは、長時間労働に陥りやすいことです。
元々、残業を見込んだ賃金制度のため、「残業するのは当たり前」と誤認する管理者は少なくありません。こうした環境下では、残業は当然という風土が根付き、付き合い残業のような状況も生じる可能性があります。こうした状況が常態化している場合は、みなし残業時間制度の適用は望ましくないといえるでしょう。
人事が知るべき、みなし残業(固定残業)が違法となる5つのケース
これまで、みなし残業制度の概要やメリット・デメリットを見てきましたが、ここでは、みなし残業が違法となるケース5つを解説します。
1.就業規則等にみなし残業の定めがない
法律上、賃金や労働時間などの労働条件を書面などで明示することが義務付けられています。みなし残業は、賃金の計算・支払い方法として明示する必要があるため、就業規則や労働契約に定めていない状態で、みなし残業制度を適用している場合は違法といえます。
2.みなし残業時間を上回る残業代が支払われていない
労働基準法37条では、所定の割増率「以上」の支払いが義務付けられています。そのため、あらかじめ設定した「みなし残業時間数」を超えた残業が発生している場合、その超えた残業代を追加で支給しないと違法となります。
3.月45時間超のみなし残業時間が設定されている
みなし残業制度も通常の残業同様に、労働基準法第36条の規制対象となります。この36条では、残業時間の限度を原則、「⽉45時間・年360時間」と定めており、企業はこの定めに基づき「36協定」を締結しています。このため、月45時間を超えるみなし残業を設定した場合、実残業時間が定常的に法定限度を超える恐れがあります。
4.みなし残業代が基本給に組み込まれている
みなし残業代が基本給に組み込まれている場合、「法定の割増賃金が支払われていない」など、みなし残業代をめぐるトラブルが生じる恐れがあります。こうしたトラブルを避けるため、厚生労働省は、若者雇用促進法に関する指針として、みなし残業(固定残業)代と基本給は区分して表示することを求めています。
5.みなし残業代を除いた基本給が異様に少ない
みなし残業代が基本給に組み込まれているケースにおいて、みなし残業代を除いた基本給が異様に少ない場合、最低賃金を下回っている恐れがあります。最低賃金は、都道府県毎に定められていますので、その最低賃金を下回っている場合は違法となります。
知っておきたい、みなし残業(固定残業)の判例
ここでは、みなし残業制度をめぐる裁判例を紹介します。
判例1:割増賃金の算定基礎(除外賃金か否か)、および管理監督者にあたるか否か
概要
アルバイトスタッフの管理・指導をおこなっていた元従業員が懲戒解雇されたことを機に、未払賃金、割増賃金等を請求した事案。割増賃⾦請求権の有無や額の判断において、元従業員における「管理監督者性」、営業⼿当の「みなし残業代性」などが争われた事件です。
判決
みなし残業に関する判決は、営業手当は営業活動に対するインセンティブとして支給することが妥当であり、実質的な残業の対価と認めることはできないため、営業手当は残業手当ではないと判断されました。
参考:公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会|未払賃金等請求事件(アクティリンク事件)平成23年(ワ)1954号 ![]()
判例2:月45時間超の通常残業及び深夜残業を手当とすることの有効性
概要
ホテルの料理人兼パティシエが、時間外賃金の未払分および付加金を請求した事案。労働者に対する賃金減額の合意、および95時間分の割増賃金を「職務手当」としたみなし残業の合意有効性が争われた事件です。
判決
みなし残業に関する判決は、95時間のみなし残業を無効とし、45時間の限度で有効と判断されました。
参考:公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会|賃金等請求事件(ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件)平成22(ワ)1359 ![]()
みなし残業(固定残業)制度を適切に導入する5つのポイント
最後に、みなし残業制度を法に沿った適切な制度として導入するためのポイントを解説します。
1.みなし残業手当とそれ以外の手当を明確に区別する(区分要件)
みなし残業とそれ以外の手当の区分がなされていないと、本来のみなし残業の対価と、それ以外の手当の対価が判別できず、違法リスクが生じます。
判例では、基本給や営業手当、職務手当などにみなし残業手当を含めていたケースがあります。こうした違法リスクを避けるため、通常の労働時間の賃金とみなし残業における割増賃金を明確に判別できるようにしてください。
2.時間外労働の対価として支払う旨の合意をする(対価要件)
みなし残業手当として支給する割増賃金は、みなし残業時間数〇時間分の時間外労働の対価であることを労使で合意しておくことが重要です。労働基準法37条における割増率の支払い要件を満たしているか、労使で認識できるようにしておくことがポイントになります。
3.みなし残業(固定残業)時間を超える割増賃金の差額を追加で支払う(差額支払要件)
労働基準法37条では、所定の割増率「以上」の割増賃金支払いを義務化しています。この定めの下、実残業時間がみなし残業時間数を超えた場合、この超過分の割増賃金の支給が必要です。
4.45時間超のみなし残業時間は設定しない(36協定)
みなし残業時間数を法定限度の月45時間以内に収めれば、実際の残業時間を36協定の範囲内に収めやすくなります。ただし、働き方改革の観点では、極力、限度上限でなく、余裕をもったみなし残業時間数の設定が望ましいでしょう。
5.みなし残業(固定残業)制度導入時の明示事項を求人票等に明示する(若者雇用促進法)
近年、みなし残業に関する賃金表示をめぐるトラブルを背景に、厚生労働省では、「若者雇用促進法」に基づく指針でも、みなし残業(固定残業)の適切な表示を求めています。具体的には、次の項目を明示するよう指針で定めています。
- 固定残業代を除いた基本給の額
- 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
- 固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨
詳しくは、厚生労働省のリーフレットをご参考ください。
参考:厚生労働省|固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします(PDF) ![]()
まとめ
本記事では、みなし残業制度の仕組みやメリット・デメリットのほか、違法リスクや判例、適法に導入するポイントを解説しました。
みなし残業制度は、人件費の管理がしやすい、従業員の収入が安定するなどのメリットがある一方、運用を間違えるとさまざまな違法リスクがあります。違法が発覚すれば、企業評価の低下は免れず、採用にも影響するなど、さまざまな方面からレピュテーションリスクによる損害を被る恐れもあります。
違法リスクを十分に理解し、社会保険労務士などの専門家のアドバイスを受けるなど、みなし残業制度を適法に導入・運用しましょう。
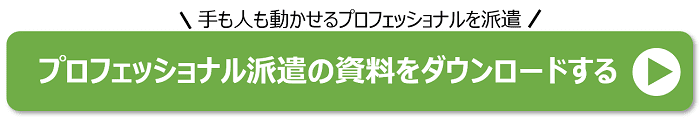
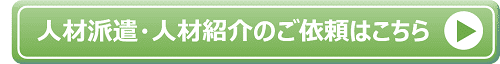
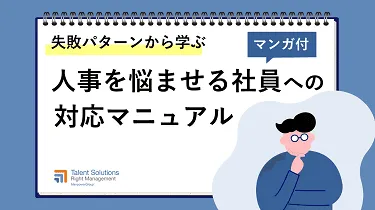
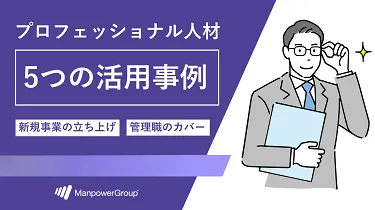


















 目次
目次