


派遣先にも適用される?男女雇用機会均等法における不利益取扱いの禁止とは

目次
男女雇用機会均等法は、正式名称を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(PDF) ![]() 」といい、1985年に性別による差別をなくすことを目的として制定されました。この法律では、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを禁止しています。対象は自社の労働者に限らず、派遣社員にも及ぶため注意が必要です。
」といい、1985年に性別による差別をなくすことを目的として制定されました。この法律では、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを禁止しています。対象は自社の労働者に限らず、派遣社員にも及ぶため注意が必要です。
この記事では、男女雇用機会均等法による不利益取扱いについて具体的に説明をします。
男女雇用機会均等法は、派遣先にも適用される
男女雇用機会均等法を自社の労働者に適用することは、事業主の義務となっています。その中で、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産等に関するハラスメント対策、母性健康管理措置についての規定は、派遣社員を受け入れている派遣先にも適用されます。
なお、育児・介護休業法では、会社が労働者や派遣社員に対し、育児休業の申出や取得を理由として不利益取扱いをすることを禁止しています。
男女雇用機会均等法とは
男女雇用機会均等法は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする法律です。
労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては、母性を尊重されつつ充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本理念としています。
参照:厚生労働省|雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(PDF) ![]()
育児・介護休業法とは
育児・介護休業法とは「育児休業・介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で、育児及び介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図れることによってその福祉を増進するとともに合わせてわが国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。
参照:厚生労働省|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(PDF) ![]()
派遣社員の受け入れには、派遣法に基づき多くのルールが定められています。
派遣先責任者や現場担当者向けが押さえておきたい12のポイントをわかりやすく解説した資料をご用意しました。
派遣先に求められる具体的な義務と配慮事項
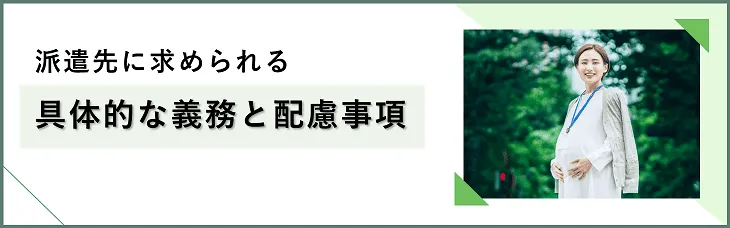
派遣先にも労働者派遣法により男女雇用機会均等法における以下の内容についての義務が適用されます。
- 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
- 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
- 妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント対策
- セクシュアルハラスメント対策の措置
- ハラスメントにおける派遣先が講ずべき措置
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
妊娠・出産等を理由として女性労働者に不利益取扱いをすることは禁止されています。禁止されている不利益取扱いの例は以下になります。
- 解雇する
- 期間を定めて雇用される者について契約の更新をしない
- あらかじめ契約の更新回数を上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げる
- 就業環境を害する
- 不利益な自宅待機を命ずる
- 不利益な配置の変更を行う
- 派遣先が派遣労働者に勤務を拒む
また、派遣社員に関する具体例として厚生労働者は以下を挙げています。
- 妊娠した派遣労働者が、派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにもかかわらず、派遣先が派遣元事業主に対して派遣労働者の交替を求めること
- 妊娠した派遣労働者が派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにもかかわらず、派遣先が派遣元事業主に対して派遣労働者を拒むこと
参照:厚生労働省|派遣先にも男女雇用機会均等法や育児・介護休業法が適用される(PDF) ![]()
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
派遣先は、自ら雇用する労働者と同様に派遣社員についても妊娠中及び出産後の健康管理に関する必要な措置を講じなければなりません。
- 妊産婦が、保健指導または健康診査を受けるために必要な時間の確保
- 妊産婦が保健指導または健康診査に基づく主治医等の指導事項を守ることができるようにするために講じなければならない
例として、時差出勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮措置、休業等があげられます。
さらに適切に措置を講じるために派遣社員についても「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を促しましょう。女性労働者がこのカードを提出した場合、派遣先はカードの記載された内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。
妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント対策
妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント対策については、平成29年1月1日から防止措置を講じることが事業主に義務付けられました。いわゆるマタニティハラスメントです。
妊娠、出産等に関するハラスメントの発生原因や背景には以下があります。
1.否定的な言動が横行する職場風土
妊娠、出産等に関する否定的な言動(他の女性労働者の妊娠、出産等の否定につながる言動で、単なる自らの意思の表明を除き、本人に直接行わない言動も含みます)がひんぱんに行われると、制度等の利用や請求をしにくい雰囲気が生まれます。
例えば、つわりでよく休む同僚に対する「妊娠は病気ではない」「皆が迷惑をしている」「仕事がすすまなくて困る」などの言動が当てはまります。
2.制度の周知不足
制度等の利用ができることが職場内で十分に周知されていなければ、結果としてハラスメントが発生する原因となる可能性があります。マタニティハラスメント防止が事業主の義務になっていることや、どんな言動が該当するのか知らない労働者は多いものです。
妊娠中は心身ともにデリケートな時期のため、周囲の言動が思わぬ負担になることがあり、職場全体での理解と配慮が不可欠です。
そのため、管理職はメンバーの職場内の言動に注意を払う必要があります。「よく休めていいなあ」「病気じゃないのに」などの言葉は、妊娠中の従業員に対する配慮を欠いた発言であり、本人の状況によっては精神的な負担となる可能性があります。
管理職はこうした言動が職場で起こらないよう、日頃から注意を払い、必要に応じて事前に周囲へ配慮を促すことが重要です。管理職がそれを放置しておくと、何かあった場合、事業主の責任となり、さらには管理職の責任となります。
セクシュアルハラスメント対策
派遣先は自社の労働者と同様に派遣社員について、職場におけるセクシュアルハラスメント(以下セクハラ)対策として雇用管理上および指揮命令上必要な措置を講じなければなりません。
また、職場のセクハラは、異性に対するものだけでなく、同性に対するものも該当します。相手の性的志向または性自認にかかわらず、すべての人が対象となりうる問題です。
例えば、「子どもは若いうちに作るべき」「何人作る予定?」などの発言は、話し手にとっては軽い雑談のつもりでも、受け手の価値観やプライバシーを侵害する可能性があり、セクハラに該当することがあります。
セクハラの発生の原因や背景には、性別役割分担意識に基づく言動もあると考えられ、こうした言動をなくしていくことがセクハラ防止の効果を高めるうえで重要です。お茶を入れるのは女性、荷物を持つのは男性、顧客の受付は女性などまだまだ性別で役割を決めている会社もあります。
このため、男女雇用機会均等法は、職場におけるセクハラ防止のために雇用管理上必要な措置を講じることを事業主に義務付けているのです。
ハラスメントにおける派遣先が講ずべき措置
ハラスメント対策として、自社の労働者に対しては様々な措置を講じているかと思います。しかし、派遣社員はどうでしょうか?派遣社員にも同じように以下の措置を講じなければなりません。
- 事業主の方針及びその周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応する
- 事後の迅速かつ適切な対応
- 1から3までの措置と併せて講ずべき措置
-
- プライバシーの保護
- 不利益取扱いの禁止
1から4までの措置の他に望ましい取組として厚生労働省は以下をすすめています。
妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため、妊娠等した派遣労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を周知し啓発することが必要です。企業が何も言わなければどんな制度があり、どのように利用できるのかわかりません。また同時に派遣労働者が周囲との円滑なコミュニケーションを図りながら、自身の体調等に応じて、適切に業務を遂行できるように意識を持つことの重要性も伝えることが必要です。
参照:厚生労働省|派遣先にも男女雇用機会均等法や育児・介護休業法が適用される(PDF) ![]()
派遣先がすべき対応策
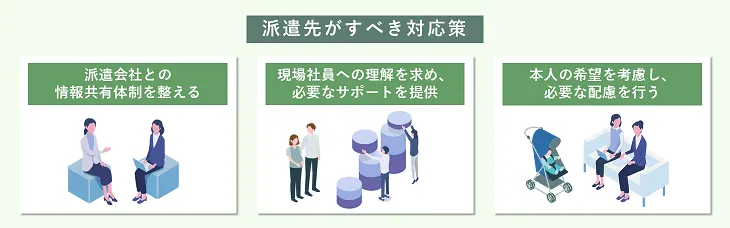
派遣先に男女雇用機会均等法に沿った制度があったとしても、その内容について派遣社員が知らなければ、制度の活用はできません。その結果、派遣先の意図するものではなくても派遣社員が不利益な取り扱いを受ける可能性があります。
また、ハラスメントに関しても、派遣先の従業員が何をハラスメントと認識すべきかを理解していない場合、無意識のうちに加害行為をしてしまうケースがあります。また、被害者が不快に感じていても、制度や相談窓口の存在を知らなければ、問題を指摘する機会を失い、結果として見過ごされてしまうことも考えられます。
不利益取扱いやハラスメントの発生は、信用低下や行政指導を受けるなどのリスクがあります。このようなことにならないための対応策をご紹介します。
派遣会社との情報共有体制を整える
派遣会社との情報共有体制の整備は必須です。特に妊娠について派遣社員から申出を受けた場合は、すぐに派遣会社に連絡を入れて連携することが重要です。派遣先での「まだ妊娠初期だから大丈夫」などの自己判断は避けるべきです。
また、妊娠に伴う健康リスクや過去の健康状態について派遣会社を通じて確認しておくことで、適切な対応が可能になります。
現場社員への理解を求め、必要なサポートを提供する
現場の管理職や同僚に理解がなければ、派遣社員は制度を使いづらくなってしまいます。
たとえば「なぜ休憩が必要なのか」と理由を聞かれることで、結果的に相談することを躊躇してしまうケースも少なくありません。管理職に対しては法令や制度の内容を周知し、ハラスメントにあたる行為を未然に防ぐ教育が必要です。また、同じ職場で働く仲間として、派遣社員が困っているときには協力できるよう職場風土を醸成することも大切です。
また、妊娠中は突発的な休暇や早退が生じやすいため、派遣社員の増員を検討するなど、現場への負担軽減策を取ることも望まれます。
本人の希望を考慮し、必要な配慮を行う
派遣社員とよく話し合い、今後の勤務について本人の希望を考慮しながら、必要な配慮を行う必要があります。
配慮の一例として、以下のような対応があります。
- 時差出勤
- 在宅勤務の併用
- 勤務時間の短縮
- 業務量の調整や変更
など
一方で、制度自体が存在しない場合や、人員配置の都合上で本人の希望に完全に沿うことが難しいケースもあります。その場合は、なぜ希望に応じられないのかを丁寧に説明しつつ、業務の一部を調整するなど、できる限り負担を軽減できる方法を検討することが重要です。
派遣先担当者からよくあるご質問
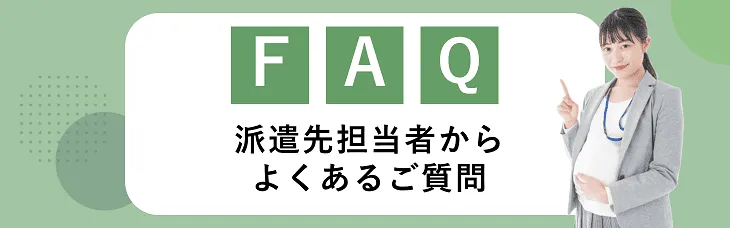
派遣先の担当者からよくある派遣社員に関するご質問をご紹介します。
妊娠に伴う欠勤が続く場合でも契約を終了(または満了で終わらせる)ことはできないのでしょうか?
妊娠中・産後1年以内の派遣社員に対する契約終了は、事業主が妊娠等の理由ではないことを証明しない限り無効とされています。
そのため、妊娠・出産を理由に契約更新を拒否したり、契約を途中で打ち切ることはできません。欠勤が続く場合は、まず派遣会社に相談し、業務量や勤務形態の調整、必要に応じて追加で派遣社員を手配するなどの対応策を検討することが大切です。
重量物の運搬や立ち仕事が多い現場ですが、本人が継続を希望している場合は、就業を継続させても問題はありませんか?
妊娠中の女性から請求を受けた場合には、会社は他の軽易な業務に転換させなければなりません。
しかし、本人が継続を希望しているのであれば、しばらく様子を見ることをおすすめします。そして、つらそうな様子が見えたり、休憩が多くなったりしたら「いつでも配置転換をするからね」と伝えておきましょう。一言伝えることで「頑張らなくもいいんだ」と不安がなくなります。
ただし、主治医等から作業の制限について指導を受けた場合は、いくら本人が「大丈夫です」と言っても会社としては負荷の軽減された業務に転換をしなければなりません。
業務が変わる場合、業務内容変更に伴う契約の巻きなおしが必要となる場合があるため、事前に派遣会社と話し合うことをおすすめします。
軽作業業務から事務への切り替えを希望されたが、用意できない。どうしたらよいのか?
妊娠中の女性労働者が請求をした場合には、会社は他の軽易な業務に転換させなければなりません。
しかし、転換させるために新たに仕事を作る必要はありません。希望する業務が用意できない場合は、その理由を明確に説明し、代わりに他の軽易な業務を紹介します。軽易な業務であれば、1つの職場でなくても軽易な仕事であれば2つの職場にまたがっても構いません。
要点は、妊娠中の従業員に対して業務上の配慮を行うことであり、本人の希望通りの仕事が提供できなくても、同等の軽易な業務を紹介すれば、会社としての義務を果たしたことになります。受ける受けないは、本人の判断となります。
つわりによる休憩を求められた場合、対応は必要ですか?
必要です。つわりの程度は人によって異なります。また、業務内容も個々によって異なるため、法律では休憩回数を定めていません。
しかし、本人が業務中に休憩を求めた場合は、適切な対応を行うことが大切です。その場合、自由に取得させるのではなく、母性健康管理に携わっている関係者(人事、上司、産業保健スタッフ等)とも相談をしましょう。
休憩時間の調整例としては、「昼休憩を1時間から30分に短縮し、午前・午後に都度休憩を挟む」「休憩時間を1時間から1時間30分に延長し、その分就業時間を調整する」などのケースがあります。
なお、派遣社員は時給制が多いため、休憩時間を多く取得した場合、延長分の派遣料金の請求はありません。
定期検診や母親学級に伴う通院時間、中抜けを求められた場合、勤務時間の取り扱いはどう考えればよいですか?
定期検診の通院時間や中抜け時間については、法律上認められた権利であり、配慮が必要です。男女雇用機会均等法では、会社は派遣社員が検診を受診するための通院時間を確保することを義務づけています。
ただし、その時間は無給にするか有給にするかは派遣先の裁量であり、一般的には「ノーワーク・ノーペイ」の原則により無給扱いとされることが多いです。
また、会社が一方的にその時間に対して有給休暇を充てるように派遣社員に対して指示することは認められません。ただし、派遣社員が自ら希望して有休を取得することは問題ありません。
なお、母親学級については、法律で時間確保の対象としていません。ただし、このようなイベントに参加することで妊娠、出産に対する不安をやわらげることができるため、会社としては参加できるように配慮することが望ましいです。
派遣先が知っておきたい派遣法とは
派遣先担当者が知っておきたい派遣法の12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。
<この資料でわかること>
・ 派遣先が押さえておきたい項目
・ 派遣法の概要と注意事項
・ 派遣先がすべきこと

まとめ
男女雇用機会均等法による、妊娠・出産等に関する不利益な取扱い禁止は、働く女性にとっての権利を守る重要な法律です。自社の労働者だけでなく、派遣社員を受け入れている場合は、派遣社員も対象となります。
会社はこの法律を遵守し、労働者が安心して働ける職場を形成する義務があり、法律を守らなければ責任を問われる可能性が出てきます。
従って、まだまだ男女雇用機会均等法の内容を自社の規定に一部しか盛り込んでいない、労働者に周知をしていない会社は、早期に適切な対応を実施する必要があります。女性が、妊娠・出産という人生のライフイベントを働きながら乗り越え、自分自身のキャリアを築くことを応援する会社は、女性だけでなく企業自身にとっても成長につながっていくことでしょう。
こちらの資料もおすすめです



















 目次
目次