


派遣社員に言ってはいけないこととは?法律とマナーの両面から解説

目次
人材不足が深刻化する中、派遣社員は多くの企業で欠かせない存在です。人材派遣は「派遣会社」「派遣先企業」「派遣社員」の三者関係で成り立ちます。
雇用主は派遣会社で、契約や給与管理などを担います。派遣先は現場での指揮命令を行いますが、雇用判断はできません。正社員の直接雇用とは関わり方が異なるため、現場の何気ない一言が契約や業務範囲の逸脱につながり、大きなトラブルになる可能性があります。
本記事では、派遣社員に言ってはいけないことを詳しく整理・解説していきます。
派遣社員に言ってはいけないことの具体例
派遣社員に対して不用意に発した言葉は、法的に不適切となる場合や、信頼関係を損なう原因となる場合があります。ここからは、現場で起こりやすい具体例を挙げながら、そのリスクと避けるべき理由を解説します。
給与・待遇に関すること
給与や賞与の決定権限は、労働者派遣法に基づき派遣会社が担います。派遣先は雇用主ではないため、たとえ世間話でも給与・待遇について尋ねることは、派遣法の趣旨に反する行為です。
具体的なNG発言
「いくら時給もらっているの?」
→ 賃金決定は派遣会社の専権事項であり、派遣先が尋ねるということは契約範囲を逸脱していることになります。
「正社員より給料高いんじゃない?」
→ 自社の正社員との比較は差別的な扱いにあたります。
なお、派遣会社からの請求金額には派遣社員の賃金だけではなく、有給や社会保険料などの諸経費や派遣会社の運営経費なども含まれています。
「ボーナス出たの?」
→ 多くの派遣社員は派遣先の賞与制度の対象外です。派遣社員のいる前で、正社員同士でも賞与などの待遇に関する話題は控えることが望ましいです。
契約に関すること
派遣社員の雇用契約は派遣会社と本人との間で結ばれます。一方で、派遣社員を受け入れるための派遣契約は派遣先と派遣会社の間で取り交わされ、その契約内容に基づいて人材派遣が行われます。
日常の業務に関する指揮命令は派遣先が行いますが、雇用条件や契約更新の決定権限は派遣会社にあります。
具体的なNG発言
「契約更新はするつもり?」(派遣社員に直接確認する)
→ 契約更新の可否は派遣会社が説明すべき事項です。派遣先が直接伝えてしまうと食い違いが生じ、法的トラブルにつながるおそれがあります。
また、契約終了の可能性がある場合も、必ず派遣会社を通して伝える必要があります。
「この仕事もやってもらうことになるかも」(業務範囲を逸脱させる発言)
→ 契約内容に含まれない業務を示唆することは派遣法違反にあたり、派遣社員を不安にさせるだけでなく行政指導の対象となり得ます。まずは、派遣会社に相談しましょう。
「そのうち正社員にしてあげるからね」
→ 正社員登用の判断権限は派遣先にはありません。軽い気持ちで言うことによって期待を持たせ、後に大きな不満やトラブルにつながります。正社員への切り替えを希望する場合も、まずは派遣会社に相談しましょう。
「派遣だから」と区別する発言
派遣社員も契約範囲内で責任を持って働いています。それを理解せず扱いに差をつけないようにしましょう。
不適切な言葉は派遣社員だけではなく職場全体のチームワークにマイナスの影響を与え、派遣社員本人の意欲や信頼も大きく損ないます。
具体的なNG発言
「派遣さん」と呼ぶ
→ 名前ではなく派遣さんと一括りにして呼ぶことは、本人を一人の人として、またチームの一員として尊重していない印象を与えます。
「電話は派遣さんが取ってね」
→業務は契約内容に基づいて指示すべきであり、雑用全般を押し付けるなどは大きな問題となります。
「派遣だから責任がなくていいよね」
→雇用形態で相手を軽視する発言はハラスメント行為にあたり、派遣社員のモチベーションや定着率の低下につながります。
プライバシーに踏み込む発言
プライベートに関わる質問は、控えましょう。派遣社員の場合、直接雇用ではないため個人情報を管理するのは派遣会社であり、派遣先が本人に個人情報について直接尋ねてはいけません。コンプライアンス上も大きな問題となります。
具体的なNG発言
年齢や家族構成、「住所はどこ?」などと尋ねる
→ 個人情報の管理は雇用主である派遣会社の役割です。派遣先が直接聞くのはプライバシー侵害として受け取られる可能性もあります。緊急時の連絡先が必要な場合でも派遣会社を通すようにしましょう。
「ずっと派遣でやっていくの?」などキャリアプランに踏み込む
→ 将来の働き方は本人が決めるもの。また、キャリアについてのカウンセリングも派遣会社が行います。
「学歴は?前職は?」といった過去の経歴を深掘りする
→ 採用面接のような質問を派遣先で行うことは適切ではありません。派遣会社から提供される情報が業務に必要な情報であると理解しましょう。
ハラスメントに該当する発言
人格を否定する言葉は典型的なハラスメントです。派遣社員に限らず許されませんが、特に直接雇用ではない派遣社員は言い返しづらく、不利な状況に置かれやすいものです。
周囲の社員が無自覚に行ってしまうケースもあるため、組織全体で気づいたら注意をするなど防止策を徹底することが重要です。
具体的なNG発言
「なんで派遣やってるの?」と働き方を否定するような言い方
→ 派遣社員という選択自体を軽んじる発言は、本人のキャリア観を否定し差別的な扱いと受け取られます。
飲み会やイベントへの強制参加
→ 断りにくい立場にある派遣社員へ参加を強要することは、パワハラの一種となり得ます。派遣社員の中には、家庭や学業、他の事情から時間に制約をもって働いている人も多く、強制参加は大きな負担になります。
また、本人の意思に反して参加を義務づけた場合は、実質的に「業務の一環」とみなされ、賃金が発生する可能性もあります。
飲み会やイベントはあくまで「任意参加」であることを明確にし、各々が参加の可否を自由に選択できる配慮が必要です。
「即戦力だから高い派遣料金なんでしょう?出来ないの?」と能力を否定する
→ 感情的な叱責や人格否定は職場環境を悪化させ、心理的安全性を壊します。派遣社員に対しては特に「見下されている」と感じやすく、深刻なメンタル不調を招く恐れがあります。
派遣社員への業務指示でもNGな発言
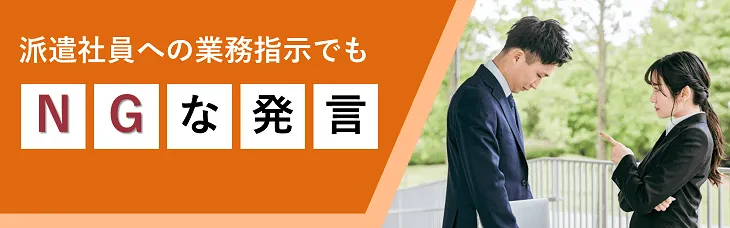
派遣社員への業務指示は契約内容に基づいて行う必要があります。契約外の依頼や強制的な残業は派遣法違反やトラブルにつながるため注意が必要です。
契約外の業務を指示した
派遣社員が行う業務は派遣契約書に明記された業務範囲内に限られます。そして、その内容は派遣会社から派遣社員本人にも就業条件通知書として交付、明示されています。
契約外の業務を依頼すると派遣法違反にあたり、たとえ本人が快く引き受けたとしても後々トラブルにつながります。
<NG例>(契約外の業務指示)
- 事務業務の契約なのに、テレアポや営業同行を頼んだ
- 電話対応はないと依頼していたが、繁忙期に一時的な対応をお願いした
- 他部署で欠員が出たため、ヘルプで業務を依頼した
派遣会社へ依頼するタイミングで、ルーチン業務でなくても、発生する可能性がある業務については発生頻度もあわせて伝えておくとよいでしょう。
「一般事務」といっても、会社ごとに業務範囲は異なります。派遣社員にお願いしたい業務をあらかじめ精査し、契約外の業務指示にならないようにすることが大切です。
契約内容にない残業や休日出勤、出張を指示した
派遣社員の働き方に関する条件(残業・休日出勤・出張の有無や上限)も、すべて派遣契約書に明記されています。
現場担当者がその範囲を超えて直接依頼することは、派遣法違反にあたり、たとえその場で本人が応じたとしても契約外労働として問題となります。必ず派遣会社を通して調整するようにしましょう。
<NG例>(契約外の働き方を指示)
- 「残業してでも、今日中にこの資料を仕上げてください」
- 「イベント対応で休日出勤できますか?」
- 「明日から地方出張に同行してください」
残業や休日出勤の有無、出張の可能性なども就業前に派遣会社に明確に伝えておく必要があります。「残業は繁忙期に月10時間程度」「月1回の休日出勤あり」といったように、発生時期や頻度を具体的に伝え、契約書や就業条件明示書に明記しておくことで、契約外労働の発生を防ぎやすくなります。
パフォーマンスや勤務態度の悪さを叱責した
派遣社員の勤務態度やパフォーマンスに改善が必要な場合、叱責するのはNGです。改善が必要な場合は、業務上の具体的な指示として伝えるか、必要に応じて派遣会社に相談して解決するようにしましょう。
<NG例>(叱責・契約逸脱となる発言)
- 「やる気あるの?」
- 「これくらいもっと早くできないの?」
- 「遅刻ばかりだけど、社会人として失格だね」
例えば、遅刻が多い場合には、「最近、始業時刻に遅れることが続いているようですが、何か事情がありますか? 」といったように、事象に焦点を当てて話すことが大切です。
業務パフォーマンスにおいても、「そんなこともできないのか」と否定するのではなく、何に躓いているのか、どうすれば改善できるのかを一緒に考え、サポートする姿勢が適切です。それでも改善が見られない場合には、派遣会社に相談し、対応を依頼しましょう。
トラブルを防ぐ派遣社員とのコミュニケーション術
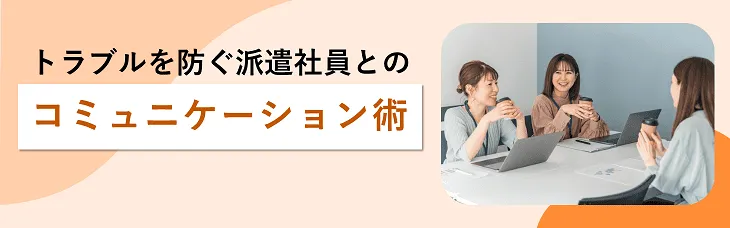
派遣社員との信頼関係を築くには、契約の枠組みを理解したうえで適切な伝え方を心がけることが大切です。また、チームの一員としてコミュニケーションを取りやすい雰囲気を整えることがトラブル防止につながります。
勤務態度・業務への改善要望は可能、伝え方に注意
派遣先が派遣社員に叱責することは避けるべきですが、改善点を伝えること自体は問題ありません。大切なのは「叱責」ではなく「業務指示」として具体的に伝えることです。
<心掛けるポイント>
- 業務内容に焦点を当てて伝える
→ 「この書類はこういったやり方でお願いします」のように、やり方や手順を具体的な言葉で明確に伝えましょう。
- 比較や人格否定は避ける
→ 「社員より遅い」「能力が低い」などの言葉はNG。本人を否定する発言はハラスメントにつながる可能性があります。
- 意図を伝える
→ 「ミスが起きないためのしくみを考えましょう」といったように、目的とサポートを共有することで改善につながります。
- 行動ベースで伝える
→ 「始業時間には業務が開始できる時間に出勤してください」「電話対応は言葉が明瞭に伝わるように話してください」など「やる気がない」「姿勢を改めろ」といった抽象的・感情的な叱責は避け、どのようにすればよいかを伝えます。
相談・報告がしやすい雰囲気をつくる
派遣社員にとって働きやすい職場とは、相談や報告がしやすい環境です。たとえば「困ったことがあれば声をかけてください」と伝えたり、定期的に面談を設け、状況を確認したりするだけでも安心感が生まれ、信頼関係が築かれていきます。
また、派遣社員は孤立化しやすいのでチームメンバーで業務に関する情報を共有する場を積極的に設けることも大切です。さらに、「人によって指示が違う」といった事態にならないように、指示命令系統を明確にしておくと、誰に報告や相談をすればよいかがはっきりし、迷いや不安が減ります。
もちろん前述のプライバシーへの配慮も忘れてはなりませんが、節度ある会話で、業務に関するやり取りや安心感を与える声かけは、積極的に行うことが職場全体の雰囲気を良くしていきます。
受け入れ部門の社員にルールを周知する
派遣社員との接し方は、派遣先責任者や指揮命令者だけが理解していれば十分というものではありません。現場で一緒に働く社員全体がルールを理解し、無自覚にNG発言や契約外の依頼をしないようにすることが不可欠です。
そのためには、派遣先として事前の仕組みづくりが求められます。
- あらかじめ部署内に派遣社員と接する際の基本ルールを説明する
- マニュアルやチェックリストを配布する
こうした取り組みによって、現場全体が同じ認識を持ち、派遣社員が安心して働ける環境が整います。
派遣社員に言ってはいけないこと・させてはいけないこと
派遣社員を受け入れている現場部門では、運用ルールの誤解や情報不足により、契約外の業務指示や契約更新に関する直接の声かけなど、 トラブルにつながる対応が発生してしまうことがあります。
本資料では、こうしたトラブルを未然に防ぐために押さえておきたいポイントをわかりやすく整理しました。
あわせて、忙しい現場担当者の方へ配布しやすいよう、必要なポイントを簡潔にまとめたリーフレットもご用意しています。ぜひご覧ください。
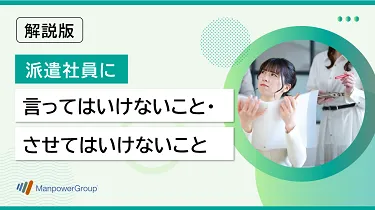
まとめ
派遣社員を受け入れることは、業務の効率化や生産性向上に大きく貢献します。厚生労働省の調査(令和4年派遣労働者実態調査 ![]() )によれば、2022年10月1日時点で派遣労働者が就業している事業所は全体の12.3%にのぼり、特に製造業(23.6%)、情報通信業(23.1%)、金融保険業(21.0%)など幅広い産業で活用されています。
)によれば、2022年10月1日時点で派遣労働者が就業している事業所は全体の12.3%にのぼり、特に製造業(23.6%)、情報通信業(23.1%)、金融保険業(21.0%)など幅広い産業で活用されています。
また、1,000人以上規模の企業では8割以上の事業所で派遣社員が働いており、すでに多くの職場で欠かせない戦力となっています。
しかし、その一方で現場での何気ない一言が大きなトラブルに発展するリスクもあります。「派遣社員も共に働く仲間」という意識を持ち、尊重ある対応を徹底することです。基本的なルールを守りながら信頼関係を築けば、派遣社員にとっても受け入れ先にとっても、安心して力を発揮できる働きやすい職場環境が実現できます。
こちらの資料もおすすめです
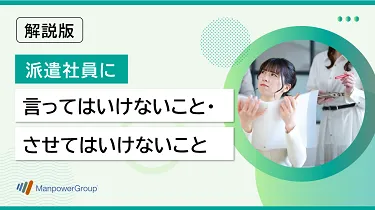





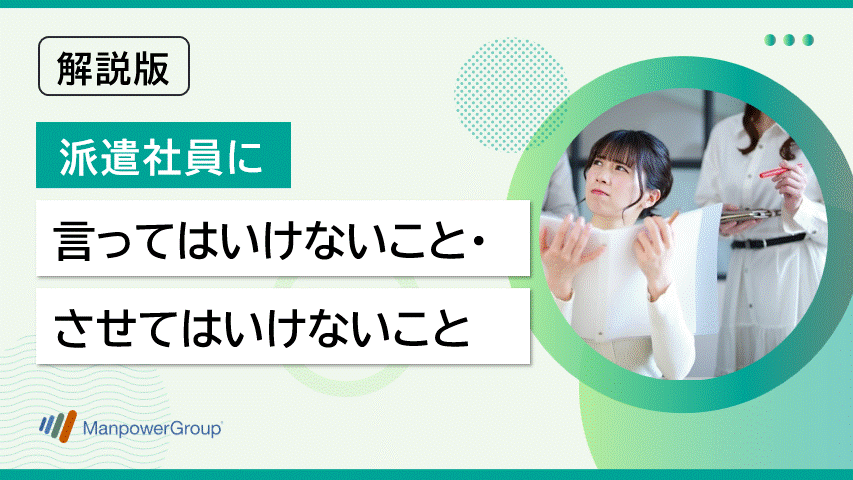













 目次
目次