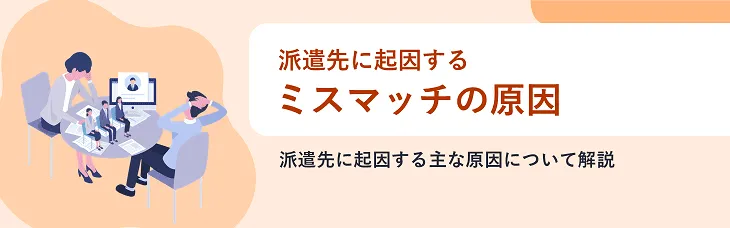


派遣のミスマッチを防ぐには?原因と企業ができる対策
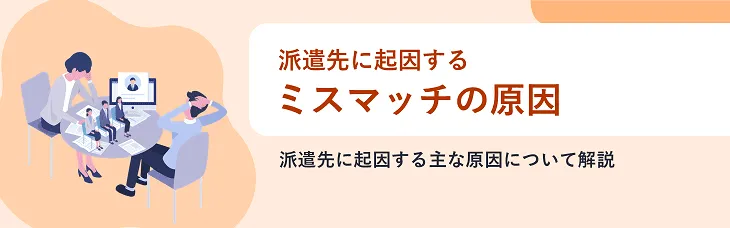
目次
派遣社員の定着率改善実践ガイド
派遣社員の離職理由や定着率改善の考え方を、実務目線で整理した資料をご用意しています。記事内容の理解を深める補足資料として、ぜひご覧ください。
人材派遣では、派遣先が直接選考に関与することは法律上認められていません。このような仕組み上、受け入れ後にミスマッチが生じる可能性があります。
一言に「ミスマッチ」といっても、派遣社員のミスマッチは単なる相性の問題にとどまらず、求められるスキルや業務内容の適合度、組織文化とのマッチングなどさまざまな要因が絡み合って発生します。
本記事では、ミスマッチの原因やリスクを解説し、派遣先がこれらの課題を未然に防ぐための具体的な対策についてご紹介します。
派遣のミスマッチとは?
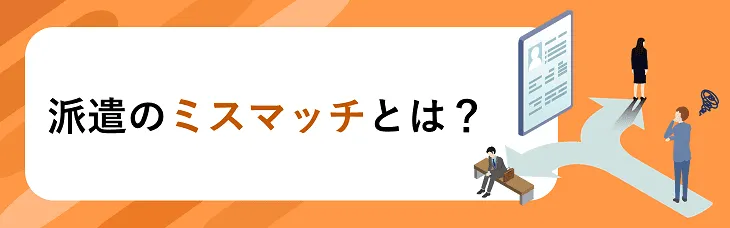
人材派遣は派遣会社が間に入る仕組みであるため、採用業務の負担軽減など企業にとって安心感のある手法の一つです。しかし、情報連携が不十分な場合には、ミスマッチが生じることがあります。
業務内容に関するミスマッチ
派遣社員が想定していた業務内容と、実際に依頼される業務内容が異なるケースです。
- 「電話対応は無い」と聞いていたが、実際には電話対応を依頼された
- 「受発注や書類作成などの内勤業務」と聞いていたが、営業同行など外出業務が含まれていた
- 「中級レベルのExcelスキルが必要なレポート作成」と説明をされていたが、入力・修正程度の初級レベルの業務だった
こうした齟齬は、派遣会社と派遣先の業務内容の共有が不十分な場合に起こりやすく、派遣社員の不安や不満につながります。
就業条件に関するミスマッチ
事前に説明された条件と実際の就業状況が異なると、派遣社員にとって「聞いていた話と違う」と大きなトラブルにつながります。
- 「残業なし」を希望していたが、実際には月20時間以上の残業が発生
- 「在宅勤務希望」だったが、完全出社が必須だった
- 「オフィス勤務希望」だったが、ほぼ在宅勤務で出社は月1回のみ
働き方に関する条件の不一致は、生活との両立や職場定着に大きく影響します。
スキルや経験に関するミスマッチ
まず挙げられるのは、派遣社員のスキルが業務に対して不足しているケースです。派遣先は派遣社員の採用面接を行うことができないため、求めていたPCスキルや語学力、接客経験などが、実際に就業してみると期待水準に達していないという事例は少なくありません。
また、求める水準を大きく上回るスキルを有している場合も、ミスマッチといえます。この場合、依頼する業務が派遣社員にとって容易な作業ばかりとなり、業務の質や職場の人間関係にも影響を及ぼす可能性があります。
職場環境や人間関係に関するミスマッチ
業務内容や条件が適切であっても、職場の雰囲気や文化が合わない場合、派遣社員がストレスを感じることがあります。
例えば、業務を進める際に細かく確認しながら進めたい派遣社員が、担当者の外出が多く一人になりやすい環境や、社員同士で声をかけづらい雰囲気のある企業に配属された場合などです。こうした環境要因もパフォーマンスや定着に大きく影響します。
派遣先に起因するミスマッチの原因
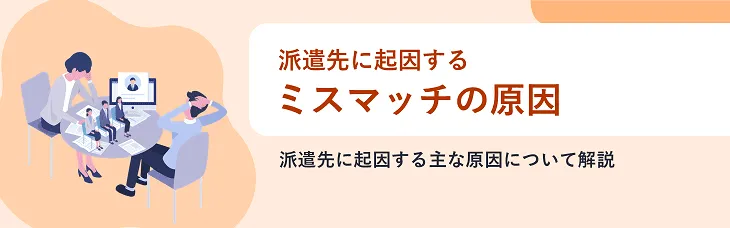
派遣のミスマッチの原因は必ずしも派遣先にあるわけではありませんが、ミスマッチを少しでも防止するために、派遣先に起因する主な原因について解説します。
業務内容や必要スキルの求人要件が曖昧
求人票には「事務業務」とだけ記載しているが、実際には経理処理やデータ分析、顧客対応など幅広い業務を任せることが想定されているーーなど、求めるスキルや作業範囲を明確に定義しないまま、派遣会社へ発注してしまうと、派遣会社は適切な人材の選定が難しくなり、結果として業務に合わない人材が配属されるリスクが高まります。
「パソコン操作ができる方」という要件も、単にWordやExcelの基本操作ができれば良いのか、それとも関数やピボットテーブル、VLOOKUPなどある程度の実務経験を前提としたスキルが必要なのかを明確にしなければ、スキルのギャップが発生します。
「中級程度」「高度なスキル」などは、受け手によって捉え方が異なる可能性があるため、注意が必要です。現場での教育コストや業務習熟までの時間が想定以上にかかり、結果的に双方に不満が生じる可能性があります。
また、派遣契約開始後に「実は繁忙期には電話対応もお願いしたい」「新しいシステム導入に伴いマニュアル作成も担当してほしい」といった追加業務が発生するケースもあります。業務追加が必要な場合は、派遣会社を通じて正式な契約変更手続きを行う必要があります。
人事と現場担当者の認識が乖離している
採用担当と現場担当者の間で、業務内容や求めるスキルに関する認識が一致していないケースも、ミスマッチの原因となります。
例えば、現場担当者からは「帳票整理」と聞いていたが、実際には簿記レベルの知識を求められる業務であったりするケースもあります。現場で実際に求められているスキルを担当者から丁寧に聞き取っておかないと、派遣社員が就業開始後に期待される水準に届かない、といったミスマッチを招くことにつながります。
求める要件の優先順位付けが違った
求める条件をすべて「必須」として記載してしまうと、どれが必須でどれが望ましいスキルなのかが曖昧になり、派遣会社も人選の基準を絞り切れません。その結果、必要以上に条件を満たす人材や、逆に肝心なスキルが欠けている人材が派遣されてしまう可能性があります。
例えば、「事務経験3年以上」「法人相手の営業経験あり」「Excelでピボットテーブルを活用できるスキル」「英会話がビジネスレベルでできる」などの要件をすべて必須と記載してしまうと、該当する候補者が極端に限られてしまいます。条件合致のみを優先した結果、条件に合っても本来の業務には不要なスキルばかりを持つ人が選ばれる、重要なスキルのレベルが不十分な人材が配属されるケースもあります。
ミスマッチにより生じるリスク
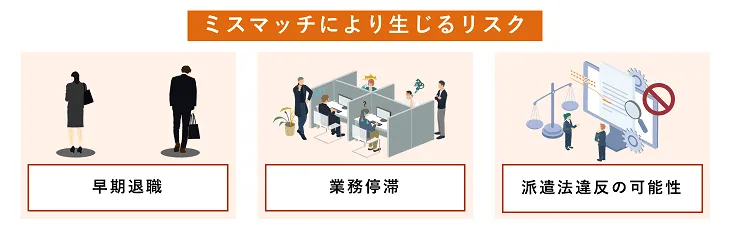
人材派遣の活用は、業務の効率化や柔軟な人材確保に対する有効な手段ですが、ミスマッチが起きるとその効果が損なわれ、業務の停滞や法的リスクを招くこともあります。派遣社員のミスマッチによって生じるリスクについて解説します。
早期退職
派遣社員のミスマッチは、早期退職につながる大きな要因となります。派遣社員も正社員の際のミスマッチと同様に、業務内容や職場環境、必要スキルなどが事前の説明と大きく異なる場合、モチベーションの低下やストレスの増大から早期離職が発生します。
早期離職は、せっかく時間と労力をかけて行った採用・教育のコストが無駄になるだけでなく、再募集や再教育の手間も発生し、現場の生産性を下げる原因となります。
業務停滞
派遣社員とのミスマッチが起きると、スキルが不足していて教育に時間を取られたり、業務知識が乏しく確認作業に時間を要して処理が滞ったりすることがあります。特に専門知識やシステム操作を伴う業務では、こうした負担が大きくなりやすいのが実情です。
さらに、早期離職では本人の業務習熟度が低いうえ、急な退職となるケースが多く、引継ぎも不十分なまま業務が宙に浮いてしまうことがあります。その結果、他の社員が緊急対応として業務を肩代わりすることになり、優先度の高い本来業務が後回しになるなど、組織全体のパフォーマンスの低下を招きます。
派遣法違反の可能性
ミスマッチの内容が派遣法に抵触する可能性もあります。派遣法では、契約時に明示した業務内容や条件から逸脱して派遣社員に業務を行わせることを禁止しています。
例えば、契約上は「データ入力業務」として派遣したにもかかわらず、実際には肉体労働や販売業務など全く異なる業務をさせることは、業務逸脱にあたります。派遣社員が自主的に対応した場合であっても、派遣先の指揮命令下で行われた業務とみなされ、違反と判断される可能性があります。
また、労働条件の明示義務に反し、契約内容を派遣会社・派遣社員双方に正しく提示していなかった場合も違法となる恐れがあります。このような法令違反は、行政指導や改善命令、場合によっては派遣契約の停止や損害賠償請求といった重大なリスクにつながるため、派遣先としても細心の注意が必要です。
関連記事:派遣社員にさせてはいけない6つの業務としてはいけない指示
派遣のミスマッチを防ぐために企業ができる対策
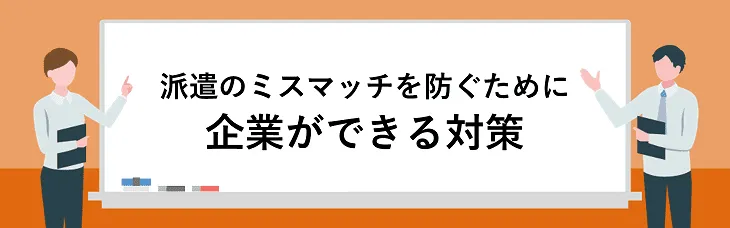
では、ミスマッチを防ぐために受け入れ企業が実践できる具体的な対策について解説します。
業務内容や勤務条件を実態に合わせる
業務内容や勤務条件は、“実態に即して”求人票や派遣会社との労働者派遣契約書に反映することが重要です。特に、日常的に発生する残業の有無や頻度、突発的な業務の可能性などは、事前に明記することで勤務開始後のギャップを防げます。
例えば、「残業はほとんどなし」と記載していたのに、繁忙期は毎日1〜2時間残業が発生する場合、派遣社員の不満や離職につながりやすくなります。事前に「繁忙期(3月・9月)は1日1〜2時間の残業が発生」と伝えておけば、本人も心構えができ、定着率向上につながります。
また、たまにしか対応しない作業であっても発生頻度を含めて、事前に現場の実態を確認し、実態にあわせることが重要です。
人材要件を具体的にし、優先順位をはっきりさせる
人材要件を可能な限り具体化し、さらに「必須条件」と「望ましい条件」を明確に分けます。例えば、「PCスキル」では漠然としすぎており、人選の精度が下がります。
具体的には、「Wordで社内規程レベルの文書をゼロから作成できる」「ExcelでVLOOKUPやピボットテーブルを用いた集計ができる」「PowerPointで図解や色使いを工夫したスライドを作成した実務経験がある」など、行動ベースで表現すると、派遣会社が適切な人材を選びやすくなります。
さらに、すべてを必須条件にせず、「Must(必須)」「Want(尚可)」と優先度を明示することで、条件過多による候補者不足や不適合を防げます。
職場の雰囲気やカルチャーも伝える
派遣会社とのコミュニケーションを密にし、書面だけでは伝わりにくい職場の空気感」や「カルチャー」をしっかり共有することも重要です。
例えば、「上司は細かい指示を出すタイプ」「チームは20〜30代中心で会話が多い」「月末は数字の締め作業で非常に慌ただしい」などの情報は、派遣社員の適応度や満足度に大きく影響します。
事前に共有すれば、「スピード感のある環境が得意な人」「静かに集中して作業したい人」など、性格や働き方にマッチする人材を選びやすくなります。
ミスマッチを防止し、定着率を上げるために
派遣社員の早期離職は、個人の問題だけでなく、派遣先・派遣会社・派遣社員それぞれの認識のズレが重なって起こるケースも少なくありません。
本資料では、離職理由の整理から、定着率を改善するための具体的な施策、受け入れ前・就業初期・日常運用で確認したいポイントまでをまとめています。
記事内容を踏まえつつ、自社の受け入れ体制や現場対応を整理するための確認資料として、必要に応じてご活用ください。

派遣のミスマッチに関するよくあるご質問
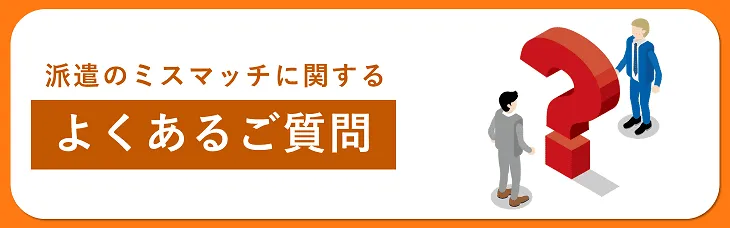
人材派遣を利用する企業の現場担当者や人事担当者から、実際によく寄せられる質問をもとに、対応のポイントを解説します。
派遣契約が決定した後に、条件の変更が発生した場合はどうなりますか?
原則として、派遣契約は契約書に記載された条件に基づいて運用する必要があります。派遣先と派遣会社間の「派遣契約書」と、派遣会社と派遣社員間の「労働条件通知書」に記載された内容を逸脱して業務を行わせることは、派遣法に抵触するおそれがあるため、突発的な業務を依頼する場合でも、注意が必要です。
やむを得ない事情で条件を変更する場合は、必ず派遣会社と協議のうえ、変更内容を文書で取り交わし、派遣社員本人にも書面で通知する必要があります。特に、就業場所や業務内容の変更は「業務逸脱」に該当する可能性があるため、口頭のみで対応することは避けるべきです。
就業後にミスマッチが発覚、契約途中で終了することは可能ですか?
一方的な派遣契約の途中終了は、原則として認められていません。派遣法では、契約期間中の派遣受け入れを途中で打ち切る場合、派遣会社と協議し、合理的な理由が必要とされています。合理的な理由の一例として、無断欠勤やハラスメント行為などの素行面での重大な問題に加え、業務遂行に著しく支障をきたす能力面での深刻な不適合が挙げられます。
合理的な理由がなく一方的に契約を終了した場合、損害賠償の対象となる可能性もあるため注意が必要です。
ミスマッチが発覚した場合は、まずは、派遣会社を通じて事実を共有し、改善策(業務内容の調整、教育支援など)を検討しましょう。それでも解消が難しい場合は、派遣会社と派遣社員の双方が合意したうえで契約を終了するか、代替人材を配置するのが望ましい対応です。
早期退職が続くポジションを改善したい。何から始めればよいですか
早期離職が繰り返される場合は、まず離職理由の分析が重要です。派遣会社を通して派遣社員の退職理由を正確に把握したり、派遣会社に事情を説明して率直な理由を集めたりすると、実態に即した原因分析が可能です。
早期離職の原因が、契約書等の内容と乖離していた場合は、派遣会社と連携して、求人票や契約内容の記載を見直し、実態に即した条件提示を行うことが必要です。
契約内容等と実態に乖離がなかった場合は、現場の雰囲気やコミュニケーションの取り方など、定着支援の観点からの改善が効果的です。受け入れ社員とのとの関係構築をサポートする仕組みなど、業務の進め方や相談のしやすさを工夫すると定着率向上につなげられます。
現場と十分に連携が取れていない場合、どうすればよいですか?
派遣会社とのやりとりに現場担当者にも参加してもらい、業務内容や必要なスキルについて直接説明してもらうのが有効です。また、人材要件が曖昧なことによって起こるトラブルやリスクについても十分に説明しておきましょう(結果的に困るのは現場であることを伝えることで、協力してもらいやすくなります)。
一方で、現場の負担を軽減するために人事が窓口となる場合は、要件テンプレートを用意して記入してもらうなど、ヒアリング方法の工夫でミスマッチのリスクを抑えることができます。
人材派遣のご相談はこちらから
マンパワーグループは、日本で最初の人材派遣会社です。全国68万人以上の登録者から、貴社に最適な人材をご提案いたします。
人材派遣の利用をご検討の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

まとめ
本記事では、人材派遣で起こるミスマッチの主な原因と、企業側でできる具体的な対策、そして見過ごされがちなリスクについて整理しました。ミスマッチは、単なる相性の問題ではなく、企業の業務効率や職場環境、法令遵守にまで影響を及ぼす重要な課題です。
教育コストや再募集の負担、業務停滞などによる損失の大きさを鑑みても、業務内容や条件の明確化、現場との連携や職場の雰囲気の共有など、細やかな対応は欠かせません。まずはできるところから見直しを行い、定着率の向上につなげましょう。
こちらの資料もおすすめです






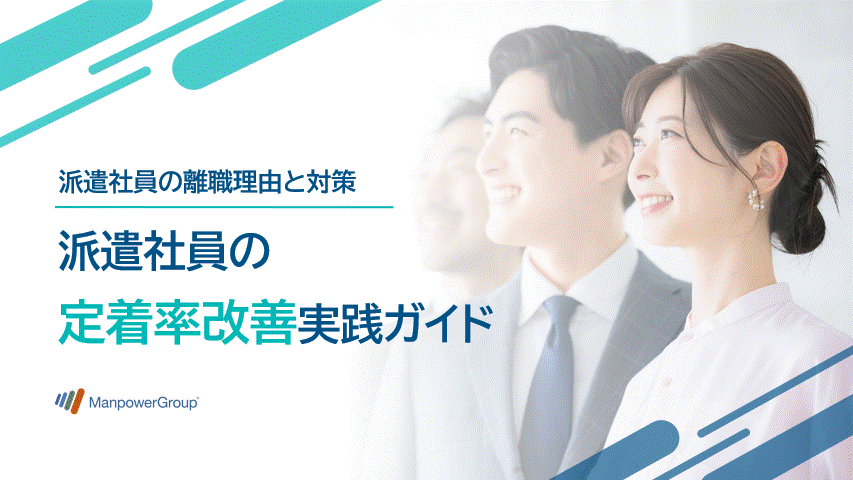

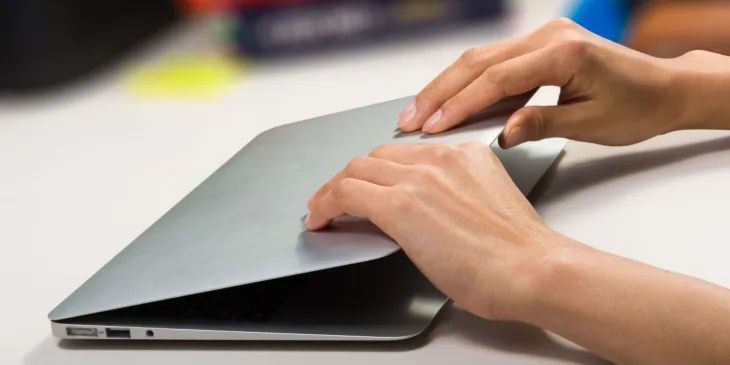













 目次
目次