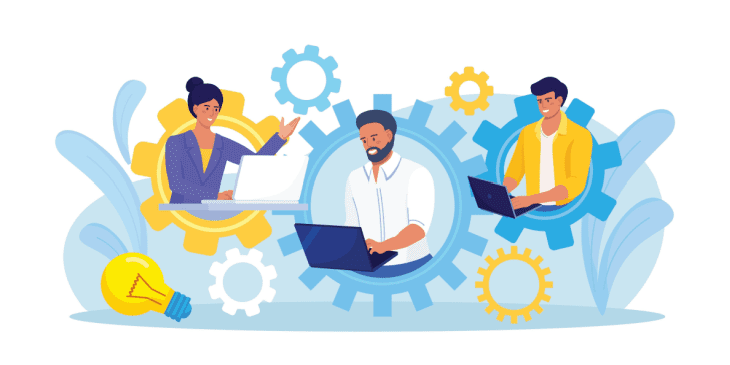


組織開発とは?人材開発との違いや具体的な手法、役立つツールを紹介
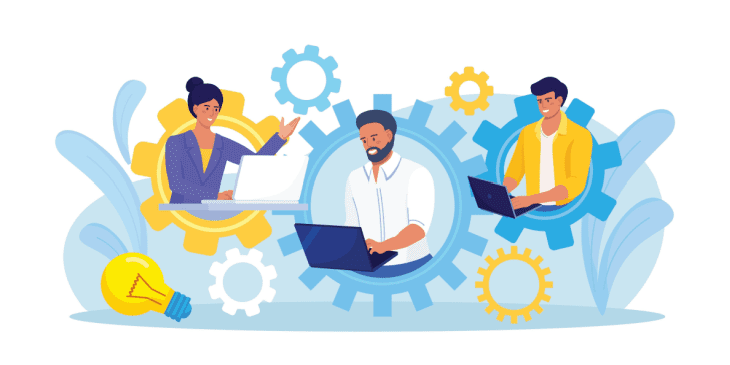
目次
変化が激しく、価値観が多様化している時代の中、組織やチームをまとめて強くするためのアプローチ方法として組織開発を導入する企業が相次いでいます。
今回の記事では、この組織開発について解説します。
組織開発とは?
組織開発とは、英語のOrganization Developmentを日本語訳したもので、通称ODと呼ばれています。まさに文字どおり、組織力を健全に発達させていく変革活動です。
組織開発は、1950年代にアメリカで生まれたもので、源流となるアプローチは2種類あります。
1つは、人間関係や心理的な成長といった人間性心理学や行動科学をもとに、チーム力、コミュニケーション力、リーダーシップといった人に対する心理的なアプローチ方法です。
もう1つは個人や組織の課題を客観的に浮かびあがらせ、一人ひとりが当事者意識を持って具体的に実行し、フィードバックを通してブラッシュアップさせて次の打ち手に繋げるといったサーベイフィードバックです。
この2つを元に組織開発は発展してきました。
組織の置かれている状況はさまざまなので、組織により適した組織開発の手法は異なり、数多くの組織開発の手法が存在します。
背景
組織開発が近年注目されるようになった背景は2つあります。
働き方に対する価値観の変化
1つは、働き方が大きく変わったことです。
終身雇用の時代は「定年まで1社に勤め上げることが前提」「上が決めたやり方やルールが正解」など一律的でしたが、「多様性」の時代に変化しています。
一律的なルールに抑え込むのではなく、多様な人材にとっての最適な解を出し、アップデートし続けるには、人と人との関係性やプロセスの改善とアップデートを同時にできる組織開発がフィットしているのです。
職場・事業環境の変化
テクノロジーの進化の加速や事業環境変化も影響しています。
クラウドでの管理や承認、判子レス化といった物理的な仕事の環境変化や、リモート環境で生じた人間関係の変化などは、記憶に新しいでしょう。
課題を分析して原因を突きとめ、打ち手を考え、PDCAを回すといった従来型の問題解決のアプローチだけでは、変化のスピードに追い付けなくなってきています。
原因は1つではなく複雑系で絡み合い、打ち手を出す前に次の変化が起きているのが現状です。
目指すゴールに向かい、プロセスや関係性を改善しながら、たくさんある打ち手の中から、スジがよさそうなものを選び、変化しながら最適化し続けるといった組織運営を行うことが求められますが、これを実現するには、組織開発のアプローチが最適です。
組織開発に取り組むメリット
企業が組織開発に取り込むメリットは以下のとおりです。
- 集団のシナジー効果が高くなる
- 一人ひとりが当事者意識を持ち、自ら課題解決に自走する
- 上記を通し、売上や生産性を向上させる
組織開発と人材開発
組織開発(Organization Development:OD)と似た言葉で「人材開発」(Human Resource Development:HD)があります。
組織開発と人材開発がどのように違うのかについて解説します。
人材開発とは
人材開発(HD)とは、社員に対し教育や訓練を行い、知識、スキル、意識・スタンスを高めて、社員一人ひとりのパフォーマンスを向上させることです。
社内外の研修、OJTなどが代表的な手段になります。
組織開発と人材開発の違い
組織開発と人材開発の一番の違いはアプローチ対象です。
人材開発の対象は「人」である一方で、組織開発は「人」そのものではなく組織やチーム内の「関係性や相互作用」です。
同じ生産性をあげる目的でも、人材開発は個人の知識・技術・スキルを研修やOJTなどを通してレベルアップさせるアプローチです。1を強く太い「1」にするようなものです。
一方の組織開発は、組織やチーム内のメンバーの関係をよくするために協力し、相互作用が生まれるようにするアプローチです。
1+1を5にも10にもするようなもので、個人の力だけでなく、チームビルディングなどを通し、組織やチームとして強くし、勝つようにするアプローチです。
人材開発と組織開発、どちらが正しいかということではありません。
うまく掛け合わせることで組織を活性化させ、成果や生産性をあげ、社員を成長させるといった好循環を生むことにつながるでしょう。
組織開発の進め方
目的を決める
まず組織開発を通して解決したい組織課題を明確にします。
なぜなら、組織開発は手段であり、目的ではないからです。
業績向上などの最終ゴールを見据え、組織の壁(サイロ)を壊す、チームの結束力を高めるなど、組織開発を通じて解決したい組織課題・目的とゴールを明確にしましょう。
最初に目的・ゴールを明確にすることで、選択する組織開発の手段の精度をあげ、目的達成の効果測定をモニタリングできるようにすることが大切です。
現状を把握する
目的を決めた後は組織の現状を事実ベースで把握します。
組織開発で扱うのは一人ひとりの「意識」「繋がり・関係性」「組織文化」といった目に見えないソフトの領域も多く占めます。
なので、現状を把握するとき、後述するマッキンゼーの7Sなど、組織の状況を把握できる組織モデルをもとに事実を整理すると具体的な現状が可視化されます。
数字やドキュメントに加え、アンケート・ヒアリングを通して具体的な事実を収集し組織モデルで整理することで、効果が高い組織開発を精度よく実施することが可能になります。
必要性を共有する
組織の置かれている状況を整理できたら、組織開発の対象者を集め、「なぜ、組織がこのような状況になっているのか」を議論して、取り組む必要性を共有しましょう。
課題解決に向けて当事者の意識や方向性がバラバラであれば、組織開発を通して組織力を高めることはできません。
事実を共有し、危機感や必要性を共有することで、解決の当事者意識を引き出し、目的・ゴールに向けて意識のベクトルを合わせましょう。
課題を設定する
現状と必要性を共有し、当事者意識を引き出した上で、取り組むべき課題を設定します。
組織開発は諸悪の根源となる個人を特定し、その個人に対してのアプローチを組むことはしません。
例えば、一人だけ万年目標未達成の営業がいた場合、チームビルディングなどでチームの関係性を強め、チームの風通しをよくする、あるいは個人の取りこぼしが無くなるよう周りからのサポートが自然発生するようにするなど、個人ではなくチーム全体の目標達成につながるような施策を実施します。
前述のように個人にアプローチするより、組織力を高めることでさまざまな相乗効果を狙うため、個人の改善ではなく組織全体をよくする視点から課題設定を行いましょう。
スモールスタートで始める
いきなり組織全体に組織開発を行うのはリスクがあります。
設定した課題に対し、どんな組織開発の手法やツールが有効そうか仮説をたて、実際にパイロットケースとして実施してみましょう。
ポイントは、いきなり大きな成果を狙うのではなく、小さな一歩から始め、確実に成果を出すことで、「組織開発は有効である」という認知を広めていくことです。
コツは、やりっぱなしにならないよう小さなステップごとに具体的なゴール(定量・定性)が見えるようにして組織開発のPDCAが回るようにすることです。
効果検証・フィードバックをする
パイロットケースの実施結果を踏まえ、効果を検証し、組織開発の打ち手にフィードバックを行い、ブラッシュアップを行います。
フィードバックの結果、効果がでたとされる打ち手をもとに、組織全体へ展開するプランを策定し、PDCAを回しながら展開していきましょう。
コツは、オープンかつクイックに行うことです。
効果検証は変に隠し事をすると逆によからぬ噂がたつので、改善点も含めてオープンにして、フィードバックを迅速に進めましょう。
その結果、共感者や応援者が増えていくので取組みの輪を広げやすくなります。
組織開発に活用できるツール
組織開発の手法やツールが数ある中、活用しやすい代表的なツールをいくつか紹介します。
ツール1:マッキンゼーの7S
マッキンゼーの7Sとは、「7つの経営資源と相互性」を示したフレームワークです。 組織開発の現状分析を行うときに活用される代表的な組織モデルになります。
7Sは、「ハード面の3S」「ソフト面の4S」にわかれます。
ハード面のS(組織の構造に関するもの)
1. 戦略(Strategy):競争優位性を維持するための事業の方向性と計画
2. 組織(Structure):組織の形態や構造の特徴
3. システム(System):人事評価や報酬、情報の流れ、会計制度、組織の仕組み
ソフト面のS(人に関するもの)
4. 共通の価値観(Shared Value):共通認識を持つ会社の価値観(MVVなど)
5. スキル(Skill):営業力、技術力、マーケティング力など自社の持つ組織能力
6. 人材(Staff):経営者や社員など個々の人材の資質や能力
7. スタイル(Style):組織の文化的特徴
ハードのSは比較的変更が容易で手間や時間はそれほど多くはかかりませんが、ソフトのSは変更に時間がかかるとされています。
また、ハード面は目に見えやすいですが、組織文化は職場の空気というように、ソフト面は目で見えにくいことも特徴です。
組織の現状分析を行う際、以下のステップで進めることで、組織の目標達成活動に向けて何が絡み合いあってボトルネックになっているかが可視化されます。
- ハードの3Sから、
目標達成に向けて組織構造やシステムなど、どのように取り組んでいるのかを整理する - ソフトの4Sから、
社員の能力やスキルのレベル、上司による統制や育成の状況、価値観の共有やコミュニケーションの円滑さなどを整理する - ハードの3Sを推進するにあたり、
ソフトの4Sがきちんと機能し後押ししてくれているか、それともボトルネックになっているかを整理する
組織開発では、7Sのような組織モデルで整理した結果をもとに、課題や打ち手の仮説をたてることに活用するだけではなく、組織開発の対象となるメンバーを集め、社員の前でデータフィードバックを行い、問題意識の認識合わせから始めるアプローチにも有効です。
ツール2:MVVの浸透
MVVとは
M:ミッション(使命・存在意義)
V:ビジョン(目指す中長期のゴール)
V:バリュー(価値判断基準・行動指針)
経営理念の3大要素であるMVVを明確にして、全社に浸透させることで、組織マネジメント面では下記のことを実現でき、組織力が高まります。
- 全社員が目指すゴールに向けて意識のベクトルが揃う
- 経営から現場までの意思決定の判断基準が揃う
- 社員のエンゲージメントの向上
上記の組織力を高めることにプラスして、企業価値の向上や人材確保、採用ブランディングの向上まで実現できるようになります。
ツール3:リチーミング
リチーミングとは、フィンランド発祥の組織開発の手法で、チームの関係性の再構築と問題解決を同時に行います。
世界から注目され先進国をはじめとした25カ国以上で普及しています。
特徴は、ロジカルに課題設定や問題解決を「頭」で考えることから入るのではなく、精神科医と社会心理学者のノウハウをもとに、「心」に働きかけ、本音を引き出し、心から「やりたい」「できそう」と気づかせる点です。
効果は一瞬ではなく、結果を出しながら、さらに、チームワークを高め、一人ひとりのやる気を引き出し、さらに結果を出すという好循環に繋がる12ステップで構成されています。
役員のチームビルディング、閉鎖的環境による弊害を取り除く、チームをまとめるなど、さまざまな局面で活用できる手法の1つです。
ツール4:ワールドカフェ
ワールドカフェは、カフェで談笑するようにリラックスした状態で行う会議のことです。
堅苦しなく、ざっくばらんに本音を言える雰囲気を醸成して進めます。4~5名単位のテーブルで話し合い、入れ替わりながらステップに沿って進めます。
標準的なステップは、次のとおりに進めます。
- 1ラウンド(テーマの深掘り)
- 第2ラウンド(アイデアの洗い出し)
- 第3ラウンド(気付きや発見を統合)
- 全体セッション(総括・発表・共有)
参加者は全体で1,000名規模まで実施可能となり、下記のようなメリットがあります。
- さまざまなアイデアや意見を出しやすい
- 相手の意見を尊重することで自分の意見も受け入れられる
- メンバーの組み合わせが変わり、4~5人の単位のテーブルで話し合いを何度か行うことで、全体で話し合っているような効果が得られる
- 参加者全員の達成感と納得感が得られやすい
全社方針を受けてアクションプランを考えるなど、全員参加型でさまざまなアイデアを出し合いながら、ポジティブな雰囲気と大まかな合意形成を得たいときによく活用されます。
ツール5:1on1ミーティング
1on1とは上司と部下が定期的に行う1対1で行うミーティングです。
目標設定や評価フィードバックなどとは異なり、部下の成長をサポートすることが目的です。
ミーティングの頻度は週1回(15~30分)など、頻繁にこまめに行うことが特徴です。 評価フィードバックなどは上司が主役で部下に説明・説得する形になりますが、1on1の主役は部下です。
上司は「対話」を中心に部下の本音を引き出し、フラットなスタンスで心の距離を縮め、信頼関係の醸成に繋げます。
部下の成長だけでなく上司と部下の絆も強くなり、エンゲージメントの向上にも繋がります。
コロナ禍でリモート勤務になり上司と部下が物理的に離れた状態が続いていても、1on1を行うことで心の距離を縮め、部下の成長を促すことに成功した組織はたくさんあります。
組織開発を実践した企業の事例
組織開発の考え方がわかったとしても、実際にどんなアウトプットに繋がったのかピンとこないこともあるでしょう。
組織開発を実践した企業の事例をいくつか紹介します。
事例1:A社(製造)リチーミング
日本を代表する規模の製造業A社の工場は品質管理や改善活動で実績を出して有名でしたが、近年は工場の現場が止まるなど、真面目に一生懸命働いているにもかかわらずミスが続出していました。
そこで、組織開発の手法のリチーミングを導入しました。
その結果、4時間のミーティングで現場に活力が満ち、強い一体感が生まれてミスは激減しました。
誰もが真面目に一生懸命な分、たこつぼ状態になり、お互いに声を掛け合う機会がなくなっていたことに各メンバーが気づきました。
それにより職場に心理的安全性が生まれ、自分の担当以外でもエラーがでそうなら声をかけたり、フォローしあったりなど、強い絆で協力しあうチームになったのです。
事例2:B社(情報・通信)MVVの浸透
IT企業のB社は、事業が成功した結果、1年で社員数が3倍以上に急成長しました。
社員が一気に増えたため採用基準が粗くなり、職務経験があっても自社に合わない人材も多く混じってしまいました。
その結果、新規採用者と既存社員の間に軋轢が発生し、優秀な人材から辞めていくなどエンゲージメントも急降下したままとなり、組織がガタガタになりました。
そこで、MVVを経営から現場まで「Yes/No」の判断基準になるように再定義し、判断に迷うケースをMVVで「Yes/No」の判断をしてみるワークショップを展開したのです。
結果、中途採用者と既存社員の相互理解が進み、目指す方向や判断基準にズレがなくなり一体感のある組織に生まれ変わりました。
また、MVVを採用基準に用いることで、「Yes/No」の判断基準が近い人材を精度よく採用できるようになり、採用ミスも激減しました。
事例3:C社(小売)ナレッジ共有の推進
C社はアパレル事業を全国展開していますが、1店舗辺りの社員数は少なく、持ち場やシフト管理の関係でOJTもままならず、サービス低下が売上減に直結していました。
ノウハウをナレッジシェアしようとしても、現場一人当たりの業務負荷が多く、能力や実績が高い社員ほどわざわざナレッジシェアする時間がなく、現場もナレッジをシェアするより、売上向上に時間を割いてほしいというマネジメントに流れていました。
そこで、社内SNSと組織開発を組み合わせたのです。具体的には、チームビルディングを1店舗ずつ行い、アクションプランを全員が社内SNSにアップし、役員・上司先輩まで全員がみえるようにしました。
その結果、いい結果がでると全国から「いいね」が集まり、「もっと詳しく教えて」「わかった」とナレッジが社内SNSに書き込む感覚でどんどん集まり、共有されるようになりました。
また、いいアドバイスに「いいね」が集まるだけではなく、ほかの上司や先輩もその指導の仕方を真似るなど、社内SNSの中で全国の社員が集まり、お互いの活動をインタラクティブにコメントし合うことで、ナレッジシェア、各人の成長が加速化したのです。
それにより全国どこにいても社内SNSを介して一体感のある組織になり、社員のエンゲージメントも高くなり、業績もV字回復しました。
まとめ
組織開発は、組織まとめてパフォーマンスを最大化できることが一番の効果です。
組織のプロセスや関係性を改善することで、生産性の向上、変化への対応力の向上、イノベーションの実現など、最終的に企業力強化につながる組織運営を可能にします。
組織開発の具体的な効果は5つあります。
- メンバー一人ひとりが当事者意識を持ち、自ら課題解決に取り組む姿勢を持つ
- 集団のシナジーが高まる組織風土が醸成される
- 変化への対応スピードがあがる
- メンバー一人ひとりのスキルと組織力が同時にあがる
- 組織のパフォーマンスや生産性が向上する
当然ですが、組織開発は「一度取り組んで終了」というものではありません。
常に環境変化を踏まえ、組織が成長し続けるよう、継続して取り込み、必要に応じ組織開発の手段を変え、変化に対応しながら集団シナジーが発揮できることが当たり前な組織風土を醸成していきましょう。
こちらの資料もおすすめです


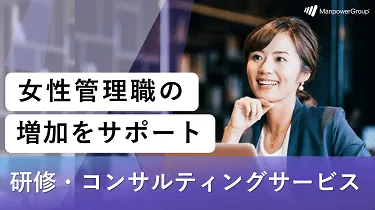

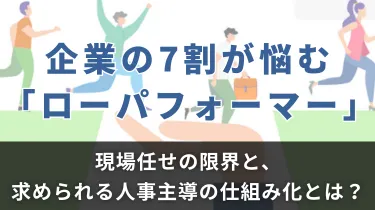
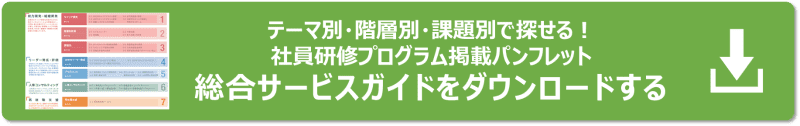
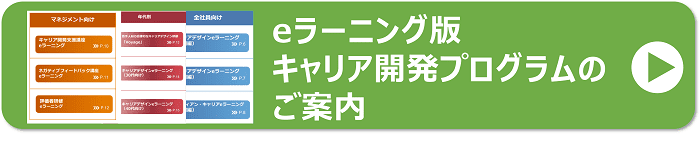
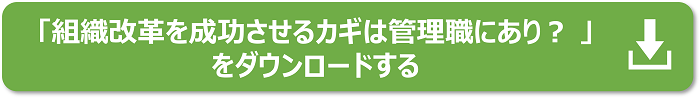
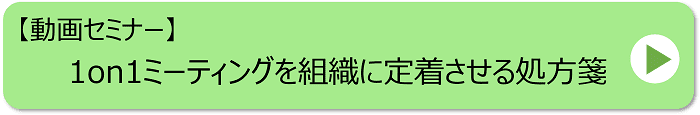






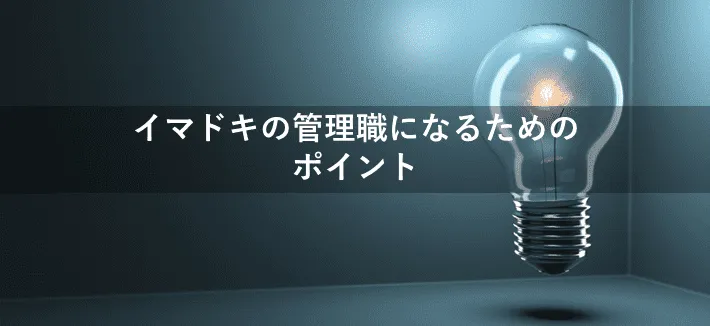











 目次
目次