


テレワークが生んだ社員のストレス・不調の原因は?

目次
コロナ禍においてテレワークが普及し、働き方に変化が起きました。テレワークにはコストが削減できたり、効率性が向上したりするメリットがある一方で、見えないところで社員の不調が起きる恐れもあります。ここでは、テレワークが社員の不調を増長させることなく、関係性の構築や効率アップに繋がるようなヒントをお伝えします。
テレワークで起こりがちな社員の不調
まずは、筆者が相談業務をしている中で感じた、テレワークで起こりがちな2つの不調について解説します。
孤立感(孤独感)による不調
テレワーク導入時は、通勤時間が無くなった分、「朝の時間に余裕が出来た」「身体的に楽」「嫌な上司と顔を合わせずに済む」「家で仕事ができるなんてラッキー」といった前向きな声も多くありました。
しかし、テレワークが長期化(もしくは永続化)する中で、孤立感を訴えるケースは増えています。
特に、ひとり暮らしのように自宅で話し相手がいない場合は顕著にこの傾向があります。趣味のイベントに出掛ける、友人と飲みに行くということが、思うようにできなくなっている今は、他者との接点が希薄どころか、全くなくなっているケースもあるのです。
直接誰とも話さないという時間が長きにわたると、「自分自身が何をしているのかわからなくなり不安になる」「何のために生きているのかを考え始めて怖くなる」などと訴える方もいます。
また、家族と同居の場合も、家庭での精神的な居場所がなかったり、「他の人はうまくやっているのになんで自分はできないのだろう」と比較して落ち込むといったことも増えています。
コミュニケーション不足による不調
コミュニケーション方法がオンラインになり、文字ツールでのやりとりが増え、情報共有の量が圧倒的に減ってしまいました。雑談レベルの会話や細かなニュアンスをやり取りすることができなくなり、行き違いや誤解も生じています。
例えば、社員が資料を見てわからないことを上司に質問しても「書いてあるから、よく読んで」と応答されたりすると、極端な場合、パワハラととらえられてしまうことがあります。
不明瞭な指示だと社員はどのように関わっていけばよいのかわからなくなり悩んでしまうのです。齟齬のリカバリーがしづらく、ニュアンスも伝わりにくい、また、自分自身のメンタルも弱くなっている中で、ちょっとしたやり取りの影響を強く受けてしいます。
また、オンライン会議で「何かありますか?」と問いかけられても、「みんなの前で言うほどのことじゃないかな」と思うと、発言を遠慮してしまう。それが続くと、何かを言うこと自体を諦めてしまうという声も聞かれます。こうなると、相互理解には程遠くなり、業務に対する意欲が失われる由々しき事態です。
マンパワーグループでは20代~50代の男女400名の管理職を対象に、テレワークに関するアンケート調査を2020年に実施しました。
テレワークにおけるメンタルケアの方法
社員を不調にさせないために 、テレワークではどのように部下と接していけばよいのでしょうか。管理者であれば担うことになる安全配慮義務は、結果責任ではなく、予防措置であり、未然に防ぐ対応が重要です。
孤立させないための雑談
社員をテレワーク不調にさせないためには、孤立にさせないことです。ひとりで業務に向き合っていると、どうしても自分の不安と向き合う時間が増えてしまい、些細なことから不調の引き金になりかねません。人との交流が必須で、精神的に安定を保つ基盤になります。
そのためには、コミュニケーションの取り方を工夫することが必要です。定期的なミーティングを実施しているところも多いとは思いますが、効率重視で連絡、報告だけにとどまってしまうと、部下の変化に気づきにくくなります。対面していれば顔色や様子もある程度分かりますが、画面を通じてだと、そこまで判断することは難しいです。
そこで、「雑談」をするようにしましょう。雑談を通じて生活の状況や体調などを把握することが可能です。対面でも同じですが、些細な日常会話ができてこそ、社員はちょっとした相談がしやすくなります。今はその日常会話がしにくい状況だからこそ、あえて雑談の時間を作ることが大切です。ただ、ここで気を付けたいのが、会話を促す質問の仕方です。
オープンクエスチョンによる雑談で会話を広げる
質問には、大きく分けて2つのパターンがあります。「よく眠れてる?」 「何か困っていることある?」などの質問をクローズドクエスチョンと言い、相手が「はい、いいえ」で答える質問形式を指します。実はこの質問形式は、相手との会話を形式上のものにしてしまいがちで、内容が深まらず、会話が続かなくなります。
色々と質問しているのだけれど、なんだかかみ合わず話が深まらないと思っている管理者は、無意識にクローズドクエスチョンを多用しているかもしれません。
そこで、オープンクエスチョンを使っていくことを意識しましょう。「この件についてどう思う?」「これ読んで何を感じた?」など、「はい」か「いいえ」では答えられない質問がオープンクエスチョンです。この質問形式をとると、部下は、自分の意向や考えを発言しやすくなります。自発的な言動が増えると、「そういえば」や「関係ないかと思うのですが」などと他の話題にも自ら触れてくれるようになります。
テレワークでは、生活リズムの乱れや変化による不調も起こりやすいです。仕事とプライベートの境が曖昧になり、切り替えがうまくいかずに鬱々としてしまうということもあるでしょう。そんな状況も会話の中で確認し、話を聴くことで、早めに対処することが可能になります。
相互理解を深めるテレワークでの業務指示の方法
上司が取引先と電話する様子を見て話し方を習得したり、他の人がミスして注意されているのを聞いて学んだり、周囲にいる人たちの行動を見て、自分に足りない部分に気づいたりすることから、習得することは多々あります。
それらの機会をテレワークで補うのは至難の業です。特に同調性や協調性を育てることに無理が生じます。組織は、相互理解をとりつつ、同じ方向性で取り組む必要があるので、この部分を丁寧に埋めていくしかありません。
テレワークの効率ばかりを追い求めると、ここがすっかり抜け落ちてしまうのです。
管理者の方から、部下が何をしているのかわからず、管理に困るという話をよく聞きますが、部下の方も同じように、自分は仕事を覚えてきちんとこなしていけるのだろうかという大きな不安を抱えています。
「このくらいわかるだろう」ではなく、細かいステップで、相互理解を繰り返しながら、業務を進めていくことが必要です。
今まで以上に指導や指示を細分化し、具体的にしていくようにしましょう。その際に気をつけたいのが、ある程度説明した後に「何か質問はある?」と聞いても、質問がないから「理解してくれたんだな」と安心してしまうパターンです。
絞り込んでから「質問を聞く」「指示を出す」
質問は、ある程度分かっていることにしか生まれず、「何か質問は?」と言われても範囲が広すぎて何を尋ねてよいのかわからないということがよく起こります。
そのため、質問は、ある程度絞り込んだ状態で促すこと。また「何でも聞いて」などの大まかな表現を避け、「○○について、▲▲をしてみてもわからなければ、どこまでできたのかをふまえて知らせて」など、より焦点付けすることが必要です。
さらに「なるべく早く」とか「できれば」といった指示出しも部下を不安にさせます。「なるべく」とはどのくらいなのか、「できれば」はやらなくていいのかなど、混乱を招きます。曖昧さを避けて、具体的に指示出しすることも大切です。
テレワークでも指導は必要。悩む管理職。
「反発されたり、嫌われたりするのでは?」「パワハラだと思われるのでは?」と躊躇せず、部下に現状を正しく受け入れてもらうためには、どのような伝え方をするべきなのでしょうか。
本資料にて部下の行動改善を促す「ネガティブフィードバック」について解説しています。
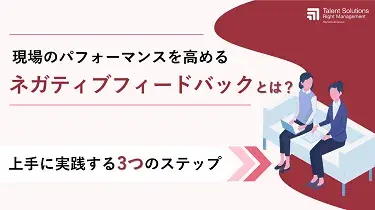
まとめ:管理者自身の心のケアも大切に
相互理解は、管理者の関わり方次第で、深めることができます。働き方の変化により不安なのはお互い様です。些細なことでもやり取りができるよう、よりハードルを下げた交流が求められます。管理者自身のストレスケアも大切で、自分にゆとりがないと部下への配慮もできません。是非、管理者自身の心のケアも大切にしていただきたいと思います。
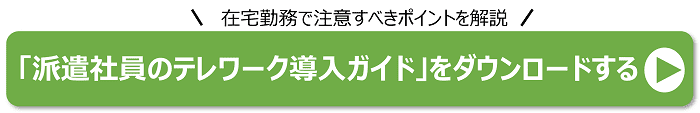
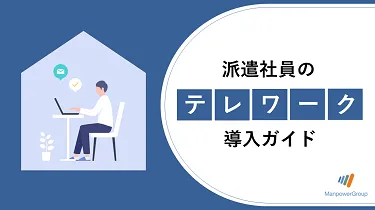
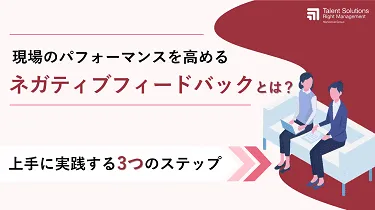






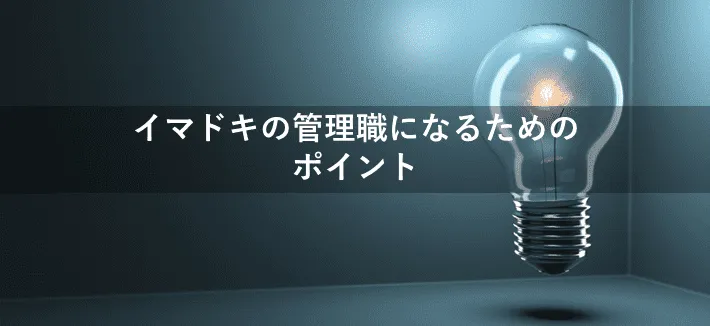











 目次
目次