


守りに入っている?変化を恐れる社員への処方箋

目次
心理学と脳科学から解き明かす 部下の本来の力を引き出す指導法
部下への指導法は「気合と根性」だけでどうにかなるものではありません。
本コラムでは、個人個人が本来持っている力を引き出すための指導法について、心理学と脳科学のフレームを用いながら4回にわたって解説します。
第1回 「守りに入っている?変化を恐れる社員への処方箋」
第2回 「増加する叱れない上司、正しい部下の𠮟り方とは」
第3回 「部下の成長を促すために上司が行うべき行動とは」
第4回 「仕事への好循環をもたらす部下とのコミュニケーション方法」
パフォーマンスの判断基準は「能力の高低」ではない
「パフォーマンスがあがらず停滞してしまっている部下」を指導する際に気をつけるポイントとして、まずはパフォーマンスの判断基準について陥りがちな誤りについてご説明します。
「パフォーマンスの高低」は、能力の高低を指すものではないということです。
本来であれば、成果と周囲(会社・上司・組織・顧客)の期待とのギャップの生じた度合いであるはずです。
「ハイパフォーマーとは、周囲の期待を大きく上回る成果を出す人」であるはずなのに、実際には能力や成果の数字だけでパフォーマンスを判断されてしまっているケースがあります。
例えば、「新入社員」は業務スキルも業績もベテラン社員と比べれば低い(少ない)のが一般的です。
だからといって、新入社員全員を押し並べて「パフォーマンスが低い」と位置付けることはしないでしょう。
新入社員として期待している役割・成果に対して、どのくらいのパフォーマンスを発揮しているかで判断しているはずです。
一方、中堅社員以降の「期待役割」は個別性が高く、明確になっていない場合があります。
また、本人も十分理解していないというケースもあります。
会社と本人とで、この「期待役割」に対する認識がズレていると、頑張りどころを間違えてしまう、もしくはわからなくなってしまうなど、社員が本来の力を発揮できなくなるリスクが高まります。
基準となる「期待役割」が明確に言語化されているかどうか、まずは確認をすることが重要です。
キャリア開発・階層別・課題別のセミナー
マンパワーグループでは、人材育成・組織開発などを中心にサービスの提供を行っています。人材育成分野では、さまざまなタイプの研修メニューを用意しており、課題や状況に合わせたカスタマイズも対応可能です。ご興味のある方は下記の資料をダウンロードください。

定年延長・定年撤廃で「シニアの再活性化」が企業課題に
「期待役割と成果の齟齬」という観点でいうと、定年延長・定年撤廃を検討する企業の増加に伴い、ベテラン社員・シニア社員に対する再活性化のご相談が増えています。
社会や技術の著しい変化は企業活動にも影響し、おのずと企業が「社員へ期待すること」も激変しています。
どの年代にも変化に対して後ろ向きな社員は存在しますが、ベテラン社員・シニア社員がこの周囲の激しい変化についていけなくなるというケースが特に増えているのです。
「元々はハイパフォーマーだったエース人材が、今やご意見番。しかも、そのご意見が古臭く、周囲も困惑している」といった相談も珍しくありません。
社員本人が成長・変化を止めたときに会社がすべきことは、「もう何年かすれば定年退職なので」「○○さんは年上なので指導しづらい」などと放置することではありません。
コンピューターに置き換えればメンテナンス・アップデートにあたる活動を、適切に社員に行うことが必要です。
例えば、「期待する役割などを明確に伝える」という面談や研修などの活動がそれにあたります。
なぜ、環境の変化に適応しようとしないのか
そもそも、なぜ環境の変化に適応しようとしないのか。それは本人が変化する必要性を認知していないためです。
なぜ認知しないかというと、「変わってもメリットが少ない」あるいは「変わらなくてもデメリットが少ない」と考えているからです。
人には「プラスまたはマイナスの動機付けが無い限りは変わりにくい」という、心理的一貫性の法則があります。

現在の自社の人事制度を思い浮かべてみてください。
期待役割以上のパフォーマンスやチャレンジを発揮したとき、昇給・評価・インセンティブ・賞賛など、変化に見合う明確な報酬はありますか。
逆に、期待役割から大きくギャップを生じたとき、注意・指導・減給・降格・異動など、ギャップを解消するための適切な対応やメッセージはありますか。
変わるための動機付けが弱いと、人は変わりたくない理由を探し出し、そこに安住してしまいます。
人事制度に問題が無い場合は、上司とのコミュニケーションに問題がある可能性があります(上司との関係性については、次回以降のコラムで解説します)。
最後に
変化を恐れ「期待役割」以上の力を発揮できない社員が発生する要因は、以下の3つです。
1. 社員が期待役割を認識できていない
⇒ 会社も明確に言語化していない
2. 社員が社会の変化についていけない
⇒ 変化ごとの社員に対するケアが不足している
3. 社員が変化する必要性を感じていない
⇒ 変化を促す動機付けが弱い
これらの要因を解消する環境・仕組み作りが必要です。
次回は、その環境の構成要素である、部下と直接対峙する上司の問題について解説します。
心理学と脳科学から解き明かす 部下の本来の力を引き出す指導法
第1回 「守りに入っている?変化を恐れる社員への処方箋」
第2回 「増加する叱れない上司、正しい部下の𠮟り方とは」
第3回 「部下の成長を促すために上司が行うべき行動とは」
第4回 「仕事への好循環をもたらす部下とのコミュニケーション方法」
こちらの資料もおすすめです
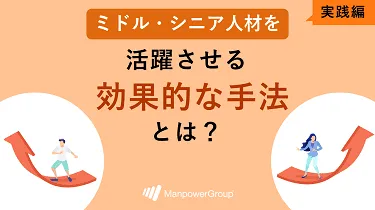

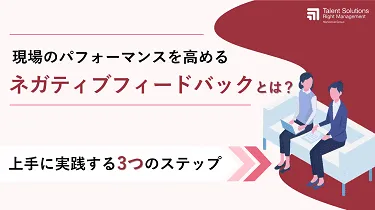







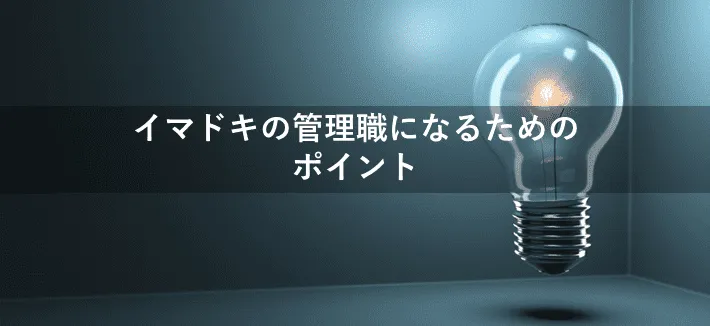











 目次
目次