


チームビルディングに求められるリーダーの役割とは

目次
部門やチームに課せられている目標やタスクは、所属するメンバー全員で達成を目指すものです。
結果的にチームがどのような業績を収めているかということが評価されるため、リーダーにはメンバーや自身の個人目標の達成も視野に入れつつ、チーム一丸でパフォーマンスが出せるようメンバーを導いていくことが求められます。
ここでは、チームビルディングを行ううえでのリーダーの在り方について解説します。
チームビルディングとは
チームビルディングとは、名前のとおりチーム(Team)を構築(Build)する取り組みを指します。
では、チームとは何かというと、共通の目的とゴールを持つ集合体(グループ)を指します。
とある「グループ」の中に共通のゴールが生まれた時、グループのメンバーはその共通のゴールに向かって行動を起こすことになり、「グループ」は「チーム」にトランスフォーム(転換・変身)したことになります。
この、グループからチームへのトランスフォーメーションによる共通の目的とゴールに向けたメンバー間の協業関係を築くことをチームビルディングと言います。
チームビルディングは、単に1+1が2になるような1人ひとりの働きを足し合わせただけの関係性を築くのではありません。
人的資源を含む限られた経営資源でのパフォーマンス最大化を目指し、それよりも高い成果を発揮する相乗効果の発生を目指す行為です。
チームビルディングのゴールとは
前述したように、チームビルディングの目的は「限られた資源でパフォーマンスを最大化すること」にあります。
しかし、一足飛びに「できるチーム」にトランスフォームするわけではありません。
チームにはさまざまなタイプの考え方やスキル、個性を持つ人材が集まっているわけですから、「できるチーム」としてまとめあげていくにはステップがあります。
現時点の状況を把握し、理想を定めつつも客観的な視点を忘れずに取り組むことが大切です。
チームの成長過程
チームビルディング研修やワークショップの中でよく紹介される、チームの成長段階を示すモデルにタックマンモデルがあります。
これは心理学者のブルース・W.タックマンが提唱した、チームの発展ステージを表す4段階モデルです。
1970年代後半に入り、ステージが1段階増えた5段階のモデルとして紹介されることもあります。
タックマンモデルの5つのステージ
それぞれの段階におけるチームの状態を説明します
Form(形成期)
チームが組まれたばかりでメンバーが互いをよく知らず、遠慮しがちであるためにまだ衝突や混乱が起きていない状態
Storm(混乱期)
段々とメンバー同士の遠慮が消え、それぞれの主張が全面に出てくることで、信頼関係がまだ構築されていない状態の中で様々な意見が衝突し、チームの中で混乱が巻き起こる状態
Norm(統一期)
混乱期を経て、チームがやっと落ち着いて共通の目的やゴールを共に検討できる状態に成熟し、信頼関係も確立されつつある状態
Perform(機能期)
メンバーの役割が互いに明確化され、かつ信頼関係も構築され、1人ひとりが自分の役割を発揮することでチームが機能するようになった状態
Adjourning(散会期)
1970年代に追加されたステージ
プロジェクトの終了や会社の方針転換などの状況の変化により、チームが解散するタイミングになった状態
チームビルディングがうまくいかない際に注力すべきこと
タックマンモデルにおける4段階目にあたるPerform(機能期)を迎えることが、チームビルディングのゴールに該当します。
ところが、実際にはこの5段階を順調に順番どおりに進めるのは容易ではありません。
途中段階でリーダーを含めたリーダーの入れ替わり、外的要因による目的やゴールの変更などが発生すると、Norm(統一期)から一気にForm(形成期)に戻ってしまったり、長期間Storm(混乱期)にとどまってしまったりなどの現象が起こることがあります。
では、うまくPerform(機能期)に向けて進めていくには何に注力すべきなのでしょうか。
タックマンモデルの流れでは、チームが第一段階であるForm(形成期)から理想的な状態にあたるPerform(機能期)に向けて成熟していく過程において、長い時間をかけて以下のふたつの行動が、メンバー間で行われているとされています。
①チームメンバーが互いを知ること
②チームメンバーが互いに信頼し合うこと
成熟過程におけるこれらの成果がが満ちてくることで、Perform(機能期)となるわけですから、このふたつの行動はチームビルディングのカギとも言えます。
チームビルディングにおけるリーダーの役割
チームメンバーが互いを知り、チームメンバーが互いに信頼し合うためには、チームメンバー同士の頻繁な交流と言語・非言語のコミュニケーションが必要です。
チームビルディングにおけるリーダーの役割には、このふたつの行動を促進するためのきっかけやコミュニケーションを生み出す役割(ファシリテーション能力)と、リーダー自身がいち早く各メンバーの強みとニーズを把握し円滑なコミュニケーションを支援する役割が含まれます。
リーダーがこの役割を果たすには、各メンバー、そしてチーム全体とコミュニケーションをとる必要があります。
そこで重要となるのは、他者との良い関係を築きそれを維持・発展させる対人スキルと、周囲の人々を動かすリーダーシップです。
対人スキルとリーダーシップには、本人が本来持っている性格上の特徴との結びつきが強く表れます。
無意識の行動や自然に発揮する強みには、その人自身に備わる特徴が潜在しているものです。
リーダーが自分自身の特徴を理解し、必要な場合には意識して自身の言動をコントロールすることで、より効果的な対人スキルとリーダーシップを発揮することができるようになります。
チームビルディングのカギは自己理解に
チームビルディングがうまくいっていないと感じている場合、まずはチームリーダーの自己理解を深めることが重要です。
チームビルディングのカギといえる、「理解と信頼」は、相互理解のためにだけにあるものではありません。対人スキルの向上には、深い自己理解も重要なのです。
リーダー自身が客観的に自分の特徴を理解できておらず、自分の行動や発言がどのように周囲へ影響しているかを把握できていないと、メンバーとの関係をうまく築けず、チーム内でのトラブルや、期待されている成果がなかなか出ないなどの弊害につながります。
自分自身が周囲にどういう影響を与えがちかという行動傾向を理解しておくと、物事をうまく相手に伝えやすくなり、チームづくりやメンバーの育成においても一歩引いた視点で考えられるようになります(最近耳にするようになった"メタ認知"はこれにあたります)。
誰しもが持っている個人独自の価値観や無意識の偏見などを自分自身で理解しておくことで他者に対する言動のコントロールがしやすくなり、良好な関係性構築に役立ち、結果的にそれがチーム成果自体にもつながってくるのです。
自己理解と相互理解を深めるための具体的手法
自己理解は、チームビルディングを成功させるだけではなく、リーダー自身のストレス軽減にも役立ちます。
うまくいかない理由やコミュニケーションリスクを自身で想定できるのとできないのとでは、メンタル面においてもダメージに差が生まれます。
では、客観的に自身の特徴を知る方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
上司やメンバーからのフィードバックも考えられますが、それぞれバイアスがかかってしまうことも事実です。
リモートで交流する機会が増えている昨今、他者理解も自己理解も以前より難しくなってきています。
おすすめしたいのは、アセスメントツールを使った、利害関係のない第三者によるフィードバックです。
第三者からの客観的な診断であるため、受けた本人も結果を受け入れやすく、具体的な行動に移しやすいというメリットがあります。
行動傾向や対人リーダーシップをフィードバックするアセスメントは、特定の能力の良い/悪いや高い/低いを測定する認知力テストではありません。
本人の特徴を理解し、期待役割に応じた行動変容の検討に活用するための「強み・課題の発見ツール」で複数の種類が存在します。
受検者の傾向を特定のタイプ・型に分類する診断結果が得られるタイプのものは個人の自己理解ツールとして活用する以外にも、他者理解や多様性の考察に基づくチームビルディングの考察にも利用可能です。
そのほか、個人の傾向や興味・関心などを行動や思考のベンチマークに基づいて診断するツールもあります。
このタイプのツールは、ある程度社会人として経験を重ねて「自分スタイル」がある程度確立されている人や、リーダーの役割を担う人が、能力開発や特定の課題の強化に取り組む際の自己理解に活用できます。
また、周囲との信頼関係構築のきっかけづくりとして、アセスメント結果の一部を用いた自己紹介や自己開示を行うという利用方法もあります。
リーダーシップはリーダーだけのものではない
チームビルディングとは、同じ目的とゴールの達成にむけ、メンバーのパフォーマンスを最大化する相乗効果(シナジー効果)の発生を目指す行為であると説明しました。
「チームビルディング」に関する社会人向けのトレーニングやワークショップは数多く存在しており、社員研修や自己学習の一環でこれらのプログラムに参加した経験があるという方もいらっしゃることでしょう。
プログラムのネーミングはそれを導入する組織や提供者によって異なりますが、内容は一般的にチームのリーダーが参加するプログラム、あるいはチーム単位で参加するプログラムのふたつが主流です。
チームビルディング研修/ワークショップを開催する目的の多くは「チームのシナジー効果を引き出す」ことであり、チームのシナジー効果を引き出すためのリーダーシップを考察するプログラムであることが多いです。
"リーダーシップ=リーダーが発揮するもの"というイメージをお持ちの方が多いかもしれませんが、リーダーシップは本来、どの階層、どの立場の人にも求められる行動です。
リーダーシップの発揮は、周囲への影響力の発揮です。組織に所属する従業員は1人ひとりが自分の役割を担っています。
その役割を果たすために周囲に働きかけ、何らかの影響を与えることもまたリーダーシップなのです。
チームビルディングにおけるリーダーシップも同様です。
リーダーひとりにリーダーシップの発揮を求めるのではなく、メンバー1人ひとりがチームのプラスになるリーダーシップを発揮しなければチームシナジーの発生は困難であり、結果が出るまでに多くの時間を要することになります。
メンバーそれぞれがリーダーシップを発揮できる環境づくりとは
メンバー1人ひとりが各自の役割を理解し、その役割を果たすために適切だと思うことを積極的に行うだけでは、チームシナジーの発揮に十分ではありません。
チーム内で他のメンバーが行動しやすいような動きが互いにできる関係性を築くことも重要です。
互いにフィードバックし合う文化をチーム内に築くことを目指すことで信頼関係も深まります。
近年の研究では、職場などの組織の中で自分の考えや気持ちを表現しても、他のメンバーから拒絶されたり罰を受けたりする心配がない、心理的安全性の高い状態が生産性の向上に効果的だといわれています。
チームリーダーは、自身とメンバーのことをよく理解したうえで、以下の4点を主眼においてチームビルディングを進めていくとよいでしょう。
- チームメンバー1人ひとりの役割を明確にする
- メンバー全員が互いの役割を理解し合う
- 互いを信頼して担当役割を各自に任せる
- 各メンバーが必要とする支援を互いに提供し合う
動画セミナー:「心理的安全性」を生み出す具体的方法とは?
リモートワークやハイブリットワークでのチームパフォーマンス向上のカギとなるのが、チーム内の「心理的安全性」。
- 「心理的安全性」とは?アセスメントの視点を含めて
- 「心理的安全性」を阻害する要因~環境と個人2つの視点
- 「心理的安全性」を創る具体的方法~短時間で起点を創る
この3つの切り口から、「心理的安全性」を生み出す具体策について解説するセミナー動画を公開中です。
関連記事
さまざまな職歴、雇用形態のメンバーが集まるアウトソーシングの現場におけるチームビルディングの手法について、マンパワーグループのアウトソーシング部門プロジェクトマネージャーへのインタビュー記事を公開しています。
こちらもぜひご覧ください。
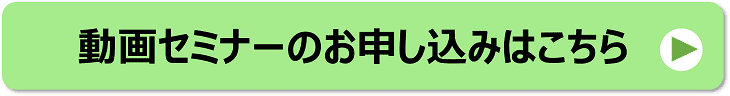



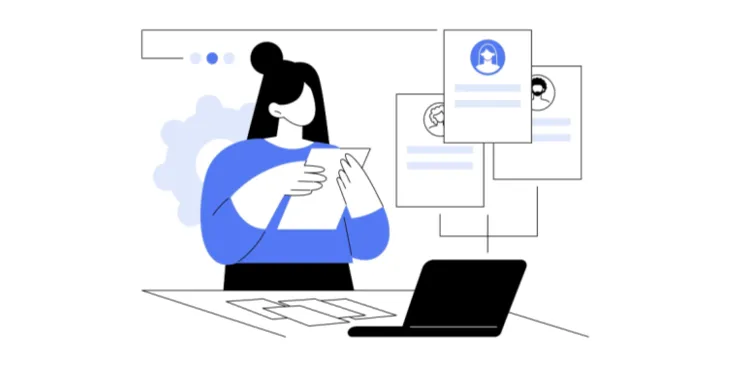
















 目次
目次