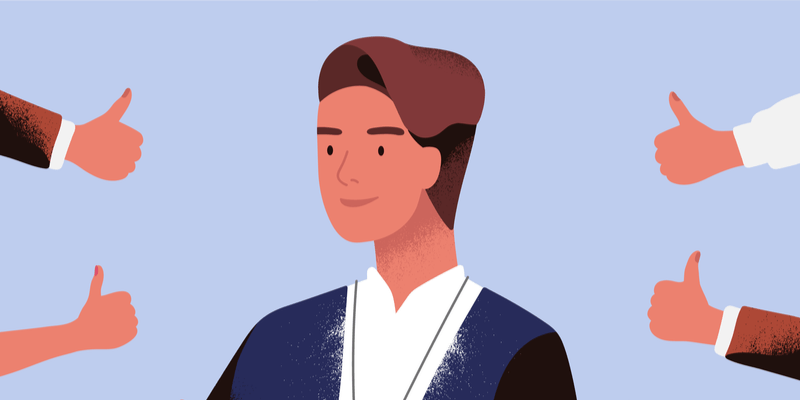


心理的安全性の高め方とは 企業へのメリットやチェック手法を解説
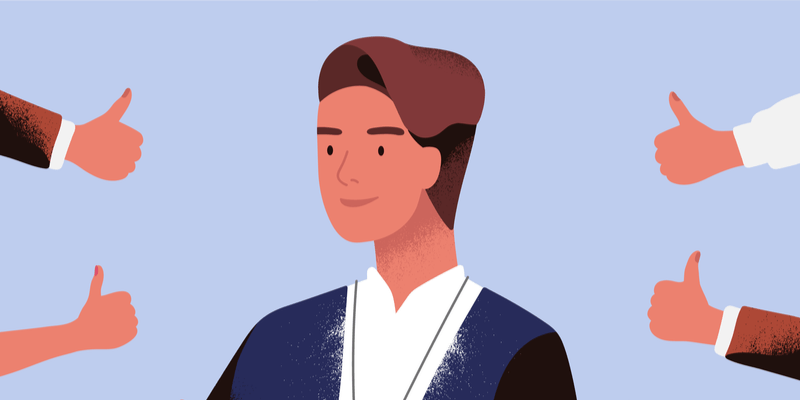
目次
企業が自社の生産性の向上を図る手段のひとつとして、社員が働きやすい職場環境の構築が挙げられます。職場環境には、騒音の有無や照明の明るさ、設備などの「物質的な要素」と、メンバー間の人間関係にかかわる「人的な要素」の2つの観点があります。本記事では、人的な要素から見た職場環境改善の方法の1つである「心理的安全性」の考え方や、活用方法などを解説します。
心理的安全性とは
「心理的安全性」とは、英語で「サイコロジカル・セーフティ(psychological safety)」といい、本来は心理学の用語です。「職場などの組織の中で自分の考えや気持ちを表現しても、他のメンバーから拒絶されたり罰を受けたりする心配がない状態のこと」を指します。
心理的安全性が注目を集めるようになった研究
心理的安全性は、アメリカ大手インターネット会社が自社の生産性を向上させる目的で、社内に数百あるプロジェクトチームの働き方を調査し、どのチームがより生産性の高い働き方をしているかを分析したことがきっかけで注目され始めました。
この分析の結果、生産性の向上につながっていたのはチームメンバーの能力や働き方ではなく、「メンバー間において業務上気づいたことやアイデアなどを安心して発言できる環境がある」という心理的な要素のほうが重要だったことが確認されました。
その後、日本でも心理的安全性への関心が高まっています。例として、農林水産省の「食品製造業における労働力不足克服ビジョン」![]() 、金融庁の「金融行政のこれまでの実践と今後の方針」(PDF)
、金融庁の「金融行政のこれまでの実践と今後の方針」(PDF)![]() などの中で、心理的安全性が取り上げられています。
などの中で、心理的安全性が取り上げられています。
心理的安全性が高い職場の4つのメリット
職場の中で心理的安全性を高めることによるメリットを紹介します。
離職率の低下
業務の中で自分の持つスキルを活用できない、メンバー間でのコミュニケーションが上手くいかないなどの原因で職場環境が悪化すると、従業員が退職するリスクが高まります。逆に、自分の能力を十分に発揮することができ、人間関係も順調な心理的安全性の高い職場なら、やむをえない事情がない限り勤続を望む従業員が増えるでしょう。その結果、退職者の減少はもちろん、優秀な人材の流出も抑えられるでしょう。
生産性アップ
心理的安全性が高い職場は、メンバーが建設的な意見を述べやすく、安心して議論を行えるので、目標に納得して行動に移しやすいという特徴があります。個々がバラバラに動くのではなく、目標に向かって一致した行動を取れるため、仕事の生産性も向上します。
ブラッシュアップがしやすくなる
メンバーがお互いを認め合い尊重できる環境では一人ひとりが安心して発言できるので、行動や考えに対して複数のフィードバックを得る機会が増え、製品やサービスもよりブラッシュアップされます。また、フィードバックを受けることは従業員が学びを得る機会でもあり、従業員自身のスキル向上にもつながるでしょう。
ノウハウの蓄積がしやすくなる
一人の従業員が仕事でミスをした場合、スムーズにミスを報告できれば、原因や対策などをメンバー間で共有でき、以後同じミスの発生を防ぐことができます。顧客から受けたクレーム対応や、仕事の進め方での気づきなども、運用ノウハウが蓄積されれば、業務がより円滑に進むようになります。
心理的安全性に関する3つの誤解・注意点
本章では、心理的安全性に関する誤解や注意点を解説します。
気遣いすぎて意見の言えない雰囲気を作ってしまう
チーム内の人間関係の悪化を恐れるあまりお互いに気を遣いすぎると、業務上で必要な意見さえも言えない雰囲気になってしまいます。この状態を避けるには、上司が中心となり、メンバーが自分の意見を躊躇せず言えるような環境を整えることが必要です。例えばミーティングなどで、メンバーが自分の意見が言えるように、上司が質問を投げかけて誘導することなどが考えられます。
馴れ合い・ぬるま湯のようなチームになってしまう
メンバー内のコミュニケーションが上手くいっている職場だとしても、場合によってはチーム内に馴れ合いやダラダラした雰囲気が生じていることがあります。仕事の目標達成や個人のスキルアップに対する意欲が失われ、適当に働いていればOKだと考えるメンバーもいるかもしれません。
チーム内でそのような状況を作らないためには、職場として明確な目標を掲げるとともに、各メンバーにも明確な目標や責任を与えることが重要です。上司が面談などで業務状況を確認しながら目標や責任の妥当性を判断し、都度フォローを入れるといいでしょう。
上司が果たすべき役割を放棄してしまう
メンバー間のコミュニケーションがスムーズな職場は一見雰囲気がよく働きやすそうですが、場合によっては上司と部下が友達のような関係になってしまい、上司が部下に対して必要な業務指示や注意を怠っていることがあります。
上司の役割は業務が円滑に進むように、部下にそれぞれの役割や責任を与え、指示を出し、褒めたり、注意したりしながら指導することです。そのような上司の役割を放棄すると、一見すると心理的安全性が高まってはいるものの、チーム内の士気は上がらず、生産性が低下しかねません。上司は、目標の設定や責任を与えるなどで部下の仕事へのやる気を引き出し、部下の能力を高めサポートできる環境づくりを意識することが重要です。
心理的安全性のチェック手法
自社の心理的安全性の有無や問題点を確認するために有効な方法が、心理的安全性の提唱者であるハーバードビジネススクールのエイミー・エドモンドソン教授が提唱する「7つの質問」です。
心理的安全性を測る7つの質問
以下の7つの質問を、自社の状況と照らし合わせて考えたり、メンバーに質問をしてみたりしましょう。
1.自分がチーム内でミスを起こした場合でも、最初から非難されることはない
ミスをしたときに上司や先輩のメンバーから「何をやっているんだ」「こんなこともできないのか」と最初から非難ばかりされていないか
2.チームのメンバー内で、課題や難しい問題を指摘しあうことができる
業務上で発生したトラブルや問題に対して、メンバー内で意見を出し合い改善することができるか
3.チーム内のメンバーは、自分と違った考えを受け入れてくれる
業務に対する考え方で自分と違った考えを持つメンバーに対して、「そんなことはだめだ」などと否定的な言動をするメンバーがいないか
4.チームに対して、リスクがある行動を取っても安心である
初めて行う仕事などでリスクを伴う場合「もし失敗しても責任は持たないよ」などと否定的な言動をする上司はいないか
5.チーム内のメンバーに助けを求めることができる
自分の業務が忙しくなったときや困難な内容の業務を担当するときに、ほかのメンバーに質問をしたり、業務の軽減(手伝ってほしいなど)を求めたりすることはできるか
6.チーム内で自分を騙すようなメンバーはいない
メンバー内で共有する情報が自分にだけ伝達されなかったり、嘘の情報を渡されたりすることはないか
7.現在のチームで業務を進める際、自分のスキルが発揮されていると感じる
担当する業務の中で、自分が持っている能力、スキル、経験、知識などが活かされていると感じるか
これらの7つの質問に対して、肯定的回答が多い職場は「心理的安全性」が高く、否定的な回答が多い職場は「心理的安全性」が低いといえるでしょう。
心理的安全性を損なう4つの要因と特徴行動
心理的安全性が低い職場で起こりやすいケースとして、エドモンドソン教授が4つの要因と特徴行動を示しています。
無知だと思われる不安
仕事に関する質問をすることで「こんなことも知らないのか」と思われかねない状況だと、上司やほかのメンバーに業務上必要な質問ができなくなり、メンバー同士のコミュニケーションが疎遠になってしまいます。
無能だと思われる不安
仕事でミスをした際に「こんなこともできないのか」と思われかねない状況だと、怒られるのが嫌なのでミスを報告しなかったり、自分のミスを否定したりするようになります。
邪魔をしていると思われる不安
例えば、ミーティング中自分が発言したために会議の時間が伸びたり、本題からはずれた議論になったりすることがあります。そのようなときに「いつも議論の邪魔をする」とほかのメンバーから思われていないか不安になってしまうと、だんだん自分から発言や提案をしなくなり、業務改善への気づきや発展に結びつくきっかけが減ってしまいます。
ネガティブだと思われる不安
例えば、業務改善を提案する際に「いつも他人に文句を言う」などと否定されないか不安になるような状況だと、業務上必要な発言や指摘、提案などを控えるようになります。この状態が続くと、徐々に仕事に対するやる気が失われてしまいます。
心理的安全性の高い職場を作る4つのポイント
これから心理的安全性の高い職場を作るときにチェックしたいポイントを解説します。
上司が部下や新人の意思や行動を尊重する
上司が自分の考えだけで行動したり、特定のメンバーの意見のみを聞き入れたりすることは避けましょう。さまざまな部下や、新人の考えでも意見を聞き、その言動を尊重するようにします。このような行動は、各メンバーに「自分は職場に必要な人間だ」という安心感を生み、心理的安全性が高まります。
発言機会を均等に用意する
ミーティングや面談も含め、すべてのメンバーに発言機会を用意することが重要です。ミーティングの場であれば、発言するのが毎回同じメンバーとなることは状態化しないように、各メンバーに平等な発言機会を設けることが大切です。発言することが苦手なメンバーであれば、上司側から意見を求めたり、ミーティングや面談前後にメールや文章で意見してもらったりする方法もあります。個々のメンバーが「自分の意見を聞いてもらえる」と思えば、心理的安全性が高まり、仕事に積極的に打ち込むようになります。
競争より協力を重んじる
チームでの目標達成よりも個人の目標達成を重視してしまうと、メンバー間での競争が激しくなり、困ったときの協力体制の維持が難しくなる恐れがあります。心理的安全性を高めるためには、メンバー間の競争よりも、ひとつのチームとしての目標を重点におき、協力し合いながら業務を進められる環境づくりを心がけましょう。
アサーティブ・コミュニケーションを心がける
アサーティブとは、相手の気持ちや考えを尊重しながら自分の気持ちや考えを伝えることです。心理的安全性を高めるには、自分と相手の双方が互いの立場や考えを理解しながら意見交換することが重要です。アサーティブ・コミュニケーションの考え方は自然に身につくものではないため、場合によっては研修や訓練を取り入れることも検討しましょう。
キャリア開発・階層別・課題別のセミナー
マンパワーグループでは、人材育成・組織開発などを中心にサービスの提供を行っています。人材育成分野では、さまざまなタイプの研修メニューを用意しており、課題や状況に合わせたカスタマイズも対応可能です。ご興味のある方は下記の資料をダウンロードください。

テレワーク環境での心理的安全性の高め方
テレワーク環境下では、オフィス環境とは違い仕事中のメンバーの様子がわかりません。この状況はコミュニケーション不足を生み、メンバーの不安感を大きくしてしまいます。テレワーク環境でも心理的安全性を確保するために、下記のようなことを意識しましょう。
メンバー同士が雑談できる環境を作る
趣味など、業務外の話題を気軽に話せるようなチャットルームやLINEグループなどを立ち上げたり、オンライン上での飲み会を設けるのも有効な方法です。雑談を通じて互いへの警戒心が薄まることで、仕事上でも気軽に質問ができ、自分の意見を話せるようになるので、心理的安全性が高い職場を作ることができます。
一対一での対話を心がけるなど、部下とのやり取りを密にする
上司と部下の間で1週間に1回など定期的な面談を行い、業務状況を確認する機会を作りましょう。また、部下からの質問などに対してはできる限り早く返事をすることで、テレワークでも部下が安心感を持って仕事できるよう心がけましょう。
メンバーを信じる
部下の業務状況に対して、逐一報告を求めたり、WEBカメラで監視したりするような過度な干渉は避け、メンバーを信じて仕事を任せましょう。仕事の成果を出すことは重要ですが、上司による過度な監視や干渉は精神的に部下のやる気を削いでしまいます。
部下が安心して力を発揮できるテレワーク環境にすることが、心理的安全性を高めることに繋がります。
上司が部下に与えた仕事のゴールを設定する
テレワーク環境下では、メンバーはある程度自分自身で仕事の区切りをつける必要がありますが、与えられた仕事の終わりが見えないと、長時間勤務につながってしまい、ストレスがたまる要因になります。上司がゴールを明確にすることで、部下はスケジュール管理がしやすくなり、仕事がやりやすくなります。
まとめ
心理的安全性の高い組織は多くのメリットを生み、生産性の向上も期待できます。そして、企業が心理的安全性をベースにした職場環境の改善をするときにキーマンになるのは、メンバーのマネジメントを担う管理職であるため、まずは管理職が心理的安全性の重要性について理解をする必要があります。書籍やインターネット、研修への参加などを通じ、知識を深めながら職場内で実践していくとよいでしょう。
こちらの資料もおすすめです
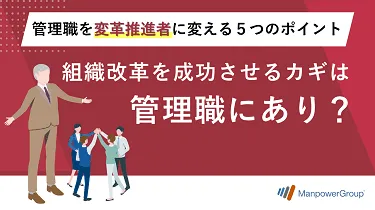
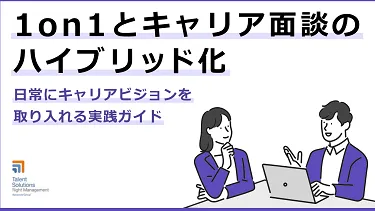
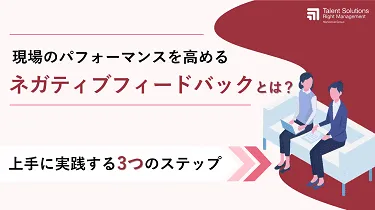
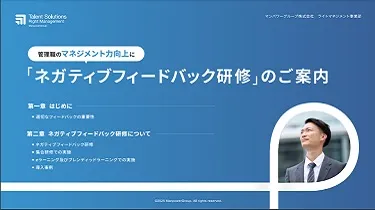
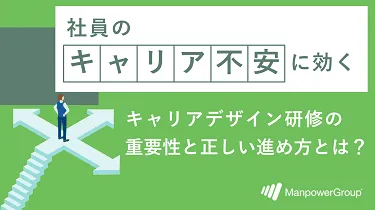
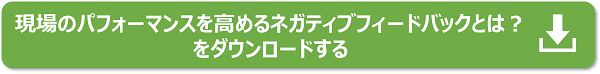
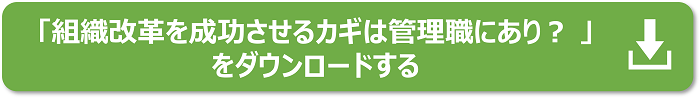






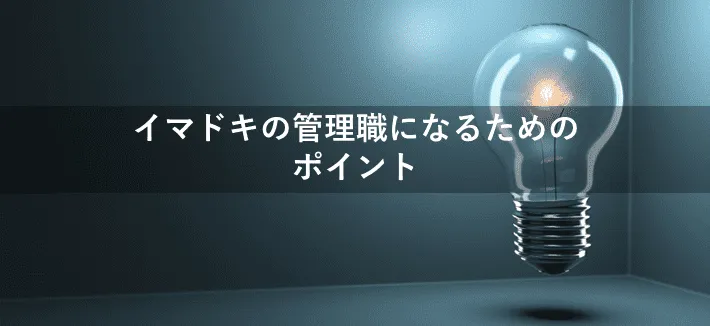











 目次
目次