


障害者雇用率が未達成の場合はどうなる?雇用を促進するポイント

目次
障害者雇用推進法では、障がい者の雇用安定を図る目的で、国、地方公共団体、一定数以上の従業員のいる民間企業に対して障がい者の雇用を義務化しています。
この記事では、障害者雇用促進法の内容、法定雇用率の意味と算出方法、法定雇用率(障害者雇用率)が未達成の場合の扱いと、未達成により企業が受ける影響、障がい者雇用を推進するための準備方法について解説します。
企業には障がい者雇用の義務がある
障害者雇用促進法の内容と、法定雇用率(障害者雇用率)について説明します。
障害者雇用促進法とは
障害者雇用促進法は、正式名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」といい、1960年に制定された「身体障害者雇用促進法」が原点になっています。以降複数回の改定を経て、直近では、2020年4月に改正されました(2023年1月現在)。
この法律ができた目的は、障がい者が職業生活において自立することを促進し、障がい者の職業生活の安定を図るためであり、事業主と障がい者本人に対してそれぞれ措置を講じています。
事業主に対する措置
1.雇用義務制度
- 法定雇用率(障害者雇用率)に相当する人数の雇用を義務化する
- 法定雇用率(障害者雇用率)を超えて障がい者を雇用するなど、給付条件に該当した企業に対して納付金や調整金を支給
- 障がい者を雇用する目的で特別な措置をした場合(施設の設置など)に対して助成金を支給
2.差別禁止と合理的配慮の提供義務
- 募集、採用について、障害がない人と同じ機会を設ける
- 障がいがあることを理由に、賃金、教育訓練の機会、福利厚生などの待遇面について不当な差別的取り扱いを禁止する
- 社会的な障壁をなくし、平等な就業機会を確保するために個々の障がい者に応じた対応や支援を行う
3.障がい者を5人以上雇用する事業所は「障害者職業生活相談員」を選任する義務を負う
4.障がい者雇用に関する届出義務
従業員43.5人以上の事業所は、毎年ハローワークに障がい者の雇用状況を報告し、障がい者を解雇する場合は、その旨を速やかにハローワークに届け出る
障がい者本人に対する措置
ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者生活支援センターなどで職業相談や指導、職業リハビリテーションなどを行う
法定雇用率(障害者雇用率)とは
法定雇用率(障害者雇用率)とは、全労働者数に対する障がいを持つ人の割合を示す政令で定められた基準をいいます。障がい者雇用促進のため、企業にはこの法定雇用率を乗じた人数以上の障がい者雇用が義務付けられています。
2025年2月時点では、民間企業の法定雇用率は2.5%、国や地方公共団体は2.8%、都道府県などの教育委員会は2.7%の法定雇用率が設定されています。
※2024年4月1日から、0.2%引き上げになりました
雇用を義務づけられている法定雇用障害者数は、以下の計算式で求めます。
(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×法定雇用率(%)
※小数点以下は切り捨て
「常用労働者」とは、1週間の労働時間が30時間以上の者、「短時間労働者」とは、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の者です。1週間の労働時間が20時間未満の労働者(パート、アルバイトなど)は計算に含まれません。
例えば、常用労働者が200人、短時間労働者が20人の企業の場合は、(200人+20人×0.5)×0.023=4.83となり、小数点以下を切り捨て、は4人となります。
除外率制度について
一般的に障がい者の就業が困難であると認められる業種(船員、建設業など)については、雇用する労働者数を計算するときに、除外率に相当する労働者数を控除し、障がい者の雇用義務数を軽減していました。
この制度は2002年の法改正により段階的に廃止することが決まり、現在も経過措置として段階的に除外率を引き下げ、縮小する方向で運用しています。
法定雇用率の算定対象になる障がい者
法定雇用率の算定対象である法令内で「対象障害者」とされている定義は次のとおりです。
| 身体障害者 | 身体障害者手帳を持つ人 |
| 知的障害者 | 療育手帳を持つ人 |
| 精神障害者および発達障害者 | 精神障害者保険福祉手帳を持つ人のうち、症状が安定し就労が可能な状態にある人 |
なお、手帳を保持していない障がい者は算定対象外です。
障がい者の雇用状態と人数の数え方は、原則として下記のとおりです。
- 常用労働者は1名相当、短時間労働者は0.5名相当とする
- 重度身体障害者(身体障害者手帳の等級が1級・2級の人)、重度知的障害者(療育手帳の区分がAの人)1人を常用雇用した場合、2名相当とする
- 重度身体障害者・重度知的障害者の短時間労働者は、1名相当とする
※短時間労働者の精神障害者は、2018年4月から設けられた特別措置により、下記1、2の要件を両方満たす場合は1名相当、満たさない場合は0.5名相当とする
- 新規雇用から3年以内もしくは精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合
- 2023年3月31日までに雇用され、精神障害者保険福祉手帳を取得した場合
例えば自社の法定雇用障害者数が4人の場合、合計して4名相当になればよく、常時雇用労働者4人あるいは、常時雇用労働者2人+短時間労働者4名など、複数の組み合わせが可能です。
障がい者雇用で陥りやすい失敗とは?
「ターゲットとしている層から応募がない」
「面接が適切に行えているか不安」
「採用してもすぐに辞めてしまう」
よくある失敗例をもとに、障がい者雇用における課題解決のヒントをまとめた資料をご用意しました。ぜひご活用ください。

法定雇用率が未達成の場合はどうなる?
法定雇用率未達成の企業が受ける扱いについて説明します。
障害者雇用納付金の徴収
企業が本来雇用するべき障がい者の人数が、法定雇用障害者数と比べて不足している場合、常用労働者101人以上の事業主は、不足している障がい者数1人につき毎月5万円を国に納付する義務を負います。
例えば法定雇用障害者数が4人の企業で常用労働者2人しか雇用できていない場合、納付金は毎月10万円です。
この納付金の目的は、障がい者の雇用数をクリアしている企業と未達成企業の経済的な負担を調整するものであり、罰金とは意味合いが異なります。従って、納付金を払っても障がい者を雇用する義務は残ることに注意が必要です。
ハローワークからの行政指導
従業員45.5人以上の事業所は、毎年6月1日現在の障がい者雇用状況報告をハローワークに提出しなければなりません。その中で実雇用率(実際に雇用している障がい者の割合)の低い事業主については、下記の流れでハローワークが雇用率達成指導を行い、「雇い入れ計画」の着実な実施を促します。
- 翌年1月から2年間の「雇入れ計画」を作成し、ハローワークに提出する
- 計画の実施状況が悪い企業に対して、雇入れ計画の適正実施勧告を行う
- 雇用状況の改善が特に遅れている企業に対しては、計画期間終了後の9か月間、公表を前提とした特別指導を実施する
- 最終的に改善が見られない場合、企業名が公表される
また、雇用者の不足数が特に多い場合は、当該企業の幹部に対して厚生労働省による直接指導も行われます。
企業名が公表される
厚生労働省では、法定雇用率未達成の企業名および、代表者名、所在地、業種を「障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について」として、厚生労働省のWebサイトやプレスリリースを通して公表しています。
法定雇用率未達成による企業名公表の影響
企業名が公になることによる企業が被るデメリットは次のとおりです。
企業イメージの低下
少子高齢化による労働力不足、消費の多様化などの環境変化に対応するために、企業におけるダイバーシティ&インクルージョン(多様な人材がその能力を発揮できるような企業風土をつくること)への取り組みが注目されています。
障がい者雇用の推進は、ダイバーシティ&インクルージョンに取り組む企業として対外的なイメージアップに繋がります。
法定雇用率未達成により企業名を公表された場合、「ダイバーシティ&インクルージョンに対して消極的」よりも、「法律を守っていない企業」として社会的に認知され、新規顧客の獲得に支障が出たり、取引先の企業や顧客から取引を敬遠されたりするなど、会社経営上のリスクになることもあり得ます。
採用計画や人員計画への影響
昨今では就職・転職を検討する企業のWebサイトをチェックするなど、ほとんどの求職者が事前に情報収集を行っています。障がい者雇用の義務違反をしている企業は、求職者から「法律を守らない企業」「柔軟な働き方ができない企業」として見られ、応募を敬遠する可能性があります。
現在、そして将来的な労働力不足で悩む多くの企業にとって、新規人材の採用は経営上重要な問題です。企業名公表によって応募者が集まらなければ、採用計画や人員計画が進まず、企業経営に大きなリスクをもたらすことも考えられるでしょう。
社員のモチベーション低下
企業名を公表された企業は、法定雇用率の未達成にとどまらず、年次有給休暇の取得率が低い、社員の事情に合わせた柔軟な働き方ができないなど、従業員の働き方についても労務管理上の問題を抱えているケースがみられます。その場合、企業名の公表がさらに従業員のモチベーションを低下させ、退職に繋がることもあります。
障がい者雇用を促進するには
障がい者採用のみに力を入れていても、社内の受入体制が整っていないと早期退職に繋がり、雇用の定着がはかれません。
障がい者雇用を促進するためには、次の項目について確認しながら受け入れるための準備をすすめましょう。
社内の理解を進める
障がい者雇用を推進するためには、まず事業主が「障がい者雇用の社会的意義」を把握し、企業の方針として従業員に浸透させる必要があります。
今まで従業員に障がいをもつ人がいなかった企業の場合、「接し方がわからない」「自分たちの仕事量が増えるのではないか」などの不安や不満が生じることがあります。
しかし、そのような先入観にとらわれず障がいの特性を把握することによって、業務配分、サポート方法やコミュニケーションの取り方などを工夫することが可能です。そのために障がいに対する知識を深める研修を行うことも有効な手段です。
採用計画を綿密に立てる
障がい者雇用を実施する場合、前もって採用時期や採用人数、待遇などの詳細な採用計画を立て、それに従ってすすめますが、採用後の担当業務を事前に決めておくことも必要です。企業によっては採用した人材に適した業務の割り当てができず、ケースもあります。
そのためにまずは、業務全体の職務を洗い出し細分化するところから始め、前もって配属部署と担当業務を決めます。その後、本人や家族などとの面談を通じて障がい特性や本人の能力を把握した上で、必要に応じて業務内容を一部変更するなどの調整を行います。
もう一つ大切なことは、障がい者が業務を行う部署の管理者に対して、障がい特性や本人の能力に合った指導や育成を担ってもらうことです。雇用定着率を上げるためには、管理者の役割が重要です。管理書へは健康上や業務上のトラブルが起きた場合の対処方法をはじめ、障がいを持つ人と接する際に特に気を付けておきたいコミュニケーション方法などの教育の機会や情報提供などを行う配慮が必要です。
サポート体制を整える
障がい者の就労に関しては、平等な機会や待遇を確保するための合理的な配慮が必要です。合理的配慮とは、障がい者が働く上で不都合が生じる場合には、働きやすいように労働条件や業務方法、職場環境などの調整や変更、見直しなどをすることです。
配慮事項は、事業主が障がい者または障がい者の家族の要望を聞き、双方で話し合いの上で配慮する内容を決めます。併せて、社内・関係者に対してしっかりと情報共有しておくことが大切です。
また入社時の研修、管理者や障害者職業生活相談員による定期的な面談など、フォローアップできる体制を整えましょう。
関連機関と連携を進める
障がい者雇用には、社内の受け入れ態勢を整えることが重要ですが、企業努力だけでは対処が難しいこともあります。
ハローワーク、障害者就労支援センターなどの障がい雇用のための就労支援機関との連携を持ち、相談やアドバイス、具体的な支援が受けられるような体制づくりを進めましょう。
障がい者雇用を支援してくれるサービスを活用する
障がい者雇用を行う場合、障害者雇用促進法や合理的配慮など法的な知識だけではなく、実際に受け入れるための体制づくりや定着のための施策など、専門的な知見がある方がスムーズに進みやすくなります。
また、障がい者採用を実施する際の人材要件設定や母集団形成、面接など一般的な採用とは異なる配慮や押さえておくべきポイントもあります。その場合、障がい者に特化した人材紹介や定着支援をしてくれるコンサルティングサービスなどを利用してみてもよいでしょう。
まとめ
法定雇用率は単に達成すればいいというものではなく、安定した雇用による人材の定着が重要です。障がいの特性や本人の能力に応じた適切な業務配分とサポートにより、業務の担い手として活躍できる場の提供ができるかどうかが法定雇用率達成の可否に大きくかかわります。
また、障がい者雇用の推進によって職場におけるダイバーシティ&インクルージョンが浸透し、職場環境の改善や柔軟な働き方の実現など、すべての従業員にとって働きやすい職場づくりに発展することで、離職率の低下や企業価値の向上など相乗効果が生まれることも考えられます。
労働力人口の減少するなか、障がい者雇用を法的義務の面からだけではなく、人材確保の観点から見ていくことがこれからますます大切になるでしょう。
こちらの資料もおすすめです
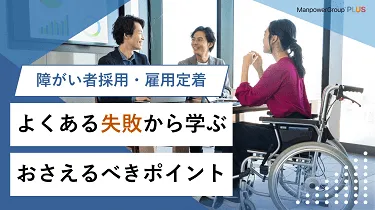

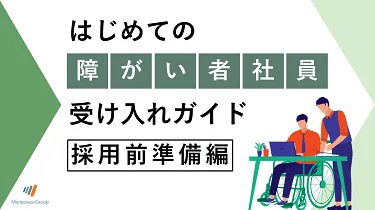
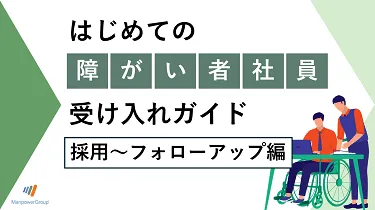



















 目次
目次