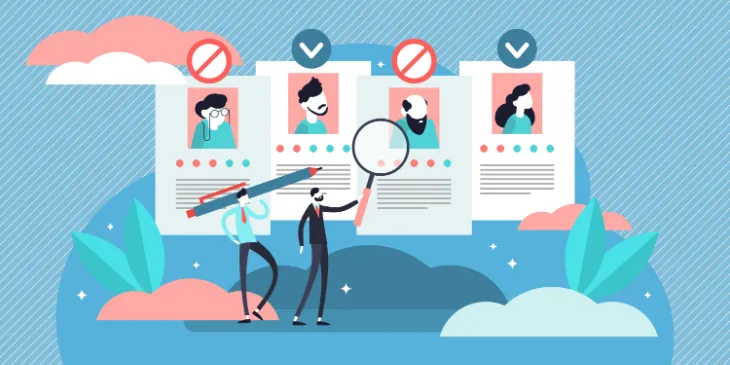


求人票で年齢制限を設けるのはNG?認められるケースについても解説
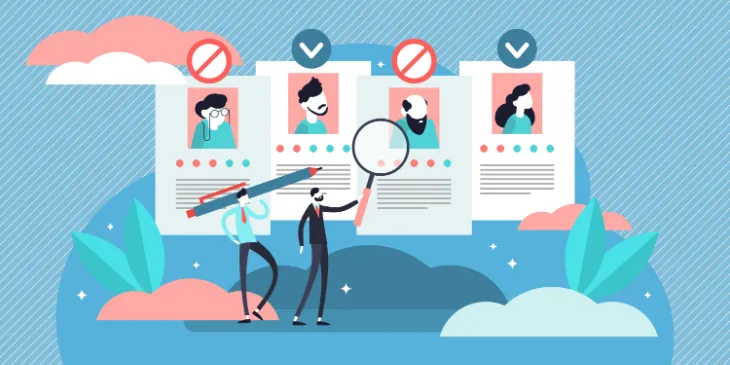
目次
「35歳までの方募集」「50歳以下の方募集」など、求人票への年齢制限の記載は原則として法律で禁止されています。現場で若年層の採用を望む声がある場合など、人事担当者は「どこまでが違法なのか」「例外的に認められるケースはあるのか」を正しく把握し、適切に対応する必要があります。
そこで本記事では、年齢制限に関する法的ルールを整理し、適切な求人募集を行うためのポイントを解説します。
採用時に年齢制限を設けることは可能?

まずは、採用時に年齢制限を設けること自体が法的に認められているのかという点について解説します。
求人募集で年齢制限をすることは原則的に禁止されている
2007年10月に雇用対策法(現:労働施策総合推進法)が改正されたことにより、求人募集での年齢制限が禁止されました。求人募集での違法な年齢制限は行政指導の対象となり、企業名が公表されることもあります。
禁止されている年齢制限は、「30歳未満の方募集」「40代以下の方募集」のように明確な年齢を表すものだけではありません。以下のようなものも同時に禁止されています。
NG例
- 「35歳くらいの方募集」「30歳前後の方募集」のように境界をぼかしたもの
- 「40歳以上の方歓迎」「35歳未満の方歓迎」のように制限とまでは言えないが他の年齢層に比べて優遇されていると捉えられるもの
- 「業務経験30年以上の方募集」のように事実上の年齢制限と捉えられるもの
求人募集による年齢制限の禁止は、ハローワークの求人票をはじめ、民間の求人媒体、自社ホームページでの募集まで、募集方法を問わず適用されます。また、募集する人材の雇用形態も問いません。すべての求人募集で適用されます。
求人票に「年齢不問」と記載していても、年齢を理由に応募を断る、以降の選考で年齢を理由に採用判断を行うことも、違法行為と扱われます。表向きだけ「年齢不問」とするだけでは不十分で、募集から採用決定までの全プロセスで年齢制限が禁じられていることも注意したいポイントです。
年齢制限が禁止されている理由
年齢制限が禁止されている主な理由は、年齢による差別を防ぎ、働く意欲と能力のある人材の機会均等を保障するためです。年齢に関係なく多様な人材が活躍できる職場環境の実現を目的としています。
年齢制限の撤廃で応募者の幅が広がるため、少子高齢化における労働力不足の解決に寄与すると期待されています。
例外として年齢制限が認められるケース
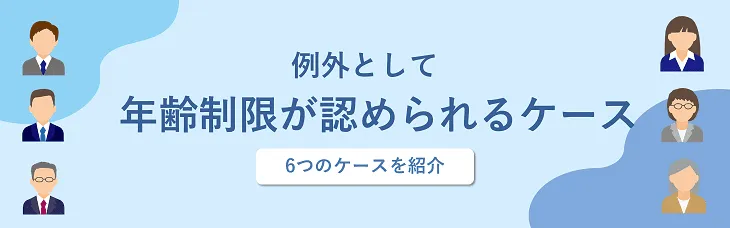
年齢制限は原則禁止ですが、例外として年齢制限が認められるケースが法令で定められています。つまり、法令で認められた場合を除き、それ以外の理由で年齢制限を設けることはできません。例外的に年齢制限が認められるケースは次の6つです。
- 定年年齢を上限として募集・採用する場合
- 労働基準法その他の法令の規定により、年齢制限が設けられている場合
- 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から若年者を募集する場合
- 技能・ノウハウの継承のために特定の年齢層を募集する場合
- 芸術・芸能の分野で特定の年齢層を募集する場合
- 雇用管理上の理由による特定年齢層を募集する場合
定年年齢を上限として募集・採用する場合
次のいずれも満たす場合には定年年齢を上限とした年齢制限が認められます。
- 定年がある
- 期間の定めのない労働契約
例えば、定年が65歳の企業で「65歳未満の方募集」とすることは問題ありません。しかし、「65歳未満の方募集(1年契約で更新あり)」のような有期契約だと、上記条件の「期間の定めのない労働契約」を満たさないため認められません。更新を続ければ期間の定めがない労働契約にも見えますが、契約自体は有期契約のため、定年年齢を上限とした制限ができません。
また、「40歳以上65歳未満の方募集」のように下限を設けること、定年が65歳だが「60歳未満の方募集」のように実際の定年年齢ではない年齢を上限にすることもできません。
| 募集内容の例 | 雇用形態 | 可否 |
| 65歳未満の方の募集 (定年が65歳の場合) |
無期雇用 | OK |
| 65歳未満の方の募集 (1年契約で更新あり) |
有期雇用 | NG 有期雇用がNG |
| 40歳以上65歳未満の方の募集 | 無期雇用 | NG 40歳以上がNG |
| 60歳未満の方の募集 (定年は65歳の場合) |
無期雇用 | NG 65歳未満ならOK |
近年では、高年齢者雇用安定法の改正により定年制を廃止する企業もあり、そういった企業では当然この例外ケースは適用されません。
「定年後を見据えた人事制度設計とは」を資料ダウンロードする >>
労働基準法その他の法令の規定により、年齢制限が設けられている場合
法令で年齢制限がかけられている業務があります。こうした業務に従事する人を募集する場合には、年齢制限を設けても問題ありません。企業が法令違反で罰せられないよう、募集段階から適切な年齢制限を設ける必要があると言えます。
例えば、満18歳未満は22時~翌5時の深夜業が、原則禁止されています。そのため、コンビニやレストランの深夜時間帯の人員募集で「18歳以上の方募集」と記載することは認められます。
年齢制限のある業務の一例は次のとおりです(いずれも満18歳未満は禁止)。
- 有害物質や危険物を取り扱う業務
- 坑内労働
- 警備業務
- 深夜業(22時~翌5時)
なお、これらの業務でも「20歳以上の方募集」など、法令で定められた禁止年齢以外の年齢制限は禁止されています。
長期勤続によるキャリア形成を図る観点から若年者を募集する場合
新卒一括採用と長期雇用を前提とする日本の雇用慣行との調和を図るため、若年層(おおむね35歳未満)に限定した年齢制限が例外的に認められています。これは、自社内での育成とキャリア形成を前提とする制度設計であり、かつての就職氷河期世代のように、若者が正規雇用の機会を得られないまま年齢を重ねる事態を繰り返さないための措置でもあります。
次の要件をすべて満たす場合に、若年層の年齢制限が認められています。なお、若年層とは35歳未満が想定されていますが、あくまで目安で必ずしも35歳未満に限られるものではありません。
- 対象者の職業経験は不問
- 新卒者と同等の育成環境や配置
- 期間の定めのない労働契約
一例
例えば、「35歳未満の方募集(経験不問)」や「令和7年3月大学卒業見込みの方募集」のような記載は認められています。新卒者のみを募集する場合、卒業年の記載は年齢制限にあたりません。
一方で、「35歳未満の方募集(1年契約で更新あり)」のような有期契約だとこの例外ケースは認められません。また、「35歳未満の方募集(1級建築士保持者)」のように実務経験がないと取得できない資格を条件に付与する、「20歳以上35歳未満の方募集」のように下限年齢を設けることもできません。
なお、業務上必要であっても、取得に実務経験を要しない資格であれば、「要普通運転免許」のように募集条件に含めることができます。
技能・ノウハウの継承のために特定の年齢層を募集する場合
社内の年齢構成が偏っており、特定の年齢層に技能・ノウハウ継承が必要な場合には、次の条件を全て満たせば年齢制限が認められます。
- 技能、ノウハウの継承が必要となる職種
- 上下の年齢層と比較して労働者が1/2以下の年齢層がある
- 2.の1/2以下の年齢層は30~49歳のうち5~10歳幅の年齢層
- 期間の定めのない労働契約
一例
例えば、福祉事業サービスを提供する企業で社内のホームヘルパーの人数が次のようになっている場合、30~39歳が前後の年齢層である20代・40代と比べて1/2以下であり、条件①~④をすべて満たすため、「ホームヘルパーとして30~39歳の方募集」という記載が認められます。
- 20~29歳 10人
- 30~39歳 2人
- 40~49歳 8人
一方、同じ例で「ホームヘルパーとして25歳~39歳の方募集」とすると上記条件③の年齢層も年齢幅も満たさないため認められません。また、30~39歳が6人いる場合には、上記条件②を満たさなくなるため求人募集で年齢制限はできません。
芸術・芸能の分野で特定の年齢層を募集する場合
ドラマや演劇で子役を募集するケースでは「子役のため10歳以下の方募集」のように年齢制限が認められます。具体的には、子役の役者、子役のモデルが挙げられ、それ以外の業務の募集では年齢制限を行うことはできません。
雇用管理上の理由による特定年齢層を募集する場合
高年齢者や就職氷河期世代など、就労が不安定になりやすい層への雇用促進を目的として、特定の条件に限り年齢制限が認められる例外があります。具体的には、以下の2つのケースです。
60歳以上の高年齢者に限定する
「60歳以上の方募集」の記載は認められます。ただし「60歳以上70歳未満の方募集」のように上限を設けることはできません。
特定の年齢層の雇用を促進する国の施策を活用する
特定の年齢層の雇用と人材開発を国が促進するために、特別な施策(助成金・補助金等)を設けていることがあります。例えば、「人材開発支援助成金」の中には対象労働者の年齢が「15歳以上45歳未満」と定められているコースがあります。このような助成金を利用する場合、該当の助成金制度の対象年齢で、求人募集時に年齢制限を設けることが認められています。
具体的には、「15歳以上45歳未満の方募集(人材開発支援助成金の対象者)」のような記載ができます。ただし、「15歳以上35歳未満の方募集(人材開発支援助成金の対象者)」のように制度で決められた年齢層以外の下限・上限を定めることはできません。
なお、年齢制限が認められる施策は厚生労働省が公表しており、2025年4月1日現在、18の施策(助成金・補助金等)が指定されています。指定されていない施策を理由にした年齢制限はできません。
年齢制限を設ける際の注意点
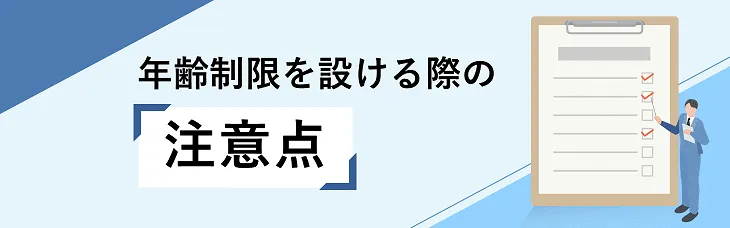
設けようとしている年齢制限が、法令上認められた例外に該当するかどうかは必ず確認してください。
また、年齢制限が例外的に認められているケースでも、65歳未満の上限年齢を設定する場合には、応募者と職業紹介事業者(ハローワーク、転職エージェント等)に理由を提示することが義務付けられています。義務がないケースでも、求人票に年齢制限の理由を明記しておくことで、年齢制限が法令に則ったものであることを明確にでき、トラブルの防止にもつながります。
求人募集では性別も制限することができない
男女雇用機会均等法により、求人募集における性別の制限も禁止されています。例えば、次のような表現は、性別制限とみなされます。
- 「男性3名、女性1名」のように性別ごとに異なる募集人数
- 「男性は大卒以上、女性は高卒以上」のように性別で異なる条件
- 「看護婦」「営業マン」「ウェイトレス」のように性別を絞った名称
上記例や「男性限定」「女性歓迎」のような直接的な表現はもちろん、「身長170cm以上」のように直接性別を指定していないが、どちらかの性別に明らかに偏るような表現も性別制限と捉えられる点は押さえておきましょう。
なお、年齢制限と同様、法令により性別により制限・禁止されている業務の性別制限については、当然問題ありません。例えば、坑内労働や危険有害物質を扱う業務などが該当します。
人材選考における年齢に関する先入観の影響
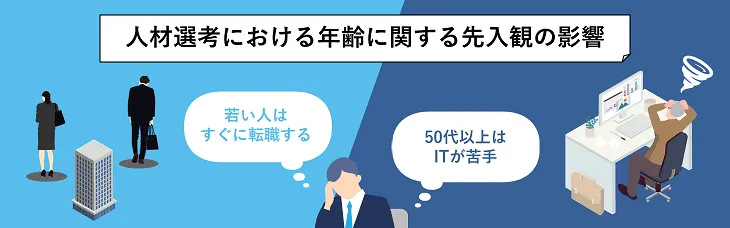
年齢に関する先入観が、採用判断に影響を与えていることもあります。よくある先入観には次のようなものがあります。
- 50代以上はITが苦手
- 中高年層は新しい技術についていけない
- 若い人はすぐに転職する
- わが社の社風に合うのは20~30代
しかし、年齢はスキル、意欲、定着力とは直接的な関係はありません。「若手はこういう傾向がある」「ベテランは必ずこう考える」という先入観は、採用の幅を狭めてしまいます。採用難と言われるなか、こうした先入観が結果的に自社の採用機会を狭めてしまっている可能性もあります。
年齢に関する先入観を排除した採用事例
「若い世代が入社した方が職場に活気が出る」「全員が30代以下の企業なので、40代以上を採用しても指導しにくいだろうし、浮いてしまう」との理由で40代以上の採用を敬遠していた企業のケースです。
募集時の年齢を不問とし、人柄や意欲を重視して40代の人材を採用したところ、年下上司の指導も謙虚に耳を傾け、誠実な仕事ぶりが他の従業員の刺激になっています。
また、「重労働は高年齢者には無理だろう」と考えていた企業で、重量物を配送するトラック運転手の募集で年齢を不問とした結果、経験が豊富な50代の人材を採用できたという事例もあります。
このように仕事の意欲、人柄、体力は個人によって異なり、年齢だけで判断することはできません。年齢だけにとらわれると優秀な人材を見逃すリスクを高めるため、その人の本質を見極める採用が重要です。
年齢にとらわれない“人材の見極め方”とは

選考では、年齢という一部の情報にとらわれず、個人の能力や経験、ポテンシャルを正しく見抜くことが必要です。以降では、年齢にとらわれない人材の見極め方の一例を紹介します。
「なぜ応募したか」を深掘る
選考での志望動機の確認は、深堀りすることで、その裏にある価値観やキャリア観を確認できます。本気で自社に興味を持っているのかの見極めは、年齢に関係なく、自社に合った人材かどうかを確認する第一歩になります。
【質問例】
- この職種を選んだ理由を具体的に教えてください
- 当社について調べて、最も印象に残ったことは何ですか?
- 当社に興味を持ったきっかけをもう少し詳しく教えてください
さらに深堀りをする際には、「先ほどはこうおっしゃっていましたが、いかがですか?」と矛盾点を確認する、「もう少し具体的に教えてください」と追加質問をする、「なぜそう思ったのですか?」「そのときどう思いましたか?」と感情面を聞くなどの問いかけが効果的です。
「行動」に注目する
過去にどのような行動をとったか、問題をどのように解決したかに注目すると、その人がどのように課題に向き合い、チームにどんな形で貢献してきたかを具体的に把握できます。こうした実際の行動について知るようにすると、年齢にとらわれず、その人の問題解決力や協調性などを判断しやすくなります。また、「今後どのように行動するか」の未来の話だと、理想を並べることがいくらでもできるため、「過去の行動」が注目するポイントです。
【質問例】
- これまでの仕事で最も工夫したことは何ですか?
- 過去の仕事の失敗から学んだことを教えてください
- これまでの仕事で1番の困難は何ですか?それにどう対応しましたか?
- これまでチームで意見が対立したときに、どのように解決しましたか?
カルチャーフィットの確認
企業の価値観や仕事の進め方に合う人材かを見極めることは、ミスマッチを防ぐためにも重要です。現に、スキルよりも「一緒に働ける人か」を重視する企業が増加しています。年齢よりも「どう考え、どう動く人か」を知ることがポイントです。
【質問例】
- 理想のチームや理想の職場環境を教えてください
- 仕事でやりがいを感じる瞬間・ストレスを感じる瞬間はどんな状況のときですか?
- 周囲から反対されても信念を貫いたことはありますか?そのときの状況を教えてください
- 個人の成果とチームの成果のどちらを優先しますか?その理由も教えてください
変化への対応力や学ぶ姿勢
社会も企業も変化し続けていきます。「変化に対応できる人か」は年齢関係なく必須能力とも言えるでしょう。「実際に変化に対応できるか」ではなく「新しい物事を吸収する気持ちがあるか」を丁寧に見ると良いです。
【質問例】
- 最近、新しく覚えたことはありますか?どんな状況でどのように覚えましたか?
- これまでと異なる企業文化の会社で働くことについて、どう思いますか?
- これまでの仕事で最も大きな変化があった時の状況と、その変化にどう対応したかを教えてください
- 知らないことや使ったことのないツールに出会ったとき、どう対応しますか?
“意欲と定着意志”のチェック
転職が前提のケースもあるため、「今後どう働きたいか」「この仕事をどう続けていきたいか」に注目することで、入社後の意欲と定着意志を確認することも大切です。
【質問例】
- 入社して5年後、10年後にどんな働き方をしていたいですか?
- この職種でどのようなキャリアプランを考えていますか?
- 当社でどのような成長を期待していますか?
複数名で判断する
年齢にとらわれず、その人の本質を重視した選考を行うには、複数名での判断が効果的です。先入観は個人の経験等に基づいて生まれるため、人1人の評価に頼るとバイアスがかかる可能性があります。
例えば、「この人は若いので経験不足で不安」と感じる担当者もいれば、「新しい発想力を持つので期待できる」と前向きに捉える担当者もいるかもしれません。このような複数の考え方を総合的に判断することで、バランスがとれ、客観的な選考に繋がります。
面接官のための実践ガイドブック
採用の成否を左右する面接。その精度を高めるための「面接官のための実践ガイド」をご用意しました。面接官の基本スキルから評価基準の明確化、質問例まで、すぐに活用できる実践的な内容です。
<この資料でわかること>
・ 面接官として必要な基礎スキル
・ 候補者を見極めるための質問・評価のポイント
・ 面接官としてのNGな行動と態度
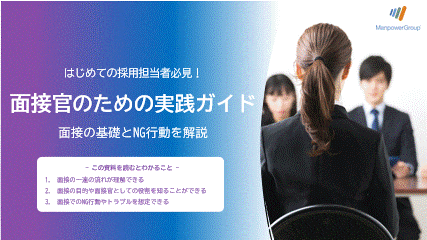
まとめ
例外的に認められているケースが一部あるものの、求人募集での年齢制限は原則として禁止されています。年齢制限を設ける前には、必要性の有無だけでなく、法的な妥当性も必ず確認し、社内で根拠を共有したうえで判断しなければいけません。
安易な年齢制限は採用難を深める一因です。年齢による先入観にとらわれず、意欲や姿勢、経験その人の本質を見極める採用への視点の切り替えが重要です。






















 目次
目次