


採用支援サービスの種類と選び方を徹底解説

目次
採用を強化したいものの、自社内のリソースが不足している、新卒採用をはじめたばかりでノウハウがないなどのお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では採用支援サービスの概要から活用例、採用支援サービスを提供するベンダーの選び方まで、はじめて採用支援サービスを検討する際の基礎知識を解説します。
採用支援とは?
「採用支援」とは、採用担当者が担う企画立案・広報・データ管理・選考・応募者との連絡・研修など、採用に関する業務の一部を代行するサービスを指します。
採用支援サービスはインターネットを通じた就職・転職活動が中心となり始めた2000年頃から徐々に増え始め、ここ数年は若年層の労働力人口不足を背景に、企業規模や業種を問わず導入を検討が拡がっています。
採用支援サービスを提供するベンダーにはそれぞれ強みがあり、自社の採用を成功に導くためには採用支援のどの分野を中心に委託するべきか、慎重に検討する必要があります。
関連記事: 新卒採用コンサルティングサービスのメリットと主なサービス内容を解説
関連資料: 「採用代行とは?」をダウンロードする
採用支援サービスの種類と内容
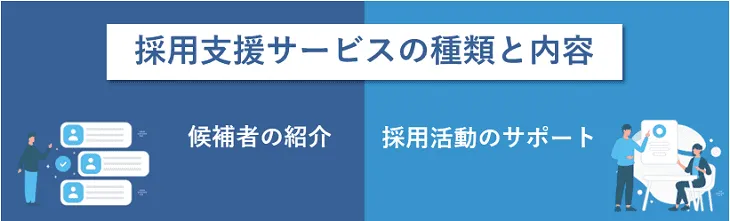
まずは、採用支援サービスの種類とその内容について確認しましょう。
採用支援サービスは大きく「候補者の紹介」と「採用活動のサポート」にわけることができます。二つの分野をそれぞれわかりやすく解説します。
候補者を紹介してほしい
母集団形成における支援は、多岐にわたります。特に昨今の人手不足では、外部サービス・支援をどう活用していくかが重要です。採用人数や職種に地域、求める人材像によって、母集団形成の難易度を見極め、適切な施策を立案するには知見が必要です。
求人媒体
求人媒体とは、求人情報を集約・公開し、応募者を集めるメディアのことです。ターゲットに合わせて、さまざまな種類があります。その代表的なサービスをピックアップして紹介します。
- 新卒者向け就職ナビサイト(マイナビ、リクナビ、キャリタスなど)
- 経験者向け転職ナビサイト(マイナビ転職・リクナビNEXT、dodaなど)
- 求職情報特化型検索エンジン(Indeed、Google求人など)
- 新聞求人広告欄、折り込みチラシ、フリーペーパーなどの紙媒体
- インターネットハローワークサービスなどの公的職業紹介情報
- 民間企業主催の有料合同企業説明会など
求人媒体の特徴・共通点は「メディアに求人情報を出稿し、それを見た求職者の応募を待つ」というスタイルです。メディアの種類が多いため、出稿する記事の内容やタイミング、出稿する媒体の選定などの工夫が求められます。
求人媒体は基本的に「広告出稿」の費用が発生します。ターゲットに対して自社の魅力をうまく訴求できれば、効率よくたくさんの応募を集められますが、結果として採用に至らない場合でも出稿料として費用が発生する点に注意が必要です。
なお、Indeedなど無料掲載が可能な媒体も増えており、いかに多数の求人の中から自社の情報にたどり着いてもらうかがポイントになります。
人材紹介
人材紹介は「有料職業紹介」とも呼ばれ、成功報酬型で企業と求職者のマッチングを行うものです。応募者への広報・母集団形成・書類選考などの一次スクリーニングを人材紹介会社が代行してくれるため、企業は面接選考に集中できます。
人材紹介は、企業が合格を出し求職者が入社を決定するまで費用は一切発生しません。また、人材紹介会社との契約内容によっては、入社数か月以内など早期離職に至った場合、一定額を返金する仕組みもあります。
成功報酬費用の相場は一般的に想定年収の30%前後です。求めるスキルや経験、転職市場の状況によってパーセンテージの設定が異なる場合があります。
人材紹介は告知や母集団形成の手間がかからず、採用に至らない場合の費用のリスクがないため、報酬は求人媒体と比較すると高額になるケースが多くなります。
ヘッドハンティング
ヘッドハンティングはその名の通り、企業の人材要件に合致する人材をヘッドハンティング会社がリサーチしてスカウトを行う「声かけ」型のサービスです。
前述の人材紹介と仕組み似ていますが、ヘッドハンティングは転職を希望していない層もターゲットとし、転職市況では見つからないキャリアや資格、スキルを持つハイクラス人材を対象にしているのが大きな違いです。
そのため、報酬も想定年収の40%~60%程度と比較的高額で幅があるのが特徴です。また、着手金が発生します。(着手金は成功報酬ではない)
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングとは、企業が求職者の応募を待つのではなく、条件に合った求職者を探して直接アプローチする求職手法です。
大きく分けて以下の3種類の手法があります。
- ダイレクトリクルーティングサービスのデータベース
- X(旧Twitter)などのSNS
- 社員などの紹介
このなかで、最も認知度の高い方法がダイレクトリクルーティングサービスの活用です。代表的なダイレクトリクルーティングサービスを紹介します。
| 会員数 | 特徴 | 費用 | |
| ビズリーチ | 236万人以上 | 管理職など経験者採用が 強み |
基本利用料と成果報酬 |
| doda Recruiters | 237万人以上 | さまざまな職種経験者が 登録 |
基本利用料 |
| リクルートダイレクトスカウト | 非公開 | 専属のヘッドハンターが 人選・スカウトを実施 |
年間利用料と成果報酬 |
ビズリーチのような「求職者のデータベースをもつダイレクトリクルーティングサービス事業者」のサービスでは、データベースの中から自社の求人要件に合致する人物を企業側が検索し、求職者1人一人にスカウトメッセージを送信することができます。
求職者は送信されるスカウトのなかから自分の希望に合致した会社を選び、応募するか判断する流れです。現住所や希望職種、希望年収と言った属性だけでなく、登録内容に応じて個別にアプローチすることで、よりミスマッチのない採用の可能性が高まります。
ダイレクトリクルーティングサービスの料金体系はさまざまで、初期費用が安価もしくは無料であることが多く、成功報酬との組み合わせのパターンもあります。人材紹介と比較すると1件あたりの成功報酬が安価であることが大きなメリットです。
WantedlyやLinkedinのようなビジネス向けSNSを利用する場合、アカウントを作成し、個別にメッセージを送る機能は無料でスタートできます。
しかしながら、ダイレクトリクルーティングはPR力が必要であり、母集団形成ツールのなかで最も工数のかかるものになります。
人材派遣
直接雇用ではありませんが、人材派遣も労働力を確保するための採用支援サービスのひとつです。
一時的な労働力を確保したい、支社支店・部署ごとに細かなニーズに合わせた人員配置を行いたいといったニーズに合わせて人材を配置できます。ただし、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院・診療所などにおける医療関連業務など、派遣法で定められた禁止業務があります。
また、派遣期間を通じて業務適性や社風とのマッチングを見極め、派遣期間終了後に直接雇用することを前提とした紹介予定派遣を活用するなど、人材派遣を通じた採用も可能です。
人材派遣の料金は、時間単価の場合が多く派遣社員の就業時間で計算され、毎月請求があります。
参考記事:人材派遣の料金・費用|相場のつくられ方と仕組みを解説
採用活動をサポートしてほしい
初めて本格的な採用活動に取り組む、大幅な採用人員増を計画している、従来の採用とは異なるターゲットの採用を実施するなど、自社内のリソースでは採用活動に対応できない場合、採用活動そのもの、あるいは一部を外部の専門業者に委託することができます。
さまざまな代行業者があり、業者によって得意なサポート範囲や対応可能なエリアが異なります。
ここでは、代表的なサポートサービスを3つ紹介します。
採用代行
採用代行はRPO(Recruitment Process Outsourcing)とも呼ばれ、事務的な作業や応募者との諸連絡、説明会の運営、面接の代行など、採用に必要な工程の一部または全部を代行してもらうことができます。
採用難や人材の流動化を背景に、採用手法や採用メディアの多様化・複雑化し、採用は難しくなるのに、業務は増えるという傾向がでています。限られた人員で採用活動を行い、また成果を出す目的で導入する企業は増えています。
採用代行で依頼できる業務例
- 採用問い合わせ窓口(メール・電話)
- 応募者データの一元化
- 応募書類受付、管理
- 応募書類の選考
- 求人募集広告の作成
- 大学やハローワークへの求人票手配
- 学校訪問
- ダイレクトリクルーティングでのスカウトメール対応
- エントリー者への随時レスポンス
- 説明会会場の手配~会場設営~当日運営
- 面接/筆記試験会場の手配~会場設営~当日運営
- 書類選考代行
- 面接代行
- 合否連絡
- 内定者フォロー
- 内定者研修
採用コンサルティング
採用コンサルティングとは、採用課題の分析から採用戦略や施策の立案、面接官トレーニングなど、採用全般のコンサルティングを行うサービスです。
コンサルティングの一例
- 中長期経営計画から策定した人員計画に基づいた採用計画の立案
- 同業他社の動向など、採用市場のリサーチとリポートを作成
- 採用課題の発見と解決策の立案
- 採用成功に向けた運用体制構築
- 人事採用担当者への採用手法レクチャー
- 母集団形成に向けた採用広報手法の策定
- 採用計画の進捗確認と修正対応
- 選考基準の策定
- 面接を担当する役職者や社員を対象にした面接官トレーニング
- 採用力向上のための社内労働環境改善や社内制度整備の提案
依頼するコンサルティングの対象が広範囲になればなるほど、多くの費用が必要になりますが、採用コンサルティングのみで発注するケースよりも、採用代行のサービスの一部として上記コンサルティングが付帯するケースも多く見られます。
実施した業務量に応じた従量課金制、コンサルティングフィーを基本料金に含める月額制、採用が成功した人数で精算する成功報酬制など、あるいはそれらを複合的に組み合わせるなど支払い条件も様々なため、費用の決済方法と提供されるサービスの範囲、免責部分など、ベンダーの選定の際は比較検討項目をしっかり把握しましょう。
新卒採用代行・コンサルティングサービスの資料をみてみる >>
採用管理システム
採用管理システムとは、応募者の個人情報管理のデータベース、受付システム、連絡ツールなどを一元的に管理、効率化するシステムのことです。
採用管理システムは、ATS(Applicant Tracking System):応募者追跡システムとも言います。応募者がどのようなルートで自社に応募し、その後どのような選考ステップにいるかリアルタイムに把握でき、面接の日程管理や面接評価など情報の更新履歴を残すことが可能。応募者一人一人の情報管理から全体の進捗状況の把握まで管理できます。
このような採用管理システム自体は、特に新卒採用の場面で数十年前から活用されてきましたが、近年の応募窓口の多様化、複数化、採用選考の長期化などを背景により細かい進捗管理ができるよう、さまざまな機能が追加されています。
簡易な機能で利用制限はあるものの、無料で導入できる採用管理システムが増えていることもあり、これまで採用管理システムを利用していなかった少人数採用の中小企業にも広がりを見せています。
有料の場合でも比較的安価な月額料金制のもの、単年度のごとの買い切りのもの、自社サーバで運用を行うオンプレミス型のものなど、ニーズに合わせた多様な選択肢があります。
「新卒採用の人手が足りない」の解消・サポートに
新卒採用は小さな作業が膨大に発生し、結果的に採用担当者の工数を圧迫しやすい傾向にあります。また、母集団形成が難しく、継続的な改善や新しい手法を取り入れるなどの活動も必要です。
マンパワーグループでは、多くの企業の新卒採用を支援した実績で得たノウハウで、新卒採用をサポートします。下記のようなお悩みの方は、新卒採用コンサルティングや採用代行をご検討ください。
「ナビからの応募が減ってきている気がする」
「なにを伝えれば響くのかわからない」
「事務作業が多すぎて、学生とのコミュニケーションに時間を割けない」
<この資料でわかること>
・ 新卒採用支援サービスの提供内容
・ 採用成功に向けたプロセスとポイント
・ 支援実績や導入事例のご紹介

採用支援サービスの活用例

以上のように、採用支援サービスはさまざまな人材サービス事業にまたがるように展開しており、自社のニーズに合わせて使い分けることになります。
それぞれのケースでどのような採用支援サービスを選ぶべきか、活用例を紹介します。
事例1. 初めて新卒採用を行う
はじめて新卒採用を行う場合、新卒採用の知識が不足している、経験者採用や労務管理などを兼務していて、実務を担うのは現実的ではないというケースもあるかもしれません。
このような場合におすすめしたい採用支援サービスは、次の2つです。
- 採用コンサルティング
- 採用代行サービス
採用コンサルティングで得られるメリット
新卒採用はスポットで実施できる経験者採用と異なり、年度の単位で計画が必要であり、その年によって学生の動きや効果的な広告媒体のトレンドも変化します。また、採用エリアや募集対象となる学部学科などによって、異なる対応が必要なケースもあります。
採用コンサルティングでは、多数の実例からベンダーが得た経験や、最新の採用トレンドをもとに、自社の個別状況に合わせた施策を立案できます。
採用代行で得られるメリット
多くの場合、新卒採用では一度にたくさんの応募者の対応を行わなければなりません。また、ピーク時とそれ以外の時期によって業務量が大幅に異なるため、必要な採用担当スタッフ数も変化します。
採用業務を圧迫しがちな面接の調整や採用事務など周辺業務の委託で、業務負荷による採用活動の品質低下や活動量の不足を防ぎ、採用目標達成に近づけることが可能です。
事例2.管理職の後任を採用したい
管理職が近々退任を予定しているが、社内から管理職に登用できる人材がいない、新事業を立ち上げるので社内にはない知見をもった人材が必要といったケースでは、次の採用支援サービスが活用できます。
- 人材紹介
- ヘッドハンティング
- ダイレクトリクルーティング
優秀な管理職経験者の採用では、自社サイトやハローワークなど、コストをかけずに応募を待つ採用は現実的ではありません。
また、求める人材要件によってどの採用支援サービスを利用するかが重要です。
チームリーダークラスであれば、人材紹介サービスを中心に活用してみるとよいでしょう。幹部クラスの場合、転職市況では見つかりにくいため、ヘッドハンティングを検討してください。幹部クラスのミスマッチは経営への影響が大きいため、時間とコストをかけるべきです。
ダイレクトリクルーティングは、採用担当者のスキルと活動にかける時間の確保が成功のカギです。しっかり注力できると、コストを抑えつつ良い人材を採用する可能性がでてきます。
事例3.繁忙期だけ人手がほしい
繁忙期やイベント対応など一時的に人手がほしい場合、「必要な時期に人員が揃っていること」「人件費の側面から期間限定であること」という条件が発生します。
この場合、次の2つの採用支援で一時的な人員補強が可能です。
- 人材派遣サービス
- 求人媒体で期間限定の社員を募集
人材派遣サービスのメリット
人材派遣は自社で直接雇用する必要がなく、業務に適した人材が紹介されます。給与支払いや社会保険料の手続きなどが不要で、採用のためのコストも抑えることができます。
また、時短勤務や週3日勤務、2か月間だけなど、必要に応じて契約期間をフレキシブルに設定できることも大きなメリットです。
ただし、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院・診療所などにおける医療関連業務など、派遣法で定められた派遣禁止業務があること、契約で定められた以外の仕事を指示はできないこと、日雇い派遣は原則禁止であることに注意が必要です。
求人媒体で期間限定の社員を募集
いわゆるアルバイト・パートスタッフを含む・自社で直接雇用するため、適正な人件費に調整しやすいことがメリットです。
また、単発~30日以下の仕事を依頼したい場合、人材派遣の利用は厳しくなります(日雇い派遣の原則禁止)。
直接採用の場合、採用コストと労務管理が必要であること、必ずしも期待通りの応募が集まらない場合もあることに注意が必要です。
事例4.煩雑な応募者・選考管理をどうにかしたい
自社サイト内の採用ページやハローワーク、転職サイトへの募集広告出稿にSNSを活用した採用、社員からのリファラルなど、ターゲットや時期、応募者の利便性を増やすために応募窓口対応が年々煩雑なものとなっている……というケースは、企業規模や採用職種に関わらず増えています。
この場合、次の2つの採用支援を検討する余地がでてきます。
- 採用管理システムの導入
- 採用代行
まずは採用管理システムを使って応募者データの一元化に取り組むことからはじめましょう。採用管理システムで応募者とのやりとりのタイムラグを減らし、抜け漏れをなくすだけでも、採用効率が大幅に改善することがあります。
また、採用代行サービスを活用し、膨大な事務処理を委託したり、採用管理システムの導入支援やマニュアル作成などをしてもらうのもよいでしょう。
採用支援サービスの選び方
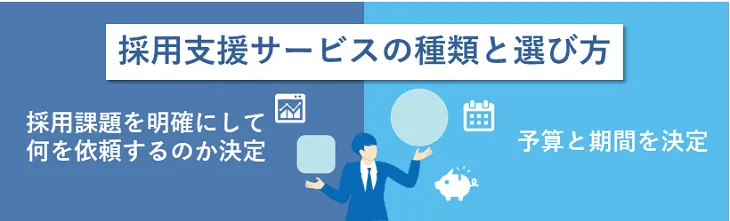
最後に、さまざまな採用支援サービスのなかから、どのようにサービスの種類を選ぶべきか、2つのポイントを解説します。
採用課題を明確にして何を依頼するのか決定する
漠然と「採用を成功させたい」という発注でベンダーにすべてを任せてしまうことはおすすめできません。ベンダーによっては、サービス内容と解決したい課題がマッチしないこともあるからです。
現状の課題が曖昧な場合、必要以上に広報に予算をかけてしまう、オーバースペックな運用オペレーションを組んでしまうなどのリスクがでてきます。
複数のベンダーと話す機会を設け、自社の状況を簡単に伝え、他社事例を踏まえながら課題をクリアにしていくこともおすすめです。
ベンダーに共有することの一例
- 現状の採用手法と結果
- 採用体制と採用フロー
- 理想とする採用人物像
- 直近の採用人物像
- 現時点での採用計画
予算と期間を決定する
採用代行サービスは、種類によってかかる費用が大きく変わります。特に、採用コンサルティングや従量課金制の採用代行は価格幅が大きくなりがちです。
自社が設定する採用コストが世間と比較して著しく乖離していないか確認しつつ、投資できる範囲の予算を設定します。
もう一つ、採用代行サービスの選択肢を決めるのが採用活動を実行できる期間です。募集開始から入社までどれくらいの期間の余裕があるかも、選択肢に大きな影響を与えます。短期的なスポット採用計画だけではなく、中長期的な人員計画に基づいた採用を検討しましょう。
まとめ
採用支援サービスは大きく分けて「候補者の紹介」と「採用活動のサポート」の2分野があり、それぞれの分野の中で複数の選択肢があります。
企業のニーズによって選択・組み合わせるべきか、一気通貫で依頼すべきか、それを判断するためには自社の抱える採用課題を適切に把握することが第一歩です。
採用支援サービスベンダーの事業範囲はもちろん、これまでの成功事例や強みを発揮してきた事例について詳しく情報収集しましょう。情報収集を通じて、自社の採用課題が改めて浮き彫りになるかもしれません。
こちらの資料もおすすめです



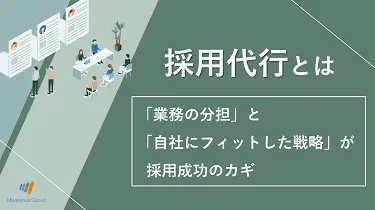
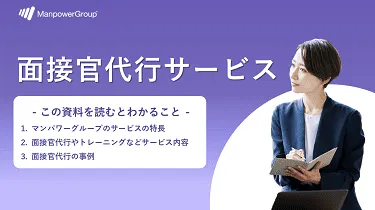


















 目次
目次