


正社員・パート・派遣の違いを徹底比較|業務や人件費に応じた最適な雇用形態の選び方

目次
労働人口の減少により、必要とする人員の確保が年々難しくなっています。一方で、地域限定正社員や短時間正社員、テレワーク人材など、働き方は多様化しているため、人事担当者の選択肢以前より増加しています。
雇用形態の選び方次第で、人材確保のしやすさや人件費のバランスは大きく変わります。
それだけに、採用手法の見直しは、経営にも直結する重要な判断です。
本記事では、採用手法を検討するうえでの判断材料として、正社員、 、派遣社員の3種類の雇用形態について、「人手不足への対応」「コスト管理」「柔軟な組織づくり」の観点から比較します。
各雇用形態の基本的な特徴
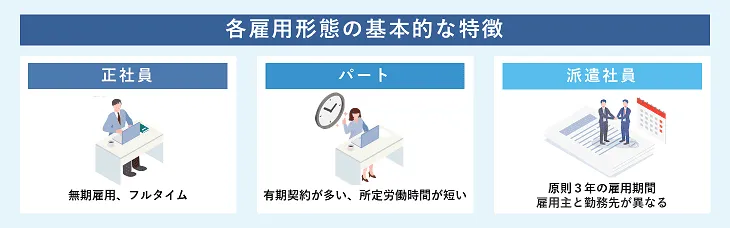
正社員、パート、派遣社員の基本的な特徴は次のとおりです。
| 正社員 | パート | 派遣社員 | |
| 雇用期間 | 無期雇用 | 無期の場合もあり | 原則3年 |
| 労働時間 勤務日 |
フルタイム | 柔軟に設定が可能 | 柔軟に設定が可能 |
| 社会保険 | 加入 | 条件を満たせば加入 | 加入(派遣元が対応) |
| 雇用主 | 自社 | 自社 | 派遣会社 |
また、正社員、パート、派遣社員の採用手法に関する特徴は次のとおりです。
| 正社員 | パート | 派遣社員 | |
| 採用手法 |
|
|
|
| 採用スピード | 長い (採用まで1-2カ月程度) |
比較的短い (採用まで1~3週間程度) |
短い (1週間以内に就業開始することも可能) |
| 選考方法 | 書類選考+複数回の面接での選考が可能 筆記試験がある場合もある |
1回のみの面接が多い 書類選考がある場合もある |
派遣会社が選考・スクリーニングを実施 |
正社員の特徴
正社員は長期雇用を前提としているため、企業文化への適応や継続的な組織貢献、高い定着率が期待できます。
一方で、長期的なキャリア形成を前提とした教育や評価制度の整備が欠かせず、採用コストに加えて、昇給・賞与などの人件費上昇も継続的に発生します。また、解雇には厳しい法的制約があり、試用期間中であったとしても安易に契約を打ち切ることはできません。
最近では、地域限定正社員、短時間正社員など、働く場所や時間に一定の制限を設けた制度も普及しつつあります。また、中途採用で即戦力人材を求める場合には、職務内容を明確に定義した上で募集を行う「ジョブ型雇用」も増えています。
パートの特徴
パートは、一般的に正社員よりも勤務日数や勤務時間数が少ない働き方を指します。有期契約の場合が多く、契約期間満了の度に契約更新するか判断ができるため、企業としては柔軟な検討ができると見なされがちです。
更新手続きが形骸化している、明らかに契約更新の期待を持たせるような言動がされているような場合は、契約更新をしない判断が不当と扱われることがあるため、契約管理には十分な注意が必要です。
2013年4月から導入された「無期転換ルール」では、有期労働契約が更新されて通算5年を超えた従業員から申し込みがあった場合、無期労働契約に転換させる義務が生じます。
さらに、2021年4月からは「同一労働同一賃金 」のルールも適用され、雇用形態にかかわらず、同じ業務内容・同じ責任の範囲・同じ異動の範囲の場合には、正社員との待遇差を設けることが禁止されています。また、業務内容・責任の範囲・異動の範囲が異なる場合にも、不合理な待遇差は認められていません。そのため、パートに対しては、業務範囲や責任を明確に限定したうえで雇用する企業が増えています。
社会保険についても、雇用形態に関わらず要件を満たせば加入義務が発生します。
特に、週の労働時間数が要件になっているため、シフト設計や労働時間の管理にも注意が必要です。
派遣社員の特徴
派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結んでいる人材であり、就業先(派遣先企業)とは直接の雇用関係がありません。この「雇用主と勤務先が異なる」という点が、正社員やパートとの大きな違いです。
派遣社員の雇用主は派遣会社ですが、派遣社員の受け入れにあたっては、労働者派遣法に基づいた管 理・対応が、派遣先にも求められます。
同一の事業所で3年を超えて派遣受け入れをすることができない「3年ルール」や、「同一労働同一賃金」も派遣社員に対して適用されます。また、労働時間の把握・管理や安全配慮義務など、派遣先企業が負うべき義務も多数あります 。
さらに、法改正や最低賃金の上昇、派遣社員の待遇改善などを背景に、派遣料金が上昇するケースも多く、派遣先企業には派遣会社からの料金交渉の要請に応じる配慮義務もあります。
正社員・パート・派遣にかかる人件費の内訳
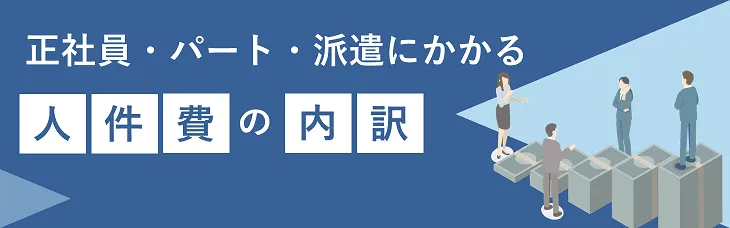
正社員・パート・派遣にかかる人件費の内訳として、どのような項目があるか解説します。
正社員にかかる人件費の内訳
初期費用
- 採用コスト
求人サイトの掲載、人材紹介会社の利用、合同説明会への出展など、採用手法に応じた費用が発生します。また、採用活動にかかわる担当者の人件費も含まれます。近年では、人手不足による採用難により、1人当たりの採用コストは増加傾向にあります。
関連資料:採用コストとは|計算方法と一人あたりの平均、5つの削減ポイントを解説
- 教育費
社内での集合研修やOJTを実施する場合は、講師やトレーナーの人件費、外部研修を受講させる場合は受講費用などが発生します。
ランニングコスト
企業の福利厚生や従業員のにもよりますが、正社員1人当たり、給与の1.5~2倍程度のランニングコストが発生すると言われています。
ランニングコストには、勤怠システム、ファイル共有システム、チャットツール等、様々なITツールも含まれます。こういったITツールは利用人数×月額制なことが多く、それぞれは少額でも、合算で考えると一定のコストになりえるため、ランニングコストとして考えておくべきです。
- 給与
基本給は月給であることが多いです。基本給に加え、時間外・休日・深夜手当も支給対象です。会社独自の手当(役職手当、家族手当など)がある場合には、その額も考慮に入れる必要があります。
- 賞与、退職金
賞与や退職金がある企業では、毎月ではないものの一定のタイミングである程度まとまった金額の支出が発生します。
- 社会保険料
毎月、以下の社会保険料の負担が発生します。
| 加入保険名 | 保険料率 | 負担者と負担割合 |
| 労災保険 | 0.3%~5.2%(業種による) | 事業主が全額負担 |
| 雇用保険 | 1.45%~1.75%(業種による) | 事業主と従業員で負担 (事業主の方が負担割合が多い) |
| 厚生年金 | 18.3% | 事業主と従業員で折半 |
| 健康保険 | 約10%(都道府県による) | 事業主と従業員で折半 |
| 介護保険 | 1.59% | 事業主と従業員で折半 (40歳以上の従業員が対象) |
保険料率は従業員に支払う賃金(給与だけでなく各種手当等を含む)に対しての割合ですので、給与や手当が高ければその分納付すべき保険料も高くなります。また、健康保険と介護保険は、協会けんぽであれば上表のとおりですが、健保組合の場合には料率が異なります。
いずれの場合でも、正社員1人あたりの給与の30%程度の保険料の納付が必要で、そのうち半分以上が企業負担です。ランニングコストとしては比較的大きな金額になります。
- 昇給
正社員は業務内容も徐々に高度になり、責任の範囲も増えていくため、キャリアを積むにつれ昇給をさせることがほとんどです。基本給があがると、時間外・休日・深夜手当 ・賞与にも影響します。前述の通り各種社会保険料も支払う賃金に対して計算されるため、昇給により各種社会保険料も増額される点は注意しましょう。
- 教育費
正社員の場合、長期的な雇用を前提とし、業務の中枢に携わることが多いため、パートに比べ教育費がかかります。管理職研修、リーダーシップ研修等の育成費用は念頭に置く必要があります。
- 福利厚生費等
福利厚生は、企業によって負担の有無や金額は異なります。
〈一例〉
- 健康診断
- 通勤手当
- 予防接種
- 民間の医療保険等の一部負担
- レジャー施設の割引等
パートにかかる人件費の内訳
初期費用
- 採用費
パートの採用にも、求人掲載費や面接対応など、正社員採用と同様の費用が発生しますが、面接回数を少なく設定したり、使用する採用媒体を限定したりするなど、採用工程の簡略化により、正社員採用に比べてコストを低く抑えられているケースが多いです。
- 教育費
正社員と同様、入社時の教育費用も発生します。前述の通り、同一労働同一賃金が適用されているため、業務内容と責任の範囲が正社員と同じであれば、パートに対しても教育も正社員と同じく実施する必要があります。
ランニングコスト
- 給与、賞与、退職金、昇給、教育費、福利厚生費
原則、正社員と必要な項目や考え方は変わりません。同一労働同一賃金の考え方も同様に適用されるので、業務内容と責任の範囲が正社員と同じであれば、これらのランニングコストとして挙げられる待遇も差異を設けることはできません。ただし、以下の点は正社員と異なる待遇となることが多いです。
- 給与
時給制が多くみられます。また、業務や責任の範囲が正社員異なることが多いため、会社独自の手当の種類も正社員と違いが見られます。
- 教育費
パート社員は正社員に比べて業務内容や責任範囲が限定され、長期雇用を前提としないケースも多いため、パート向け研修は多くない企業が大半です。結果的に教育コストは正社員よりも低く抑えられる傾向があります。
- 社会保険料
パートについても、以下の要件を満たしていれば、毎月、正社員と同様に社会保険料の負担が発生します。
| 加入保険名 | 加入条件 |
| 労災保険 | 労働条件に関わらず全員加入 |
| 雇用保険 | 次の要件をいずれも満たす場合には加入
|
| 厚生年金 |
<被保険者数50人未満の企業> 1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上 <被保険者数51人以上の企業> 次の要件をいずれも満たす場合には加入
|
| 健康保険 | 同上 |
| 介護保険 | 同上(ただし40歳以上の従業員が対象) |
社会保険加入状況、労働時間、待遇差によって異なりますが、総じて正社員よりコストは抑えられる傾向にあります。
派遣社員にかかる人件費の内訳
人材派遣を利用する場合、契約期間や就業時間に応じた派遣費用が発生します。この費用は、派遣会社が雇用する人材を自社に派遣してもらう「サービスの利用料」であり、厳密には人件費には該当しません。ここでは、派遣社員の受け入れ時に発生する費用について説明します。
初期費用
- 備品等費用
自社での雇用と同様、PC等の業務に必要な備品の準備費用は発生します。一方、採用や教育は派遣会社が実施するため、派遣先企業での費用負担はありません。そのため、自社雇用よりも初期費用は圧倒的に抑えられます。
ランニングコスト
- 派遣会社から請求される毎月の派遣料金
ランニングコストは、派遣会社から請求される派遣料金のみです。派遣料金の主な内訳は以下のとおりです。
| 名目 | 内容 | 派遣料金に占める平均割合 | |
| 派遣社員の給与 |
|
70.0% | |
| マージン | 社会保険料 |
|
10.9% |
| 派遣社員有給費用 |
|
4.2% | |
| 諸経費 |
|
13.7% | |
| 営業利益 |
|
1.2% | |
参考:一般社団法人日本人材派遣協会 https://www.jassa.or.jp/know/data/
毎月の料金には派遣会社へのマージンが含まれるため、場合によっては自社雇用よりもランニングコストが高くなることもあります。ただし、マージンには自社雇用でも企業が負担する費用(社会保険料や有給休暇など)が含まれているため、福利厚生の内容や年次有給休暇の取得状況、初期費用などによっては、派遣社員の方がコストを抑えられるケースもあります。
【目的別】雇用形態×活用シーン
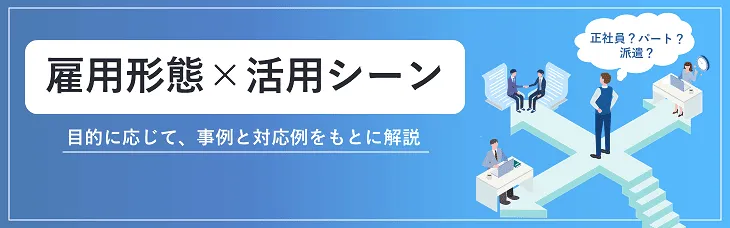
目的に応じて、雇用形態(正社員、パート 、派遣社員)をどのように活用するのが良いか、事例と対応例をもとに解説します。
- 中核業務・マネジメントを任せたい
- 特定の時間帯や繁忙期に業務を補いたい
- 産休・育児休暇で一時的に代替要員が必要
- 新規事業立ち上げで、スピード感を持ってプロジェクトを進めたい
- 単発イベントでスタッフが必要
中核業務・マネジメントを任せたい
| 事例 | 会社の将来を考え、継続的に管理職候補や組織の中枢事業を担える人材を確保したい。 |
| 適した選択 |
正社員を採用し、長期的な育成を前提とする。 役割を継続的に担ってほしい、企業の中枢業務を任せたい場合には、長期雇用を前提としている正社員雇用が適しています。計画的な育成をしながら企業特有の知識が蓄積でき、組織にフィットした人材への成長が期待できます。 |
特定の時間帯や繁忙期に業務を補いたい
| 事例 | 毎日決まった時間帯に忙しくなる業務・毎年決まった時期に忙しくなる業務があるため、そのときだけ人手を増やしたい。 |
| 適した選択 |
繁忙時間あるいは繁忙期に限定した雇用契約や派遣契約で対応する。 時間や期間が限定された業務は、正社員よりもパートや派遣社員による対応が適しています。双方に特徴があるため、用途に応じて雇用形態を選択するといいでしょう。 |
パートが向いているケース
1日の労働時間は短いが長期間継続的に必要な業務には、パートが向いています。パートであれば第三者を介さずに直接契約変更も打診できるため、更なる繁忙期等に労働時間の交渉もしやすいです。また、採用は自社で行う必要がありますが、派遣社員よりもランニングコストが抑えられる可能性があります。
派遣社員が向いているケース
「3か月だけ」のように明確な期間限定ができる業務や、即戦力が必要な場合は派遣社員が向いています。派遣会社が人選するため採用プロセスも省け、必要な人材をすぐに確保できるメリットがあります。労働時間等の条件変更も派遣会社を通して打診できるため、本人への交渉の手間も省けます。ただし、派遣社員は30日以内の派遣(日雇い派遣)が禁止されているため、契約期間には注意が必要です。
産休・育児休暇で一時的に代替要員が必要
| 事例 | 正社員が産休・育休に入るため代替要員が必要だが、社内で調整できない。 |
| 適した選択 |
産休代替派遣制度を利用し正社員が復職するまでの代替要員として派遣社員に来てもらい、復職後も勤務が安定するまではサポート要員として就業してもらう。 また、派遣社員から自社での直接雇用に切り替えを行うなど復職後も状況に合わせて柔軟に対応。 |
労働者派遣の中には、産休・育休等の代替要員を派遣する「産休代替派遣」という制度があります。派遣社員に産休・育休を取得する従業員の代替要員を担ってもらう制度です。派遣会社へ依頼するときに「産休代替派遣」であることを伝えるとスムーズです。育休の場合、復職のタイミングが契約当初は確定していないので、契約期間に柔軟性を持たせるよう派遣会社に依頼をすることを推奨します。
また、産休代替派遣として来ている派遣社員を直接雇用に切り替えたい場合には、派遣会社に申し出る必要があります。その後、派遣会社から派遣社員に対して直接雇用化への打診を行います。双方合意が取れ次第直接雇用に切り替えることが可能になります。なお、切り替え時には紹介手数料が発生します。(想定年収の30~35%目安)
新規事業立ち上げで、スピード感を持ってプロジェクトを進めたい
| 事例 | 社内に専門性・ノウハウのある人材がいない分野で新しいサービスを立ち上げたい。 |
| 適した選択 | その分野に詳しい即戦力の人材派遣を数カ月単位で契約し、立ち上げフェーズを一緒に進める。 |
社内でゼロから育成する場合と比較して、即戦力人材の派遣サービスを活用すれば、教育コストを抑えつつ成果も早く出しやすくなります。ただし、派遣社員には3年ルールがあるため、長期的に中枢業務を担ってほしい場合には、正社員採用も検討したほうがよいでしょう。
単発イベントでスタッフが必要
| 事例 | 週末に大規模な販売イベントを実施予定で、短期間だけ受付・案内・軽作業の人手を増やしたい。 |
| 対応例 | パートを募集。経験者を優先しつつ採用し、イベント前に簡単な研修を実施。 |
短期間・単発・軽作業の業務にはパート採用が向いています。特別なノウハウが不要であれば、未経験者でも事前に簡単な研修を行う程度で対応可能です。前述のとおり、派遣社員は原則30日以内の派遣(日雇い派遣)が禁止されているため、「週末だけ」などの単発業務の派遣依頼は難しいケースがほとんどです。
派遣社員が就業開始するまでは、派遣料金はかかりません
派遣サービスの検討材料として、派遣料金やどんな人材が派遣されるかなど、確認したいことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
人材派遣は、派遣社員が勤務開始するまで費用はかかりません。
まとめ
適切な雇用形態の選択は、企業活動と密接に関わります。正社員は長期的な企業の中核業務を担い、パートは柔軟な時間活用とコスト効率を両立し、派遣社員は即戦力を必要とする場面で真価を発揮します。単純なコスト削減ではなく、雇用形態の特性を活かし、活用シーンに合わせた戦略的な人材配置ができることが理想的です。
こちらの資料もおすすめです

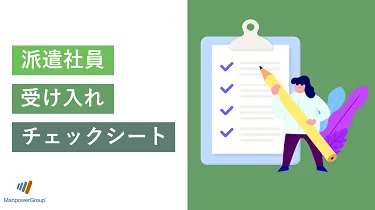


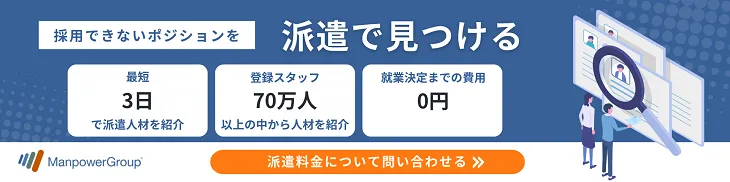

















 目次
目次