


連鎖退職が発生する原因とは?連鎖を止めるために会社が講じる対策

目次
ひとりの社員の退職が引き金となり、他の社員の退職が連鎖的に続く「連鎖退職」は、組織に深刻な影響を及ぼすことがあります。特に優秀な人材や信頼を集める従業員の離職は、職場全体の士気や安定性を揺るがしかねません。
退職が続いてしまった原因を調べずに放置すると、気がつけば人員不足や業務停滞に陥り、人材が定着せず採用コストも増大します。なぜ連鎖退職が起こるのか、その背景を知り、適切な対策を取ることが重要です。本記事では、原因と有効な防止策について解説します。
連鎖退職とは

「連鎖退職」とは、ある従業員の退職をきっかけに、次々と退職が発生する現象を指します。
多くの企業で人手不足が慢性化している昨今、連鎖退職が起こることは企業にとっては大きな痛手となります。まるでドミノが倒れるように広がることから、「ドミノ退職」とも呼ばれます。
青山学院大学・山本寛教授は著書『連鎖退職』(日本経済新聞出版社刊)で、連鎖退職の現象を大きく2つのタイプに分類しています。また、この2つのハイブリッド型もあると述べています。
ドミノ倒し型:1人の退職によって残された社員の業務負担が増え、それが原因となってさらに退職が起こるパターン。特に少人数の部署や中小企業では起こりやすい傾向があります。
蟻の一穴型:影響力のある従業員(エース社員やリーダー的存在)が辞めることで、もともとあった職場の問題が表面化し組織に不安や不信感が広がり、他の社員も「自分も辞めよう」と動き出すパターン。小さなきっかけが大きな崩壊につながる点が特徴です。
海外でも「Turnover Contagion(離職の伝染)」として研究されており、「離職の伝染とは、従業員が自分の退職意向を周囲に伝播させる現象を指し、人は他者と自分を比較したり模倣したりする傾向があるために生じる」と指摘されています。実証データも、同僚の退職が残る従業員に心理的影響を与えることが確認されています。つまり連鎖退職は偶然ではなく、組織に潜むリスクとして示されている現象なのです。
優秀な人材を立て続けに失わないために、退職理由を知る「退職者インタビュー」
連鎖退職が起こる主な原因

連鎖退職は偶発的に起こるものではなく、必ず背景に組織の課題があります。連鎖退職を招く主な原因について詳しく整理していきます。
労働条件に関する不満
労働条件への不満は、連鎖退職を引き起こす代表的な要因のひとつです。給与水準が市場相場と比べて明らかに低い、昇給が見込めないなどの状況は、社員に「ここにいても将来はない」という不安や不満を抱かせます。
有給休暇などが自由に取得できず心身を休めにくい、長時間労働やサービス残業が常態化しているなど、疲れやストレスが蓄積しやすい環境も同様です。
ひとりの退職をきっかけに、「この職場にいても、改善は望めない」と考える社員が続き、退職の連鎖につながります。労働条件の不備は、単なる個人の不満ではとどまらず、組織全体に波及するリスクをはらんでいます。
エース級の従業員の退職
組織の中核を担うエース級の従業員が退職すると、その影響は計り知れません。成長の指針であるロールモデルの喪失は、モチベーションの低下や「自分も限界かもしれない」という諦めにつながります。さらに、優秀な人材が会社を去る事実が「この会社の未来は大丈夫なのか」という不安を増幅させます。
加えて、蓄積されたナレッジやノウハウが十分に引き継がれないままの退職は、業務効率やチーム全体のパフォーマンスが著しく低下します。社員への心理的ダメージ・組織的な業務効率へのダメージが重なることで、残された社員も退職を考えるようになり、連鎖退職が一気に進みます。
上司に問題がある
上司の存在は、社員の働きやすさや職場への定着意欲に大きな影響を与えます。評価制度が整っておらず、昇給や成長の機会が与えられない環境では、努力が報われないという失望感が広がります。さらに、パワハラなどのハラスメントが蔓延している場合、心身への負担は深刻で、社員は「この職場に居続けるのは難しい」と考えることが多くなります。
不公平な評価や一方的な指示、コミュニケーション不足が重なると、上司と部下の信頼関係は崩れ、安心して働ける環境が失われます。こうした状況で誰かが退職すると、「自分も退職を選んで、この環境から解放されよう」という心理的影響が働き、連鎖退職を引き起こす要因になります。
現場のパフォーマンスを高める「ネガティブフィードバック」とは?
過剰な業務の増加
退職者が出ると、残った社員に過重な負担がのしかかります。休日出勤や長時間残業など過労を招きやすくなり、ワークライフバランスが崩れがちになります。休息を取れない状態が続くことで、疲労が蓄積し、心身の不調だけでなく、仕事への意欲低下にも直結します。人材が慢性的に不足している職場では、一人ひとりの負担が増え続け、終わりの見えない状況に、社員の不満や不信感が高まっていきます。
企業としても業務量を軽減するために採用活動を進めたいところですが、現場の余裕がないため採用に割く時間も不足し、採用活動が進まない・採用の精度が落ちるなど、結果として人手不足が改善されない悪循環に陥ります。
こうした環境下では組織は負のスパイラルに陥り、連鎖退職が一気に加速します。
経営不振
会社の経営状況は社員の安心感に直結します。経営不振に陥った組織では、「リストラがあるらしい」という、うわさが広がるだけで、本来辞めるつもりのなかった社員まで将来への不安から退職を検討し始めます。賞与カットや昇給の見送りなどの待遇面の悪化は、生活設計やキャリア形成に対する不安が強まるとともに「この会社は危ないのではないか」という印象も高まります。
経営不振そのものが社員の士気を下げるだけでなく、情報の不透明さや将来への不信感が組織全体を揺るがし、連鎖退職という深刻なリスクを引き起こす要因となります。
企業イメージの悪化
企業が不祥事やサービス品質の著しい低下などにより社会的信頼を失うと、従業員の間に「この会社に居続けて大丈夫か」という将来への不安が広がり、結果として連鎖退職を招きやすくなります。
また、退職者によるネガティブな口コミが採用活動に悪影響を及ぼすと、新規採用が停滞します。既存社員の業務負担増により職場環境が悪化し、結果としてさらなる離職につながる可能性もあります。
こうした状況が続けば、企業の競争力は低下し、業績悪化や組織の衰退、最悪の場合は存続そのものが危ぶまれる事態にもつながりかねません。つまり、社会的信頼の喪失は、単なるイメージダウンにとどまらず、社員の定着や企業の将来を左右する深刻なリスク要因なのです。
退職者一人ひとりの退職理由を知ることで、組織に潜む思わぬ改善点が見えてきます。
連鎖退職を防ぐための対策
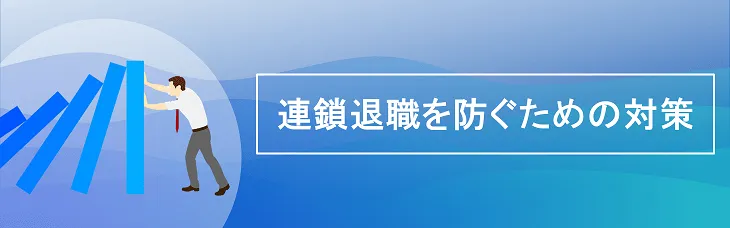
ここまでお伝えしてきたように退職者が短期間に続々と増えていくことで、企業の組織力や競争力が大きく損なわれることになります。しかし、その多くは日常的な取り組みによって予防ができます。
ここからは、連鎖退職を防ぐための具体的な対策について、それぞれの手段を詳しく解説します。
退職理由を知るための仕組みづくり
連鎖退職を防ぐためには、まず「なぜ社員が辞めていくのか」原因を正しく把握することです。退職は個人の選択という側面だけではなく、背景には社員全体に共通する課題や組織に潜む深い問題が隠れている場合が多くあります。改善のカギとなる退職理由を把握するための手法をご紹介します。
社内アンケートの実施
定期的に社員の満足度やストレス度を把握するアンケートを行うことは、退職理由を知るのに有効です。匿名性を確保しつつ「仕事量に無理はないか」「上司や同僚との関係は良好か」「会社に将来性を感じるか」などの設問を設けることで、社員は本音を伝えやすくなります。代表例としてはエンゲージメント調査やストレスチェックがあげられます。これらに加えて、類似した施策で上司・同僚・部下・自己評価を組み合わせた360度フィードバックも社員の不満や課題を多角的に把握する手法として有効です。こうした調査は自社で実施することも可能ですが、専門会社のサービスを活用すれば設問設計や集計・分析の精度が高まり、結果を組織運営の改善に直結させやすくなります。
退職者インタビューの実施
退職者インタビューとは、辞める社員から直接意見を聞き、退職の背景や職場の課題を把握する方法です。「一身上の都合」など当たり障りのない理由ではなく、給与や労働条件、日常的に感じていた働きにくさや上司との関係、キャリア形成への不安など、本音の部分を聞き出すことで、改善すべきポイントが明確になります。
実施にあたっては、直属の上司が行うと本音を言いにくいため、人事部門の担当者や外部のキャリアコンサルタントなどの第三者が担当すると率直な意見を得やすくなります。安心して話せる体制を整えれば、得られた情報は再発防止や制度改善に直結します。退職者の声を真摯に受け止める姿勢こそが、連鎖退職を防ぐための第一歩です。
退職者の本音を知る
若手や優秀な社員の退職は企業にとって大きな痛手です。採用難であり、補充が難しく、また原因を知らないとドミノ離職が起こるリスクもあります。
退職防止施策の選択を間違わないためには、離職者の本当の退職理由を知ることが先決です。退職者の本音を探るための資料をご用意していますので、ぜひご覧ください。
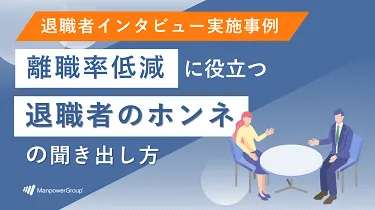
従業員の相談窓口を開設する
従業員相談窓口の設置も有効な手段のひとつです。匿名性や第三者性を確保することで、上司や周囲に言いにくいハラスメント、労働条件への不満、キャリアへの不安などの声を早期に吸い上げることができ、問題が深刻化して退職へとつながる前に改善策を講じることが可能になります。
相談窓口の開設は、退職連鎖を止める仕組みであると同時に、従業員の安心感や働きやすさを高める効果もあります。さらに、「社員の声を真摯に受け止め改善している会社」としての社外からの評価にもつながります。結果として、採用力や企業イメージの向上にも寄与し、組織を守るための基盤となります。
なお、近年ではILOや国連などの国際機関も、企業が従業員やステークホルダーの申し立てを公正に受け止め、改善につなげる「グリーバンス制度」の整備を推進しています。
働きやすい就業環境への改善
退職理由を正しく把握しても、環境そのものが改善されなければ、社員の不満は解消されず退職は繰り返されてしまいます。アンケートやインタビュー、相談窓口などの手段は、課題の特定手段にすぎず、重要なのはその結果を踏まえた具体的な改善です。
よく見られる課題として、過剰な業務負荷による心身の疲弊、人間関係に起因する不安や摩擦、不公平な評価やハラスメントなど管理職のマネジメントに起因する問題が挙げられます。これらは退職の直接的な要因であり、放置すれば連鎖退職の火種になります。
ここからは、特定した課題にどう対応するかという視点で、「業務負荷」「人間関係」「管理職」の3つに分野について改善策を解説します。
業務負荷が原因の場合
過剰な業務負荷は社員の心身を疲弊させ、退職の大きな要因となります。まずは業務の棚卸しによる必要性や効率性の検証が重要です。形骸化した報告書や重複する承認プロセスを削減するだけでも負担は軽減されます。
定型業務や反復的に発生するタスクについては、外部委託やツール導入による効率化を図ると、社員はより付加価値の高い業務に集中できます。こうした改善は生産性の向上に加え、働きやすさや、やりがいの実感にもつながります。
人間関係に問題がある場合
職場での人間関係の悪化は、社員の孤立感や不安を生み、退職につながりやすくなります。多くの人が感じている悩みでもあり、早期の対応が重要です。
有効な施策としては、上司や人事担当者と定期的に対話できる1on1ミーティングの導入が挙げられます。日常の悩みやキャリアの希望を共有する機会を設けることで、突然の退職なども防ぎやすくなります。
また、部署を越えた交流を促す社内イベントやチャットツールによる気軽なコミュニケーションの促進なども、職場に安心感や一体感が生まれ、人間関係の問題を未然に防ぐ効果が期待できます。
管理職に問題がある場合
管理職の姿勢やマネジメントスキル不足は、部下のモチベーション低下や職場不信につながり、連鎖退職を引き起こす大きな要因となります。そのため、まずは管理職向けの研修を実施し、評価や目標設定の方法、ハラスメント防止、適切なコミュニケーションなど、基本的な知識の習得・マネジメント力を高めることが重要です。
特に最近は若手社員への指導の仕方で問題が起こるケースが多くあります。前時代的な叱責や「背中を見て覚える」など一方的な指導ではなく、時代に合ったフィードバックや再現性のある育成スタイルが求められていることを知る機会を設ける必要があります。さらに、管理職が自らの強みや課題を把握し、よりよいリーダーシップを発揮するために、個別のコーチングを受けることも有効です。
マンパワーグループでは管理職向けのセミナーも開催しております。
採用段階での改善
連鎖退職を防ぐには、在籍中の従業員への対応だけでなく、採用の入り口から見直すことも重要です。採用の段階でミスマッチがあると、早期離職や不満の拡大につながり、退職の連鎖を招きやすくなります。
また、人事と現場との情報共有が不十分なまま採用を進めると、入社後にギャップが生じ、定着が難しくなるケースも少なくありません。ここからは、採用手法や現場との連携不足などの観点から改善策を整理します。
募集・評価に問題がある場合
採用の手法そのものに課題があると、入社後のミスマッチが発生し、早期離職や連鎖退職の引き金になりかねません。新人が連鎖的に退職するという状況は、組織に負の連鎖をもたらします。
たとえば求人票に「募集職種・給与・勤務地」だけを記載していると、入社後に「仕事内容や働き方がイメージと違った」という不一致を招く恐れがあります。業務内容を具体的に示すとともに、組織の風土や大切にしている価値観、将来期待する役割までを求人票に盛り込むことが重要です。
また、選考の過程でもスキルや経験だけでなく「職場文化との相性」を採用基準に含め、面接では仕事観やチームでの協働意識を確認することも効果的です。
採用活動時の現場との連携不足に問題がある場合
採用を人事部門だけで進めると、現場の実情とのズレが生じやすく、結果としてミスマッチを招く原因となります。そのため、現場を巻き込んだ採用活動を行うことが不可欠です。
人事は応募者(求職市場)と現場をつなぐ役割を担い、現場のことを理解すると同時に、求職者の動向や求めるものを現場に伝えるようにしましょう。面接に現場社員が同席し、仕事内容や求めるスキル、チームの雰囲気などを直接伝えることで、候補者は入社後のイメージが鮮明になります。
また、採用過程における現場と人事の連携は、組織全体としての一体感を候補者に伝える効果もあり、入社後の研修や面談など安定したフォロー体制構築にもつながります。こうした取り組みは、採用後の定着率の向上だけでなく、連鎖退職の防止に直結する既存社員のエンゲージメント向上にも寄与するのです。
まとめ
連鎖退職は、一人の退職をきっかけに、労働条件の不満や上司の問題、過剰な業務負荷や経営不振など複数の要因が重なって広がります。その結果、組織の信頼低下や業績悪化などの大きなリスクを招く恐れがあります。だからこそ、退職の原因を正しく特定し、課題を一つひとつ解決していく改善策を講じることが重要です。こうした地道な取り組みの積み重ねこそが、人材の安定と定着率の向上につながり、組織を持続的に強くしていきます。
こちらの資料もおすすめです

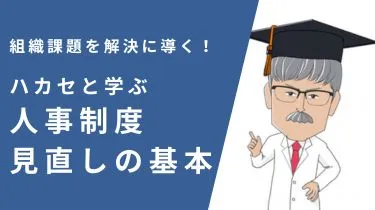
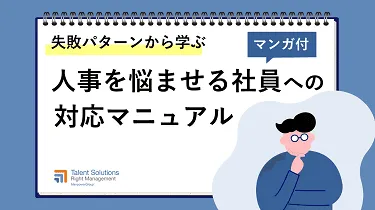
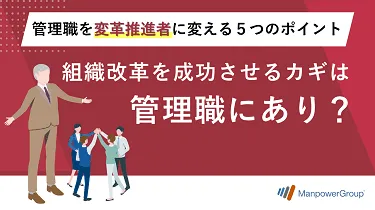
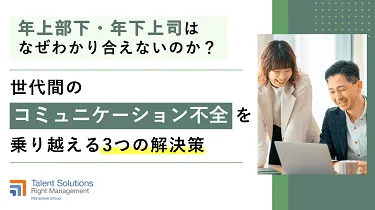
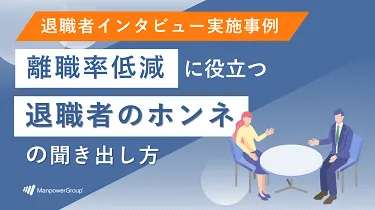

















 目次
目次