


若手採用が厳しい時代に企業が取るべき対策とは?

目次
若手人材の採用は最重要課題として、多くの企業が力をいれています。しかし、優秀な人材をめぐる採用競争は激化の一途をたどっています。なぜ今、若手採用はこれほどまでに難しくなっているのでしょうか。
本記事では、若手採用の現状と背景をお伝えするとともに、この採用難を乗り越え、若手から「選ばれる企業」になるために企業が取るべき具体的な対策を詳しく解説します。
若手採用の現状と採用難の背景
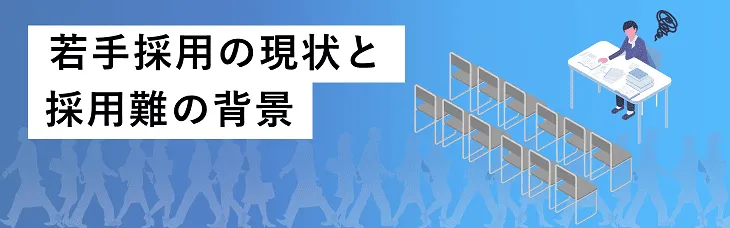
若手人材の採用は、景気や社会構造の変化により、時代ごとに状況が大きく変化してきました。近年は少子化や都市部への人口集中などの影響で採用そのものが難しくなっており、「採用の難しさ」と「定着の難しさ」という二面の困難が、企業の若手人材確保の難易度を高めています。
定着の難しさ
新規学卒者の定着は、長年にわたり多くの企業が直面している課題です。厚生労働省の調査「新規学卒就職者の離職状況」によれば、大学新卒者の約3割が3年以内に離職する傾向は、少なくとも過去20年以上続いています。2025年に発表された調査結果でも、2022年卒の大学新卒者の33.8%が3年以内に離職しており、この傾向が現在も続いています。
採用難が加速している背景
では、なぜ若手の採用難がこれほどまでに加速しているのでしょうか。その背景には、社会構造の変化に伴う需給のアンバランスがあります。
- 団塊世代の後期高齢者化の影響
団塊世代が後期高齢者となり、介護ニーズが急増しています。その子ども世代である働き盛りの層は、仕事と介護の両立を迫られる「ビジネスケアラー」としての役割を担うようになり、社会全体の労働力に影響が及んでいます。こうした背景から、不足を補う役割として、若手人材への期待が高まり、採用競争が激化しています。
- 少子化
出生数の減少により、若年層の人口が長期的に減少。企業が採用対象とする人材の絶対数が減っており、採用難の根本的な要因となっています。
- 首都圏への集中化
大学進学や就職を機に若者が首都圏に集中する傾向が続いており、地方企業にとっては人材確保が一層困難になっています。
このように、需要に対して供給が追いつかない構造的な問題が、限られた若手人材を各社が奪い合う激しい採用競争を引き起こしているのです。
若手採用の特有の採用課題
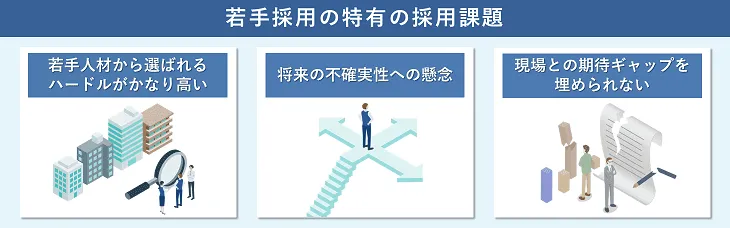
若手の採用には、これまでの世代とは異なる特有の価値観や考え方を踏まえる必要があります。
若手人材から選ばれるハードルがかなり高い
現代の若手人材は、売り手市場を背景に「企業を選ぶ立場」にあります。内定を複数持つことも珍しくなく、多数の選択肢の中からシビアに企業を吟味します。
大手企業であっても、知名度だけでは選ばれません。多様性や成長機会といった具体的な価値を提供できる企業に、優秀な人材は集中する傾向にあります。
将来の不確実性への懸念
自己実現やキャリアアップへの意欲が高い若者にとって、入社後のキャリアパスが不透明であることは大きな不安要素です。「配属先は入社後に決まる」といった従来の慣行は、自身のキャリアプランを描きたい彼らにとっては将来の見通しが不透明で、敬遠される要因となります。
この傾向は転職採用でも同様で、「リモートワーク可能と聞いて入社したのに、実際は毎日出社だった」「求人とは異なる業務を、会社都合で変更させられた」といった入社後のギャップは、エンゲージメントの著しい低下を招き、早期離職の引き金となります。
現場との期待ギャップを埋められない
現場が求める理想像が高すぎて採用につながらないといったケースもあります。
企業側が求める若手像(採用要件)が、過去の成功体験に基づいたまま変更されていない場合、市場にいる若手のスキルセットや価値観と合わなくなり、結果的に面接が通らない、早期離職が発生するという問題を引き起こします。
事務職の経験はないものの、ポテンシャルが高く、業務習得のキャッチアップが早い若手人材をコンサルタントが適性を見極めて派遣します。
- 新卒採用が充足できなかった
- 若手の採用が進まない
- 新卒が配属されなかった
上記のようなお悩みをお持ちの方にぜひ知っていただきたいサービスです。
若手人材の採用活動がうまくいかない理由
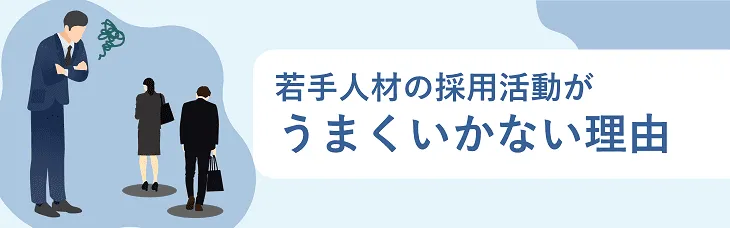
若手の価値観が変化する中で、従来のやり方に固執することが採用失敗の直接的な原因となります。
これまでの採用手法をそのまま使っている
若手人材の採用は、企業の知名度や条件だけで成功する時代ではなくなりました。そのため、求人を掲載するだけの「待ちの採用」から、企業側から積極的にアプローチする「攻めの採用」への転換が不可欠です。
若手世代に特化した採用サービスも次々と登場しています。採用担当者は常にアンテナを張り、採用経路を拡大していく取り組みが求められます。
求めるものと待遇のアンバランス
若手人材側が「選ばれる立場」にある以上、企業が提供する待遇は市場価値に見合っている必要があります。かつての採用市場と同じ感覚で待遇を設定していては、優秀な人材から選ばれることはありません。自社が求めるスキルレベルと、提供する給与や福利厚生のバランスが、現在の市場において競争力があるかを客観的に見直すことが重要です。
ポテンシャルの定義が曖昧になっている
若手を採用する際、選考で評価するのは将来性を見越した「ポテンシャル」です。ポテンシャルの定義が曖昧では、面接官それぞれの主観や経験則で評価にばらつきが出てしまい、評価にブレが生じます。
自社にとってのポテンシャルを「主体性」「論理的思考力」「周囲を巻き込む力」などと具体的に定義し、面接官全員で基準を共有することが重要です。
明確な基準を持つことで、評価のブレがなくなるだけでなく、採用のミスマッチが減り、結果として、早期離職の防止にもつながります。
情報発信力が弱い
若手人材は、SNSや口コミサイトで企業名を検索し、リアルな情報を収集することが当たり前になっています。企業の情報発信力が弱い、または情報が不透明である場合、若手は不信感を抱き、応募や内定承諾の意思決定に影響します。
「ミッション/ビジョン」「社内の雰囲気」「働き方」「どんな人がいるか」というような、社内のリアルが伝わる情報をバランスよく発信することでブランディングにもつながり、選ばれる企業になります。
また、SNSなどを利用した情報発信は、社内広報の効果もあり、人材の定着にも効果を発揮します。
若手採用に向けて企業が取るべき対策
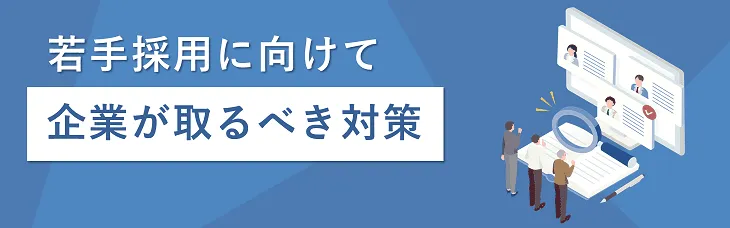
ポイントをおさえて採用活動をすることで、若手人材の採用・定着の成功確率は上昇します。ここでは、若手採用を成功させるために企業が実施するべき具体策について説明します。
若手が企業に求めていることを知る
若手採用を成功させるための第一歩は、彼らが何を重視し、何を求めているかを正確に把握することです。
- 成長機会と透明なキャリアパス
スキルアップ制度、明確なキャリアパス、充実した研修体制など自身の成長を具体的にイメージできる環境。
- 柔軟で多様な働き方
在宅勤務やフレックスタイム制度、ライフイベントへの配慮(育児・介護など)といった、個々の事情に合わせた柔軟な働き方の選択肢。
- 仕事の意義(パーパス)
自分の仕事が事業や社会にどう貢献しているのかを実感できる、企業のビジョンやミッションとの明確なつながり。
- 心理的安全性と多様性
多様性を受け入れる文化と、誰もが安心して意見を言える心理的に安全な職場環境。
- 建設的なフィードバック
成長を促す、上司や先輩からの定期的で建設的なフィードバック。
- 公正な評価と待遇の透明性
成果や貢献が正当に報われる、客観的で透明性の高い評価・報酬制度。
- 福利厚生/待遇
住宅手当や有給休暇の取得しやすさといった基本的な福利厚生、および企業独自の制度。
- ロールモデル
年齢の近い先輩社員のリアルな声や交流を通して、具体的なキャリアパスをイメージできる機会を提供。
採用手法を精査し、複数取り入れる
若手の情報収集に合わせた採用手法の多様化は必須です。複数の採用手法を取り入れることで、採用効果は最大化します。
SNSやダイレクトリクルーティングは、候補者のプロフィールを確認できるため、企業が求める人材に直接アプローチすることができます。また、SNSで企業のリアルな雰囲気や若手社員の日常を発信することは、親近感の醸成や転職を検討していなかった潜在層の関心を喚起するきっかけになります。
新卒採用ではインターンシップの実施も効果的です。早期から学生と接点をもち、業務の一部を実際に体験してもらうことで、企業の魅力を深く理解してもらうとともに、ミスマッチを防ぐ機会となります。選考エントリーの条件を「自社でのインターン経験」とする企業もあるほど、新卒採用におけるインターン経験の位置づけは高まっています。
中途採用では、一度退職した人を再び採用するアルムナイ採用も注目されています。ミスマッチのリスクが低く、企業理解もあり即戦力となる、他社での経験から外部的な視点が入る、採用コストがかからないといった理由で、若手のアルムナイ採用に力を入れる企業が増えています。
選考の透明性
選考過程における候補者との向き合い方も、入社の決め手となり得ます。
「選考通過」「内定」の通知だけでなく、評価した点などを具体的にフィードバックすることで、若手人材は「しっかり評価してもらえている」と感じ、志望意欲が高まるケースが多くあります。
また、他社の選考状況を尊重し、内定承諾期限の延長に柔軟に応じるといった誠実な姿勢は、候補者に「この会社は自分を大切にしてくれる」という強い信頼感を与えます。「承諾期限を短く設定して候補者を囲い込む」といったテクニック論もありますが、長期的な信頼関係を築く視点は、最終的に選ばれる企業になるための鍵です。
人事制度の見直し
若手人材の惹きつけや定着には、人事制度そのものが彼らの価値観に合っているかを見直す必要があります。
柔軟な働き方(リモートワーク、フレックス、副業など)や多様なライフスタイルに対応した制度(育児・介護支援、休職明けのサポートなど)の整備は、採用競争において大きな魅力となります。
中でも、「年間休日」は他社と比較されやすい指標の一つです。大企業の半数近くが年間休日120日以上を導入しており、もはや特別なことではありません。また、「アニバーサリー休暇」「リフレッシュ休暇」といった、ユニークな特別休暇は、他社との差別化につながります。
人事制度や福利厚生は、その企業が従業員に与える価値を提供しようとしているかを象徴するものです。いまの時代に見合った働き方へのシフトや制度導入が、若手人材に選ばれる会社の第一歩となります。
ターゲット層の緩和
採用難が続く中で、「新卒にこだわる」という採用戦略を見直すことも重要です。
富士通が新卒一括採用を廃止したことでも話題になりましたが、第二新卒や未経験者までターゲットを拡大することで、より多くの母集団を形成できます。彼らは社会人経験を通じて基本的なビジネスマナーを習得しているため、育成コストを抑えやすいというメリットもあります。
紹介予定派遣の活用も有効です。一定期間(最長6ヶ月)派遣社員として働いた後、企業と本人が合意すれば正社員として採用できる制度です。入社前の業務内容や職場の雰囲気を確認できるため、入社後のミスマッチのリスクを大幅に減らせます。
事務職の経験はないものの、ポテンシャルが高く、業務習得のキャッチアップが早い若手人材をコンサルタントが適性を見極めて派遣します。
- 新卒採用が充足できなかった
- 若手の採用が進まない
- 新卒が配属されなかった
上記のようなお悩みをお持ちの方にぜひ知っていただきたいサービスです。
人材派遣からの正社員転換を検討する
若手人材を確保する有効な一手として、人材派遣からの正社員登用を検討する方法があります。
この手法は、若手にとっては「まずは経験を積みたい」「職場の雰囲気を確かめたい」というニーズを満たし、企業にとっては候補者のスキルや人柄を実務の中でじっくりと見極められるという、双方にとってもメリットのある制度です。
ポテンシャル採用に不安がある場合、派遣社員としての受け入れから始めることで、ミスマッチのリスクを抑えることができます。
M-Shineは、オフィスワーク未経験の若手人材を派遣するサービスです。ポテンシャル採用に不安がある場合、派遣社員としての受け入れから始めてはいかがでしょうか?若手人材の確保に課題を抱える企業の解決策として活用されており、本資料ではサービスの特長、サポート体制、導入企業のコメント事例などを紹介しています。
<この資料でわかること>
・ M-Shineサービスの詳細
・ M-Shineスタッフの属性・人物像 など
・ 導入企業からの声
・ 正社員登用の実例 など

まとめ
若手採用の厳しさは、今後も加速していくことが予想されます。この時代を乗り切るには、企業側が若手世代の価値観を深く理解し、「選ばれる企業」になるための努力が必要です。
採用手法の多様化、市況に合わせた待遇の見直しはもちろんのこと、若手が求める成長機会、柔軟な働き方、公正な評価を制度として確立し、SNSなどを活用して透明性高く情報発信することが重要です。特に、選考プロセスを通じて候補者一人ひとりに誠実に向き合う姿勢は入社の決め手となります。
今こそ、従来の常識にとらわれず、若手人材が魅力を感じる企業文化と採用戦略を構築し、未来の成長を支える人材確保に取り組みましょう。
こちらの資料もおすすめです


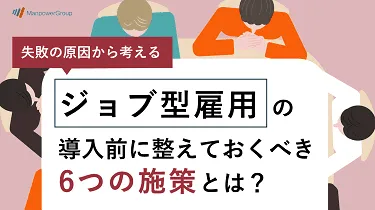

















 目次
目次