


求人広告の書き方と効果を上げるポイントを解説

目次
昨今は採用難ということもあり、「求人広告を出したのに応募者がいない」という話をよく耳にします。求職者と企業の最初の接点となる求人広告ですが、限られた中で必要な情報や会社の魅力を伝えるのはなかなか難しいことです。ここでは、求人広告を作成する上でのポイントや注意点を解説します。
「求人広告を出したのに応募者がいない」場合、採用代行サービスの活用も視野に
マンパワーグループでは、採用代行・コンサルティングサービスを提供しています。ご希望に合わせて、支援範囲を決定できるため、取り組みたい業務に集中することが可能です。ご相談やお見積りもお気軽にお申し付けください。
<この資料でわかること>
・ サービスの特徴
・ 採用支援実績
・ サービスの種類
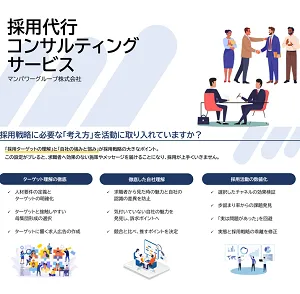
求人広告に求められること
求人広告に求められる最も大きな要素のひとつは「求職者の応募意欲を刺激して実際の応募につなげること」です。自社がターゲットとする人材から、できるだけ多くの人に興味をもってもらい、求人応募してもらうことが求人広告の役割です。
企業優位の買い手市場の環境であれば、画一的な内容でも応募者を集めることができます。しかし昨今の採用難の中では、自社にとって好ましい応募者にアピールするための工夫が必要です。
また、職業安定法の指針など、所定のルールを守った情報提供を行い、応募者が安心して応募できるようにしなければなりません。
求人広告における明示義務・禁止事項
求人広告の作成にあたっては、必ず記載しなければならない事項や、就職差別を防止するための表現方法の制限など、さまざまな法的規制があります。
代表的なものには職業安定法があり、この中に「労働者の募集・求人等における現行の労働条件等の明示義務(職業安定法第5条の3 第1項又は第2項)」が定められています。
「業務内容」「契約期間」「就業場所」「労働時間」「賃金」「社会・労働保険の加入の状況」「試用期間」「求人者の名称」「裁量労働制」「固定残業代に関すること」などが求人広告における明示義務として挙げられています。
さらに男女雇用機会均等法では性別による制限や差別が、雇用対策法では一部例外を除いた年齢制限が、それぞれ禁止されています。
これら法的なルールは、それぞれの内容を十分に確認して、必ず順守しましょう。
求人広告を作成する手順
効果的な求人広告は、自社が求める応募者の応募意欲をかき立てるために、その会社の魅力や仕事のイメージが的確に伝わるものでなければなりません。そのためにはしっかり手順を踏んで作成にあたる必要があるため、順を追って説明します。
人材要件を明確にする
初めにおこなうのは、自社が応募者に求める人材要件を明確にすることです。単に「いい人」「優秀な人」といったあいまいな要件など、広告を届けたい相手の姿をイメージしないままでは、その人材に共感される内容の求人広告を作ることはできません。
人材要件を具体化する手法の一つとして、「ペルソナ設計」があります。仮想の応募者の人材像を具体化してイメージを明確にする方法です。年齢、性別、学歴などの「個人属性」、職務経験や役職、資格などの「業務スキル」、感性や物事の考え方などの「価値観」といったことについて、それぞれ具体的な人物像を考えていきます。
アピールポイントを探す
人材要件を具体化できたら、次は、その人材像が他社と比較して魅力的に感じるであろう自社のアピールポイントを探します。自社の強みは社内ではなかなか気づいていないことがあったり、社員が思っていることと社外の人が感じる印象では、意外に食い違っていたりすることがあります。自社が求めている人材が何を求めているかという相手目線を意識し、もし直近で入社した社員がいれば、客観的な意見を聞いてみても良いでしょう。
求人原稿を作成する
いよいよ実際の記事原稿の作成です。「募集の背景」「仕事内容・やりがい」「会社の強み・雰囲気」「求めている人材像」といった主な事項を、事前に検討した「人材要件」「アピールポイント」を踏まえて、応募者の目に留まるキーワードや文言を使って表現します。情報を掲載する媒体によりますが、画像を使用して仕事風景や社内の様子を見せたり、社員紹介・インタビューで具体的な仕事内容や職場の雰囲気、人間関係の様子を伝えたりする方法もあります。
応募にあたっての必須要件と優遇要件をはっきり分けて伝えると、応募する条件がより具体的になりますが、ここであまり詳細な条件をつけると応募を躊躇されて応募人数が減ってしまうため、あまりハードルが高くなり過ぎないように注意しましょう。
また、抽象的な内容は応募者から敬遠されるので、事実や実績、数値などを用いて、できるだけ具体的なイメージがもてるように表現を工夫しましょう。
例えば、単に「未経験者可」というよりは、過去の採用実績をもとに「中途入社○名中で未経験○名」と事実を記載したり、ただ「親切に教えます」というよりは実際の研修カリキュラムを示したりするほうが、応募者は入社後の姿がイメージしやすくなります。
さらに、以降の選考や入社後での認識ギャップが起こらないように、アピールばかりに終始せず、実態をありのままに、なおかつ前向きなニュアンスで伝えることも意識する必要があるでしょう。
効果を検証する
求人広告は、出したらそれで終わり、ではありません。その後の応募状況や面接でのやり取りなどを通じて、広告で伝えたかったメッセージが伝わっているのか、その内容が共感を得られているのかといった広告効果を検証し、次回以降に向けた修正ポイントを検討しておくことが重要です。求人サイトの中には掲載後の情報修正、編集が可能なものもあるので、すぐに修正することも可能です。広告掲載後の状況に応じて、特にターゲット人材にリーチする検索キーワードや最初に目に入る求人タイトルなどを中心に見直しを検討していきましょう。
効果を上げるために意識するポイント
求人広告の効果を上げるためには、その書き方にも工夫が必要です。一般的には文章で表現される部分が多くなりますが、重要なのは「具体性」があってわかりやすいことです。
例えば、「職種名」は広告の中でも目立つ部分ですが、単に「営業」と書くよりは、「○○販売の法人向け営業」「既存顧客へのルート営業」など詳細に記載します。さらに「飛び込み営業なし」「顧客は大手企業のみ」など、具体的な情報を合わせて記載しても良いでしょう。
また応募者の目に留まるためには、興味をもってもらえるような「キャッチコピー」も重要です。ターゲットとする人材の興味や志向、想定している転職動機などに合わせてアピールできる文言を記載しましょう。ここではあまり欲張らずにポイントを絞ったほうが効果的です。
その他、目に留まる写真やデザインなどの工夫も必要でしょう。
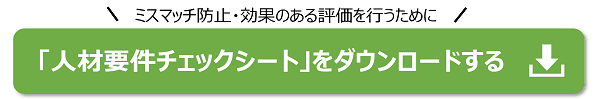
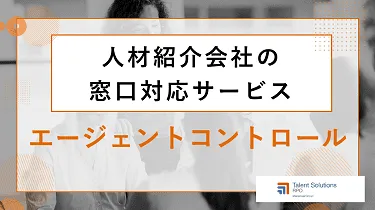



















 目次
目次