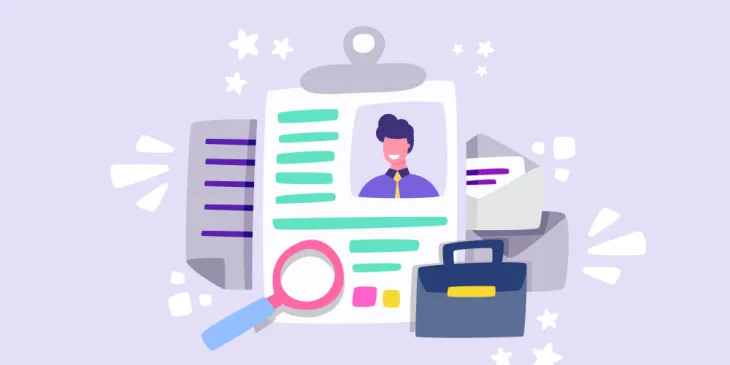


面接官のための新卒採用質問集:効果的な質問と注意点を解説
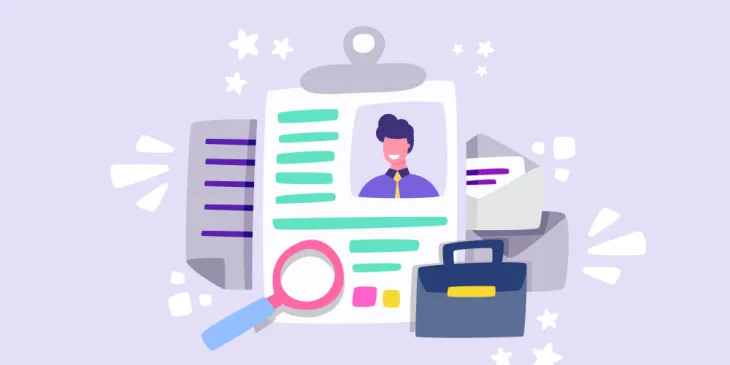
目次
この記事では、新卒採用の面接スタイルごとの特徴から新卒採用でよく使われる質問例、面接で注意するべきポイントまで詳しく解説します。
新卒採用における面接スタイル
新卒採用の面接には大きく分けて3つのスタイルがあります。スタイルによって面接も工夫する必要があるため、まずは3つの特徴を押さえておきましょう。
個人面接
最も多く用いられるのが1名の応募者と1~2名程度の面接官で行われる個人面接です。基本的には、オンラインであれば1名あたり15〜60分程度、対面であれば30~60分程度で設定されます。
グループ面接(集団面接)と異なり、他の学生との同席がないため大学名や名前、個人の活動実績などの学生の個人情報が他の学生に共有されるリスクがないこと、一人ひとりじっくり時間をかけて質問を重ねていけるメリットがあります。
新卒採用の場合、選考の初期段階を突破した二次選考以降から個人面接にするケースが多くみられます。
グループ面接
集団面接とも言い、一度に多くの学生が選考を受ける新卒採用ならではの面接スタイルです。その特性から、主にエントリーシートや適性テストなどの一次選考の次のステップによく用いられています。
学生側が2〜5名程度に対して、面接官が1〜3名程度で行われます。人数によって時間は異なりますが、一人あたり10~15分程度、全体で30~60分程度の時間をかけるのが一般的です。
一度に多くの学生に選考に参加してもらえること、選考中に学生を比較できること、自社の選考を受ける学生の傾向を判断しやすいことなどがグループ面接のメリットです。
グループディスカッション
グループディスカッションは、設定されたテーマについて学生同士でディスカッションを行う形式です。一問一答形式でやりとりをする個人面接や集団面接と異なり、面接官はその様子を確認する役割です。
4~8人程度のグループで、与えられたテーマについて30~60分話し合い、グループでひとつの結論を目指します。多くの場合、あらかじめ定められた評価シートの項目に従って各学生を採点します。
グループディスカッション後の講評で、面接官が学生に質問をする場合もありますが、基本的には面接官は発言をせず、ディスカッションの様子を見守ります。
学生同士のコミュニケーションを評価するため、面接とは異なる視点で評価できること、少ない面接官で多くの学生を選考できることなどがグループディスカッションのメリットです。
面接官の心得マニュアルをご用意しています。
新卒採用面接で使える質問集
個人面接とグループ面接では、面接官が学生と質疑応答を重ねます。見極めたいポイントごとにこれらの面接で使える質問例を紹介します。
自社の採用選考基準によって、見極めるべき優先項目は異なります。新卒採用の学生に何を求めているか、採用担当者と面接官で共有し、どのような質問をするべきか検討しましょう。
- アイスブレイクのための質問
- 学生のスキルや経験を見極める質問
- 自己理解度を確認するための質問
- 志望動機・入社意欲確認のための質問
- 企業や業界への理解度確認のための質問
- 仕事観を知るための質問
- コミュニケーションスタイルを見るための質問
- 組織の中でどう立ち回るのかについての質問
- ストレス耐性を把握するための質問
アイスブレイクのための質問
アイスブレイクとは、初対面の人との緊張する場を和ませ、リラックスしたコミュニケーションをとるために行われる、本題に入る前の雑談を指します。
とはいえ、突拍子もない質問や脈絡のない質問を行うと、学生がかえって混乱してしまう可能性もあります。面接の場に相応しいアイスブレイクになるよう配慮しましょう。
自由に回答できる「オープンクエスチョン」ではなくYES・NOで簡単に答えることができる「クローズドクエスチョン」を用いるという方法もあります。
また、あらかじめ準備されていることが期待できる質問もアイスブレイクに向いています。
- 今日はとても暑い/寒いですね。この部屋の空調は問題ありませんか?
- 弊社は駅から少し遠いのですが、迷わず来ることができましたか?
- 履歴書にトレーニングが趣味とありますね。私も興味があるのですが、いつから始めたのですか?
学生のスキルや経験を見極める質問
学生のスキルや経験は、エントリーシートに書かれている内容から判断しやすいポイントです。
エントリーシートを面接前に丁寧に読み込み、その中で特に注目したいポイントを中心に質問を組み合わせて聞き取りましょう 。具体的には、エントリーシートに記載されたエピソードに基づいて、さらなる詳細や背景を探る質問を行います。
あらかじめ学生が用意したエピソード以外の、まだ伝えられていないエピソードを確認することで、学生の長所やスキルが企業で就業する際においても発揮できるかどうかの再現性を確認できます。
- エントリーシートに飲食店でアルバイトをした経験について記載いただいていますが、どのような飲食店だったのか、そこでどのような業務を任されていたのか、具体的に教えてください。
- TOEIC800点を取得されたそうですが、受験されたのはいつのことですか?また、どのような取り組みをされたか教えてください。
- サークルのリーダーを務められたとのことですが、どのくらい数のメンバーを取りまとめていましたか?また、具体的な役割ややり遂げたことを教えてください。このほかにリーダーを任された経験はありますか?大学以前のことでも構いません。
- 学部ではどのような研究をされていましたか?これから深めていきたい研究や経験したいことを教えてください。
- アルバイトや学業、趣味などでもいいのですが、それらから得た経験や学びで仕事に生かせるものは何でしたか?
自己理解度を確認するための質問
自分をどれだけ客観的に把握しているかを確認する質問です。
自分の強みや弱みの理解は、キャリアパスの選択にも影響を与えますし、人間関係を円滑にすすめるための基礎であり、なにより成長を支える重要な要素です。
しかし、学生自身がまだ気づいていない、あるいは長所だとは考えていない点がある場合もあります。面接でのやりとりからそのような点が浮かび上がった場合は、自己分析が不十分であることを減点するのではなく、その学生の可能性を見極めることを目指しましょう。
- あなたの強みは何ですか?その強みがどのようにして生まれたのか、具体的なエピソードを教えてください。
- 自分の弱点は何だと思いますか?それを乗り越えた経験があれば教えてください。
- 周囲を巻き込む力について、メンバーからはどのように評価されていたと感じますか?直接感謝の言葉やアドバイスを受けたことはありますか?
- はじめて自分には「〇〇する力」があるのではないかと実感したのはいつのことですか?子どもの頃からでしょうか、それとも先ほどのエピソードを通して身についたものですか?
- ゼミでは〇〇についての研究に取り組まれたとのことですが、なぜそれを研究テーマにしようとお考えになったのですか?
- これまでに経験した最大の失敗は何ですか?その失敗からどのような教訓を得ましたか?
志望動機・入社意欲確認のための質問
学生の多数が社会に出て働くことについての経験や情報が限られていること、志望動機や入社意欲が選考での体験などを通じて変化していくことから、質問の回答から志望動機や入社意欲を完全に判断するのは難しいことではあります。
ただし、選考に参加している企業について調べるなど、企業について理解しようとする姿勢の有無はベースとして重要であり、入社後の適応度にも影響を与えます。入社後のミスマッチを防ぐためにも、企業の方針に考え方がマッチしているかどうかを確かめましょう。
- 募集したきっかけを教えて下さい。
- 希望されている職種(営業職/事務職/技術職など)が自分の適性とマッチしているとお考えになった理由を教えてください。
- 地元に貢献できて、ものづくりに関われるたくさんの会社がある中で、なぜ弊社に興味を持ってくださったのか、魅力に感じた点について教えてください。
- これまで説明会やOB質問会、面接などを通じて弊社の社員とお話されたなかで、特に印象に残っている人やエピソードはありますか?またそれはなぜですか?
- 当社の企業文化や価値観についてどのように感じていますか?あなたの価値観や働き方と合致する点を教えてください。
- 入社後に実現したいこと、ビジョンなどがあれば教えてください。
企業や業界への理解度確認のための質問
入社3年目までの若手社員の離職理由のひとつに、その会社の商品やサービスに惹かれて入社を決めたものの、「思っていた仕事・会社と違った」というものがあります。
先述したとおり、企業について理解しようとする姿勢があるほうが望ましいですが、それが正しく理解できているかどうかも大切です。
自分が担当する仕事内容についての理解が浅かったためギャップが生じ、仕事への意欲が持てなくなったり、能力が発揮できなくなったりする状況を避けるためには、仕事内容や業界の課題などについてある程度の知識・関心を持った状態で入社を迎えることが大切です。
- この業界に興味を持った理由を教えてください。
- 〇〇業界を中心に受けているとのことですが、〇〇業界全体について、あなたが感じる課題はありますか?
- これまで、どのような会社のインターンシップや説明会に参加してきましたか?それらの会社に、何か共通点はありますか?
- 弊社は総合職採用ですが、なかでも希望する職種や配属先はありますか?また、初任配属以降ではどのようなキャリアステップを希望していますか?
なお学生によっては、業界で応募先を絞っていないことがあります。「自社を受けているから当然同業他社も受けているはずだ」と思い込みをもって質問することがないように注意しましょう。
仕事観を知るための質問
仕事観とは、仕事に対してどのように向き合いたいかという価値観のことです。どのような価値観を持っているかに加え、なぜそのような価値観を持つに至ったかという経験やきっかけも併せて確認しましょう。
会社によっては、仕事観が一致する人を仲間として迎え入れたいと考えることが多いのではないでしょうか。共通した仕事観を求める場合、自社の採用広報を通じて学生に伝えることを意識するのがおすすめです。
- 仕事をするうえで、どのようなことを大切にしたいとお考えですか?またそのように考えるようになったきっかけは何でしたか?
- 会社は組織で動くことになります。チームで働くことについてどう考えていますか?良いチームワークを築くために心掛けていることがあれば教えてください。
- 理想とする職場環境について教えてください。その環境がどのようにしてあなたの仕事のパフォーマンスに影響を与えると考えていますか?
- インターンシップに参加して実際に社員との会話を通じて、何かご自身の仕事観に影響はありましたか?
コミュニケーションスタイルを見るための質問
コミュニケーションスタイルは面接全体を通じて確認できますが、面接慣れしている場合もあるため、自然なコミュニケーションを把握するには、具体的なシチュエーションや相手とのやり取りをイメージできるような質問を心掛けましょう。
また、面接官もオープンマインドで自己開示を心がけることでスムーズに進みやすくなります。
- 大学入学やアルバイトの初日など、初対面の人が集まる場面ではどのように振る舞うことが多いですか?自分から積極的に周りに声をかけるタイプですか?それともじっくりその場を観察するタイプですか?
- チーム内で意見が対立した経験がありますか?その際、どのように対応しましたか?
- あなたがリーダーシップを発揮した経験を教えてください。
- 困難な状況に直面した際に、どのように周囲と協力して解決に導きましたか?具体的なエピソードを教えてください。
組織の中でどう立ち回るのかについての質問
組織=チームのなかでどのような役割を担ってきたのか、どのような役回りを好むかを確認する質問です。
「ゼミは必修ではないため、資格試験や語学習得に主に時間を割いてきた」「家庭教師など個人で業務を引き受けるアルバイトをしてきた」ため、大学生活での集団行動における大きなエピソードがないと回答する学生に対しては、そこで質問を終わらせるのではなく、中学生や高校生のときに遡ってのエピソードでも構わないとするといった工夫も必要でしょう 。
また、何かシチュエーションを想定し、自分がその立場ならどのように振る舞うかという聞き方もあります。
- 今まで所属した一番大きなチームや組織はどのようなものでしたか?また、そのなかでどのような役割を担ってきましたか?
- 中学や高校ではどのような活動をしてきましたか?部活や委員会、ボランティア活動や習い事など、なんでも結構ですので教えてください。
- もしあなたがプロジェクトリーダーに抜擢され、5人のメンバーを集めることになったら、どのようなメンバーを集めますか?その理由を教えてください。
- 後輩を育てる経験をしたことがありますか?どんな学びがありましたか?
- チーム内で意見が対立したとき、どのように対処しますか?具体的な経験を教えてください。
- 会社ではさまざまな人と協力して仕事を進めます。異なる背景や視点を持つメンバーとどのような心構えが必要だと思いますか?
ストレス耐性を把握するための質問
ストレス耐性とは、ストレスの原因に対してどのように対処するか、また負荷のかかる環境にどのように適応するかといったものです。質問を通して、その学生がそもそもどんな環境にストレスを感じるのか、またそれにどのように対処するかを確認します。
ただし、これは何のためにその質問をするのかという意図を把握しやすい質問です。ストレス耐性について重ねて質問すると、「この仕事は非常に強いストレスがかかるのかもしれない」と受け取られる可能性があります。質問の仕方には注意が必要です。
- これまで何か不安で緊張したり、ストレスが原因で上手くいかなかった経験はありますか?また、その不安や緊張にどのように対処しましたか?
- これまでを振り返って、自分が最もストレスを感じるのはどのような環境に置かれたときだったと感じますか?
- アルバイトで、クレーム対応や高圧的なお客様と接したことはありますか?また、そのようなとき、どのように対処するよう心がけていますか?
面接官の心得マニュアルをご用意しています。
グループディスカッションのテーマ
グループディスカッションのテーマは、「正解がなく、多面的な物事の見方ができる」といった内容で、グループでひとつの結論を出すものが一般的です。
知識がないとディスカッションに参加できないようなテーマや、面接の場として相応しくない政治的な主義や信条などをテーマに設定することは避けます。
グループディスカッションで自社が判断したい能力、例えば論理的思考力やメンバーシップ、分析力、独創性など、評価したいポイントをよく観察できるテーマを考えましょう。
- 持続可能社会の実現に向けて、弊社が貢献できることを提案してください。
- よりよいキャリアステップとは何か、自由に話し合ってください。
- ある商品の売上データをもとに、これからどのような販売戦略を立てるべきか検討してください。
- 酷暑を過ごしやすくする、これまでにない新しい商品を提案してください。
- リモートワークが企業の生産性や社員の幸福に与える影響について議論してください。
- SNSが現代社会やビジネスに与える影響について議論してください。
面接官マニュアルをダウンロードする
面接官として知っておくべきこと、注意点をわかりやすく1冊にまとめた資料です。 下記のような方におすすめです。
「初めて面接官をするので、基礎知識を知りたい」
「面接の担当者にマニュアルを渡したい」
「面接の一連の流れを知りたい」
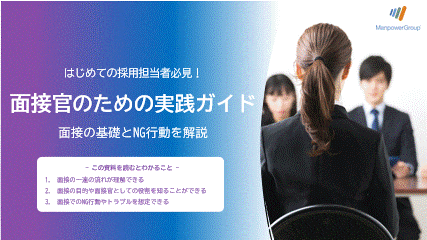
新卒採用の面接で意識するポイント
最後に、新卒採用の面接で面接官が意識するべきマナー・基本的な態度について解説します。
面接は一方的に学生を評価する場ではなく、面接官とのコミュニケーションを通じてその会社への志望度や理解度を高める場でもあります。
「どのような質問をするか」だけでなく、「どのように質問をするか」を意識しましょう。
- 学生が話しやすい雰囲気作りをする
- 共通の質問を用意する
- 一つの質問を深掘りする
- 質問への回答以外の点にも注目する
- 学生からの質問にも適切に回答する
- 不合格だと判断しても態度を変えない
- 面接の場で聞くべきではない質問をしない
- オンライン面接の場合はネットワーク環境の確認も
学生が話しやすい雰囲気作りをする
学生が話しやすい雰囲気づくりは、意識的に行うようにしましょう。学生本来の自分らしさを発揮できない場では、面接官側も自社へのマッチ度の高い人材を見逃してしまうリスクがあります。
また、「自分が伝えたいことをきちんと伝えることができた」という満足感をもって面接を終えることができると、学生も面接の結果をちゃんと受け入れることができます。
「終始面接官とのコミュニケーションが噛み合わず、なぜ合格になったのかわからない」という面接が続いてしまい、最終的にその会社への志望度も下がってしまうという話は少なくありません。
面接での雰囲気の良さは、企業に対する好印象にも繋がります。ひと昔前の本当に高圧的な圧迫面接は近年ではあまり聞かなくなりましたが、面接官が淡々と話してしまうと「圧迫感がある」「自分に対する関心がない」と感じてしまう学生もいます。
「この面接官は自分の話を聞きたいと思ってくれている」と学生が感じるような雰囲気作りをこころがけましょう。
共通の質問を用意する
学生のタイプは様々です。同じ採用基準で選考をする場合でも、多くの質問を重ねる必要がある学生もいれば、すぐに基準をクリアしていることがわかる学生もいます。そのため、全ての学生に全く同じ質問だけをする、ということは現実的ではありません。
しかし、ある程度「共通の質問」をすることによって、まったくタイプの違う学生たちを相対的に比較するというステップはあったほうが良いでしょう。
多くの場合「自己PR」「学生時代力を入れて取り組んだこと」「志望動機」「挫折を乗り越えた経験」「長所・短所」といった、多くの学生があらかじめ想定質問として準備をしているであろう質問が選ばれます。
ある程度準備してきた質問であれば、落ち着いて話すことができるため、学生の「伝えたいことを伝えられた」という満足度にも良い影響があるでしょう。
一つの質問を深掘りする
学生の自己PRをもとに、想定される能力が自社の業務で再現性があるかを確認する場が面接です。再現性を確認するためには、過去にその学生がどのような動機でどんな行動をしたのか、その頻度と強度をヒアリングする必要があります。
面接で候補者の行動や成果を具体的に評価するためには、一つの質問を深掘りするとよいでしょう。STARモデル(Situation, Task, Action, Result)を活用することで、候補者がどのような状況で、どのような課題に直面し、どのような行動をとり、その結果どのような成果を得たのかを具体的に把握することができます。
詳しくは、「【質問例あり】コンピテンシー面接とは|基礎知識とやり方を解説」で解説しています。
質問への回答以外の点にも注目する
上記のポイントで「第一印象に囚われず」と書きましたが、もちろん第一印象で判断すべき内容もあります。
一例
- 服装
- 髪型
- 爪や髭のお手入れ
- メイクといった身だしなみ
- 声の大きさや
- 姿勢
- 目線
- 敬語や挨拶といったマナー
など
これらの項目をどの程度重視するかは会社や募集職種によって大きく異なりますが、判断基準として活用するか、他の面接官がどの程度重視するかといった評価基準についてはあらかじめ確認しておきましょう。
評価がわかりやすい部分なだけに、ある面接官は一切評価対象に入れず、ある面接官は重視して評価に反映するということが起こりやすい部分です。
学生からの質問にも適切に回答する
学生が面接にあたって事前に準備することのひとつに「逆質問」があります。
昔から面接の結びの常套句として、面接官が学生に対して「何か質問はありますか?」と尋ねるのは、あくまでも学生の企業理解を深めるための「親切心」でよく使われてきましたが、最近では何を聞くかが自らの理解度や熱意に対する評価に影響すると考える学生も少なくありません。
このときに気をつけるべきことは、自ら質問を促したにも関わらず、学生からの質問に対して「それはちょっと違う部署なのでわからないですね」「それはHPを見てください」と返すなど、質問にその場で答えないことです。
もしも自分ではその場で答えられない質問の場合「後からメールで回答しますね」「少し調べますのでお待ちいただけますか」など、真摯に対応しましょう。
学生がよく逆質問として用意する質問例をいくつか紹介します。
- 内定後、入社までに取り組むべき資格や読むべき本はありますか?
- 入社後、希望する部署への異動のチャンスはありますか?
- 活躍している社員の方の共通点はありますか?
不合格だと判断しても態度を変えない
面接のその場で合否を判断できた場合、相手にそれが伝わるような言動・態度の変化がないように細心の注意を払いましょう。
特に気をつけたいのが集団面接の場合です。あからさまに学生によってコミュニケーションの時間や頻度に差が出ないように配慮してください。多くの場合、不合格となった学生だけでなく、合格の学生にとっても印象が悪くなる可能性があります。
また、面接の途中で話し方が急にフランクになる、いきなり姿勢を崩す、スマホを見る、興味が失せたように反応が少なくなるといった点にも注意が必要です。
あらかじめ面接時間を告知している場合、その面接時間を大幅に過ぎることも、極端に早く切り上げることも避けましょう。
面接の場で聞くべきではない質問をしない
厚生労働省が企業に求める「公正な採用選考」のため、面接選考の場で尋ねるべきではない、就職差別につながるおそれのある不適切な質問の例があります。
なかには、面接官自身が学生時代に面接の場で回答したような内容もあり、何が不適切な質問の例かイメージしにくい方もいらっしゃるかもしれません。
注意するべきポイントは以下の通りです。
- 本籍に関する質問
- 住居とその環境に関する質問
- 家族構成や家族の職業・地位・収入に関する質問
- 資産に関する質問
- 思想・信条、宗教、尊敬する人物、支持政党に関する質問
- 男女雇用機会均等法に抵触する質問
これらに関して具体的にどのような質問がNGになるのか、大阪労働局のサイトにそれぞれ多数の例が挙げられていますので、ぜひ参考にしてください。
参考:大阪労働局|就職差別につながるおそれのある不適切な質問の例 ![]()
オンライン面接の場合はネットワーク環境の確認も
ここ数年、面接の種類に関わらずオンラインでの面接を実施する企業はとても増えました。
面接官側も学生側も、ある程度ビデオ会議の利用経験がある方がほとんどですが、学生が用意できる通信環境には差があります。事前に準備をしていても、マンション全体の回線工事トラブルで急に遮断されてしまった……などというケースもあり得ます。
あらかじめ、万が一ネットワーク環境トラブルが発生した場合の連絡手段を学生に伝えておくこと、それ以降の面接をどのように進めるかを社内で想定しておくことが必要です。
また、面接官側も周囲の声が入らない場所、背景に社外秘の資料等が移りこまない場所で行うこと、外部のカフェなどで対応しないことなど、最低限の環境を整えましょう。
新卒採用の面接官代行・採用支援サービスとは
新卒採用は短期間に多くの学生と複数回の面接を行います。採用担当者の不足や社内から面接官を十分に出せない場合の支援として、面接官代行サービスを提供しています。リクルーターの派遣や面接周りの事務処理などもご相談ください。
面接官代行・面接官トレーニングサービス案内
年間5,000人以上の採用を支援しているマンパワーグループの面接官代行サービス案内です。下記のような方におすすめです。
「面接官が足りない」
「面接官トレーニングをしてほしい」
「面接調整などもやってほしい」
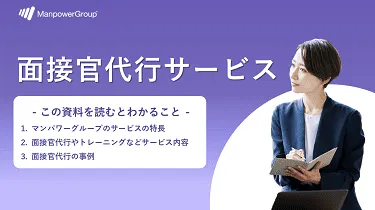
まとめ
個人面接、グループ面接、グループディスカッションそれぞれの形式にあわせて、自社の求める人物像を念頭に置き、学生一人ひとりの適性を判断するための質問例を紹介しました。
なぜその質問をしたのか、また、その回答によってどう判断したのか説明できるように意識しながら面接に取り組むことが大切です。
面接官としてのマナーとスキルを向上させ、質の高い採用活動の推進に努めましょう。
こちらの資料もおすすめです
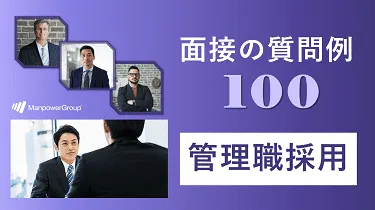

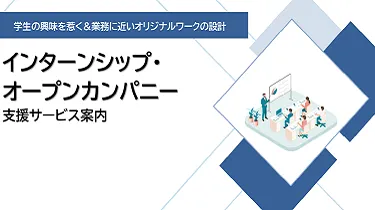

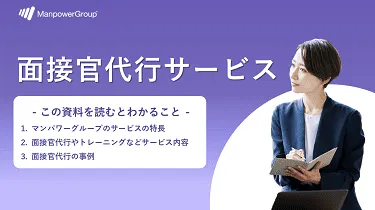


















 目次
目次