


【比較解説】雇用形態とは?5つの種類と変更する場合の注意点

目次
新たな人材の採用を検討する場合には、どのような形での雇用が最も自社の状況に合うのかを考えなければなりません。
採用担当者は雇用形態の違いを理解し、各形態に関連する制度を理解しておく必要があります。
ここでは雇用形態の定義と種類、それに基づく待遇や給与支払いの違い、さらに保険などの情報を網羅して解説します。
雇用形態とは
雇用形態とは、労働者と雇用主との間で取り決められた労働関係の形態や契約のことを指します。雇用形態により、労働条件や業務内容、給与、福利厚生などに違いがでてきます。
雇用契約とは
雇用契約とは、民法623条で明確に規定された概念です。雇用形態は、企業と労働者の双方が合意した雇用契約の内容に基づいて異なります。
通常、雇用形態は「正規の職員・従業員」や「パートタイム労働者」などの呼称を用いて分類されますが、雇用形態の種類は法律によって定められているわけではありません。労働基準法や民法ではすべて「労働者」として扱われており、法律による線引きはされていません。
労働者の定義
「労働者」については、労働基準法と民法では適用される範囲が異なるので注意しなければなりません。
労働基準法⇒「職業の種類を問わず、事業又は事務所」(「事業」)「に使用される者」
さらに、一般的には雇用される人のことを「雇用者」と呼びますが、場合によっては雇う側を指すこともあります。
この記事では、雇用される人を「雇用者」として解説していきます。そして、雇用者には「正規・非正規」と「直接・間接」の2種類の区分の仕方があります。
雇用形態の種類
雇用形態は大きく5つに分類することができます。
- 正社員(正規雇用)
- 契約社員(非正規の直接雇用)
- パート・アルバイト(非正規の直接雇用)
- 派遣社員(非正規の間接雇用)
- 業務委託(個人事業主・在宅ワーカー)
それぞれ特徴があり、雇用主も労働者も状況や要望などに合わせて雇用形態を選択しています。
次の章からは、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。
1.正社員(正規雇用)
一般的には、正社員とそれ以外とで区別されています。正社員(正規社員)は、原則として雇用期間の定めがなく、フルタイム勤務をする雇用者です。 しかし、現在は働き方の多様化により、正社員のなかにも時短勤務や変則型勤務など、さまざまな勤務時間の社員が存在しており、単なる労働時間の長短だけでは線引きが難しくなってきています。
特徴
- 雇用期間の定めがない
- フルタイムが主流だが、多様化している側面あり
正社員の種類とは
正社員には種類があり、転勤や異動が前提の総合職だけでなく、勤務地を限定する地域限定正社員、職務を限定する職務限定正社員、短時間勤務を前提とする時間限定正社員があります。働き方の多様化や求職者のニーズに合わせて、さまざまな正社員の種類が存在します。
種類の一例
- フルタイムの正社員
- 短時間労働の正社員
- エリア限定の正社員
- 変則勤務型の正社員
正社員で雇用するメリット
企業が正規雇用で採用する主なメリットは、以下の3つです。
- 人材の確保がしやすくなること
- 長期的な視点での人材育成が可能
- 優秀な人材を獲得できる
正社員は一般的に雇用期間の定めがなく、賃金や福利厚生などの労働条件も比較的良いことで安定した雇用となるため、企業の人材募集に応募する人の数も増え、求める人材の確保がしやすくなります。
さらに、正規雇用は長期的な雇用を前提としているため、時間をかけて育成することが可能です。計画的にキャリアを積ませながら将来の幹部人材を育てることもできます。
正社員で雇用するデメリット
正社員で雇用する主なデメリットは、以下の2つが挙げられます。
- 人件費負担が重くなる
- 解雇が容易ではない
正規雇用者に対しては、まとまった額の給与や賞与、退職金の支払いが発生するので、人件費負担は比較的重くなります。
また、正社員を企業側から雇用契約を解除する場合は就業規則上の解雇理由に該当する合理的な理由が求められるため、雇用の調整が必要になってもすぐに調整できません。
2.契約社員(非正規の直接雇用)
契約社員とは、一定期間の雇用契約に基づいて雇用される労働者のことを指します。契約社員は、雇用期間以外にも雇用条件や福利厚生などが正社員と異なる場合があります。
1回当たりの契約期間の上限は基本的には3年であり、契約を延長するかは企業側と労働者側、それぞれの希望が一致するかどうかで決定します。
ただし、有期の労働契約を更新して5年を超えた場合、改正労働契約法の18条に基づき、契約社員には「無期雇用に転換する権利」が発生します。企業はこれを断ることができません。
詳しくは、「【企業向け】労働契約法18条の無期転換ルールで注意すべきポイント」で解説しています。
特徴
- 1回の契約期間は3年まで
- 5年を超えた場合、無期雇用転換の権利が労働者に発生
種類の一例
- エリア限定の契約社員
- 職種限定の契約社員
- プロジェクトベースの契約社員
契約社員で社員を雇用するメリット
契約社員で雇用する主なメリットは、以下の3つが挙げられます。
- 経験やスキルが不足していても、一定期間のパフォーマンを見て正規雇用に移行することができる
- 期間限定プロジェクトなど、需要に合わせて労働力を確保することが可能
- 特定のスキルや専門知識が必要な時に、適切な人材を短期間雇用できる
働き方やパフォーマンスを鑑みて、雇用契約を更新していくことができるため、採用条件を緩和することができます。また、一定期間だけ人材を確保したい場合などにも向いています。
特に新規プロジェクトなどを立ち上げる際に、一時的に専門性のある人材を招聘したい場合などにも有効な雇用懈怠
契約社員で社員を雇用するデメリット
契約社員で雇用する主なデメリットは、以下の4つが挙げられます。
- 希望する人材が確保できない可能性がある
- 人材の入れ替わりが頻繁になり、ビジネスチャンスを失う可能性がある
- 中長期的な人材育成をしにくい
- 5年以上は無期雇用を視野に入れる必要あり
正社員に比べて雇用が不安定と感じる求職者も多いことから、ターゲットとする人材からの応募が少なくなる懸念があります。特にIT系など需要の高い職種の場合、市場調査が必要です。
契約社員を希望する求職者には、勤務形態に柔軟性を求める人が多く、より自分にマッチする条件の募集があれば他に移っていくため、人材の入れ替わりが多くなりやすい傾向があります。
その点からも、中長期視点が求められる人材育成にも注力しづらく、任せることのできる業務の範囲も限定せざるを得なくなります。ひいては正規雇用者の業務負担の増加につながる可能性もあります。
また、5年以上の契約は労働者に「無期雇用転換の権利」が発生します。期間限定プロジェクトなどでの採用は、雇用期間などを考慮して、5年以上の対策も必要です。
3.パート・アルバイト(非正規雇用)
パートタイムは、1週間の所定労働時間が正社員と比べて少ない、短時間勤務の労働者のことです。
パートタイムと似たような働き方にアルバイトがありますが、法律上の区別はありません。企業によって呼び方が異なるだけで、アルバイトもパートタイム労働者に含まれており、雇用形態としても同一です。
特徴
- 契約社員の一種だが、フルタイム以外が主流
- 契約社員同様に5年以上の雇用契約の場合、「無期雇用転換の権利」が労働者に発生
種類の一例
- 単発バイト
- 季節限定のパート・アルバイト(夏季や冬季)
- オンコールのパート・アルバイト(必要な時に出社)
パート・アルバイトで社員を雇用するメリット
パート・アルバイトで雇用する主なメリットは、以下の3つが挙げられます。
- 職種によっては母集団を形成しやすい
- 業務量に応じて人材の調整ができ、人件費が適正化されやすい
- 多様な人材を採用しやすい
企業がパート・アルバイトで採用する主なメリットは、所定労働時間などの条件を満たす必要がないため、勤務時間を柔軟に設定することが可能である点です。
そのため、勤務形態に柔軟性を求める求職者にとっても都合がよく、学生・主婦/主夫など幅広い母集団形成が可能な雇用形態です。
契約期間についても柔軟に設定できるため、企業にとっても業務量に応じた人件費の調整がしやすいという特徴があります。
パート・アルバイトで社員を雇用するデメリット
契約社員で雇用する主なメリットは、以下の4つが挙げられます。
- 労務管理が煩雑になる
- 採用コストや工数が常にかかる状態になることも
- 中長期的な人材育成がしにくい
- 5年以上は無期雇用を視野に入れる必要あり
異なる契約条件や労働時間、給与体系などが組織内で複数存在することがあります。これによって労務管理が煩雑化し、従業員のスケジュール調整や労働条件の遵守が難しくなる可能性があります。
また、学生や主婦など働ける期間や時間に制限がある人材を多く雇用する場合、人材の入れ替わりが頻繁に起こります。常に採用活動をするケースも少なくありません。
契約期間にも注意点があります。契約社員同様に「無期転換ルール」の対象となるため、5年以上の雇用契約があり条件を満たしている労働者から申し込みがあれば無期労働契約に転換しなければなりません。
関連記事:【企業向け】労働契約法18条の無期転換ルールで注意すべきポイント
4.派遣社員(非正規の間接雇用)
派遣社員は、自社と直接雇用契約を結んでいない労働者です。雇用主は派遣会社ですが、就業先は派遣先企業であり、業務を指示することができます。
雇用主と業務に従事する場所が異なることから、「労働者派遣法」によりさまざまなルールがあることが特徴です。派遣についての詳しい説明は、「【図解】人材派遣とは?仕組みと注意点をわかりやすく解説」で詳しく説明しています。
特徴
- 雇用主は派遣会社だが、業務指示が可能
- ひとりの派遣が同じ派遣先の同じ部署で働けるのは、原則3年
- 派遣禁止業務には、派遣できない
種類の一例
- 有期雇用派遣
- 無期雇用派遣
人材派遣サービスを利用するメリット
企業が人材派遣サービスを利用する主なメリットは、以下の3つです。
- 採用コストや労務管理コストが削減できる
- 即戦力の人材を確保できる
- 期間限定で労働力を確保できる
企業が直接的に従業員を雇用する場合は、採用活動を行い、採用後も労働時間を管理した上で給与を計算する手間が発生し、社会保険の負担もしなければならないですが、人材派遣サービスを利用した場合は、それらは派遣会社が負担し、採用よりも比較的早く人員を補充することができます。
また、出勤日や時間、契約期間も要望に合わせて派遣してもらえるため、適切な人件費が実現できます。
さらに、一定のスキルや経験を有する人材を派遣してもらうことで、雇用の現場で即座に活用することが可能です。
人材派遣サービスを利用するデメリット
企業が人材派遣サービスを利用する主なデメリットは、以下の3つです。
- 派遣期間に制限がある
- 派遣禁止業務がある
- 柔軟に業務を依頼することはできない
派遣社員は派遣契約で定められた業務しか行うことができないため、状況に応じて発生するさまざまな業務や契約に定められていない残業や休日出勤を臨機応変に対応してもらうことが難しいという点があります。
また、派遣先の同一部署で働けるのは3年までなどの就業期間に関する制限や派遣禁止業務など禁止事項もあります。
派遣サービスについて簡単にまとめた資料をご用意しています。
⇒「5分でわかる はじめての派遣サービス導入ガイド」をダウンロードする
5.業務委託(個人事業主・自営型テレワーカーなど)
企業が個人事業主や会社経営者などの自営業者あるいは自営型テレワーカーなどに対して、業務を依頼する場合があります。
この際に両者の間で交わされるのは雇用契約ではなく、業務に関する委託契約となります。
業務の遂行に対して対価が支払われ、原則として指揮命令を受けないため、先に挙げた「労働者」には区分されません。従って雇用形態の種類のなかには含まれないことに注意が必要です。
特徴
- 「雇用」ではなく「業務契約」を行う
- 業務指示をしてしまうと、「偽装請負」とみなされる
- 専門的な知識が必要な業務を依頼しやすい
種類の一例
- 業務の遂行を委託する
- 成果物の納品を依頼する
自営業者(個人事業主など)に業務委託するメリット
企業が業務委託を利用する主なメリットは、以下の3つです。
- 業務品質と効率の向上
- 採用コストや労務管理工数が削減できる
- 人員配置の最適化
業務委託を請け負う会社は、ノウハウと専門性があることが多く、業務品質が高まるだけではなく、業務効率が良くなります。また、業務に従事するメンバーの雇用や管理は、委託先が担うため労務管理工数が大幅に削減されます。
大きなメリットとして、従業員がコア業務に集中できる環境ができる、また人材という経営資源を最適化することが可能です。
自営業者(個人事業主など)に業務委託するデメリット
企業が業務委託を利用する主なデメリットは、以下の3つです。
- 業務遂行に対する指揮命令ができない
- セキュリティリスクがでてくる
- かえってコストが上がることも
業務委託相手に対して、企業は都度指示することはできません。行った場合、雇用関係にあると見なされ、「偽装請負」とみなされる恐れがあります。そのため、業務の遂行方法に対して企業は口を挟むことができなくなります。
また、自社の情報を外部企業と共有するわけですから、セキュリティリスクも高まります。アウトソーシングのメリット・デメリットについては、「アウトソーシングとは?メリットを引き出す導入ステップを解説」をご覧ください。
雇用形態の種類による違い 一覧
雇用形態によって、労働に関する法律や雇用契約が異なります。管理する側では、こうした違いについて明確に区別をしておく必要があります。
雇用形態の違いを比較表で確認しておきましょう。
| 雇用形態 | 主に関連する法律 | 雇用期間 | 主な 給与体系 |
社会保険 | 福利厚生 | 雇用契約 |
| 正社員 | 労働基準法 | 無期雇用 | 月給 年俸 |
雇用企業で加入 | 雇用企業の 就業規則による |
直接雇用 |
| 契約社員 | 労働基準法/ パートタイム・有期雇用労働法 |
有期雇用 | 月給 日給 |
雇用企業で加入 | 契約内容による | 直接雇用 |
| パート アルバイト |
労働基準法/ パートタイム有期雇用労働法 |
有期雇用 | 時給 | 雇用企業で加入 | 契約内容による | 直接雇用 |
| 派遣社員 | 労働基準法/ 労働者派遣法 |
有期雇用 無期雇用 |
時給 | 人材派遣会社で加入 | 人材派遣会社/ 派遣先企業に準ずる |
間接雇用 |
正社員は雇用される企業の就業規則に従います。休日や有給休暇などの適用に関しては労働法の規定に基づき、給与や賞与・手当は企業の規程に基づいて支給されます。
契約社員は契約期間内の昇給はなく、契約の取り決めに従った給与が支給されます。休日や有給休暇の扱いについては、正社員と同等です。
条件を満たしている場合、社会保険も正社員と変わりなく適用されます。契約期間満了時で契約が終了した場合には、「退職」として扱われます。
パートやアルバイトの場合では社会保険に適用条件があり、その条件を満たすことで対象となります。2018年から社会保険の適用範囲が拡大され、パートタイム労働者の保障がより厚くなりました。
派遣社員の給与・手当の支給、社会保険及び福利厚生については、すべて派遣元である人材派遣会社が管理します。指揮命令権は派遣先の企業にありますが、派遣社員の社会保険や健康管理については、派遣元が義務を負います。
各雇用形態それぞれの社会保険の適用範囲・条件
正規雇用
企業は、雇用者ごとに、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入させる必要があります。
労災保険は業務災害や通勤災害に対する補償、雇用保険は失業後の生活の保障や教育訓練の補助、健康保険は私傷病に対する補償、厚生年金保険は老後の生活や障害時の保障がされる公的な保険制度です。
非正規直接雇用
労災保険は非正規直接雇用であっても、すべての雇用者に加入させる必要があります。
雇用保険は、次の条件を満たす非正規直接雇用者に対して加入させる必要があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 雇用契約締結時に31日間以上働く見込みがある
- 学生ではない
健康保険と厚生年金保険は、週の所定労働時間が正規雇用者の4分の3以上ある非正規直接雇用者に対して加入させる必要があります。
なお、従業員数が101人以上の企業は、前記の内容に関わらず、次の要件を満たす非正規直接雇用者に対して加入させる必要があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月の支払い給与額が88,000円以上
- 雇用契約締結時に2か月間を超えて働く見込みがある
- 学生ではない
※2022年10月1日からは、従業員数が101人以上の企業も対象。2024年10月以降からは51人以上の企業も対象。
非正規間接雇用(派遣社員)・業務委託
非正規間接雇用(派遣社員)は派遣会社が雇用しているため、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入は派遣会社が行います。
業務委託を行う自営業者に関しては、企業との間で雇用関係が存在しないため、自営業者自身が加入します。
なお、自営業者に関しては、雇用保険への加入はできません。
雇用形態を変更する際の注意点
働き方に対する考え方の多様化や社会の変化に対して柔軟な組織をつくるなどを背景に、雇用形態の多様化が進んでいます。
しかし、今の雇用形態を変更する場合は、それぞれ注意しなければいけない点があります。
関連記事:雇用形態の多様化│企業成長の鍵とするには
直接雇用から非正規直接雇用(パート等)への変更
直接雇用(正規社員)から非正規直接雇用(パート等)へ雇用形態を変更する場合、給与などの労働条件が下がる「労働条件の不利益変更」が生じるため、注意が必要です。
育児や介護、病気などの理由で雇用者から非正規直接雇用への変更を申し出た場合は、そのことを企業が了承することで問題は生じませんが、業績の悪化などの企業側の理由で企業側から変更を申し出る場合は、雇用者の同意が必要となります。
雇用者の同意なしに一方的に労働条件の不利益変更を伴う雇用形態の変更をした場合、労働契約法第9条違反に問われてしまいます。
双方合意のもとで雇用形態の変更が行われた場合、その後のトラブル発生を防止するために、変更後の労働条件を明記した雇用契約書を新たに作成することが望ましいです。
直接雇用から非正規間接雇用(派遣社員)への変更
正規雇用/非正規雇用を問わず、正社員・パート・アルバイトなどで直接雇用をしていたスタッフは、離職から1年以内は派遣社員として迎えることができません(60歳以上の定年退職者は除く)。
禁止対象となる派遣先は事業所単位ではなく事業者単位のため、同じ企業の別部門・別支店での受け入れも禁止されています。
非正規間接雇用(派遣社員)から直接雇用への変更
派遣社員を直接雇用に切り替える際は、派遣会社に申し込みの上、基本的に派遣契約終了後に契約内容にもとづいた方法で行います。派遣会社との協議が進めば、雇用契約条件を派遣社員に提示し合意があれば、直接雇用に切り替えることができます。
なお、労働者派遣法では派遣先企業に対して「雇入れ努力義務」と「募集情報の提供義務」を規定しています。雇い入れ努力義務とは「一定の要件を満たす有期雇用の派遣社員を就労させている派遣先企業は、その労働者を雇入れるよう努めなければならない」というものです。
一方、募集情報の提供義務とは、派遣社員の「派遣先での正社員化推進」や「雇用安定措置」を目的とした制度のことで、一定の要件を満たす派遣社員には社員の募集情報を提供する義務があります。派遣社員を雇い入れる際はいずれの義務についてもチェックしておきましょう。
関連記事:【人事担当者向け】派遣社員を直接雇用に切り替える方法
紹介予定派遣とは
派遣契約時から直接雇用を前提とする紹介予定派遣サービスを用いる方法もあります。
紹介予定派遣は、派遣会社から紹介された採用候補者を派遣社員として受け入れ、派遣期間中に正式採用の可否が判断できる、雇用形態の変更を前提としたサービスです。派遣期間を経て、雇用者・候補者双方の合意が取れた場合、正式に自社の社員として採用が決定します。
但し、労働者派遣法で「派遣期間は最長6カ月」と定められているため、派遣社員としてそれ以上の契約延長は認められていません。正式に採用が決定した場合には、派遣会社への手数料が発生します。手数料率は派遣会社によって異なりますが、一般的な手数料相場は年収の20~35%程度です。
国の制度として、直接雇用/間接雇用を問わず、非正規労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取り組みを実施した事業主(会社)に対して助成金を支給する「キャリアアップ助成金制度」があります。
積極的な人材確保を実施したい場合には、活用すると良いでしょう。
「同一労働同一賃金」をおさえておこう
2021年4月1日より、すべての企業に「同一労働同一賃金」が適用されることになりました。
正規雇用者と非正規雇用者との非合理な処遇格差の是正を目的とした法律であり、その意味として「仕事内容が変わらない正規雇用者と非正規雇用者との間で、説明がつかないような処遇差を設けることは止めてください」ということです。
正規雇用者と非正規雇用者の賃金を必ず同等にしなければならないということではなく、仕事内容が同じである場合に、非正規雇用者だからという理由で処遇に差をつけてはならないという内容です。
仕事内容は、「職務の内容」「責任の程度」「配置の範囲」で判断します。
詳しくは、厚生労働省の同一労働同一賃金特集ページ ![]() を参考にしてください。
を参考にしてください。
まとめ:雇用形態の違いを知って正しい対応を
雇用形態の違いを活用することで、就業時間や契約期間を調整しながらの人材確保が可能となります。
雇用を行うに当たっては、雇用形態に対する理解を深めた上で、雇用者ごとに必要な対応を行わなければなりません。これに対して、国は、雇用形態による不合理な待遇差の是正を求めた法案の整備を進めています。
企業側に、社会保険の適用や給与体系、休暇の付与など、すべてにおいて公正に対応していく姿勢が求められています。
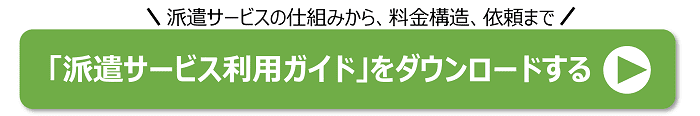




















 目次
目次