


採用KPIの立て方│設定と運用のポイントを具体例で解説

目次
業務管理に用いる基準には、定量的かつ客観的な評価が可能な、数値化した指標を設定することが非常に重要です。
採用活動も例外ではなく、プロセスの効率性や質を向上させるためのKPI(Key Performance Indicator)の設定が不可欠です。採用におけるKPIは、「採用KPI」とも呼ばれ一般化しています。
とはいえ、これから採用KPIを設定する場合、具体的にどのような指標を設定すべきかを課題としている方も多いのではないでしょうか。
本稿では採用活動におけるKPIの適切な設定と運用方法に焦点を当て解説します。
採用代行サービスの活用も視野に
採用KPI達成には、効率的な採用活動の実践がカギとなります。
マンパワーグループでは、採用プロセスの業務代行、採用戦略立案や採用プロセス設計などのコンサルティングを行う採用代行(RPO)サービスを提供しています。
採用KPIの設定や運用方法に不安がある、あるいは採用活動におけるボトルネックを解消したいなど、採用にまつわる課題がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
採用KPIとは
KPIと共によく使われる言葉にKGIがあります。まずは、そもそもKPIとKGIとはなにかを説明し、それらがなぜ採用活動においても重要なのか、また、どのような数値を指標として用いられているのかを解説します。
そもそもKPIとKGIとは
KPIとはKey Performance Indicatorの略語で、重要業績評価指標、主要業績評価指標または主要パフォーマンス指標と訳されます。
目標を達成するために必要とされるプロセスに使われる指標で、営業活動を例にすると、顧客訪問数や新規顧客の獲得数などがKPIにあたります。
KGIはKey Goal Indicatorの略語で、重要目標達成指標と訳され、最終目標を表す指標です。営業活動を例にすると、売上目標額や利益の目標額がKGIにあたります。
つまり、最終目標であるKGI達成の過程における中間目標がKPIです。「KGIを達成するために、いつまでに、なにを、どの程度、実施しておく必要があるか」をKPIとして設定していきます。
なぜ、採用活動でもKPI・KGIが重要なのか
採用KPIの設定によって目標達成までのプロセスと状況が可視化され、具体的な行動への落とし込みが容易になるという利点があります。
さらに、現在の採用手法が妥当かどうかの判断材料ともなり、改善箇所の早期把握と改善実行が可能です。
また、採用KPIを設定することで採用に関わるメンバー間で目標の共有ができるため、目標達成に向けてのチームワーク強化も期待できます。
採用KPI・KGIの指標選びのポイント
では、採用活動におけるKPIとKGIには、指標としてどのような数値が一般的に使われているのでしょうか。
多くの場合、採用活動におけるKGIは採用人数であり、KPIはKGIで設定した指標から逆算された各工程の数値が設定されています。
例えば、KGIを「○月までにX名採用する」とした場合、代表的なKPIとして「エントリー数・面接実施者数・内定者数」や「面接合格率・内定承諾率」などが挙げられます。
採用KPIの具体的な設定方法とは
代表的な採用KPIには、面接実施者数や内定承諾率などがあると述べましたが、採用KPIの立て方としては、これらをそのまま流用するのではなく、自社の採用活動において何が最も価値のある要素なのか、どの指標が本当に成功につながるのかなど、自社の課題や戦略に合致した指標を検討することが肝要です。
次に、採用KPIとなる各種指標とともに、採用課題や優先事項を考慮に入れた場合、どのような数値を重視すべきかについて解説します。
採用プロセスからみる具体的なKPIの指標例
まずは、採用KPIを設定する前に、まずは、採用活動の一連の流れ(採用フロー)を書き出します。
一般的な採用フローを例に用いて説明します。
- 求人を出す
- 説明会やインターンの実施
- 書類選考および適正検査
- 面接(場合によって複数回)
- 最終選考
- 内定
- 内定承諾
- 入社
上記フローであれば、KPIには以下のような指標が考えられます。
- 応募した人の数(チャネル毎の応募率または応募者数)
- 応募者に対する書類選考や適性検査の通過率(書類選考通過率または書類選考通過数)
- 設定できた面接に対して実際に面接を行った比率(面接実施率または面接実施数)
- 面接を通過した人に対して合格を出した比率(面接合格率または合格者数)
- 内定を出した人に対する入社した人の比率(内定承諾率または内定者数)
KGI(採用目標)に応じたKPIの設定方法
採用活動におけるKGIは、採用人数と採用の質の両面から考える必要があり、自社の状況によりどちらを重視するべきかが異なります。それによって、取り上げるべきKPIも変わってきます。
採用人数を重視する場合のKPI
目標とする採用人数が多い場合、応募者数の確保や、書類選考の通過率を高くする、面接設定数を多く設定するなどの必要があります。
この場合、これらの目標件数を指標とするのも大切ですが、ただやみくもに応募者数や選考数を増やしても、コストや労力が増えるだけで、最終的な採用人数増に影響しないこともあるため、他の指標を加えることも検討すべきです。
採用条件を緩和するなどして母集団の間口を広げた場合、企業や業務内容に対する理解が不足している、あるいは、志望動機がまだ固まりきっていない応募者が含まれていることがあります。
方針として、そういった応募者を除外せず、選考途中の離脱が発生しないよう、入社意欲が高められるような面接・対応を行うとした際、それが有効に働いているかを判断するためには、「面接した人数からみた入社率」が重要な指標となってきます。
また、採用人数を重視する場合には、今後の事業計画や経営目標を達成するために必要な人員数だけでなく、予想される退職者数も考慮することを忘れないようにしてください。
採用の質を重視する場合のKPI
候補となる人材としっかり向き合い厳選採用を行う、採用者の「質」を重視する採用の場合、募集要件に合致した応募者を集められているか、選考できているかということを意識する必要があります。
その場合、書類選考からの面接設定率や、各工程における通過率が重要なKPIの指標となります。
面接等の通過率があまりに低い場合、関係者間で優先順位などを含めた募集要件の認識にズレがある、合否判定の基準にバラツキがあるなどの問題が考えられます。
もうひとつの重要な指標は、内定辞退率です。
厳選した選考のうえで内定を出したにも関わらず、本人承諾に至らず辞退が多いとなると、工数が多くかかっている分、ダメージが大きくなってしまいます。
選考ごとの入社意思確認や自社のアピールは適切にできているか、面接官の態度に問題が無いかなど、KPIの数値を通して問題を探していきましょう。
効果的な採用KPIの管理・評価方法の紹介
採用KPIの設定後は、設定した指標を効果的に管理・評価し、採用プロセスの改善に役立てていくことが重要です。
ここでは、KPIのモニタリングと改善、そしてKPIの結果分析と採用戦略の見直し方法について説明します。
採用KPIの定期的なモニタリングと改善
せっかく設定したKPIも適切に運用されなければ、期待する効果を得ることができません。定期的にモニタリングを行い、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを常に回しながら日々のKPIに対する進捗率を管理することが重要です。
採用フローを整理し、各フェーズでの数字やデータをExcelや採用管理ツールなどを用いて収集する仕組みを構築します。そして、定期的なモニタリングを通じて、KPIに関連するデータを追跡し、KPIに対する進捗率や達成率のチェック・評価を実施しましょう。
評価は、週次あるいは月次や四半期ごとなど、ある程度まとまった期間で実施されることが多いですが、測定結果は日次・リアルタイムで適宜チェック出来る状態にあることが望ましいです。
採用プロセス全体が設定された期限内に進行しているかどうかの判断や必要に応じた調整がしやすくなります。
採用KPIの結果分析と採用戦略の見直し方法
採用活動を進めていくなかで、設定した採用KPIと現状に剥離が生じることがあります。都度原因と改善策を検討し、次の行動を決めなくてはいけません。
例えば、一次面接の実施率がKPI設定した数値より低い場合、前後のフローでKPIの進捗を振り返り、どこに課題や原因があるのかを突き止め、改善策を練ることが重要です。
応募者数が目標値を達成していないのであればターゲットに効果的な求人広告を出せているかどうか、書類選考通過率が想定値以下であれば求職者に必要以上のスキルを求めていないかなどを、見直してみましょう。
また、先に紹介したような各KPIを採用メンバーの個人目標に落とし込むことも効果的です。自身のやるべき行動がイメージしやすくなり、効率的に作業を進めることができるでしょう。
人材育成における個々人の目標設定の重要性や設定方法については「人材育成における適切な目標設定とは?」で詳しく解説しています。
採用KPI設定時の注意点
以下に、採用KPIの設定に際して留意すべきポイントを示します。
KPIは数多く設定すればいいものではない
採用KPIを過度に設定するのは禁物です。多すぎるKPI<は採用担当者の負担を増やし、モチベーションの低下やタスクの過剰な複雑化につながる可能性があります。
数値への固執は禁物
KPIの数値に固執するのも避けるべきです。採用活動は目標人数の達成が主要な目的ではあるものの、候補者のスキルや経験、企業との適合性、意欲やモチベーションなど、数値化しづらい定性的な要素も適切に評価する必要があります。
数値にばかり気が取られていると、長期的な成果である組織の発展を阻害してしまう可能性もあります。小さなことばかり気にかけて、大局を見失ってしまっては意味がありません。柔軟性を持ちながら目標達成に向かった調整を行いましょう。
KPIの明確な定義と共有は必須
採用KPIの設定には、KPIの明確な定義と共有が欠かせません。KPIがどのように計測され、どのデータを使用するのか、関係するメンバーと共有しましょう。これにより、メンバーが目標達成に向けて協力しやすくなります。
KPIの設定・管理で問題点の把握が容易に
採用活動においては多くの業務が日々進行し、その効率性を確保することが不可欠です。KPIの導入により、採用活動のポイントや優先課題、問題点をリアルタイムで把握することが可能です。
採用プロセスごとにデータを管理することで、進行状況の遅延などの課題を素早く発見し、解決策を実行できます。
フロー変更などが生じた際などは、都度適切なKPIを柔軟に設定しなおしていくことで、採用活動の質をあげることができます。自社の状況に最適化された採用KPIの運用を目指していきましょう。
マンパワーグループの採用代行・コンサルティング サービス
こちらの資料もおすすめです
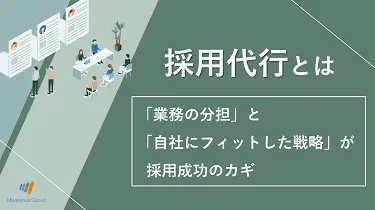



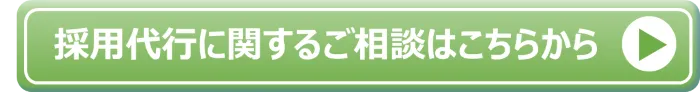
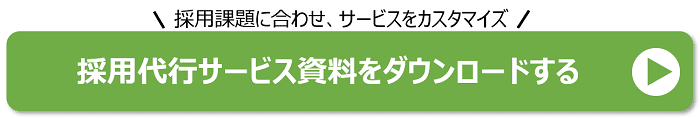
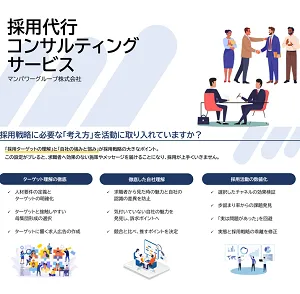


















 目次
目次