


失敗例から学ぶ新卒社員の教育|5つの育成ポイント

目次
人材不足の中、多くの企業が新卒社員の組織に対する早期適応と定着に力を入れています。一方で、新入社員の早期離職率は減少することなく「3年で約3割が辞める」状態が続いています。
今回の記事では、新卒社員の教育で陥りがちな失敗例と現代の新卒の特徴を考慮した効果的な新卒社員教育のアプローチについて、具体的に解説します。
新卒社員教育の目的と重要性
新卒社員教育の目的は、新卒社員がいち早く組織に貢献出来るよう、社会人としての基本的な知識および業務上必要な知識やスキルを習得させることにあります。新卒社員に正しい教育を行い育成することで、自社の生産性が向上し会社全体の士気も上がります。
アルバイトやインターンシップなどの経験があったとしても、新卒社員は、社会人としてのマナーやビジネスの基礎知識、自社の価値観やルールを深く理解していない状態が一般的です。
この状態のまま職場に配属すると、新卒社員は仕事の意義を見出せず、モチベーションの維持もままなりません。上司や先輩社員にも負荷がかかり、結果、職場全体の生産性低下につながります。
まずは、上司や先輩社員によるOJTなど現場での指導を実施する前に、それを効果的に実施するための素地づくりが必要です。
早期に独り立ちできるようなサポートが重要
新卒社員の教育を適切かつ効率的に行い、新卒社員全員の立ち上あがりの速度と確度をあげていくことが非常に重要です。
社会人としての適応力を高めるための「業務に関する基礎知識と基本スキル」「自社の価値観やルールに沿った行動」を理解する場によって、職場配属前に新卒社員を「自律的に仕事を教わることができるレベル」まで引き上げます。
近年、新卒社員研修は座学でビジネスマナーを学ぶだけでなく、ゲーム要素のあるものや、ロールプレイング、グループワークなど参加型の研修が取り入れられ、実践的なスキルやコミュニケーション能力を磨くための新たなアプローチが広まっています。対象者との相性を踏まえたうえで、これらの施策の導入を検討してもいいでしょう。
キャリア開発・階層別・課題別のセミナー
マンパワーグループのライトマネジメント事業部は、人材育成・組織開発などを中心にサービスの提供を行っています。人材育成分野では、さまざまなタイプの研修メニューを用意しており、課題や状況に合わせたカスタマイズも対応可能です。ご興味のある方は下記の資料をダウンロードください。

新卒社員の教育に力を入れるべき3つの理由
新卒社員の教育の重要性は前述したとおりです。早期退職が続いている場合やこれから新卒採用に力を入れたい場合は、新卒社員の特性を踏まえ、これまでの新卒社員教育内容の見直しも検討する必要があります。ここでは、先述した社会人としての素地づくり以外の新卒教育に力を入れるべき3つの理由と効果を解説します。
生産性の向上
新卒社員への指導は、上司や先輩の時間や手間がかかることは事実ですが、時間軸でみると新卒社員の育成は職場の生産性向上につながります。短期的な手間をみるのではなく、「投資」と「リターン」での視点で考えましょう。
新卒社員の教育はまさに組織にとっての戦略的な「投資」です。新卒社員が仕事を習得すれば、組織の適材適所を叶えるための選択肢が広がり、組織全体の業務効率の向上という大きな「リターン」に繋っていくのです。
モチベーションの向上
新卒社員教育を機能させることにより、職場全体のモチベーションがあがります。
新卒社員は、自社の事業や取り組む仕事の意義を教育中に教わることで、仕事に対する誇りが生まれます。結果、同じ作業への取り組みでも「相手にどう喜んでもらうためのものか」が意識できるようになるため、作業をただこなすだけにならず、モチベーション高く取り組めるようになります。
また、新卒社員が仕事を覚え、できることが増えることで成長へのモチベーションも向上します。新卒社員でも職場で役にたっている実感があれば、「ここにいても大丈夫」と安心できますし、その結果が評価や報酬に反映されることで、モチベーションが高い状態が続く好循環へとつながります。
上司・先輩などの職場のメンバーも、新卒社員が成長するにつれ、育てがい・やりがい・喜びに繋がります。さらに新卒社員が仕事を覚え、活き活き働くことが、いい刺激になり、職場全体の活性化する好循環になります。
早期離職を防ぐ
新卒社員教育を行うことで、早期離職を防ぎやすくなります。理由は3つあります。
理由1 やりがいと成長感を覚える
今の新卒社員はラクな仕事よりも、「仕事に取り組む価値」や「成長の実感」で会社や職場を選ぶ特徴があります。事業や業務への理解を深める機会がやりがいと成長感をうみ、早期離職の抑制に繋がります。
理由2 職場に新卒社員の居場所ができる
居場所がある安心感から、コミュニケーションに忖度や遠慮がなくなり、素直なやりとりが増えます。コミュニケーションを通して、上司・先輩含めた職場の人々との絆が深くなることも引き留めに繋がります。
理由3 「同期」意識が芽生え、同期でお互い助けあう、横の繋がりが強まる
今の新卒は一人の時間も大事ですが、SNSの普及によりグループでの繋がりも大事にしています。一人では挫折しそうだけど、同期の支えや叱咤激励、刺激があるから、残って頑張れるという新卒社員も少なくありません。
コミュニケーションツールが今のように発展していなかった昔は、配属後、同期とは帰宅後に電話する、飲みに行く、会議や研修で集まる時しかコミュニケーションが取れませんでした。
今は、同期とグループLINEやチャットやメール、zoom等で繋がれるツールも増えています。同期とこまめに繋がれるので孤独に陥らずに済むことも早期離職の防止に役立っています。
関連記事
若手社員の早期離職については、「若手が早期退職してしまう理由とは?退職阻止で心がけることを解説」をご覧ください。
動画セミナー:「なぜ若手・中堅社員は会社を去るのか?」を見る ![]()
新卒社員の教育担当者が失敗する4つの代表例
新卒社員教育の失敗は早期離職や悪評の原因になりかねない要素になるため、注意したいところです。
社員教育に関するスキルを身に付けた人事担当者や研修講師をきちんと配属して研修を実施する企業もありますが、特にトレーニング等を受けていない職場の上司・先輩が新卒社員の教育・指導にあたるケースも多くあります。
指導方法が今の時代にあっていなかったり、新卒指導に慣れていなかったりするなどして、熱心に指導することが逆効果になることが多々あります。新卒社員への指導で陥りがちな失敗の代表例と理由、対処方法を解説します。
高圧的・逆説的・感情的な指導
指導役が高圧的に感じる指導はやってはいけないと自覚しているつもりでも、「パワハラされた」と新卒社員が受け取ることは多いものです。
なぜ、そのような事態が起きるかというと、
- 新卒社員に指導する立場が、自分が偉くなったと錯覚する
- 新卒社員に舐められたり、馬鹿にされたりしてはいけないと感じる
などの心理が働いてしまうからです。
また、勇気づけるつもりで「私が新卒の時はすぐできた」など、自分の新卒時代や新卒社員のあるべき姿と比較して「あなたならもっとできるはずだ」と激励する言動は、今の新卒にとっては強いプレッシャーをかけられた、差別され否定されたと受け取られかねません。
人は、好き/嫌いに関わらず自分の指導経験が強くインプットされてしまうため、これまで自分が習った通りに指導してしまうことも、パワハラ指導に繋がります。
また、物事の本質を自分の頭で考えられるようになってほしいと、正攻法な問いかけを用いず逆説的に問うことも、新入社員には経験値が少なく基本を一から学んでいる最中なので、答えるには荷が重すぎます。
そもそも今の新卒社員は「競争するより協業しよう」というフラットな意識が高く、大学の友人や部活・サークル、バイト先含め、同質性が高い人の輪の中で育ってきているため、体育会系でも昔のような上下関係の強さはありません。
新卒社員にとって、会社組織にいることすら未経験の異文化体験です。感情的な指導にも慣れていないため、想定している以上に受け止めきれないものです。その結果、上司・先輩には悪気がなく、逆に新卒社員に気を使っているにも関わらず、パワハラ認定されてしまうこともあるのです。
関連記事
パワハラについては、「パワハラ防止法とは?企業に義務付けられた措置の対応方法を解説」で詳しく解説しているのでご確認ください。
意図しないパワハラを防ぐには?
それを防ぐには、教育担当者は、自分の新卒時の経験を含めた「新入社員とはこういうものである」という新卒社員像にはとらわれず、自分達とは全く違うキャラクターだと割り切るのが早道です。
新卒社員を部下や後輩ではなく「対等な関係」だと捉えると、指導のスタンスや内容を柔軟に切り替えることができ、ストレスなく効果的に指導しやすくなります。
相手が対等な関係なら、上司や先輩の言うことを聞かない方が悪いという姿勢ではなく、相手の視点に合わせて伝え方を変えてみようという意識に切り替えられるので、おすすめの方法です。
動画セミナー:「法令順守だけでは根絶できない!?
パワハラが起きにくい職場のつくり方」を見る ![]()
業務内容の説明が不十分
新卒社員に仕事を割り当て、具体的に指示をしても、意図とずれたこと結果が生じることがあります。
新卒社員は全ての業務が未知であり、業務の全体像や目的、目指すアウトプットもイメージできていません。教える方は業務内容を把握しているので、新卒社員から見えている世界や誤解に気づきにくいのです。
新卒社員に仕事を割り当てる時は、きちんと手順に沿って説明することが重要です。業務の流れや手順に沿って説明することで、新卒社員は作業内容だけでなく、どんな成果物を出せば良いかも理解できます。
また、手順に沿ってどう進めればいいかわかるので、安心して作業に取り込むことができますし、目的とずれてくるなど違和感を覚えれば、上司・先輩に確認や指示を的確に求められるようになります。
業務の背景や目的を説明しない
新卒社員が、業務内容の詳細を知らないのは当然の前提です。1から全てを教え込もうとするのではなく、まずは簡単な作業を切り出し、段階的に習得を促すというアプローチは一般的な方法です。しかし、そこにも落とし穴はあります。
「習うより慣れる」の感覚で「まず、やってみて」と実際に作業する手順や内容についてのみ指示を与えると、実際に作業をしながら勘所を掴んでいくことに納得感がうまれ、仕事に貢献している感じが出るのは事実です。
ただし、それだけでは具体的な指示どおりの作業をこなすことに特化してしまい、応用力を発揮することができません。ただ単に指示に従って作業を繰り返すだけでは、成長や貢献の実感もなく、新卒社員本人のモチベーションもあがらなくなります。
新卒社員は仕事の全体像がみえていない段階にあります。与えられた仕事や指示が、「誰の仕事にどう繋がるのか」「最終的に、どんな成果に結びつくのか」など業務全体や最終的な成果とどのように関わっているのかが把握できていないため、与えられた指示の範囲をこなすことしかできず、応用力が発揮できません。
「受け身社員」にならない解決法
指示待ち姿勢の社員をつくらないための解決方法は簡単です。
「急がば回れ」で作業指示に加え、業務の背景や目的、最終成果を伝えることです。担当する作業がどのように最終成果や目的に繋がっているのかの流れを理解することで、仕事の全体感や自分の役割の重要性が掴め、モチベーションとやりがいが上がります。
全体感を把握することで、似た業務や目的にも応用が効き、仕事への理解と応用力が向上します。
改善策を言わない・言いすぎる
新卒社員が担当した仕事が不十分だった場合、改善策を適切に伝えることが重要ですが、伝える情報量のバランスをとるのが難しい場合があります。
新卒社員はまだ業務に不慣れなので、自ら改善策を考えることを求める前に業務に慣れさせる「習うより慣れる」のアプローチをとることがセオリーと言われてきました。
この方法をとると、ひたすら指示どおりに作業と修正を繰り返す、あるいは「ここまでやってくれてありがとう。後はこっちで修正するね」と、途中で上司や先輩が業務を引き取るといった光景がよく見られます。
でも、ここで考慮すべきは新卒社員の心理状況です。現代の新卒社員には、「上が絶対。言われた事をただやればいい」というような昔の体育会系のノリはなく、自分の頭で考え、納得し、理解したうえでの「正解」を求める思考が強い傾向にあります。
つまり、単に指示どおりに作業をこなすだけのアプローチは効果が限られており、言われた作業をする以上の事を考えず、気を回さなくなるなどのモチベーション低下や、新卒社員は「使えないやつだと思われた」と自尊心が傷ついてしまう可能性があります。
これを解決するには、「自分達の頃はこうだったから」と決めつけるのではなく、新卒社員の心理状況に配慮し、適切なバランスをとることです。
「慣れれば見えてくる」「できない段階で改善策を考えさせるのは可哀そうだし、パワハラだと思われそう」という新卒社員に対する勝手な思い込みを捨て、指示を受けるだけではなく、自分で考え、提案する機会を設け、新卒社員が自身の成長に貢献できるようにサポートすることが必要です。
改善策の情報量が多すぎると消化できないことも
一方で、改善策の説明が詳細で具体的であっても、伝える量が多ければ、新卒社員の負担になることがあります。
「説明の情報量が多く理解できなかった。だが、理解できないと言うとさらに説明が増える。そうすると余計に覚えられないのではないか。」と考えてしまい、これ以上情報量を増やさないためにとりあえず「わかりました」と返事してしまうなどの悪影響があります。
さらには、新卒社員が理解できていないことを察した教育担当者が「もっと丁寧に、わかりやすく、具体的に伝えなくては」とさらに伝える情報量を増やすという悪循環に陥るケースもあります。
適度な情報提供のためには、指示や説明をする業務の量と粒度を調整し、理解するのに過度な負担をかけないように心がけることです。また、新卒社員が質問や疑問が浮かべられるような余裕を持たせると、教育担当者との適切なコミュニケーションを促すことができます。
指導がわかりやすいか、納得感があるか、成長した感覚を持てるか、そもそもついていきたいと感じるか?など、アンケート調査をするなどして実施新卒社員からのフィードバックを受け取り、教育担当者には指導方法を適切に調節し、バランスをとるようにしてもらいましょう。
新卒の教育担当が心得るべき5つのポイント
新卒社員教育を成功に導くためには、対象となる新卒社員の個人の特性や志向を理解する必要があります。対象である社員を理解し、時代に合わせ育成方法や内容を柔軟に調整していくことが重要です。
これからは、先述した失敗例を踏まえた、時代にあわせた新卒社員教育を実施するための5つのポイントを紹介します。
「育てる」ための7つの視点
外部講師を招くこともありますが、通常、教育担当者は職場の上司や先輩が担うのが一般的です。その役割は指示通りの作業を教えるだけではありません。教育担当者の役割は、新卒社員を「育てる」と強く理解しましょう。
ただし、「育てる」という言葉は、人により異なる解釈や想いが含まれやすいため、教育担当者全員が解釈や想い、その背景も含めた共通認識を持つことが重要です。
具体的には、以下のスキルと視点が「育てる」ことに必要とされています。
- 作業の単なる実行法だけではなく、業務の流れと役割を理解させる
- 「何をする(タスクの内容)」だけでなく「こうすればうまくいくコツ」を伝えて、問題の解決・改善策を考える能力を養う
- わからないことは抱え込まず「報連相」など適切なコミュニケーションによる正しい理解を深めさせる
- 自社の文化や価値観に適合した判断力を養う
- 正しく褒めることで、「何をどうすればOKなのか」を理解させ、促進させる
- コミュニケーションを通じて新卒社員のモチベーションを引き出す
- 新卒社員が1~6を納得し、変な忖度などなく素直に行動に移せるようにする
7まで出来れば、新卒社員も上位方針や職場の状況を捉え、自律的にPDCAを回せられるようになります。
忘れてはいけないのは、単に仕事のスキルを伝えるだけではなく、自社らしさとその人らしさを一緒に成長させる視点で新卒社員と向き合うことです。
今の新卒社員は、自分らしくしなやかに活躍できる環境を求めており、教育担当者である上司や先輩のコピーをつくる一方的なスタンスでは今の新卒者はついてきません。
変に気を使う必要はありませんが、「部下・後輩」という上から目線ではなく、「職場の人はすべて同僚」だという共感と尊重のスタンスを持ちましょう。
「伝え方」と「聞き方」で信頼関係を作る
一方的な情報提供ではなく、対話を通じたコミュニケーションを構築しましょう。新卒社員の主観(優先度と判断基準)を踏まえ、それにあわせた情報提供が大切です。
新卒社員はビジネスコミュニケーション自体も不慣れです。教育担当者が新卒社員一人一人の立場や視点を考慮しながら伝えることで、新卒社員は「自分の事を理解してくれたし、わかりやすかった」と信頼関係を築くことができます。
また、コミュニケーションをしやすい状態にするために、教育担当者や先輩に声をかけやすい環境を整えることも重要です。
新卒社員にとって質問や確認をすることは勇気がいることです。業務についてもう一度確認したいと思っていても「できてない、ダメなやつだ」「こんなことを聞いてくるのか、ちゃんと聞いていたのか」と教育担当者に思われたら怖い、と聞けずにいるケースもあります。
コミュニケーションのポイント
新卒社員がコミュニケーションを取りやすくする工夫の一例として、「最近どう?」と世間話的に話かけてみる、ランチに誘う、隣の席に座って一声かける、趣味など自身のことを教育担当者から率先して自己開示するなど、新卒社員が自分のことを話しやすい雰囲気を作るなどがあります。「関心を持ってくれている」という印象を与え、心の距離を縮めやすくなります。
ただし、ランチミーティングは参加必須あるいは、参加が評価に影響するなど実質強制参加に近い状態での開催は業務時間扱いになるため、その点は注意しましょう。
伝え方も重要です。同じ事を伝える場合でも「こまめに報告して」ではなく、「重要なポイントだから、ここで確認した方がいいよね」と相手を尊重する伝え方の方が新卒社員は安心してコミュニケーションを取りやすくなります。
現代の新卒社員世代は「私が責任を取るから任せる」という上下関係ではなく「任せるね。でも、もしトラブったら一緒にやるから遠慮なく声をかけてね」と並走してくれるアプローチの方が受け入れやすいようです。教育担当者の指導する言葉も、新卒社員世代に受け入れられやすいものにアップデートすることが重要です。
「ソラ・アメ・カサ」のフレームワークで目線合わせをする
新卒社員に任せた仕事が、指示どおりに進めていたにも関わらず上手くいかないのはよくあることです。
このような状況下において、上司や先輩社員がリカバリー策を講じたり、再発しないよう上司や先輩の視点から指示をより詳細に説明しようとしたりするのが一般的ですが、意外と効果的ではありません。
なぜなら、教育担当者と新卒社員の持つ視野は、往々にして経験則から異なるためです。
同じ視野で物を見ること、つまり、目線を合わせるのは簡単なようで難しいものですが、コツがあります。
「報連相」ではなく「ソラ・アメ・カサ」のフレームワークを活用する方法です。「ソラ・アメ・カサ」はマッキンゼーの日本支社で考えた思考やコミュニケーションのフレームワークで、次の要素から成り立っています。
- ソラ(事実):事実を示す
例 空が曇ってきた - アメ(洞察):事実を踏まえた洞察や考え
例 (空が曇ってきた事実を踏まえた洞察)雨が降りそうだ - カサ(判断):洞察をもとにした判断
例 (洞察を踏まえ)傘を持っていこう
このソラ・アメ・カサをセットにすれば目線が合い、正しく伝わるというものです。報連相は、ソラ・アメ・カサにおける「ソラ(事実)・カサ(判断)」だけで、「アメ(洞察)」が抜け落ちます。
ソラ・カサでアメがないと「どうなりそうか」の読みの目線にズレが生じるため、同じ打ち手を行うにも温度差やズレが生じてしまいます。このアメの解釈の差が目線のズレの原因です。
新卒社員と「ソラ・アメ・カサ」を共有することで、新卒社員は目線のズレに気づき、どう解釈すればよかったのかを理解し適切な判断ができるようになり、成長が促進されます。
相談できる場を作る
教育担当者と新卒社員がうまく噛み合わない場合もあります。これは、教育担当者とて完璧な存在ではなく、避けられないことです。そのため、新卒社員が教育担当者以外に相談できる場も用意しておきましょう。代表的な方法としては、メンター制度、相談窓口制度があります。
メンター制度とは、新卒社員や教育担当者の上司に当たらないナナメ上の上席や、他部署の先輩等にメンター(相談役)になってもらい、定期的な面談や、新卒社員が相談したい時に相談できるようにする仕組みです。
新卒社員は教育担当者に直接利害関係がない人に相談することで、違う視点からヒントを得ることができます。メンターからのアドバイスで、教育担当者が伝えたかった意図が理解しやすくなるケースも多いものです。
伝えたい本質は一緒でも、個々のキャラクター(個性)やアプローチの違いから、指示やコミュニケーションがうまくいかないこともあります。
例えば、テレビゲームで打撃力に特化したキャラクターがスピード力を重視するステージに挑むのが難しいように、教育担当者のアプローチと新卒社員のスタイルがマッチしないこともあるでしょう。
教育担当者の熟練度が低いと、ひとつのアプローチ方法でしか伝えられこともあります。新卒社員のキャラクターに合ったメンターからアドバイスを受け、本質は同じだと理解することで新卒社員教育を充実させる一助となるでしょう。
教育担当者の上司や人事に相談する「相談窓口」は、いわば最終手段です。「物理的にどうにもならない時の助け舟」とすることで、新卒社員の早期退職を防ぎ、教育担当者の成長や新卒社員の定着を促すことに活用しましょう。
動画セミナー:「1on1ミーティングを組織に定着させる処方箋」を見る ![]()
マニュアルを作ってもらう
新卒社員に仕事を任せる際、業務全体の流れや位置づけの理解促進と、行き詰った時のガイドブックとして活用するため、マニュアルを渡すのも一般的な方法です。
新卒社員教育をさらに充実させるには、新卒社員自身にマニュアルをアップデートしてもらうといいでしょう。特にアップデートの際に焦点をあててもらいたいのは、「注意点」と「コツ(How To)です。
経験豊富な社員は業務を行う時の勘所やコツを身に付けていますが、初心者はこれらを把握していません。上司や先輩は業務を理解した上でマニュアルを作成しており、初めて実施する人が陥りがちな「注意点」を見逃してしまうことも少なくありません。
新卒社員には、指示やマニュアルどおりに進めたものの、行き詰まったり、判断に迷いがでたり、上手くいきにくかったりした箇所をピックアップし、教育担当者とアップデートするようにしてもらいます。
これにより、今まで可視化されていなかった勘所・注意点・コツが浮き彫りになります。その結果、新卒社員は業務の手順だけでなく、勘所・注意点・コツも習得し成長が促進されます。
年々、「マニュアルのバージョンアップ」を行えば、新人向けにますます内容が充実したガイドブックが完成するはずです。
まとめ
教育担当者は、誰もが新卒社員だった時の自身の経験をもとにした指導を行ってしまいがちですが、過去の経験に固執することは、新卒社員個々の特性や価値観を無視することになり、良かれと思ってやったことでも時代に合わず失敗に繋がってしまいやすくなります。
新卒社員教育は単なる一過性のプロセスではありません。新卒者員がいずれ教育担当者として未来の新卒社員を指導する、そのスタート地点です。部下は上司や先輩の背中をみて育ちます。社員の成長と企業の発展に向け、新卒社員のマインドを踏まえた新卒社員教育を行うスタンスを、未来の教育担当者にも引き継がれるように、新卒社員教育の今を変えていくことをおすすめします。
こちらの資料もおすすめです


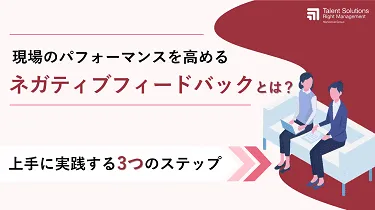

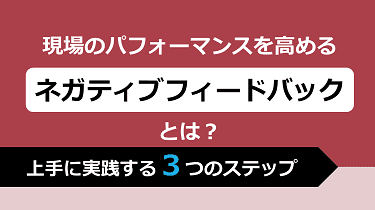
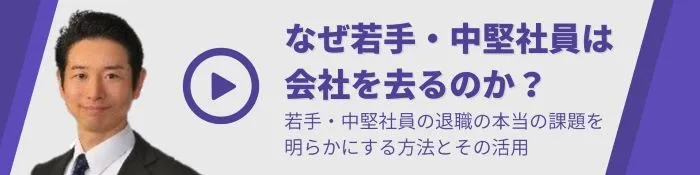
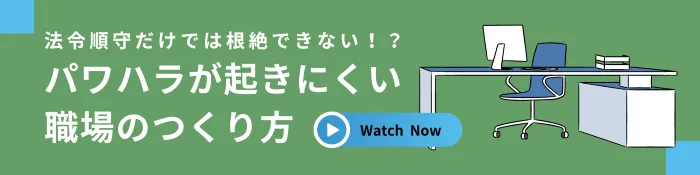
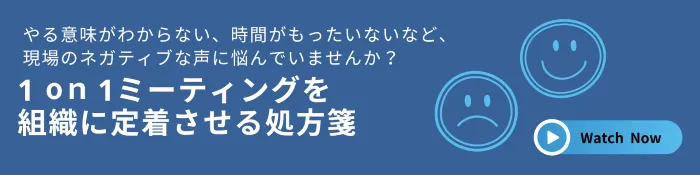






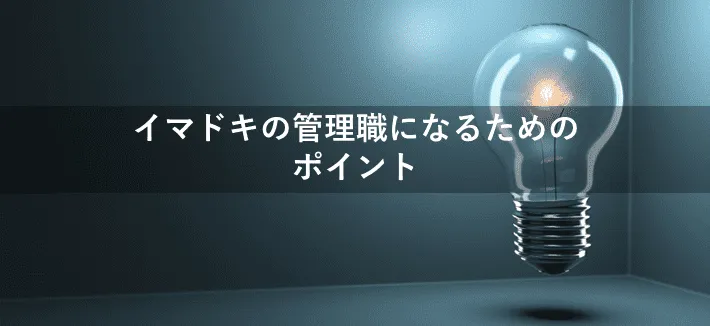











 目次
目次