


リクルーター制度とは|制度導入のステップと成功のポイント

目次
リクルーター制度とは、社員による採用活動を制度化したものです。
日本では、一般的に新卒採用で導入されており、以前から大企業の新卒採用を中心にさまざまな企業で活用されています。この記事では、新卒者を対象としたリクルーター制度について解説します。
リクルーターとは
そもそもリクルーターとは、広義では「人を募集する仕事をする人」を指す単語で、一般的に採用に携わる社員のことを指しています。
リクルーターは自社社員である社内リクルーター以外にも、クライアント企業のために人材を見つける仕事をする人材紹介会社の社員(エージェンシーリクルーター)も、リクルーターに分類されます。
また、社内リクルーターにおいても、採用担当者として専任で担当する場合と、営業や製造など他の主業務との兼任で担当するケースがあります.
新卒採用におけるリクルーターは、社内リクルーターの一種で多くは採用担当部門外から、若手社員を中心に選出されます。
<若手社員がリクルーターを担当する理由>
- 学生と年齢が近いことから共通の話題が多く学生が打ち解けやすい
- リクルーター側も自身の経験から学生の状況を理解しやすい
- ターゲット校の卒業生の場合、人脈をいかした関係構築が可能
リクルーターの役割
新卒採用におけるリクルーターは、学生と企業をつなぐ架け橋の役目を担います。
母集団の拡大
母集団形成はリクルーターの役割のメイン要素と言っても過言ではありません。
リクルーターは学生に積極的にアプローチし、優良な母集団の拡大を目指します。
具体的な活動
- 後輩にコンタクトを取る
- 教授に推薦を依頼する
- 求人データベースからスカウトする
- 就活サイトからプレエントリーを行った学生へのアプローチ
- 出身大学のゼミやサークルに出向き、気になった学生へコンタクトを取る
- 大学で企業説明会を実施する
自社の魅力付けを行う
採用担当者よりも身近な「先輩社員」という立場で、学生個々の理解度にあわせた情報提供ができるのが、リクルーター制度の強みです。
具体的な活動
- 就職に向けてのフォロー(自己分析の手伝い、アピールポイントの発見、簡潔かつ効果的なアピール方法の伝授)
- 自社の情報や魅力を伝える
- 個別や少人数とコミュニケーションの場を設ける
リクルーターが、ターゲット層に「この会社で働きたい」と思せる情報発信を実施するには、「採用ブランディング」の考え方が役立ちます。
「採用ブランディング」については、「【徹底解説】採用ブランディングとは?進め方と展開方法、導入事例」で解説しています。
選考の評価者
企業によっては、一次面接あるいは、リクルーター面談をリクルーターに任せるケースもあります。
リクルーター面談とは、学生とリクルーターが面談を行うことを指し、「リク面」として学生の間でも広く認知されています。
一般的に、役職者との面接のような堅苦しい雰囲気のものではなく、カジュアルな雰囲気で行われるため、企業と学生の双方が相手をより一層理解しやすくなる効果があります。
リクルーター制度のメリット・デメリット
リクルーター制度のメリット
優秀な学生を確保できる
リクルーター制度の最も大きなメリットは、自社に興味をもっている優秀な学生と早期の段階でコンタクトをとることができる点です。
今や、多くの企業がインターンやリクルーター面談など、早い段階から学生との接点を持つ活動を取り入れています。
政府が要請している新卒採用スケジュールでは、採用選考活動の解禁は、6月1日以降とされています。しかし、面談は面接と異なり、選考の合否判定を行う場でないため、学生と密接なコミュニケーションを早期に取ることが可能な手段として活用されています。
近い距離感で魅力を伝え、動機付けできる
前述したとおり、リクルーターは卒業生や年齢の近い社員が担当することが多く、学生の身近な存在としてコミュニケーションを取っていきます。
募集要項やホームページ、会社説明会などでは伝わらない自社の魅力を伝えられ、また、採用担当者には直接聞きにくいと感じる質問も、近い存在のリクルーターになら気軽に尋ねやすいという利点もあります。
インターネットの普及で、SNSなどから多くの情報を得られるようになった一方、昨今ではその情報の正確さや信ぴょう性は不確かなものになっています。
ネットの情報だけに流されず、事実確認をきちんとしたいというニーズは高まっているため、学生に近い距離でしっかりと情報を伝えることで、不安を払しょくし、興味関心を高め、応募へとつなげることが可能です。
ミスマッチの防止につながる
2024年にマンパワーグループが実施したアンケート調査では、8割超の人事担当者が新卒採用後のミスマッチを経験したと回答しており、うち約6割がミスマッチの結果「採用した人が早期退職した」とも回答しています。
情報不足による「こんなはずではなかった」というミスマッチをできるだけ抑えるためにもリクルーター制度は有効です。
リクルーターとのやりとりから、短い面接でのやりとりだけでは知ることができない学生の特性やキャリア志向を確認し、自社の社風に合う人材かどうかの検討材料にできます。
また、学生側も説明会や面接だけでは得ることができない情報を、リクルーターを通して知ることで、より具体的に就業後のイメージを持つことができます。
「攻めの採用」ができる
ナビサイトや自社サイトでの募集は、募集を告知し学生の応募を待つ、いわゆる「待ちの採用」です。アピールの仕方によっては、多くの学生の応募を集めることができる反面、大勢に向けてのアピールであるため、狙ったターゲット層から応募が確実にあるかという点については未知数です。
採用活動が解禁されると特に、学生は膨大な量のメールを受信します。DMを送っただけでは、興味を引くことが難しく、開封さえしてもらえないこともあります。
リクルーター制度には、企業が能動的に動く「攻めの採用」という側面があります。リクルーターがターゲット層である学生との接点を積極的に増やし、学生それぞれの状況に応じた情報提供やフォローを行うことで、自社についてより深く訴求することができます。
面接・内定辞退防止にも
リクルーターの役割は、学生を集めるだけではありません。学生との信頼関係構築による「囲い込み」「ロイヤリティ向上」も大きなポイントです。
リクルーターが、選考や入社における不安や疑問、面接対策をはじめとした学生の様々な相談にのるなど、継続して学生との接点を持ち信頼関係を築くことで、学生の企業に対する興味関心を継続させ、面接・内定辞退の防止に繋がります。
また、「すでに信頼できる相談相手がいる」ことで、入社に対して安心感や前向きな姿勢を持ちやすくなります。
リクルーター制度のデメリット
リクルーター制度の導入時には、想定される以下の事項に対して事前に対策を立て、円滑に運用できる方法をしっかりと検討する必要があります。
社員の工数がかかる
リクルーター業務専任として任命する場合は大きな問題にはなりませんが、ターゲット校出身の社員などにリクルーター業務を兼任させるケースでは、通常業務に対する影響が少なからずでてきます。
また、所属部門の理解も必要です。業務の調整や、リクルーターとしての活動を鑑みた評価を行うなど、担当社員に大きな負担や不利な状況とならないよう調整が求められます。
リクルーター次第では逆効果になる
リクルーターは学生に近い立場で活動するため、リクルーターの言動は学生の企業に対する印象に大きく影響します。自社の魅力を強く訴求できる一方、誤った対応をすれば不信感を持たれ、悪評が広がるリスクもあります。
そのため、リクルーターを担う社員は慎重に選定する必要があり、教育研修の実施も重要です。特に、普段から採用業務を担当していない社員の場合、やるべき/やるべきではない行動のポイントなど、採用担当者が当たり前だと思っていることを必ずしも共通認識として持っているわけではないことに注意が必要です。
事前の研修などで、採用担当者内では暗黙の了解とされているような事項でもきちんと共有し、リスクを低減しましょう。
また、公平性を欠く対応にも注意が必要です。自社が求める人物像を理解し、個人的な価値観や第一印象などの主観に偏らない評価がリクルーターには求められます。
- 採用プロセスが不明確
- しつこい勧誘
- 連絡の頻度が多すぎる、非常識な時間帯の連絡
- 上から目線や高圧的な態度
アプローチできる学生が限定され、多様性が失われる
通常、リクルーター面談は1対1で実施するため、一人のリクルーターが対応できる学生数や学校数には限りがあります。
その結果、リクルーターがアプローチする学生は、同じ出身校やインターン参加者中心に限定されがちです。これにより、応募者の多様性に欠けてしまうことも懸念事項としてあげられます。変化に強い組織であるためには、人材の多様性は必要な要素です。
リクルーター制度の強みは、特定の層の学生に深くアプローチできる点にあるので、多様性確保のためにはオンラインイベントや広報活動などを実施するなど、幅広いバックグラウンドの学生にリーチする工夫を別途行うとよいでしょう。
リクルーター制度導入のステップ
ステップ1: 目標設定と計画
はじめに、リクルーター制度導入の目的を明確にし、具体的な目標を設定します。
制度の成功には社内からの理解が不可欠です。特に、リクルーター業務と通常業務を兼任する社員がいる場合は、上司や同僚の協力が重要です。
計画段階のうちに、上層部に対してリクルーター制度の意義やメリットを周知し、制度が効果的に運用される土壌を整えましょう。
ペルソナ設定の重要性
効果的な目標設定には、「どのような資質やスキルを持った人材が何名必要なのか」を明確にすることが重要です。
採用担当者とリクルーターが事前にターゲット層について共通の認識を持つことで、齟齬のないアプローチが可能となります。
そのため、ターゲット層のペルソナをできるだけ具体的に設定し、リクルーターに共有することが目標達成への鍵となります。
理解促進とフォロー体制
リクルーター制度の運用にあたり、経営層や関係部署からの理解を得るため、説明会を実施します。
リクルーターが通常業務から離れる際のフォロー体制を事前に整え、負担軽減に配慮します。
さらに、採用イベントや出張にかかる経費の精算方法などの社内ルールを明確にしておくことも必要です。
ステップ2: リクルーター選定とトレーニング
リクルーターの選定基準を明確にし、対象者への育成プログラムを構築します。特に、新卒採用では採用活動が主業務でない社員がリクルーターを兼任することもあるため、「企業の顔」としてのトレーニングが必要です。
選定基準
年齢が近い若手社員をリクルーターに選ぶことで、新卒者が身近なロールモデルとして接しやすくなります。また、自社事業や業界動向に詳しく、採用者の質問に的確に回答できるベテラン社員も適任です。
リクルーターに向いている人材とは
- 自社について深く理解しており、自社に対してエンゲージメントが高い人材
- アピールと傾聴のバランスが取れた高いコミュニケーション力
- 社内で評価の高い人材
- 客観的で公平な対応・判断ができる人材
- 訪問予定大学のOB/OG
トレーニング内容
リクルーター向けトレーニングでは、求める人材像の具体的イメージを共有し、選考基準に対する理解を統一します。これにより、リクルーターが目指すべき人物像を把握し、一貫したメッセージを新卒者に伝えられるようになります。
また、新卒者対応のマナーや、質問しやすい雰囲気づくりなどについてもカリキュラムに組み込んでおくといいでしょう。
ステップ3: 制度の運用と管理
制度の運用に際しては、リクルーター活動を定期的にモニタリングし、フィードバックを収集します。リクルーター活動開始後も、リクルーターとの定期的なコミュニケーションは不可欠です。
採用活動の進捗状況を確認するとともに、リクルーターたちが抱える課題についてもきめ細かく拾い上げ、対処していきましょう。
ハラスメント対策
リクルーターハラスメントへの対策も欠かせません。新卒者と早期接触をはかり、ときには個人で連絡を取り合うこともあるリクルーター制度を悪用し、新卒者にセクハラやパワハラをするケースが問題になっています。
これに対して、厚生労働省は職場におけるセクハラ・パワハラ行為の禁止について「就職活動中の学生等の求職者、労働者以外の者(個人事業主などのフリーランス、インターンシップを行う者、教育実習生等)に対しても同様の方針を併せて示すこと」とする指針を発表しています。
社内報、パンフレット、社内ホームページ等へのハラスメント行為の禁止に関する記載や、それらの周知・啓発のための研修・講習等を実施など、従業員に対する対策と同様の具体的な対策が企業に求められています。
すでにリクルーター制度を設置している企業では、1対1での面談時には社内や公共の施設を利用することや、飲酒の誘いや異性からのOB訪問は禁止することをルールに盛り込むなどの対策が実施されています。
新卒者が将来一緒に働く可能性のある大事な仲間であることを伝え、リクルーターハラスメントへの対策を講じましょう。
参照:
就職活動中の学生等に対する ハラスメント防止対策を強化します!|厚生労働省 ![]()
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)|厚生労働省 ![]()
面接官代行・面接官トレーニングを導入してみませんか?
マンパワーグループでは、採用支援の一環で面接官トレーニング・面接官代行サービスを提供しています。ご興味のある方は、ぜひ資料をご覧ください。
ステップ4: 成果の評価と報告
最後に、リクルーター活動の成果を評価し、経営層への報告を行います。
リクルーター制度を成功させる4つのポイント
人物像を具体的に共有する
リクルーター制度の重要な役割は、「ターゲット層の学生を集め、志望度を高める」ことです。
学生に近い距離でコミュニケーションを取れるという特徴をいかし、学生の資質やパーソナリティ、キャリア志向などを確認し、「この企業なら自分に合っていそうだ」と、学生の応募意欲を引き出すことがリクルーターには求められます。
そのため、リクルーターにはターゲット層をより深く理解してもらう必要があります。 採用担当者とリクルーターで、事前にターゲット層に対する認識合わせを行い、齟齬が起きないよう努めましょう。
ポイントは、以下のような人物像をできるだけ具体的に共有することです。
- 能力(思考や学力など)
- スキル(専門性や資格、学生時代の経験など)
- パーソナリティ(コミュニケーションのスタイル、価値観、キャリア志向など)
これらを曖昧にしたままだと、ターゲット層が求める要素にあわせたアプローチが難しく、せっかく時間をかけて学生とコミュニケーションを取っても、ターゲット層からの応募につながらないという結果になりかねません。
リクルーター自身の自社に対する理解度を上げる
ターゲット層と接触するだけで、応募が増えるわけではありません。学生の興味関心を引きだし、「会社説明会に参加する」「エントリーする」など具体的なアクションにつなげるアピール力がリクルーターには必要不可欠です。
学生のなかには、SDGsなど社会的貢献に対する企業の姿勢を重視する人もいます。ただ会社概要を伝えるのではなく、「どのような考えで商品やサービスを提供しているのか」「どんなポリシーをもった企業なのか」など、学生の関心に応じた回答やアピールができるようにしましょう。
また、社風やキャリアパス、仕事に求められることなど、会社説明会やホームページだけでは知ることができない「生の声」を伝えることで、働くイメージがより具体化しやすくなり、応募意欲の向上につながります。
こうした役割を実行するためには、リクルーター自身が自社について深く理解していなければいけません。自身の業務とあまり関わっていない他部門の新しい取り組みや事業なども知っておく必要があります。
そのためにも、学生に対して魅力付けができる人材の選抜と、事前に時間の研修が重要です。
ただし、学生を集めたいからと良い面ばかりを強調すると、ミスマッチや早期離職の原因となりかねません。入社後のことも想定し、誠実で適切な情報提供を心がけましょう。
候補者と信頼関係を構築する
学生との信頼関係は、リクルーター制度の成否に関わります。信頼できないリクルーターの会社に応募しようとは思えないものです。信頼関係の強化は、志望度や最終的な入社意思の決定にも寄与します。リクルーターは常に「会社の顔」としての自覚をもって活動しなければなりません。
信頼関係を構築するために意識すべきポイント
- 学生の不安に親身になって相談にのる
- しつこい勧誘は避ける
- 適切な距離感を保つ
- こちらから声をかけ、言いにくい質問や不安を聞き取る
- 学生の話をよく聞く(傾聴)
学生と年齢の近い社員をリクルーターにするケースが多いのは、親しみを感じてもらいやすくするためです。ただし、信頼関係が構築されるのはいいことではありますが、同時に適切な距離感を保つことも意識しましょう。
採用代行サービス(RPO)の活用も視野に
新卒採用におけるリクルーター制度の導入は、企業にとって大きな効果をもたらす半面、人材の選抜、業務工数や求められる知識など導入の壁になる課題もあります。
リクルーター制度には、人事以外の社員の協力が不可欠です。制度設計や運用、効果測定、問題点の見直しなど関係者には多くの負担がかかります。
新卒採用はただでさえ多忙を極める業務です。忙しいからと片手間でやってしまうと、逆効果になりかねません。リクルーターが気軽に相談できる環境や、制度運営を担う社員のフォローも必要です。
社内ノウハウや人手が不足している場合には、リクルーター業務を採用代行サービスに委託する方法もあります。プロフェッショナルの支援により、効率的な採用活動が期待できます。ただし、委託にはコストが発生するので、実績やスキル、得意とするターゲット層などをしっかりと確認するのが重要です。
新卒採用における採用代行サービスの一例
採用代行サービスでは、リクルーターの代行だけではなく、さまざまなサービスを受けることが可能です。
新卒採用は中途採用とは異なり、多くの学生へ向けた説明会の開催や、選考を行うため、案内や各種調整にまつわる業務が一時的に増大します。しかし、そのような状況でも、ひとりひとりの学生に対して迅速かつ丁寧な対応は欠かせません。
こうした一時的な業務をアウトソースすると、社内リソースが確保でき、学生対応の品質を維持しやすくなります。
業務一例
- ナビサイト提案・初期設定(管理画面設定、定型メール設定・配信・更新・修正)
- ナビサイト管理(エントリー受付、説明会・適性検査・面接設定、学生データ分析、各種レポート作成)
- 会社説明会の企画立案、当日運営
- 会社説明会スライドショー、当日配布資料提案、説明会アンケー作成・集計
- 説明会・選考事前連絡
- 説明会・適性検査・面接日程調整
- 書類受付・書類選考・合否通知
- 応募者対応(当日連絡、受電架電対応等)
- 内定者フォロー
- 入社後フォロー
- インターンシップのサポート
新卒採用をニーズに合わせて支援
新卒採用の計画から新卒研修支援まで、新卒採用をご要望に合わせて支援するサービスを提供しております。初めて新卒採用をしたい、カバーしてほしい業務がある、など様々なニーズで利用いただいております。
<この資料でわかること>
・ 新卒採用支援サービスの提供内容
・ 採用成功に向けたプロセスとポイント
・ 支援実績や導入事例のご紹介

リクルーター制度の成功には入念な準備が必要
リクルーター制度の導入は、優秀な人材の早期発掘や確保に効果を発揮します。しかし、準備が不足していては期待する成果は得られません。
リクルーターには、自社の魅力や採用基準など、採用活動に関する重要な情報をしっかりと共有する必要があります。また、リクルーターだけでなく、関係者含む全社員の理解と協力も欠かすことができません。
厳しい採用競争のなか、企業の将来を担う優秀な人材を採用するために、リクルーター制度の有効活用を検討してはいかがでしょうか。
こちらの資料もおすすめです

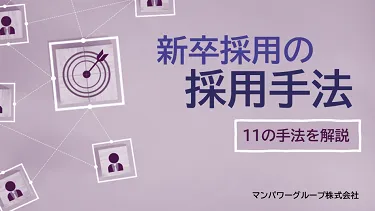

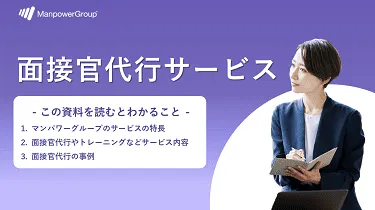
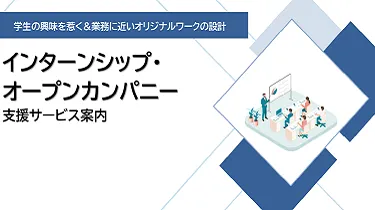

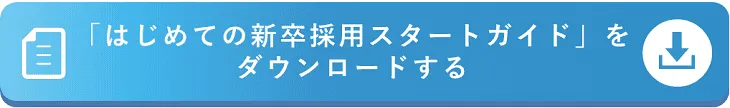

















 目次
目次