


人手不足により企業が直面する問題とは 解消に向けた対策を解説

目次
新型コロナウイルス感染防止対策を続けながらも経済活動の再開に舵を切る企業が直面している深刻な問題は「人手不足」です。コロナ以前から深刻でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大以後、さらに問題が複雑になってきています。
今回の記事では、現在の人手不足の背景や原因とあわせて、解決方法などを解説します。
企業における人手不足とは
企業における人手不足とは、企業が業務を行うのに必要な人材が足りず、予定している業務の遂行がままならない状態を指します。
人手不足は放っておいても解決せず、企業成長の大きな足かせになります。
なぜなら、物理的に業務を遂行できないなど、事業計画の未達成や下方修正が求められる経営上の課題はもちろん、既存の人材で無理やり業務を回そうとすると長時間労働に伴う残業代などのコストが発生する恐れがあるからです。
さらには、無理が続くことで心身の不調が発生し休職する社員が発生したり、優秀な人材から退職してしまったりなど、さらに人材不足に拍車がかかるという悪循環に陥るのです。
人手不足の現状【業種・企業規模別】
人手不足はどの業界や企業でも共通した課題ですが、その深刻度には業界や規模によって濃淡があります。
厚生労働省のデータなどをもとにその傾向を解説します。
業種
産業別の人手不足感をみてみましょう。
厚生労働省「労働経済動向調査(令和4年11月)(PDF)![]() 」をみると、特に人手不足感が強い産業は、「建設業」「情報通信業」「運輸業・郵便業」「医療・福祉業」の4つです。人手不足が顕著な産業毎の特徴を解説します。
」をみると、特に人手不足感が強い産業は、「建設業」「情報通信業」「運輸業・郵便業」「医療・福祉業」の4つです。人手不足が顕著な産業毎の特徴を解説します。
出典:厚生労働省「労働経済動向調査(令和4年11月)の概況」![]()
建設業
地方都市部の新規開発に加え、首都高をはじめ、高度成長期とそれ以降の建設ラッシュで建てられた築50年以上の建造物の老朽化対応が急務であり、求められる労働力もそれに比例して増加傾向です。
しかしながら、厳しい職場であるイメージや、親分・子分の体育会系の文化、休日が取りにくいなど、現場技能者を希望する人材が少ない上、ベテラン技能者の高齢化に伴う大量定年退職が目前に控えています。
その結果、建設技術者の人手不足は今後も厳しくなると予想されています。
情報通信業
ITをはじめ、情報通信業こそ今の時代を牽引している産業ですが、労働力不足も深刻です。AIやWeb3.0の技術者が足りないだけではありません。
経済産業省の「IT人材需給に関する調査」によると、最大約79万人のIT人材が2030年には不足、 最低シナリオでも約16万人不足するといわれるほど労働力が不足しており、今度もさらに厳しくなると予想されています。
運輸業・郵便業
コロナ禍以降、宅配便をはじめ、物流・運輸・郵便業に大きな負荷がかかり、労働力不足が問題になっています。
トラックドライバーの高齢化に加え、トラックドライバーの長時間労働規制が強化される「2024年問題」もあり、その事態は深刻さを増すばかりです。
国土交通省、経済産業省、農林水産省が開催する「持続可能な物流の実現に向けた検討会」の資料によると、2030年度のトラック物流は、ドライバー不足によって10億トン近い輸送力不足に陥る可能性があるほど、労働力不足は切迫しています。
出典:経済産業省「第3回 持続可能な物流の実現に向けた検討会」![]()
医療・福祉業
医療・福祉業では、特に介護分野の労働力不足が深刻です。
厚生労働省が発表した「2025 年に向けた介護人材にかかる需給推計(確定値)(PDF)![]() 」によると、介護人材は37.7万人不足もの受給ギャップがあります。高齢化が進む中、医療・福祉業の労働力の不足はさらに大きくなると予想されています。
」によると、介護人材は37.7万人不足もの受給ギャップがあります。高齢化が進む中、医療・福祉業の労働力の不足はさらに大きくなると予想されています。
出典:厚生労働省「2025 年に向けた介護人材にかかる需給推計(確定値)について」![]()
企業規模
日本銀行「全国企業短期経済観測調査 」によると、2014年度から大企業、中堅企業、中小企業ともに人手不足に陥り、年々人手不足は悪化してきています。
2022年3月全産業の実測値は、次のとおりです。
企業規模計: -24ポイント
大企業 : -14ポイント
中堅企業 : -23ポイント
中小企業 : -28ポイント
上記のようにすべての企業規模で雇用人員はマイナスに転じています。その中でも、規模が小さくなればなるほど、人手不足はより顕著になっています。
出典:日本銀行「全国企業短期経済観測調査(短観)(2022年3月調査全容)」![]()
人手不足が深刻化する原因とは
なぜ人手不足が深刻化するのか、その理由を解説します。
少子高齢化による労働人口の減少
日本は世界的にも急速に少子高齢化が進んでいます。
総務省「令和4年版高齢社会白書 」によると、国内で行われる生産活動の中心となる年齢人口と呼ばれる生産年齢人口(15〜64歳)は、1995年をピークにすでに減少へ転じました。
14歳以下の推計人口は1985年から連続して減少しており、少子化に歯止めがかからない事態が浮き彫りになっています。
結果、生産年齢人口は、2050年には5,275万人に減少するとみられています。
有効求人倍率が1倍を超えている
求職者一人あたり何件の求人があるかを示すものを有効求人倍率といいます。
有効求人倍率が1の場合は、企業が募集する求人の数(有効求人数)と仕事を探している人の数(有効求人者数)が同じなので、均衡が取れた状態と言えます。
有効求人倍率が高いほど人手不足で就職・転職しやすい、低いほど就職・転職が難しい状況をマクロの視点で把握できます。
実際の直近の有効求人倍率は厚生労働省が発表した2022年11月の有効求人倍率 では1.35倍、新規求人倍率は2.42倍というように、人手不足が顕著になっています。
出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和4年11月分)について」![]()
都市部に人材が集中している
地域によって人材不足に差があることも原因の一つです。
総務省「住民基本台帳人口移動報告」によると、3大都市圏(東京圏、名古屋圏および大阪圏)全体では6万5,873人の転入超過となっています。
コロナ禍の影響により活発化した地方移転や移住などの影響で、3大都市圏の転入は前年に比べ1万5,865人の縮小となっていますが、まだまだ都市部に人材が集中している実態は否めません。
2022年11月の都道府県別有効求人倍率をみると、最高が福井県の2.02倍、最低が神奈川県の1.09倍となっています。
東京都をはじめ、首都圏に人口と人材が集中するあまり、地方都市に欲しい人材が足りなくなっている現状が見てとれます。
出典:
総務省「住民基本台帳人口移動報告 2021年(令和3年)結果 」![]()
人手不足で起こる企業の3つの問題
人手不足で企業活動に発生する問題は具体的にどんなものがあるかを解説します。
労働環境が悪化する
物理的に人手が足りない中で、仕事を回すことになるため、一人当たりの労働負荷は当然増加します。
残業量の増加、慢性化はもちろんのこと、日々の仕事に追われ続け、閉塞感が漂うようになります。
個人の頑張りでのカバーには限界があり、誰もが物理的だけでなく心に余裕がなくなります。
結果、個人の仕事のミスが多発し、周りもフォローする余裕がなく、お互いに疑心暗鬼になり、職場の雰囲気が殺伐とするようになって職場全体の生産性も落ち、さらに残業が増えていくという悪循環に陥ります。
人材の意欲が低下し離職者増加につながる
人材に物理的にも精神的にも負荷がかかりすぎると、当然モチベーションも下がります。
有給休暇取得もままならずワークライフバランスも崩壊し、忙し過ぎるあまり、新たなスキルやキャリア機会を得る余裕もなります。
その結果、ふと我に返ったとき「なんのために忙しくしているのか」という疑念を持たれるようになってしまいます。
二人に一人が転職する昨今、仕事に追われて成長感も達成感もなく忙しいだけではエンゲージメントが下がり、優秀な社員から会社に見切りをつけて転職してしまい、人手不足が加速するのです。
事業の縮小や倒産のリスクにつながる
人手不足だと、物理的にどうしてもできる仕事量に限界があります。一人が担当できる業務量には上限があるからです。
結果、社員の人数に応じた業務量にあわせた事業規模に縮小せざるを得なくなります。
その事業規模すら現在の人員で精一杯であれば、新たな事業や取り組みを行う余裕がなく、市場チャンスを逃したり、競合他社から出遅れたりなどを招きます。
そうして競合他社との差がつけばつくほど、収益だけでなく人材確保もままならなくなります。
既存人材の流出にも拍車がかかり、事態はどんどん深刻化するでしょう。
人手不足を解消するための6つの対策
人手不足を解消するための対策を具体的に解説します。
労働条件や労働環境を見直す
人手不足の解消を考えると新規人材を獲得することに目がいきがちですが、まずは既存の社員が働きやすくなるように労働条件や労働環境を見直すことを行いましょう。
新しく採用を行う場合も、既存の労働環境や条件が劣悪なら、早期離職につながります。
現代はインターネットですぐに報酬水準や残業時間、福利厚生、人間関係や働きやすさといった情報を調べることができます。
企業側の都合による「これくらい報酬を出せばいいだろう」という勝手な都合は見透かされ拡散されてしまい、悪循環に陥ります。
人手不足を解消する一番の解決法は、誰もが長く働ける労働条件と労働環境です。
報酬水準を市場水準以上にすることはもちろん、在宅勤務や時短勤務をはじめ働き方の選択肢があることや、福利厚生が充実していることも重要です。
さらに、社員のキャリアやスキルアップを支援すること、ハラスメントがなく信頼し合える文化があることなど、誰もが働きやすいと思える環境の整備を一番に行えば、人材の離職を防げ、定着を促せるでしょう。
「やめる会議」でムダな仕事を瞬時に一掃する
現場の人材は「この仕事は実はムダではないか」「形骸化していて、いらないのでは」と気づいているものですが、その仕事をやめる権限を持ちあわせていません。
人手不足となると、それすら考える余裕がなくなり、とにかく仕事に追われてしまっています。
労働環境を改善するには、まず、ムダな仕事を一掃することが必要です。
そのためには「やめる会議」をするとよいでしょう。やめる会議とは、現場のそれぞれのメンバーが「形骸していること/ムダなこと」「その理由」「どうすればいいか(廃止・見直しなど)」を書き出し、集計してリスト化し、経営会議にかける方法です。
経営者は業務を止める権限があるので、形骸化した仕事やムダな仕事は、どんどん「止めなさい」と廃止を決めてくれます。
その結果、現場の足かせになっていたムダな仕事が一掃され、労働環境の改善がなされるだけでなく、現場で手段を考え効率化のためのツールなどを導入するなど、精神的・物理的な余裕が生まれるようになります。
DX化を推進し生産性を高める
人手不足はDX(デジタルトランスフォーメーション)といったテクノロジーを活用することで補うことも可能です。
システム化・IT化となると、以前は導入や使いこなせるまでの工数が多大にかかりましたが、現代はテクノロジーが大きく進歩したため、さまざまなツールを誰もが簡単に導入し、使いこなせるようになりました。
DXを活用することで、業務効率をあげ工数や労力を下げ、生産性をあげていきましょう。
高齢者や外国人などの雇用環境を整える
高齢者や外国人の雇用も人手不足解消の一つの施策です。
建築現場、コンビニやファーストフードといった現場だけに留まらず、アパレルや携帯事業など、高齢者や外国人の方がイキイキと活躍しているケースはどんどん増え、成功事例も増えてきています。
成功のキーになるのは体制づくりです。
俗人的な仕事や阿吽の呼吸といった旧態依然の仕事のやり方を止め、業務のプロセスを効率化し、誰でもすぐ理解し、実行できるように労働環境を整えておきましょう。
その結果、既存業務の効率化も実現できる上、高齢者も外国人も、初めての環境でも戸惑うことなく自ら動けるようになります。
注意点としては、特に外国人雇用の場合、労働条件などは日本語と母国語の双方で雇用契約をきちんと明文化し、締結しておきましょう。
また、日本語能力は個人によりばらつきがあるため、雇用後の日本語能力向上の継続的なサポートが必要です。
文化や生活習慣の違いを企業側もしっかり理解し、日本のマナーや生活スタイルに馴染めるようにサポートするだけでなく、礼拝所をつくるなど、海外の方の文化を受け入れる努力も必要です。
採用基準と方法を変え、自社にあって長く貢献できる人を選ぶ
人手不足が深刻になればなるほど、喉から手がでるくらい人手が欲しくなり、採用基準が粗く甘くなります。
結果、採用したけど、自社にあわない・馴染めないなどで、すぐに退職されてしまう悪循環はよく起きるものです。
人手不足で苦しいときこそ、採用基準と方法を見直しましょう。
能力やポテンシャルの高さ、過去実績よりも、自社の経営理念を理解できるかを判断したり、現場の仕事内容にあう人材要件を明確にして採用基準にしたりすることをおすすめします。
経営理念であるパーパス、ミッション、ビジョン、バリューなどは、経営から現場までの共通の判断基準なので、これらの判断基準に沿って普段から物事を考え、判断している人であれば、自社に馴染みやすいことは明白です。
例えば、自社の業務がイノベーションよりも飽きずにミスしないことが重要な業務がメインの場合、コツコツ続けられるタイプの資質を持つ人材であれば自社の業務にぴったりでパフォーマンスを出しやすいことになります。
このように、自社で活躍できそうな人材の基準を整理し、それを見極める手段を用いることで採用ミスが減り、人手不足の解消に繋がります。
人材派遣サービスを利用する
人手が足りない場合、採用に頼るだけでなく、外部の人手を借りることも有効な打ち手になります。
正社員の場合、給与以外にも福利厚生をはじめ人件費のコストがかさみ、解雇も容易にはできず、リスクが発生します。
一方、人材派遣サービスをはじめとした外部の人材を活用する場合、期間を定めた有期雇用であるため、繁忙期のみお願いするなども可能なことが大きなメリットです。
現在は、フリーランスで活躍するプロフェッショナル、専門性をもった副業人材など、ハイレベルな業務も外部に委託できるようになりました。
給与計算のような業務のアウトソース化も、クラウドソーシングを活用することで、その選択肢の幅は広くなってきています。
まとめ
人手不足は労働人口の減少だけでなく、現在の社員の「離職」も要因となります。
離職が多い職場は、どんなに人を採用しても、同じように退職されてしまい悪循環に陥るため、今いる社員に頑張りを強いるのは止めましょう。
やめる会議やDX化、外部を活用することで現場の負荷を減らし、働き方やキャリアの選択肢を増やすなど、誰もが働きやすい環境を整備することが、採用を強化するよりも効果的です。
「雇ってあげている」という思考から、「働いてくれてありがとう」という思考に視点を切り替えることで、人手不足を解消する打ち手はみえてくるでしょう。
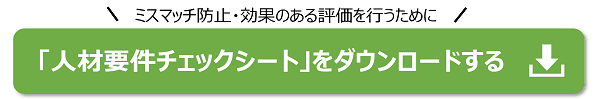

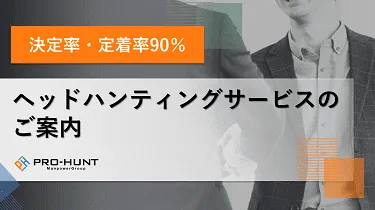
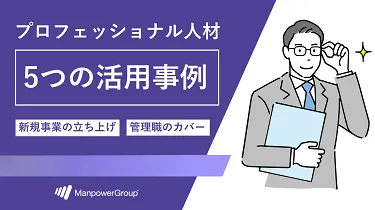


















 目次
目次