


早期離職を防ぐ!未経験者の採用・育成で成功するポイント

目次
未経験者採用を実施する企業が増える中、次の課題として浮上しているのが「定着と育成」です。「せっかく採用してもすぐに辞めてしまう」「育成が追いつかない」など、早期退職によるコスト未回収、そして育成負担の増大、それに伴う現場の疲弊など、採用後の課題は深刻です。
未経験者採用では、どうしても即戦力化を急ぎたくなりますが、それを唯一のゴールにすると、長期的な育成やフォローの視点が抜け落ち、定着を妨げる要因になってしまいます。定着に必要なのは、即戦力スキルの習得だけでなく、安心して成長できる環境の整備です。
本記事では、人事と現場の連携を通して未経験者の定着・成長を実現するための実践的なポイントを紹介します。
事務職の経験はないものの、ポテンシャルが高く、業務習得のキャッチアップが早い若手人材をコンサルタントが適性を見極めて派遣します。
- 新卒採用が充足できなかった
- 若手の採用が進まない
- 新卒が配属されなかった
上記のようなお悩みをお持ちの方にぜひ知っていただきたいサービスです。
未経験者の定着に必要な「採用後の視点」

即戦力人材の確保は年々難しくなり、採用競争も激化しています。こうした状況から、未経験者採用は多くの企業で実施されています。
技術革新のスピードが速まり、新たなテクノロジーが続々と創出され、過去の経験が必ずしも現在の業務適性を保証しない時代になったことも未経験者採用増加の一因といえるでしょう。むしろ、固定観念の少ない未経験者のほうが新しい業務フローに順応しやすいという考え方もあります。
とはいえ、短期的な補充サイクルを繰り返すだけでは、育成コストを回収できず、企業の競争力は高まりません。労働人口の逆ピラミッド化が進む中、入れ替え前提の「補充型採用」の発想では、いずれ人材確保そのものが困難になります。未経験者採用では、長期的に活躍できる人材へと育成する視点が不可欠です。
よくある未経験者育成の失敗例とその対策
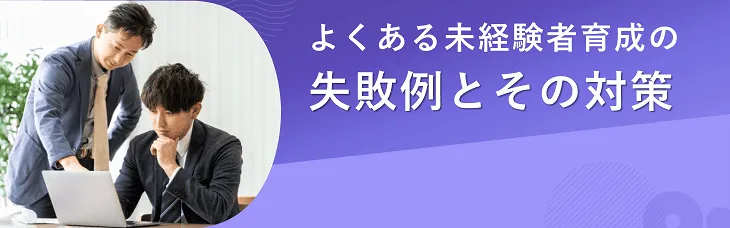
なぜ、「採っても定着しない」「育てても戦力化しない」という状況に陥ってしまうのでしょうか。その背景には、現場で陥りやすい育成の失敗パターンがあります。ここでは、よく起きる課題と、それを防ぐための実践的な対策を整理します。
教育の属人化と場当たり的なOJT
未経験者育成をOJT中心で進めると、担当者の経験や感覚に依存しやすく、標準化が難しくなります。
失敗例
育成担当者の経験や感覚に依存したOJTが中心で、教え方にばらつきが生じる。
結果
学習のペースや習得度合いが不安定になり、本人も「できているのか分からない」と不安を抱えやすい。
対策
- OJT任せにせず、段階的な育成ステップと到達目標を明確化する
- 「何を、いつ、どのレベルまで」習得するかを、企業と本人が共に把握できる形にする
- 未経験の領域に応じて説明や指導内容を調整するのがポイント
例)
業界未経験:業務の目的や業界特有の背景を説明
職種未経験:具体的な手順や判断基準を明確化
完全未経験:習得ステップを細分化し、進捗を確認しながら進める
フィードバックの不足と成長実感の欠如
未経験者の育成では、進捗確認や声かけを怠ると不安が募りやすく、モチベーション低下につながります。特に初期段階では「できている実感」を持たせる仕組みが重要です。
失敗例
業務目標に対しての進捗確認や業務習得レベルの達成状況のフィードバックができていない。
結果
自分が現在行っていることが正しいのか間違っているのか、あるいは進捗が順調なのか遅れているのかが判然とせず、不安を感じるようになる。その結果、主体性やモチベーションが低下する。
対策
- 進捗の可視化とポジティブな評価の両立が重要
- 業務ごとに「できている/あと少し」を明確にし、短いサイクルでフィードバックを行う
- 1on1や週次面談などで、上司や教育担当が進捗を共有し、「次に何を目指せばよいか」を具体的に示す
- 小さな達成を積み重ねて成長の手応えを実感させる仕組みづくりが効果的
評価制度の不明確さ
経験者向けの評価基準をそのまま適用すると、未経験者の努力や成長が正しく評価されません。評価軸の不透明さは不信感や早期離職の原因になります。
失敗例
未経験者向けの評価制度がないまま、経験者前提の基準をそのまま適用。
結果
企業側もフィットしていないと感じながら運用していることが本人にも伝わり、不信感が募る。
努力しても評価されにくく、「何を頑張れば良いか分からない」と意欲を失うケースも。
対策
- 最終成果だけを評価するのではなく、1~2週間単位の小さなプロセス目標を設定し、評価する
- 知識・行動・姿勢などの“習得度”を見える化し、成長過程を評価する「育成型評価制度」を整備する
- 評価項目の透明化(どの行動が評価されるか)と、定期的な面談での共有も信頼構築に必要不可
孤立・カルチャーギャップへの配慮不足
未経験者を単独で配属すると、質問や相談がしにくく孤立しやすくなります。前職との文化の違いに戸惑っている場合は特に、心理的な壁を感じやすくなります。
失敗例
OJT担当者が明確でない、または通常業務で多忙な担当者をOJT担当者に割り当てた状態で未経験者を1名で配属する。
結果
OJT担当者からのサポートが断続的になり、未経験者が「聞きづらい」「頼りにくい」と感じる環境に陥る。
対策
- 初期配属は近くに頼れる人がいる状態を確保し、週次のフォロー面談やメンター制度など「いつでも相談できる」心理的安全性を整える
- OJT担当者を決め、育成に十分な時間を割ける体制を整える
- OJT担当者の育成の評価を設定し、OJTの実施状況が評価に反映される仕組みとする
- カルチャーギャップがあるようであれば、率直な感想を聞いたうえで、背景情報の共有や、既存ルールの改善に向けた働きかけを行うなど、相互理解を深める
- チーム全体に「未経験者を育てる期間である」ことを共有し、協力的な雰囲気を醸成する
キャリアの見通しの提示不足
日々の業務指示だけで育成を進めると、未経験者は将来像を描けずに不安を感じます。キャリアの見通しを示すことは、定着と成長意欲の両方に直結します。
失敗例
「とりあえずこの仕事をやってください」と短期的な指示を繰り返すだけで、初期段階にキャリアパスなどの面談を設けず、中長期のキャリア像や成長ステップを共有しないまま育成を進めてしまう。
結果
未経験者は「この先に何があるのか」が見えず、長期的に働くイメージを持つことができない。
日々の業務の目的も曖昧なため、ただ作業をこなすだけになり、達成感や成長実感を得られない状態となる。
結果、将来へのモチベーションが湧かず、キャリア形成への意欲を失う。
対策
- 育成初期から「この経験が将来どう活きるか」を具体的に伝える
- 「3カ月後にはこのスキル」「1年後にはこのポジション」といったマイルストーンを設け、未来の見通しを共有することで安心感と主体性を育む
- キャリア面談や目標設定の場を通じて、本人が自分の物語を描けるよう支援することが重要
未経験者育成を成功させるポイント

未経験者の育成で成果を上げる企業には、共通する特徴があります。
単に教育制度を整えるだけではなく、現場と人事が一体となり、「人の成長を組織全体で支える文化」を育てているのです。
ここでは、特に効果の高い5つのポイントを紹介します。
1.人事だけでなく、現場と連携する
成功の鍵は、人事主導ではなく現場共創の育成設計です。
人事がいくら丁寧なプログラムを用意しても、実際に育てるのは現場のメンバーです。
だからこそ、現場が「育成を担える状況」にあるかを見極めることが第一歩となります。
たとえば、人事と現場で「育成プラン」と「受け入れ体制」を明確に分ける。現場にはOJTの段階的な役割分担を、人事にはフォローとモニタリングの役割を持たせる。
この協働モデルが確立している企業ほど、育成の質が安定し、早期離職も減少します。
2.教育担当者を支える仕組みを整える
教育担当者は、自身の業務を抱えながら育成にも関わる「最前線のキーパーソン」です。
教育担当者への支援が弱いと、教える側が疲弊し、育成全体が形骸化してしまいます。
効果的なのは、教育担当者の努力と貢献を正式に評価に組み込むことです。
- 「育成貢献度」を人事評価項目に入れ、未経験者の成長が担当者の成果として可視化する。
- OJT担当同士の情報交換会を開き、成功事例を共有する場を設ける。
- 現場メンバーにも「未経験者の育成期間中は一時的に生産性が落ちる」ことを共有しておく。
チーム全体で支える空気を醸成することが、教育担当者の心理的安全性につながります。
3.成長実感をデザインする
特に重要なのは、早期に達成感を得られる仕組みを設計することです。
最初から完璧を求めず、「最初の一歩で達成できる目標」を細かく設定します。
達成した際には必ず評価し、次のステップを明確に示す。この繰り返しが成長実感を生み、離職防止に直結します。
さらに、フィードバックやキャリア面談で「この経験が次にどう繋がるか」をしっかり伝えましょう。
いまの努力が未来につながっているという手応えが、未経験者の学習意欲と成長を後押しする鍵となります。
4.退職者の声を「再利用」する
退職者インタビューは、最もリアルな教材です。辞めた人の声には、制度では見えない職場の課題や、育成の盲点が詰まっています。
特に未経験者の離職理由には、「教育担当が忙しすぎた」「質問しづらい雰囲気」「将来像が見えなかった」など、共通項が見つかることが多いです。
これらを失敗の共有知として分析・蓄積することで、改善すべきポイントが見えてきます。
部署ごとに退職理由を定点観測する仕組みを持つだけでも、早期離職率の改善が期待できます。
5.育成プランと評価基準を、常に更新する
未経験者育成は、一度仕組みを作ったら終わりではありません。
人材の質、業務内容、テクノロジーの変化に合わせて、動的にブラッシュアップしていくことが求められます。
教育計画や評価項目を定期的に見直し、現場の声や離職データを反映させましょう。
年に一度の制度改訂ではなく、四半期ごとの小さな見直しを積み重ねるのが理想です。
また、育成の基準を明文化しておくと、新任の教育担当や管理職も迷わず対応できます。
「どの段階で任せてよいか」「どのレベルで独り立ちか」を共有することで、組織全体の一貫性が保たれます。
【ケーススタディ】未経験者の育成プラン
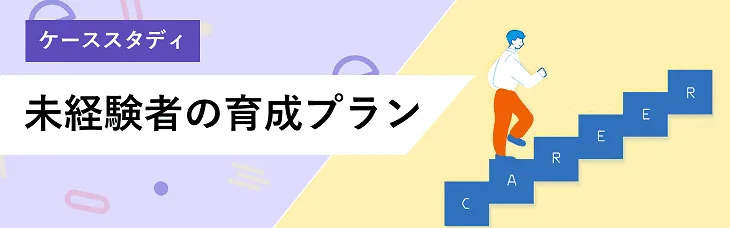
未経験者といっても、「どの経験をまだ積んでいないか」によって必要な支援は異なります。
ここでは、代表的な3パターンの未経験者を例に、効果的な育成設計のポイントを整理します。
① 業界未経験(職種経験あり)
事例:
営業経験10年のAさん(BtoC企業出身)。
前職の業界が価格競争の激しい市場へ移行したことで、顧客との関係性を築きにくくなり、「より長期的な関係性を築ける営業がしたい」と考えるように。
その思いから、より専門性の高い製造業の法人営業職へのキャリアチェンジの決意に至る。
課題:
営業スキルは申し分ないが、業界知識や商習慣の違いに戸惑いがち。
過去の成功体験が通じず、自信を失う場面も。
| 育成ポイント |
社内用語集、商流マップ、過去案件の事例集などを活用。 |
「あなたの強みはここで活かせる」「この部分は新しく覚えよう」と可視化することで不安を軽減。 |
|
1~3カ月目は「用語・構造の理解」に集中、4カ月目以降に応用・提案フェーズへ移行。 |
業界未経験者の育成で重要なのは、前職の経験を新しい業界に適応させるための支援です。未経験者の自信回復につながり、成長意欲を高めます。
単に知識を教えるだけではなく、前職で培った経験を新しい業界でも活かせるよう「このスキルはここで活かせる」「この知識はこういう場面で使える」など、キャリアの連続性を意識させる支援がポイントです。
② 職種未経験(業界経験あり)
事例:
製薬会社の研究職Bさんが、長年、研究開発に携わる中で「人の可能性を引き出す側にまわりたい」という思いが芽生え、組織づくりや人材育成に関わる仕事へ挑戦することを決意し、同業界の人事職にキャリアチェンジ。
業界の知識は深いが、人事としての実務(評価制度、面接、労務管理)はゼロからのスタート。
課題:
専門知識はあるが、仕事の対象が全く違い、職務の違いで挫折しやすい。
特に「人と接する、悩み解決のような職務」への抵抗感が出やすい。
| 育成ポイント |
|
|
|
|
|
|
大切なのは、「専門性の転換」ではなく「役割認識の再構築」です。同じ業界でも職種が変われば、見える世界が変わることを丁寧に支援します。
③ 完全未経験(業界も職種も)
事例:
サービス業からIT企業に転職したCさん。接客を通じて「もっと仕組みづくりの側から人を支えたい」と感じ、未経験ながらIT業界に挑戦したが、パソコン業務も初めてで、最初の研修から不安を抱えている。
課題:
「何が分からないかが分からない」状態。
教える側も「どこから説明すべきか」が分からず、双方が疲弊しやすい。
| 育成ポイント |
|
|
|
|
|
|
「教えること」よりも「支えること」に注力しましょう。完全未経験者には、最初の半年で「仕事に慣れる」「関係に安心する」「自分の役割を理解する」の3つを意識的に設計することが重要です。
事務職の経験はないものの、ポテンシャルが高く、業務習得のキャッチアップが早い若手人材をコンサルタントが適性を見極めて派遣します。
- 新卒採用が充足できなかった
- 若手の採用が進まない
- 新卒が配属されなかった
上記のようなお悩みをお持ちの方にぜひ知っていただきたいサービスです。
未経験者育成に関するよくある質問

ここでは、未経験者育成に取り組む際に人事や現場でよく挙がる疑問をQ&A形式で整理し、実践に役立つ考え方とヒントを解説します。
Q1.未経験者の育成には、どのくらいの期間を見ておくべきですか?
A. 一般的には「半年で基礎定着、1年で独り立ち」が目安です。
ただし職種・業界により習熟速度は異なるため、3カ月・6カ月・12カ月の3段階で到達点を設けると効果的です。
業界・職種ともに未経験の完全未経験の場合は、最初の3カ月は「安心して学ぶ期間」、半年で「一通りの流れを理解」、1年で「自走と貢献」を目指すプランが現実的でしょう。
Q2. 業務の習得が遅いときは、どう対応すればよいですか?
A. 指導方法や担当者を変えるだけで、習得が進むケースも少なくありません。まず、教え方と環境の両面を見直してください。
例えば、次のような要因が習得の遅れにつながることがあります。
- タスクの分解が細かすぎる/曖昧すぎる
- 質問しづらい雰囲気がある
- 指導者の説明スタイルが合っていない
Q3. どの時点で「一人前」と判断すればいいですか?
A. 「業務を一人で完遂できる」よりも、「判断と行動に一貫性があるか」で見極めます。完全な自立よりも、「自律的に相談できる状態」が一人前の初期段階です。
例えば、以下のような観点からチェックが可能です。
- 分からないことを放置せず、自ら確認・相談ができているか
- 依頼された仕事の目的を理解し、自分の言葉で説明できるか
- トラブルや課題を発見したときに、報告だけでなく「改善提案」まで考えられているか
- 指示待ちではなく、業務の優先順位を自分で整理して動けているか
Q4. 未経験者にどこまで業務を任せてよいのでしょうか?
A. 任せる基準は「責任の重さ」ではなく「リスクの種類」で考えましょう。
顧客対応や数値報告など、信頼に関わる領域を早期に任せるのではなく、作業系・サポート系など、実際に手を動かしながら体験的に学べる仕事から少しずつ範囲を広げていきましょう。失敗しても周囲がリカバリーできる体制を整え、安心して試行錯誤できる環境を意図的に設計することが理想です。
Q5.現場から「戦力にならない」と不満が出た場合、どうすれば?
A. まず「未経験者を育てることが組織の成長投資である」ことを丁寧に共有する必要があります。
育成担当者だけに責任を押しつけず、評価制度や工数設計の段階で育成期間を前提化しましょう。
現場にとっても「余白のある育成」が納得できる制度で支えられていることが重要です。
Q6. フィードバックがうまく伝わらないとき、どうしたらよい?
A. 抽象的な表現ではなく、行動事実+感情+期待の3点セットで伝えるのがコツです。
例:「この資料は見やすかった(事実)。落ち着いて丁寧に作業していたね(感情)。
次は要点をもう少し短くできるとさらに良い(期待)」
この構成を意識すると、指摘が叱責ではなく成長の提案として届きやすくなります。
Q7.未経験者が「思っていた仕事と違う」と言ってきたときの対応は?
A. 否定せず、まず「感じ方」を受け止めることが最優先です。
まずは「そう感じているんですね。どんな点で違いましたか?」と開くことで、単なる不満ではなく「期待とのズレ」が見えてきます。
そのうえで、本人の納得感を高めるための対応を進めましょう。
例)
もっと人と話す仕事だと思っていた
→ 【役割の調整・タスク追加】仕事の中にコミュニケーション要素を組み込むなど、要素を追加して期待に近づける
想像以上に事務作業が多い
→ 【業務価値の説明】単なる作業ではなく、組織にとって重要な情報基盤となることを説明するなど、その作業の価値を再定義する
キャリアの方向が見えない
→【情報提供・見通しの可視化】具体的な成長ステップやキャリアパスを提示し、将来像を明確化する
Q8.未経験者が自信を失ってしまったとき、どんな言葉をかけるとよい?
A. 「大丈夫」よりも、「できるようになるプロセスの途中にいるよ」と伝えましょう。
曖昧な励ましよりも、成長の物差しを具体的に示すことで安心感が生まれます。
「前よりここができている」「次はこの一歩を目指そう」と、小さな変化を言語化して共有することが効果的です。
Q9. チーム全体で未経験者を支えるには?
A. 担当者任せにしないことが大切です。
ミーティングや朝礼などで未経験者の習熟状況や理解度を共有し、チーム全体で支援意識を持つ。
また、成功体験や成長エピソードをチーム内で称える習慣をつくると、「育てる文化」が根づく。
育成は制度だけでなく、職場の“雰囲気”にも大きく左右されることがあります。
Q10. 育成を続けても成果が出ない場合、どう見直すべき?
A. 本人の努力だけでなく、「育成環境そのもの」を検証することが第一です。
研修設計、業務配置、OJT担当のサポート力、評価基準……どこにボトルネックがあるかをデータで確認します。
「本人の資質の問題」と早合点せず、仕組みの改善余地を冷静に見極めることが、
結果として次の未経験者の定着にもつながります。
未経験者採用に不安がある場合、派遣社員としての受け入れから始めることで、ミスマッチのリスクを抑えることができます。
M-Shineは、オフィスワーク未経験の若手人材を派遣するサービスです。未経験者採用に不安がある場合、派遣社員としての受け入れから始めてはいかがでしょうか?若手人材の確保に課題を抱える企業の解決策として活用されており、本資料ではサービスの特長、サポート体制、導入企業のコメント事例などを紹介しています。
<この資料でわかること>
・ M-Shineサービスの詳細
・ M-Shineスタッフの属性・人物像 など
・ 導入企業からの声
・ 正社員登用の実例 など

まとめ
未経験者育成の成否を分けるのは、教育マニュアルの厚さではなく、伴走する組織の姿勢です。採用の段階から「どんな経験をどう活かすか」を対話し、入社後は「安心して挑戦できる環境」を整えること。そして、現場と人事が一体となり、成長を「見守り」「見える化」することが定着のカギとなります。
未経験者が育つ職場は、実は「誰もが成長し続けられる職場」です。
未経験採用を育つ文化づくりのチャンスと捉え、人の可能性を伸ばす職場づくりを、全社で進めていきましょう。
こちらの資料もおすすめです
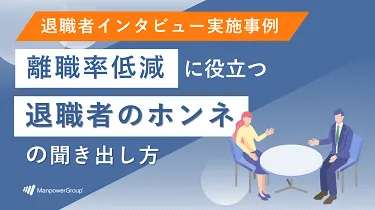

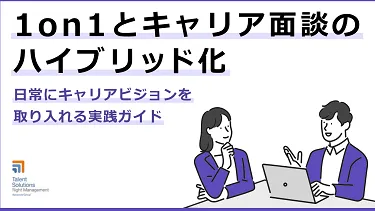
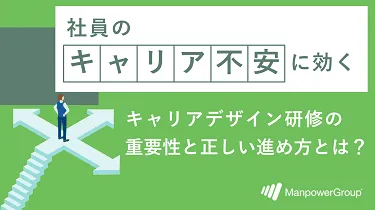





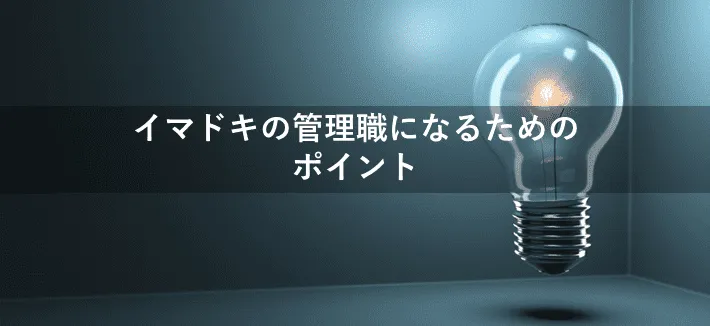











 目次
目次