


リスキリングとは|導入の必要性と注意点を解説

目次
昨今、DX(デジタルトランスフォーメーション)化や今後の成長分野であるAI・IT分野への人材シフトが起きています。そこで注目されているのが「リスキリング(Reskilling)」であり、重要な人材戦略の一つとして日本を含め世界中の企業が取り組んでいます。ここでは、リスキリングの基本的な知識から推進の注意点や導入ステップ、成功事例までを解説します。
若年層中心のエンジニア派遣 SODATEC
マンパワーグループでは、慢性的なエンジニア不足の解決策として、エンジニアを目指す意欲の高い若年層の育成に取り組んでいます。
エンジニア不足で既存メンバーの業務が増大している、残業が多い、新しい技術習得の余裕がないなどの課題がありましたら、ぜひSODATECの活用をご検討ください。
▽SODATECのサービス詳細についてはこちらから
https://www.manpowergroup.jp/client/serve/sodatec/
▽お問い合わせはこちらから
https://info.manpowergroup.jp/client/inquiry/experis/sodatec
リスキリングとは
リスキリングとは、簡単に言うと「職業能力の学び直し」のことです。経済産業省が実施した『第2回 デジタル時代の人材政策に関する検討会』では、「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」と定義されています。
引用:第2回 デジタル時代の人材政策に関する検討会「リスキリングとは―DX時代の人材戦略と世界の潮流―」|経済産業省(PDF) ![]()
2020年に開催された世界経済(ダボス)会議では「リスキリング革命」と題して「2030年までに地球人口のうち10億人をリスキリングする」と発表され、日本経団連も2020年11月に「新成長戦略」の中でリスキリングの必要性について触れています。
人生100年時代におけるスキル獲得やキャリア形成のあり方が大きく変わっていくことは間違いありません。
労働者側の視点から見れば、「技術的失業」の脅威が迫っているという現実もあります。人工知能(AI)の普及や自動化、IT技術の進歩によって、もはや人間の仕事の多くが機械に代替されるようになることは否定できません。
一方、データ分析やサイバーセキュリティーなどの新しい仕事は、すでに担い手が不足しています。そうした背景から、日本政府も、成長分野へ人材をシフトさせるためにリスキリングを推奨し、そのための支援制度を準備しているのです。
リスキリングが注目されている背景
近年、日本でリスキリングが注目されている背景として「DXの推進」「デジタル移行の加速」が挙げられます。
DXの推進
DXとはデジタル技術を用いて、製品やサービス、ビジネスモデル、ひいては組織そのものを変革することです。
その変革に伴い、ITやプログラミング、クラウド化などデジタルスキルをもつ人材が必要となります。DXを推進するためには、一部の従業員がDXに必要なスキルをもつのではなく、すべての従業員が会社や事業の変化を理解し、新たな知識やスキルを身につけ、変革に適応していかなければなりません。
そのため、今後必要とされるスキルを獲得させていくための取り組みとして、リスキリングが注目されています。
デジタル移行の加速
新型コロナウイルス感染症の影響によって働き方は大きく変化しました。リモートワークが浸透し、取引先との会議などもリアルからオンラインに移行しています。
それに伴いデジタルを用いた、生産性の向上や付加価値の高い新しいビジネスの創出が求められるようになるでしょう。従業員もこうした変化に対応するスキルを身に着けなければいけなくなっており、リスキリングの重要性が高まっているのです。
リスキリングとよく似た言葉の違い
リスキリングと似た言葉がいくつかあります。OJT、リカレント教育、生涯学習、アップスキリング、アウトスキリングです。それぞれの違いを説明します。
OJT
OJTは、各部署で現在の仕事を通じて業務に必要な知識やスキルを習得してもらう教育のことです。OJTは「現在の仕事」、リスキリングは「今後必要となる仕事」に対する教育を実施するという点で異なります。
リカレント教育(社会人の学び直し)
リカレント教育は、従業員自らが就業している組織を離れ、大学などの教育機関で学び直し、新たなスキルを身につけ、再び組織で働くことを繰り返す学び方を指します。
リカレント教育は今の仕事で必要な知識や今後必要となるスキルを従業員が主体的に外部の機関で学ぶ一方で、リスキリングは会社が従業員に対して働きながら施す教育です。
生涯学習
生涯学習は仕事で役立つ知識やスキルだけでなく、スポーツや文化活動、趣味、ボランティアなども含めて生涯で行うあらゆる学習を指す点でリスキリングとは意味が異なります。
アップスキリング
アップスキリングとは、現在の業務のスキルアップをすることです。職務内容は変わらず、高度なスキルを身に付けるためのトレーニングを行います。
一方でリスキリングは、現在とは異なる業務に就くため、例えば製造業務からデジタル関連の業務に就くためのスキルアップなどを指します。
アウトスキリング
アウトスキリングは、レイオフのリスクが高い従業員に対して解雇前に成長産業への転職に役に立つスキル教育を実施する、キャリア支援のことです。
企業側も離職する人との良好な関係を継続できるため、再雇用のためのタレントプール(優秀な人材をデータベースとして管理していくこと)を形成できる点がメリットとしてあります。
リスキリングを実施する必要性
従来の産業構造は根本的に変化し、かつての主力産業の衰退や業務のロボット化・デジタル化が急速に進んでいます。主力事業の変化やロボット・AI技術の導入により、今後必要となるスキルをもたない余剰人員を抱えることになる企業も少なくないでしょう。
それゆえにリスキリングは、企業のこれからの人材戦略で欠かせない一手となり得ます。とくに「業務効率性・生産性の向上」「人材採用・育成におけるコスト削減」「定着率の向上」において効果を期待できます。
業務効率化・生産性の向上
リスキリングは人材を持て余さずに業務フローの改善や効率化、生産性の向上を図ることに役立ちます。
例えば、製造現場で作業を担ってきた従業員にリスキリングを実施し、機械化・クラウド化に対応するための業務管理者に任ずるようなケースです。リスキリングによって運営管理やシステム管理のスキルなどを身につければ、これまでの製造現場での経験を活かしながら、さらなる業務効率化やトラブル対応の役割などを担ってもらえれば、企業全体の生産性向上が期待できるでしょう。
採用コスト削減
高いスキルをもつDX人材を何人も採用するには高い採用コストが必要になりますし、多くの企業がそうしたDX人材を欲しているため採用自体も簡単ではありません。そこで社内人材をリスキリングし活用できれば、採用コストを削減できるだけではなく、余剰人員の解雇を避けることも可能です。
定着率の向上
リスキリングによって、従業員は社内にいながらスキルアップやキャリアの転換の機会が得られることから、従業員は長期間にわたって安心して働くことができます。そのため、従業員の定着率向上とともに帰属意識の強化も図れます。
外部の人材を招き会社の変革を推進した場合、社内の従業員たちで育まれた文化や風土などが軽視される恐れもあります。さらに社内の文化や風土が一変すると、従業員が離職するリスクもあるでしょう。
関連調査データ
認知率6割のリスキリング、実施・実施予定は2割以下。取り組み内容やその効能・課題とは?
20代~50代の人事担当者を対象に「リスキリング」の実態について調査しました。取り組み内容や効能、課題についてのリアルな声を紹介します。
リスキリングの注意点と対策
リスキリングを推進する際の注意点は、従業員の賛同を得られない可能性があることです。「会社の生き残りのために、リスキリングに取り組もう!」と組織がスローガンを掲げても、「今さら新たな勉強などしたくない」「余剰人員と見なされていて、いずれは解雇の対象になるかもしれない」と、否定的な意見をもつ従業員は少なからず存在します。
従業員の賛同を得られない理由として、リスキリングの必要性やメリットが理解されていないことが考えられます。そこで賛同者を増やすための対策をお伝えします。
現状のデータを示し、会社の方針に理解をしてもらう
企業は、リスキリングの必要性やメリットをわかりやすく啓蒙活動することが重要です。「製造部門のDX化を促進するため、デジタル技術の積極的活用を行う」といった抽象的な表現ではなく、誰もが理解できる言葉とデータをもとに、以下の5つについて具体的な説明することが欠かせません。
- 対象範囲
- 背景・目的
- 推進テーマ
- 期待する効果
- 制約条件
特に、現場に隠れている業務上の制約 が原因で、従業員の反発を招くケースが少なくありません。
例えば、就業時間後に実施した研修で参加率が上がらなかったことが挙げられます。これは企業側が把握していた残業時間と、その実態に差があったことに起因しています。もともと、企業側は20時以降の残業を禁止していましたが、現場では就業時間内に業務を完了できないため、残業時間を他曜日に振替を行って調整していました。このような業務実態に加え、就業時間後の研修参加命令を一方的に会社側から受けたことで、現場従業員による反発が起きたのです。
また、「外勤業務が多いため定時までに帰社できない」、「帰社しても報告書作成や残務整理で研修時間に間に合わない」といった制約があります。あらかじめ業務担当者にヒアリングし、業務上の制約を洗い出す作業が必要です。これらを把握した上で、無理のない新たな業務フローを作成することで、現場の協力は得やすくなるでしょう。
リスキリングを推進する3つのステップ
リスキリングの仕組みを作っていく場合、はずせない3つのステップについて説明します。業界ごとの環境も違えば、企業の経営戦略の内容も異なるため、リスキリングの推進には、正しいやり方が存在するわけではありませんが、組織に最適なリスキリングを進めるために、押さえておきたいポイントをまとめました。
1.習得すべきスキルの見える化
リスキリングを進めるために、まずは従業員のスキル管理ができていることが前提です。人材のスキルデータにもとづき、事業的・組織的に不足しているスキルが明確になり(見える化)、プログラム作成や教育研修の計画作りができます。
同時に、適材適所の人員配置や業務に最適なメンバーの選出が可能です。特定の部署・従業員ではなく、DX化のために全従業員を対象としたプログラムを進めるケースもあります。的確なプログラム作成や人選をするために、まずは習得すべきスキルの見える化が欠かせません。
見える化が進むと、従業員が新たなスキルを獲得することで、どんな職務や仕事ができるのかを企業側は示しやすくなります。同時に、従業員もこれからのキャリアがイメージできるようになることで、モチベーションの維持・向上にもつながります。
2.学習プログラムの考案・選定・実施
リスキリングを行うための学習プログラムは、必ずしも自社開発する必要はありません。
社外のコンテンツや専門家を活用することも有効です。例えば、クラウドサービスやビジネスアプリケーションを提供しているMicrosoftやGoogleなどでは、コストパフォーマンスが高く、効率的に学習できるコンテンツを提供しています。また、デジタルマーケティングやデータ分析、プログラミング言語なども、多くの企業が教育コンテンツを提供しています。
社内外のコンテンツの中から、効果の高いものや直接仕事に役に立つものを選定し組み合わせて従業員に提供するような仕組みを構築できれば、一から学習プログラムを開発するよりも比較的容易に学習プログラムを展開できるでしょう。自社に合ったコンテンツの選び方が分からないときは、外部の専門家に相談するのも有効です。
リスキリングの実施にあたっては、従業員が離脱せずに学習を続けられるようにする進捗管理が重要です。理解度や到達度を把握できる学習管理システムを導入して、従業員自身が学習の進捗や獲得したスキルを確認できるようにするのも一つの方法として挙げられます。
3.スキルの実践
「スキルが身についた」レベルに到達するには、リスキリングによって獲得したスキルを実際に職場で実践してもらうプロセスが欠かせません。まずは仮想ケースを用意して習得したスキルを試し、現場と連携して段階的に現場業務に活かしていくようにするとよいでしょう。
リスキリングは、一度で終わるものではありません。継続して行うために、従業員のモチベーションの維持を図り、同時にリスキリング施策に対するフィードバックを得ながら継続的に改善を図っていくことが欠かせません。フィードバックを反映させることは、従業員への参画意識にもつながります。受講後のアンケートやヒアリングなども有効な手段です。
リスキリングの導入事例
海外では早くからリスキリングに取り組んでいる企業が数多くあり、日本においても徐々に導入されています。ここでは、海外と国内の代表的事例をご紹介します。
海外企業
アメリカ大手EC企業A社
2019年にA社は、2025年までにアメリカの従業員10万人をリスキリングする大規模な計画を発表しました。技術職ではない従業員にスキル学習の機会を与え技術職へ移行させる支援を図ったり、デジタルスキルをもつ従業員が機械学習のスキルの習得を目指したりするプログラムを提供しています。
アメリカ大手小売企業B社
B社は、店舗従業員の社内研修にVRを用いています。2016年に試験運用を開始し、2018年9月には約1万7,000台を全米の店舗に導入し、45の研修プログラムを用意しています。VRを活用して、大規模セール時や繁忙期の店舗の様子を再現し、顧客対応の訓練に成果を上げました。VRを用いたプログラムは自然災害などのトラブル時の対応や新設備の操作方法の習得などにも活躍が期待されています。
日本国内企業
大手都市ガス企業C社
C社では、従業員のデータ分析力を高める「データ分析講習」を行っています。講義に加えて、プログラムに自主演習やグループ演習を用意し、データに触れる実践の場を多く設けています。初級・中級・上級の3コースがあり、2011年からの累計で、3講座を受講したグループ従業員の数は延べ約1,900人(2019年時点)になっています。
大手総合商社D社
D社では、デジタル技術を用いた新ビジネスを創出できる人材の育成を目指し、全従業員を対象としたリスキリングを実施しています。プログラムには、Python やデータ分析、機械学習などの研修を実施するほか、データサイエンティストによる個別フォローなどもあります。さらに、優秀な成果を挙げた従業員や特に成長した従業員には、表彰や人事評価への反映も行われています。
まとめ
時代の移り変わりが激しく、人に代わってAIやロボットが活躍する時代が迫っており、労働者すべてが今持っているスキルだけでは生き残りは厳しくなるでしょう。企業にとっても人材の有効活用、生産性の向上と新たな事業開発は不可避となっています。その点で、リスキリングは労働者、企業双方にとってのサバイバル手段となるでしょう。社内に新しいアイデアが生まれる、業務の効率化が期待できる、社内の文化を知っている従業員に取り組んでもらえる(リストラが回避できる)という点は、リスキリングに取り組むメリットとして非常に大きいといえます。
業務負荷の多いIT系職種の社員のサポートを インフラエンジニア派遣
<SODATECの特徴>
・ マンパワーグループの正社員であるため、派遣期間の制限を受けない
・ 吸収力のある若年層が中心
・ IT系特化部門エクスペリスのエンジニアリーダが上司となりフォローアップ
マンパワーグループでは、慢性的なエンジニア不足を解決策として、 エンジニアを目指す意欲の高い若年層の育成に取り組んでいます。IT人材育成プログラムSODATECは、ITエンジニアを目指す若年層に10日間の研修を提供。希望者はマンパワーグループの正社員となり、お客様先での派遣、またはお客様より受託中の弊社のIT系アウトソーシング業務に従事します。
エンジニア不足で社員の業務が増大している、残業が多い、 新しい技術習得をさせる余裕がないなどありましたら、ぜひSODATECの活用をご検討ください。
▽SODATECのサービス詳細についてはこちらから
https://www.manpowergroup.jp/client/serve/sodatec/

こちらの資料もおすすめです


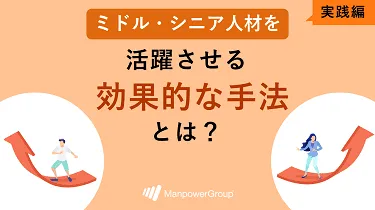

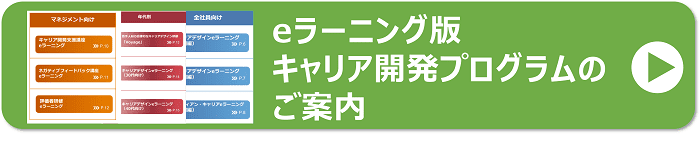






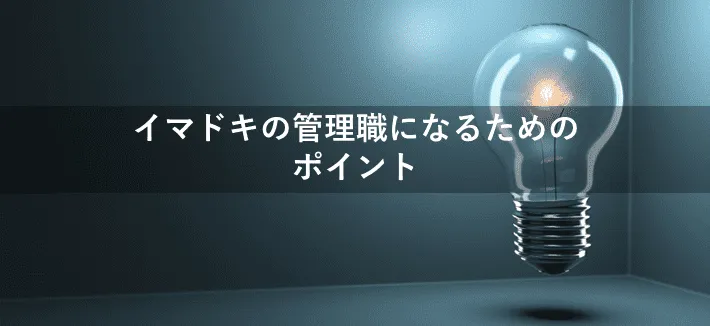











 目次
目次