


中途採用は難しい?人材が見つからない時の対策や成功事例を紹介

目次
街なかなどで転職エージェントの広告を目にする機会も多く、中途採用の市場が活性化している印象を受けますが、企業の採用担当者からは中途採用が思ったように進められないという声もあがっています。実際、中途採用の難易度は高いのでしょうか。
中途採用が難しいと言われる5つの理由
一般的に、中途採用が難しいと言われる理由として、次の5つが挙げられます。それぞれ詳しく説明します。
- 有効求人倍率が上昇している
- 転職市場に即戦力の人材が少ない
- 人材を見極めるのが難しい
- 採用するまでの時間が限られている
- 質の高い採用活動の維持が難しい
有効求人倍率が上昇している
「有効求人倍率」とは、有効求職者数に対する有効求人数の割合で、有効求人数を有効求職者数で割って算出されます。倍率が1を上回れば求職者の数よりも人材を探している企業が多いということになります。求職者からすると選択肢も多く、採用される可能性が高い状態です。
一方、求人する側の企業からすると、1人の求職者に対して複数の企業からオファーがある可能性が高いため、有効求人倍率が高いと採用しづらいということです。
厚生労働省から発表される「有効求人倍率」 をみると、2023年平均の有効求人倍率は1.31倍、つまり1人の求職者に対して求人が1.31件ある状態です。直近1年間を見ると、上昇傾向にはないものの、採用しづらい状況が続いていることには変わりありません。
なお、地域別でみると、受理地別で最高は福井県、最低は神奈川県とで差があり、地域によって状況が異なることが確認できます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 一般職業紹介状況(職業安定業務統計) ![]()
転職市場に即戦力の人材が少ない
中途採用市場では、経験・スキルが豊富な即戦力人材が求められますが、即戦力となる人材は現職で活躍しているため中途採用市場に出にくくなっています。
また、中途採用市場で求められる人材はどの企業でも枯渇しており、仮に市場で出てきたとしても引く手あまたですぐに決まってしまう傾向にあります。
更に、優秀な人材は、スカウトやヘッドハンティングをされることもよくあり、中途採用市場に出る前の段階で決まってしまうほか、フリーランスや独立を選択するなど、働き方の多様化が採用難に拍車をかけている状態です。
人材を見極めるのが難しい
一般的に、新卒採用はポテンシャルや人柄重視の採用であることが多く、また、中途採用と比較すると大きな母集団が形成しやすく、適性検査の結果などによる定性的な基準による応募者の絞り込みがしやすい傾向にあります。
一方の中途採用は即戦力採用が中心になりますが、即戦力だからとこれまでの経験や実績によるハードスキルの確認だけを行えばいいわけではありません。
スキル・経験は要求を満たしていたとしても、自社の社風や環境とマッチしていなければ、同様の活躍は見込めないため、コミュニケーション能力や仕事の進め方、成果に対する志向などソフトスキルについても慎重に判断する必要があり、見極めの難易度が上がります。
エージェント(人材紹介会社)を通す場合でも、エージェントからの情報を鵜呑みにすることなく判断することが必要です。現職での「満たされない要素」がないかなど確認するなどし、企業と求職者双方にとって入社がベストな選択であるか判断しましょう。
採用するまでの時間が限られている
中途採用の場合は、欠員補充や事業拡大による増員、新規事業立ち上げに必要なノウハウをもった人材の採用など、多くの場合は入社してほしいスケジュールが決まっています。
しかし人手不足の今、複数の企業を掛け持ちで転職活動をしている求職者は多く、自社の選考を進めている間に他社で内定が出てしまい、他社に先を越されてしまうことも少なくありません。
質の高い採用活動の維持が難しい
即戦力の人材が少なく、採用納期が決まっている中途採用市場の選考においては、時間をかけて優秀な人材を見極める質の高い採用活動が難しくなっています。選考に時間をかけすぎて、選考中に他社に応募者が流れてしまうケースは優秀な人材ほど起こりうることです。
しかし、面接の選考基準を緩める、選考面接回数を少なくして採用選考期間の短縮などすると、ミスマッチを起こしてしまうリスクを高めてしまうため、避けたいところではあります。
また、スマホの普及や情報リテラシーの向上により、近年さらに採用手法が多様化しており、人事の工数はますます増大傾向にあることも、質の高い採用活動の維持が難しいことの要因です。
急ぐ採用には採用代行サービスの活用も視野に
採用担当者の業務負担の軽減、または採用を急ぐ場合に採用代行サービスを活用する企業が増えています。マンパワーグループでは、採用プロセスの業務代行サービス、採用戦略立案や採用プロセス設計などのコンサルティングサービスを提供しています。本資料では、採用活動から採用後の定着に至るまでの各種課題に応じたソリューションを紹介しています。
<この資料でわかること>
・ サービスの特徴
・ 採用支援実績
・ サービスの種類
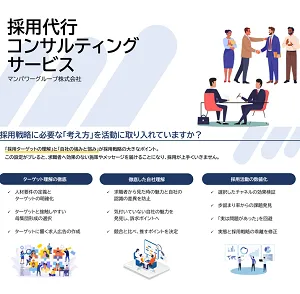
中途採用でありがちな失敗談
よくある中途採用での失敗談に「採用スピードが遅い」「入社後のフォローを怠っている」「適した求人媒体を選べていない」などがあります。それぞれの対策とあわせて解説します。
採用スピードが遅い
採用面接には、募集部門の役職者や担当役員など、人事担当者以外の協力を必要とします。ですが、人事採用担当者以外は、採用活動を周辺業務と位置付けている人が多く、面接設定の優先順位を通常業務より下げる、合否判定に時間をかけてしまうなどがたびたび起きてしまいます。
いくつもの選考でそのような状態が起きるとリードタイムが長くなり、「早く転職したい」中途採用者は選考期間中に他社に決められてしまうなど、採用スピードの遅さが採用率の低下を招いてしまうことがあります。
募集部門の担当者へは「求職者が複数の企業との選考を同時に進めるのが一般的で、内定の回答を長くは待てない」という中途採用の競争が激しい現状を伝え、選考の迅速化へ協力を求めるよう心がけましょう。
入社後のフォローを怠っている
新卒採用者の場合、集合研修を実施するなど入社後の育成プログラムが決まっている企業が多いですが、中途採用者の場合、募集部門にゆだねてしまっているケースが多くあります。
そのため、社内システムの理解や、前任者との引継ぎ、場合によっては関連部門の職務分掌の把握など、本来業務に就いてもらうまでに時間がかかってしまっています。
成果を出すまでに自分の居場所を見失ってしまう、人間関係や社風になじめない、といった精神的な部分で本来の能力を発揮できない状況を作ってしまうなど、入社後のフォローが適切でないために早期退職に繋がってしまうこともあります。
入社半年までは人事担当者と定期的な面談を行う、中途入社者の育成に成功している他部門からの支援を受けて入社時までに育成プログラムを整えるなど、入社後のフォローについても見直してみましょう。
適した求人媒体を選べていない
求人媒体の選定にあたっては、過去に採用実績のあるものを利用するのが一般的ですが、職種や人材のタイプによっては、必ずしも過去採用実績が高かった求人媒体が今回の採用に適しているとは限りません。
求人媒体を利用しても応募が来ない、求人媒体を増やしたがターゲット外の応募をさばく工数だけが増えた、といったケースがよくありますが、適切な求人媒体を選択できていないために起こっている可能性があります。自社の状況や採用したい人材などにあわせ、求人媒体それぞれの特徴を知り、適切な求人媒体を選ぶようにしましょう。
求人サイト
求人サイトは、最も利用されている媒体です。企業と求人者との仲介を目的とした企業が運営するサイト(転職サイト・ナビサイト)のほか、採用サイトや採用ページを自社運用しているケースもあります。
転職サイト・ナビサイトを利用する場合、そのサイトのターゲットを見極める必要があります。
例えばハイクラス・エグゼクティブな求人に特化したサイト、エンジニアなど特定の専門性に特化したサイト、出産・育児などでブランクのある女性に特化したサイト、20代や第二新卒のためのサイトなど、自社の採用においてどの求人サイトを使うのがベストか見極めましょう。
人材紹介
人材紹介は、エージェント(人材紹介会社)を通して、企業の採用要件に合った人材を紹介してもらうサービスです。
事前に人材紹介会社によるフィルタリングが行われるため、要件に合致した人材を探す採用担当者の工数の削減を行うことができます。人材紹介は特に、専門性の高い人材、ハイクラス人材の採用に向いています。
ハローワーク
ハローワークは公共職業安定所と言われる厚生労働省が運営する職業紹介サービスです。会社規模を問わず、無料で求人情報を公開してもらえます。
これまでは、応募者がハローワークに直接出向き、求人票を確認する必要がありましたが、現在ではオンラインで求人票を検索できる「ハローワークインターネットサービス」も提供されています。
新聞の折り込みチラシ
新聞の折り込みチラシは、地域に密着した人材の採用に向いています。エリアごとに発行され、駅やコンビニエンスストアなどの小売店などに置かれている求人フリーペーパーも同様です。
人材派遣
人材派遣は、派遣会社と雇用契約を結んでいる「派遣スタッフ」を自社に派遣してもらう方法で、特定のスキルの保有者を限定した期間内で早期に雇用したい場合に活用されています。
転職サイト・ナビサイトの利用時と同様に、その派遣会社が得意とする人材の分野などを把握しておく必要があります。
【資料】中途採用で活用される12の採用手法
採用手法には、それぞれに長所と短所があります。採用までに必要な費用や時間、内部リソースのみで対応可能か、または外部リソースが必要かなどの要素を考慮することが重要です。
これらすべてを把握した上で「この手法は本当に自社に適しているのか?」という問いを精査することが大切です。さらには、職種ごとで適した手法が違うことも多く有ります。
採用活動の効率をより良くするため、外部サービスを利用しつつ、自社に適した採用手法を増やすことが重要です。
【資料】中途採用 採用手法大全
中途採用で活用される12の採用手法を一冊にまとめました。
「採用手法の種類を知りたい」「採用手法の特徴をそれぞれ押さえておきたい」「採用手法の選び方を知りたい」方におすすめです。
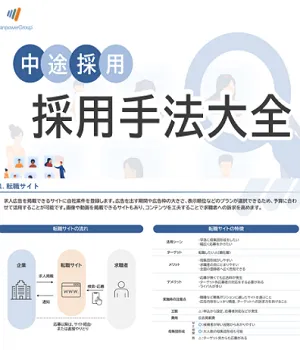
中途採用でいい人がいないもしくは見つからない時の対策
中途採用が困難である要素について解説してきましたが、対策がない訳ではありません。ここからは中途採用でいい人がいない、もしくは見つからない時の対策について説明します。
自社のアピールポイントを整理する
多くの中途採用者は職種で転職先を探しますが、職種がマッチしていても企業の魅力が伝わらないと応募してもらえません。競合他社との差別化を図るためにも自社のアピールポイントを整理する必要があります。
社内のデータや社員へのヒアリングをもとに、自社についての分析や競合他社の調査を行い、下記を参考に自社の強み・魅力を明確にしましょう。
- 業界の中でのユニークなポジショニング
- 業界の中から見た自社の強み
- 中期経営計画などから読み取れる、これからの成長分野
- 業界特性を踏まえた、募集職種に求められるスキル
人事制度や待遇、福利厚生面の内容も、競合他社との比較によって魅力として映ることも想定しておきましょう。
待遇面や福利厚生を充実させる
求職者は職務内容のみならず待遇面や福利厚生を見て応募するか否かの判断をしているため、待遇面や福利厚生を充実させることも避けては通れません。
また、近年ワークライフバランスの実現を図ろうとする意識が社会全体で高まっており、転職をきっかけにワークライフバランスの充実を図ることを想定している人材も少なくありません。
求人票に記載する労働条件については、人材紹介会社や採用コンサルティングなど、第三者や専門家視点の意見をもらいながら、社内の実施率や浸透率なども踏まえて記載する工夫も必要です。
評価基準の見直しを行う
初期選考を通過した候補者が、現場責任者や経営者の判断で不採用となるケースがあります。採用チーム内での選考基準の認識が統一されていない、あるいは採用基準に「現場の声」が反映されていないことが原因と考えられます。
一次選考を通過させた候補者の不採用が多発するときは、改めて関係者全員で採用基準の認識合わせを行う必要があります。また、現場責任者や経営者がどのような基準・要素で選考・判断をしているかを確認し、一次選考に盛り込むことも必要です。
ただし、全ての評価基準を網羅すると、評価基準が厳しすぎてしまう、あるいは煩雑すぎて選定できないことに陥る可能性もあるため、評価基準の追加・修正だけでなく、優先順位の設定も必要です。
中途採用成功に向けたポイント
欲しい人材層の採用を成功させるには「採用したい人物像や基準を明確にする」「自社の採用手法やフローを見直す」「採用業務を効率化させる」ことが重要です。
採用したい人物像を明確にする
中途採用を難しくしている原因のひとつに、人物像(ターゲットやペルソナ)設定の曖昧さが考えられます。
そこから派生する問題のひとつは、不適切な採用手法の選択です。
求められる人物像に響かないキャッチフレーズや訴求ポイントを設定してしまいターゲット層からの応募がこない、あるいは、ターゲット層に合致していない応募者への対応に追われるなどの弊害が発生します。
もうひとつの問題は、選考プロセスが非効率的になることです。
人物像が不明確だと、どのような人材を求めているのかの基準が確固としていないため、書類選考や面接の際の判断基準がバラバラになりがちです。
最悪の場合、面接官の主観によって有望な候補者を見逃してしまうことも起こりえます。これらの問題が積み重なると、入社後のミスマッチによる早期退職に発展し、欠員補充のための採用活動を再度行わなければならないという悪循環を招きかねません。
対策としては、まずターゲット・ペルソナの明確化から始めることが重要です。関係者全員が共通の認識を持つために、人物像を改めて言語化し、それをベースに採用手法の再検討を行う必要があります。また、選考の各段階での評価基準をしっかりと定義し、公平で一貫性のある評価を行える土台を作りましょう。
面接においても、共通の質問リストを用意することで、面接官間の評価のバラツキを減少させるなどの工夫が必要です。また、採用基準を人事や現場だけで決めず、経営層にも確認を入れておくことで、認識の相違を防ぐことができます。
自社の採用手法やフローを見直す
中途採用の採用手法は、自社のホームページへの掲載などによる直接の募集や職業安定所への求人、媒体への掲載などが一般的です。しかし最近は、社員からの紹介、一度退職をした人の再雇用など、間口を広げている企業もあります。募集してもなかなか集まらない、応募者はいるが欲しい人材が集まらないなど、現状を打破したい場合は採用手段を見直すことをおすすめします。
また、これまで人事面接(人事・採用部門による面接)、専門面接(募集部門による面接)、役員面接を別々に行っていた場合、人事面接と専門面接を同時または同日に行う、一部の面接はリモートでの参加にするなど、選考期間短縮のため選考のフローを見直すことも検討してみましょう。
採用業務を効率化させる
様々な採用手法を取り入れる場合、採用担当者の負荷が増す原因ともなるため、同時に採用業務の効率化を考える必要があります。業務負荷は採用活動の品質低下を招きやすく、以下のような課題・問題を引き起こす恐れがあります。
<業務負荷により引き起こされる課題・問題の一例>
- 個人情報の漏洩
- ターゲット分析を十分に行えず、ターゲットへの訴求力に欠けた内容になった
- 面接官など関係者との認識合わせが甘く、評価にバラツキがでた
- 求職者を不必要に待たせるなど、採用CX(キャンディデイトエクスペリエンス)を損ねている
業務負担の軽減のためには、採用代行サービスを利用する、人材紹介サービス(エージェント)を利用するといった一部機能をアウトソーシングすることも視野に入れてみてはいかがでしょうか。アウトソーシング以外でも、採用管理サービス、日程調整用のサイトなど、採用業部の効率化を図るためのツールやサービスもあります。
質の高い人材採用を成功させるために、周辺業務の効率化を検討してみましょう。
中途採用における成功事例
ここからは中途採用の成功事例を紹介します。自社と照らし合わせて自社に不足している部分を中途採用計画に盛り込むなどお役立てください。
電気機器メーカー:全社広報との連動
総合エレクトロニクスメーカーの成功事例を紹介します。
中途採用人材は、新事業の創造・推進と既存事業の改革に必要な人材を獲得することを目的とし、経験や実績をもつプロフェッショナルの採用が中心で、採用の質を落とさず安定的な採用を実現しています。
成功の鍵は、採用ページを大幅にリニューアルし、「全社の広報戦略と採用広報全体を連動」させたことにあります。従来は新卒採用担当者とキャリア採用担当者、それぞれが採用ページコンテンツを掲載していく運用。現在では全社広報と連動させ、認知から採用、育成まで一連のサイクルで整理しています。
サイトのコンテンツについては、「認知」を獲得することを重要との思想を軸に、働く人の仕事内容や働き方などインタビュー記事をまとめて掲載しコンテンツを強化。サイト訪問者がタグで検索し見たい情報にすぐたどりつつけるよう工夫されています。
サービス業:従業員も主体となり企業理念を確立
全国での訪問看護ステーション事業を中心に、居宅介護やデイサービス事業などを展開する企業の成功事例です。訪問看護は成長産業である一方で離職率の高い業界でありながら、毎年数百人の採用を実施し離職率を大きく低下させています。
人材の採用と離職率低下の鍵は「理念の浸透」と「育成制度」にあります。
従業員を巻き込みながら1年かけて働く意味を問い直し、行き着いた理念を採用ページ内に掲載。従業員目線で徹底的に作り込まれ、採用ページできちんと伝わるように工夫がなされています。直接応募者は企業理念に即した確度の高い人材が多いのも特徴です。
また、「人事制度・福利厚生」のページでは、現場では看取りをすることも多い中、経験の浅い若年層向けの精神面のケアを行う制度の紹介がなされているなど、応募者にとって安心できる企業であることがしっかり伝わる工夫をしています。
理念や育成制度が求める人材に刺さる内容となって訴求され、安定的な採用と離職率の低下といった好循環を生み出しています。
小売業:見る人の立場になって作り込んだサイト作り
テレビの通信販売で有名な企業の成功事例です。キャリア採用は例年80名~100名前後と、安定的な中途採用を実現しています。
成功の鍵は見る人の立場になって作り込んだ公式ウェブサイトにあります。
同社はこれまで実施してきた外部人材サービスの活用を停止し、現在は公式ウェブサイトを経由した本人からの直接応募に一本化しています。サイト経由の直接応募を原則としているため、サイトコンテンツの充実とスピード感が不可欠です。
企業概要や求人情報を詳細に掲載するだけでなく、「職種紹介」や「働く仲間紹介」などのコンテンツを充実させ、興味を持ってウェブサイトを訪問した人に「自分の活躍イメージを持ってもらえる」工夫をしています。また、リアルタイム情報発信でスピーディーに情報を発信することで、直接応募のみで中途採用が成功しています。
知名度のある企業やSNSなどで話題になっている企業、業界の中で個性的特徴がある企業、地域でよく知られる企業などがこの施策に向いています。
まとめ
人材の流動性が高まっているものの、複合的な理由で中途採用が難しいという状況は継続しています。
中途採用の成功事例の紹介では、「広報・採用の体制を一本化するなど社内体制の見直し」「理念や制度の改定と浸透」「直接応募一択で目標達成するための、充実したコンテンツ作り」など、大掛かりな施策について取り上げました。
大掛かりな施策は、予算の制約、リソース不足、組織全体の合意の難しさなどから実施が難しいという場合には、まずは「自社のアピールポイントの整理」「評価基準の見直し」「待遇面や福利厚生の充実」など、足元の解決可能な課題に対して、段階的に改善していくとよいでしょう。
こちらの資料もおすすめです

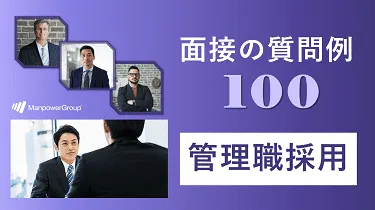




















 目次
目次